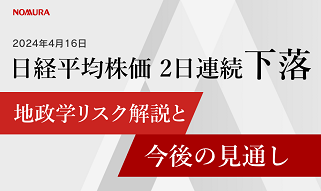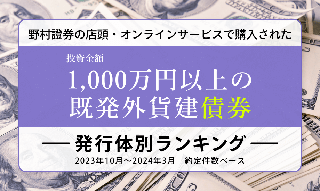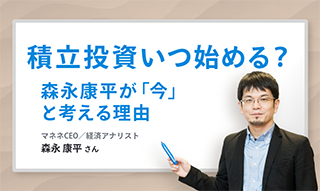2019.10.10 NEW
世界的映画祭で絶賛された長久允監督―電通社員として“サラリーマン監督”を貫くワケ

いま、世界中から注目を集める気鋭の映画監督・長久允(ながひさ まこと)。埼玉県の女子中学生が400匹もの金魚をプールに放ったという実際にあった事件をもとにした短編『そうして私たちはプールに金魚を、』(2016年)や、両親を亡くしても涙を流せなかったこどもたちが主役の長編『ウィーアーリトルゾンビーズ』(2019年)が国内外で高い評価を得ている。
そんな映画監督として世界に羽ばたく長久允だが、ふつうの映画監督とは大きく違うところがある。それは、電通社員であり、電通の仕事として映画を撮っている、いわば“サラリーマン監督”であることだ。
元々は、普段の仕事をこなしながら、プライベートの時間で映像制作をするという二足のわらじ状態だった。しかし、最新作の『ウィーアーリトルゾンビーズ』からは、自分が撮りたい作品を「仕事」として制作。そんな珍しい“サラリーマン監督”となった理由はなんなのか? 映画監督になる経緯とともに話を聞いた。
一度は映画制作の夢を諦め、CMプランナーに
- 大学在学中にダブルスクールで映像の専門学校に通い、監督として自主映画を何本も制作されていたとうかがっています。映像の道に進まずに、電通に就職されたことには何か理由があるのでしょうか。
-
本当は映画で食べて行きたかったのですが、どの作品もまったく評価されていなかったんです。映像や音楽に関連する会社も受けたのですが、内定をいただけたのが電通だけ。
これも何かの縁だと思い入社したのですが、映画を作る会社ではないことはわかっていたので、入社時点で夢は諦めていました。「サラリーマンとして、心をなくして生きようか」と(笑)。
- 電通では、長くCMプランナーとして活躍されていました。具体的には、どのようなお仕事を手掛けられたんですか?
-

一番やったのは、小売店の店頭用ビデオの制作ですね。試食コーナーの売り子さんの後ろに「この素材はこうやって育ちました」「おすすめの食べ方はこうです」という映像が流れていたりするじゃないですか。あれを年間に何本も作っていました。
うちの会社で、ステーキの焼き方を映像化させたら僕よりうまい人はいないと断言できるほど、自信があります(笑)。
- 華やかなテレビCMなどを手掛けられているイメージだったので、意外でした。
- 職人のようにコツコツと10年間、店頭用ビデオの制作に励みました。じつをいうと、広告のメインストリームにいたことがまったくないんですよ。
- 「もっと大きな仕事がしたい」という欲求はなかったんですか?
-
うーん、何といいますか……。大きな仕事になればなるほど、いろんな方が関わるじゃないですか。僕はそういう環境や仕事の進め方があまり得意ではないんです。正直、大きいプロジェクトには適性がない。
でも、自分が窓口になってクライアントやアーティストに直接プレゼンできるような仕事では、信頼を寄せてもらっていたし、制作物への評価も高かったと思っています。
- 自分の裁量と責任でやり遂げられる仕事のほうが性に合っていた?
-
そうです、そうです。クライアントと自分とが、お互いの意図を共有しながら進められるような仕事のほうが自分らしくいられるんですよ。たとえ窓際でもいいから、主体的に動ける場所にいたほうが、心身ともにストレスなく過ごせる。
だから、「たとえ大きな仕事でなかったとしても、手を抜かずにやっていれば悪いことにはならない」と思いながら仕事をしていました。
二足のわらじ時代、有休を使って撮った自主映画
- そんな中、2016年に『そうして私たちはプールに金魚を、』を制作されました。入社前に封印したはずの映画への思いが再燃したきっかけは、なんだったのですか?
-
大学時代、シュルレアリスムを専攻していたこともあって、ノイズ的な言葉のつらなりやシュールな表現を多用した映像を作りたいという思いが、ずっとあったんです。でも広告には、無駄な言葉や説明できないカットを入れるわけにはいかない。
もちろん、プロとして「ゴールがここだから、こう作るべき」と割り切って仕事をしていたんですが、一方で実際に作っている映像と、自分が人生をかけて作りたい映像とが大きく乖離していることに、強いストレスを感じてもいました。
その思いが少しずつ強くなって、「休みをとってでも、作りたい映像を作ってやろう」と思い立ったのが2016年。仕事を終えてからシナリオやコンテを書いて、役者さんの事務所に電話や手紙で出演をオファーして、有休で作った10日間を使って何とか撮影しました。
- 会社を休んでまで作った作品。達成感も大きかったのでは?
-
いや、最初は出品した映画コンクールにノミネートすらされなかったので、残念な気持ちでいっぱいでした。
「今の時代にはこういう作品があるべきだ」という一種の使命感で撮った作品だったので、それが評価されないということは、僕にとって「自分が作品を通じて描きたいものは、今の世の中に求められているものではなかった」ということとイコールだったんです。

でも、それから半年後に、「サンダンス映画祭のショートフィルム部門にノミネートされました」と連絡が入り、現地でなんと「日本映画として初のグランプリ受賞」という結果になり……。
「君はこのスタイルで映画を作っていいんだよ」と背中を押されたような気がして、すごくうれしかったですね。
つかみ取った「サラリーマン監督」という新しい働き方
- サンダンス映画祭は、名だたる監督を輩出してきた実績のある映画祭です。受賞をきっかけに映画監督として独立するという選択肢はなかったんですか?
-
なかったですね。理由はいろいろあるんですが……。
1つめは、「企画を受注する立場になったら、これまでのCM制作を通じて身につけた、資金集めやプロモーションに関するメソッドが使えなくなるのでは?」と思ったことです。
僕が作る映画は完全オリジナル作品だし、主役に知名度の高い役者さんを使っているわけでもないので、普通にやっていたらお金なんて集まらない。だからこそ、予算から何から自分で計算して、コントロールできる立場にいないと、作品が成就できない気がしたんです。

もう1つは、日本における映画監督の権限のなさとギャランティの低さ。たとえば、依頼を受けて長編映画を1本撮っても、得られるギャランティはだいたい100万円くらい。僕は家族もいるしローンもあるので、100万円で映画に向き合える期間はせいぜい3~4カ月程度ですが、その期間では自分が納得できるクオリティの作品は作れません。
電通にいる限り僕に権利収入が入ることは一切ありませんが、それよりもクオリティの高い作品を世に残すことを優先すべきだと思ったので、会社に残ることを選びました。
- 会社では引き続きCMプランナーとしても活動されているんですか?
- いえ、『ウィーアーリトルゾンビーズ』の制作開始に合わせて「コンテンツビジネス・デザイン・センター」という部署に異動しました。映画に出資したり、テレビ局と何かを作ったり、アニメの開発をしたりという部署で、その中で映画を作ることだけに専念させてもらっています。
- 電通にはさまざまな職種の方がいらっしゃいますが、「映画監督」を仕事にしている社員というのは、前例があるのでしょうか?
- ないと思います(笑)。
- どうやって現在の立場を会社に認めてもらったのですか?
-
まず、「CMではなくコンテンツをつくる部署に行きたい」と異動して、その後、「今の時代にはこういう映画が必要で、それを作ることは会社のためになる。だから僕をこのまま会社に残して映画に投資すべき」とプレゼンしました。
何とかゴーサインを出していただいて、2年がかりで『ウィーアーリトルゾンビーズ』を作ったのですが、ちょうど会社として広告以外の事業を探していた時期だったので、タイミングがよかったのかなと思います。
映画でなくてもいい、すべての人を肯定したい
- “サラリーマン監督”という立場を確立されたいま、どんな目標を抱かれていますか?
-

うまくいえないのですが、自分の中に「すべての人を肯定したい」という思いがあるんですよね。だから、「人にいいも悪いもない」「夢を追わなくたっていい」みたいな、優しいまなざしのものを作っていきたいと思っています。
それがかなうならどの国に住んでもいいし、極端な話、映画でなくてもいい。悩んでいる人に届くのであれば、ネット動画でも、マンガでも、イベントでも、一行の詩でもいいと思っています。
- 80年代生まれが思春期を過ごした90年代から2000年代初頭は、どこか冷めていたり、少し斜に構えていたり、といった独特の空気感がありました。長久さんの言葉や作品からも、あの時代のエッセンスが強く感じられます。
-
確かに……。忌野清志郎さんのユーモアやスチャダラパーの脱力的処世術に影響を受けていましたね。すごく冷めた人間だったので、当時の世の中の冷めたスタンスに救われてもいました。
そのせいでしょうか、今の時代はポジティブさのみをよしとする意識や、「夢は追いかけて当たり前」みたいな風潮が強すぎるように感じます。とにかくポジティブなものとか熱いものが多いから、もうちょっと斜に構えたもの、冷めたものがあってもいいのかなと。
それが世の中にあることで、僕のように救われる人がいたり、救われる何かがあったりするようにも思うんです。
ちなみに海外からは、日本人の冷めたスタンスってすごく新鮮なものに見えているみたいですよ。経済が上向きではないのにみんなひょうひょうとしていて。でも不思議な冷めた前向きさがある。それもあって海外で「禅」とか「こんまり」とかブームになっているんですって。
そういう鈍感力みたいなものを備えた日本人はクールだという話を聞いていると、僕の表現はもしかしたら、国籍を超えて世界中で悩んでいる人たちに、新しい処世術として機能するんじゃないかという予感もしています。
僕が80年代に生まれたのはたまたまですが、あの時代に体得した生き方が、映画を通してより多くの人に届いてくれればうれしいです。
- 最後にEL BORDE(エル・ボルデ)読者に向けて、メッセージをお願いします。
-
何か気になっていることがあるなら、やったほうがいいと思います。やりたいのにやらないのは辛いじゃないですか。
もちろん、会社を辞めるとか思い切ったことをする必要はなくて、できる範囲のことからやってみればいい。「1日10分羊毛フェルトをつつく」でもいいと思うんですよね(笑)。
自分の人生って結局自分のものだし、会社のために生きているわけじゃない。そのことだけは忘れずに生きてほしいです。
- 長久 允(ながひさ まこと)
- 1984年生まれ、東京都出身。青山学院大学フランス文学科を卒業後、電通に入社。『ウィーアーリトルゾンビーズ』は長編デビュー作ながら、サンダンス映画祭審査員特別賞、ベルリン国際映画祭スペシャル・メンション賞(準グランプリ)など高い評価を受けた。トレードマークの三つ編みは6~7年前から採用。普段はまっすぐ降ろし、公の場に出るときに「戦闘服」のような意味合いを込めて結うのだという。