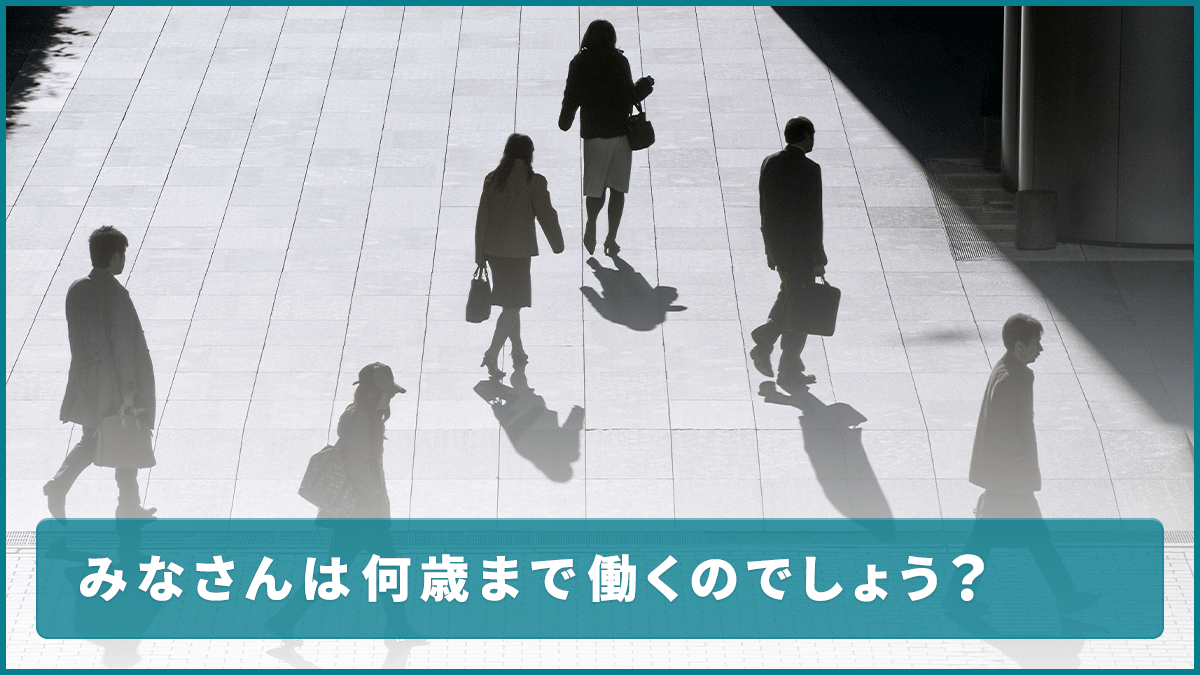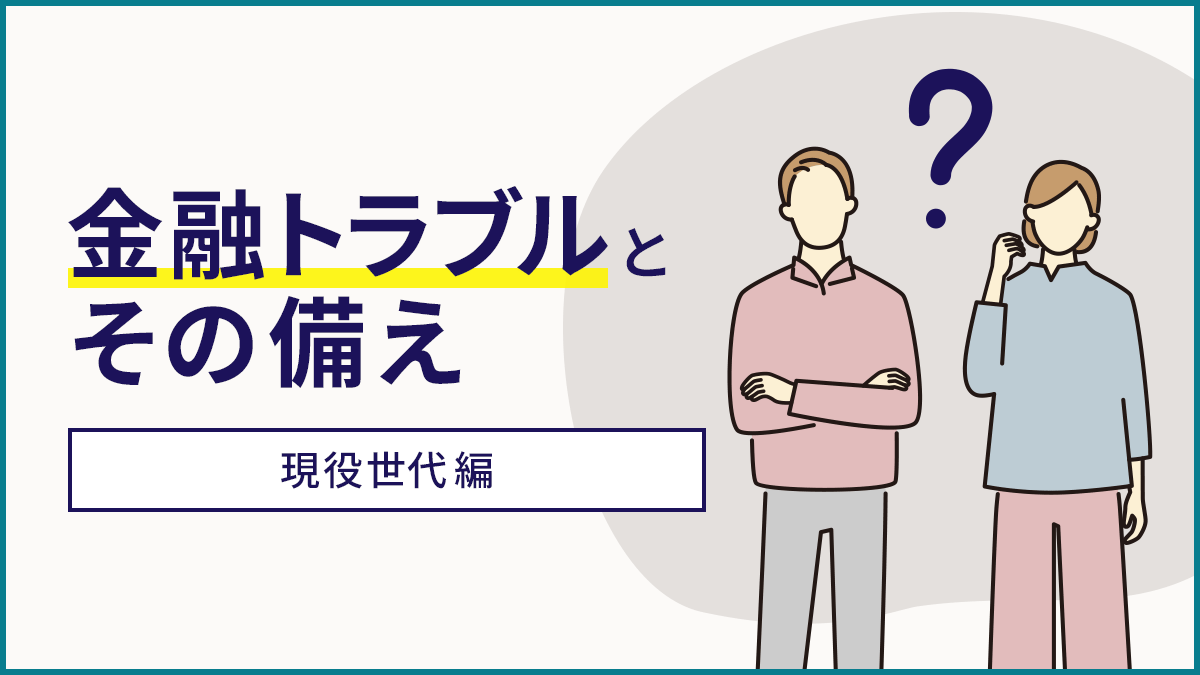退職後から独立するための準備と手続き 人生の転機を安心して踏み出すために〈転職&退職時に必要な手続きとは?〉
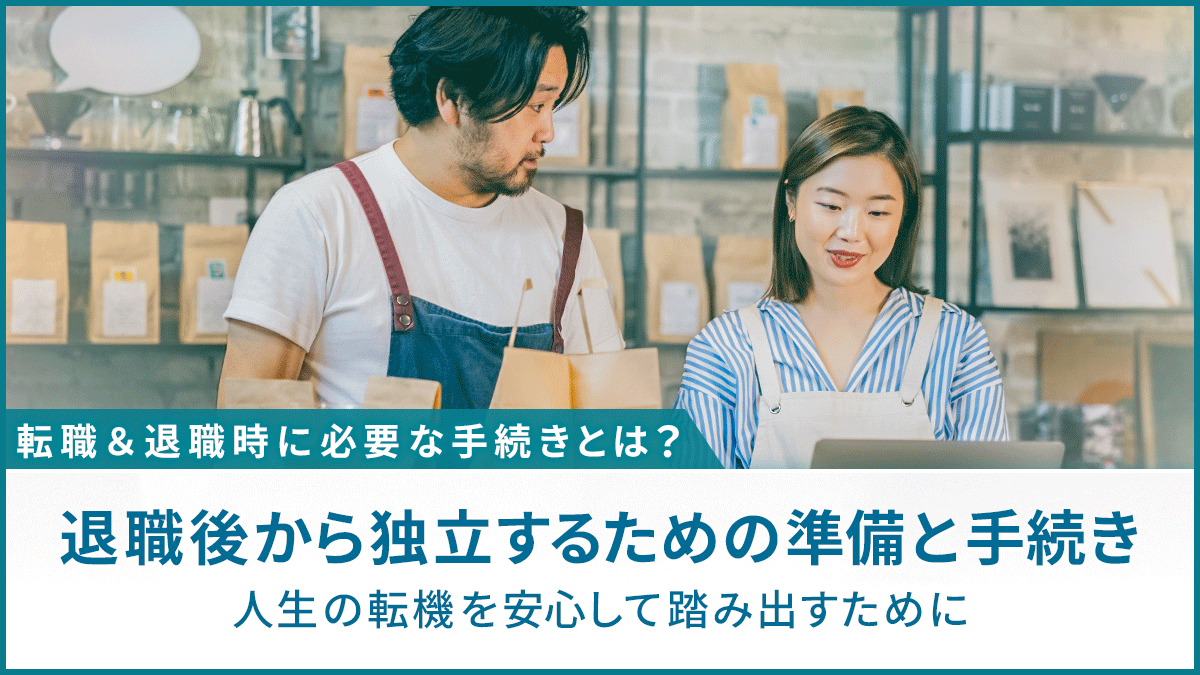
退職後に独立する方へ
はじめに
独立するための退職は、これまでの職場を離れ、新しいステージに進むための前向きな選択肢のひとつです。とはいえ、「退職後、家族の扶養に入れるの?」「フリーランスになると社会保険ってどうなるの?」「国民健康保険以外の制度はあるの?」といった疑問が浮かぶ方も多いのではないでしょうか。
実際、退職を決意してから次の一歩を踏み出すまでのあいだには、多くの手続きや確認事項があります。このコラムでは、退職後に独立する方が安心して次のステージへ進めるよう、退職前後に必要な準備や手続きをわかりやすく整理していきます。
退職前の準備
退職の意志を固めたら、まずは上司への報告と所属先への正式な退職届の提出が必要です。まずは所属先の就業規則に記載されている期日を確認し準備を進めましょう。所属先の就業規則では「退職の1か月前までに申し出ること」(民法上は2週間前でも可能だが、職場への配慮として1か月前が一般的)とされている所が多いため、退職希望日から逆算して準備を進めることが大切です。
退職の手続きとあわせて、身の回りの準備も着実に進めておくことで、円滑な退職と気持ちのよい新しいスタートにつながります。たとえば、退職日と有給休暇のバランスを確認し、計画的に取得すること、これまでの業務内容を整理した引き継ぎ資料を準備しておくこと、そして、お世話になった方々への感謝の気持ちを込めた挨拶の準備も大切です。退職に伴う手続きは多岐にわたるため、下記のチェックリストをもとに、抜けや漏れのない準備をしておくと安心です。
また、退職後まもなく独立開業を考えている方は、すぐに動き出せるよう、開業準備や名刺、ロゴなどのビジネスインフラの整備も早めに始めておきましょう。但し、現在在職中の場合は、業務時間外で行うべき事項なので注意が必要です。
退職時に必要な手続き
独立して起業する前には、行政や社会保険関連の手続きを完了させておく必要があります。これらをスムーズに進めておくことで、安心して次のステージへ踏み出せます。
① 離職票
ハローワークに雇用保険の基本手当(失業手当)を申請するために必要な書類です。届かない場合は勤務先に早めの確認をしましょう。
② 雇用保険被保険者証
被保険者証雇用保険に加入する際に提出を求められ、被保険者番号の確認に使用します。
③ 源泉徴収票
1年間の給与収入、所得税額などが記載された書類です。再発行は所属先でしかできないため、必ず受け取りましょう。
④ 健康保険資格喪失証明書
国民健康保険(以下、国保)への切り替えや、家族の扶養に入る手続きで提出を求められます。国保や国民年金の加入手続きの期限は、退職日の翌日から原則14日以内です。
⑤ 年金手帳(2022年4月以降は廃止)または基礎年金番号通知書
国民年金や厚生年金の手続きに必要となります。マイナンバーでも代用可能な場面が増えていますが、確認書類として保持することを推奨します。
⑥ 退職時の給与支払明細書
退職時の給料明細は、退職後に届く住民税の確認や、年末調整・確定申告時の所得把握に使えるため、証明として保管することを推奨します。
| 書類名 | 内容 | 目的 | ||
|---|---|---|---|---|
| ① | 離職票 | 退職理由や給与額 | ハローワークで 失業手当を受ける | |
| ② | 雇用保険被保険者証 | 雇用保険の記録 | 失業保険や雇用保険加入 | |
| ③ | 源泉徴収票 | その年の収入と納税額を記録 | 年末調整や確定申告で使用 | |
| ④ | 健康保険資格喪失証明書 | 健康保険の資格喪失日を証明 | 国民健康保険の手続き | |
| ⑤ | 年金手帳 または基礎年金番号通知書 | 基礎年金番号の確認 | 国保や厚生年金加入手続き | |
| ⑥ | 退職時の給与支払明細書 | 社会保険料や住民税の最終調整 | 収入や税額の確認 |
独立時に整えたい「4つのポイント」
自らのビジネスをスタートさせる際には、制度と実務の両面でやるべきことが多々あります。退職後まもなく独立開業を考えている方は、すぐに動き出せるよう、開業準備や名刺、ロゴなどのビジネスインフラの整備も早めに始めておきましょう。但し、現在在職中の場合は、業務時間外で行うべき事項です。
以下は、独立時に押さえておきたい4つのポイントです。
1. 開業の届け出と青色申告の準備
個人事業主として事業を始める場合は、税務署へ「開業届」を提出します。あわせて提出する「青色申告承認申請書」により、最大65万円の特別控除※など、税制面での優遇措置を受けることができます。これらの書類は、開業から原則2か月以内の提出が必要です。
税制に関しては2025年10月時点
2. 社会保険の切り替え
勤務先を退職後に国保・国民年金に加入する場合は、14日以内にお住まいの市区町村で手続きを行う必要があります。保険料は前年の所得をベースに計算されるため、起業直後で収入が不安定な時期に、家族の扶養に入りたい場合は、家族が加入する社会保険の規定を確認しておきましょう。一時的に扶養に入り、収入が安定してきた段階で国保や任意継続保険に切り替える方法もあります。
他には、作家・デザイナー・イラストレーターなど、特定の職業に就いている人が加入できる文芸美術国民健康保険組合(文美国保)などもありますので、情報収集するとよいでしょう。
会社設立等を行わずに独立する方は、国民年金に加入します。さらに、国民年金基金・付加年金などの年金制度に任意加入できます。国民年金は、厚生年金と違って退職金制度がないため、小規模企業共済を検討する方法もあります。この掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象のため、節税対策にもなります。更に、個人型確定拠出年金(以下、iDeCo)へ加入する選択肢もあります。
3. 事業資金の確保と資金計画
事業収入が安定するまで時間がかかることも想定しておきましょう。生活費とは別に数か月分の運転資金を用意する、公的な創業支援融資制度や補助金・助成金の活用を調べ、金融機関や支援機関との打ち合わせも早めにしておくことをおすすめします。
4. 事業のインフラ整備
開業後の業務を円滑に進めるためには、会計ソフトの導入、名刺やロゴの制作、事業用銀行口座の開設、SNSやホームページの整備など、実務インフラの準備も欠かせません。
退職後、起業するまでにブランク期間がある方
様々な事情があり意図的に少し時間を空けて次のステージを選びたい場合も、社会保障や税務面の手続きはしっかりと進めておくことが大切です。
1. ハローワークへ雇用保険の基本手当(失業手当)申請
所属先から受け取った「離職票」をもとに、ハローワークで失業手当の受給対象となるか確認しましょう。離職票が手元に届いたらすぐに申請を行います。
2. 健康保険の任意継続保険 or 国保の加入
健康保険の任意継続加入を希望する場合は、退職日翌日から20日以内の手続きが必要です。任意継続加入期間は最長2年です。しかし、在職中は勤務先と本人で折半していた保険料が、退職後の任意継続加入期間は事業主の負担がなくなるため、実質倍額近くになることもあります。
また、配偶者の健康保険に加入する場合は、配偶者の勤務先へ申請し、扶養条件を満たす必要があります。
3. 社会保険の切り替え
会社設立等を行わない場合、厚生年金(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)へ変更する必要があります。また、配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる場合には、国民年金第3号被保険者の手続きを行います。配偶者の勤務先を通して、書類を提出します。
4. 税金の納付
年末調整や確定申告に関わる情報は、早めに準備しておくことで、思わぬ税金の負担や手続きミスを防げます。
住民税は「前年の所得」に対して課税されるため、退職後もしばらく納税義務が続きます。従業員・職員時代は給与天引き(特別徴収)されていたものが、退職後は自分で納める(普通徴収:年4回に分割支払い)方法に切り替わります。
所得税に関しては、退職時点までの所得に応じた所得税が源泉徴収されますが、年の途中で退職する場合は年末調整が未完了のままになるため、確定申告が必要なケースがあります。次のような方は、翌年の2月〜3月の確定申告期間に手続きを行う必要があります。年内に再就職せず他の収入がない方(所得税が還付される場合あり)、転職先で年末調整に間に合わなかった方、副業収入がある方や、医療費控除などを申請したい方などです。
見落としに注意!退職後によくあるトラブル
独立は新たなスタートですが、その準備は思った以上に複雑です。実際の手続きに入ると予想以上にやることが多く、見落としや勘違いから不利益につながってしまうケースが少なくありません。それぞれの手続きを確実に進めることで、トラブルを未然に防ぎ、次の一歩を踏み出すことができます。以下は、特に注意しておきたい代表的な項目です。
| 離職票の受け取り忘れ | |||||
| 失業手当の申請に必要な離職票です。退職後2週間を過ぎても届かない場合は、前職の勤務先やハローワークに早めに確認しましょう | |||||
| 健康保険の任意継続加入手続きを失念 | |||||
| 健康保険の任意継続制度は、退職後20日以内の申請が必要です。申請期限を過ぎると加入できなくなり、国民健康保険に切り替えるしかないケースもあります。ただし、任意継続保険では保険料を労使折半ではなく全額負担する必要があります。 | |||||
| 企業型確定拠出年金(以下、企業型DC)の移換漏れ | |||||
| 企業型DCに加入していた方は、6か月以内にiDeCoへ移換手続きを行わないと、国民年金基金連合会へ「自動移換」扱いとなり、積立金の運用が停止され、毎月の手数料が発生しますので忘れずに行いましょう。 | |||||
| 健康保険証や年金手帳の返却・受領漏れ | |||||
| 退職前後は、所属先からの書類受け取りや返却の管理が重要です。必要書類が手元にないと、のちの手続きで支障が出ることもありますのでチェックリストを作成しましょう。 | |||||
ライフプランの見直し
独立して起業直後は、収入がしばらく不安定になる可能性も想定して、生活費の予備資金や保険・年金などの社会保障の整備を計画的に進めましょう。また、住宅ローンや教育費などの中長期的な支出計画も見直しが必要です。たとえば、家賃などの固定費を見直すこと、公的制度の活用を検討することも非常に大切です。独立により、働き方の変化や生活のスタイルが変わるため、ライフプランを見直すことにより、生活の土台を整えて自分らしい働き方を実現、チャレンジができるのではないでしょうか。
まとめ
独立するために退職する際には、多くの手続きや判断が求められます。しかし、必要なステップを時系列で整理し、確認して進めていけば、決して難しいことではありません。このコラムが、独立という人生の転機をスムーズに進め、新たな道を安心して踏み出すための手助けになればと思います。
編集協力:寺澤真奈美 2級ファイナンシャル・プランニング技能士編集/文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部
記事公開日:2025年10月2日