2023.08.24 NEW
日本株式を30年見続けた「達人」が占う市場の行方 渡部清二【前編】
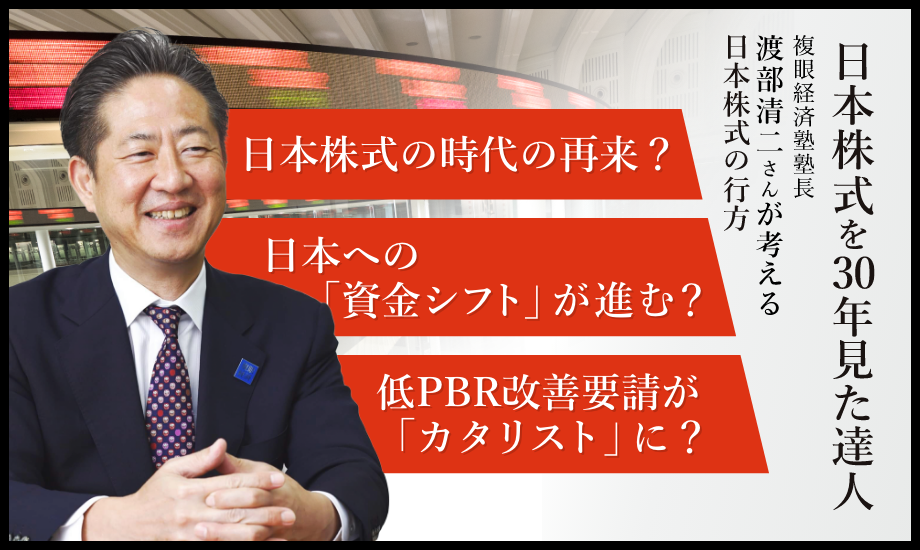
撮影/竹井俊晴
今年に入り、日経平均株価が30,000円台を回復するなど、日本の株式市場は1990年以来の水準となりました。野村證券で機関投資家向けの日本株セールスなどに携わった後、個人投資家が経済や市場について学ぶ「複眼経済塾」を設立した渡部清二さんに、今後の株式市場の動向や東京証券取引所の「PBR(株価純資産倍率)改善要請」などについて聞きました。
「日本株式の時代」、60年ぶりに再来か
- 日本株式のパフォーマンスが好調です。市場の現状と今後をどう見ていますか。
-
独立して複眼経済塾の前身となる会社を設立したのは2014年です。当時から「近々ジャポニズムは再来する」、つまり日本株の時代がまた訪れると考えていました。
私は、戦前から戦後にかけて株価が40年間上がり続け、20年余り下落、調整するという60年のサイクルが繰り返されてきたと考えています。戦後のサイクルは1回目が1949年5月から2013年まで。2013年は、東京証券取引所と大阪証券取引所が経営統合した年です。そこから2回目のサイクルがスタートしているのではないか、と。
1989年末には、世界の上場企業の時価総額ランキングの上位50社のうち日本企業が半数以上を占めていました。現在は米国企業が上位50社のうち半数以上を占めていますが、それと同じことが日本でも起きていたのです。
1989年以降、日経平均株価は20年余りで8割下落した一方で、1990年代からNYダウ平均株価は10倍になりました。しかし、私は過去の傾向や数値を分析し、2023年には日経平均株価とNYダウ平均株価の上昇率が逆転するであろうとかなり前から見ていました。1929年に高値を付けたNYダウ平均株価と1989年に高値を付けた日経平均株価の相関を分析する限り、日経平均株価は2030年頃までに10万円を超える可能性があるとも思っています。
その理由は、海外から日本への資金シフトです。私が主宰する複眼経済塾では今、「外国人」がテーマであると塾生の皆さんには伝えています。外国人が日本に集まるのと同時に、投資資金も日本に流入してくるのです。
- 実体経済と株価の動きが矛盾しているようにも見えますが、この状況をどう分析しますか。
-
これまでは、「日本経済が成長しているから日本企業の株価も連動して上昇する」という論理で市場は動いていたのだと思います。その論理が限界にきているのではないでしょうか。
一方、「資金をどの国に置くか」というのは世界の投資家が常に考えていることです。現在は日本に資金を置きたいと考える投資家が増えているため、日本株が上昇していると見ています。
例えば、半導体産業などでも同様の傾向があると言えます。TSMC(台湾積体電路製造)が熊本に工場を進出させることを決めたのも、経済安全保障などの観点から、日本に工場を設置するのが妥当という結論になったと考えられます。
テンバガーを探す考え方とは
- かつてとは異なる理由で日本株が上昇している状況の中、個人投資家はどのような姿勢で投資に臨むべきでしょうか。
-
まずは資金シフトも含め、マクロ経済の基礎や世界経済のルールをある程度理解した上で投資すべきです。
しかし、個人投資家は必ずしも、株の値上がり益で儲けたいと考えているわけではありません。株主優待や配当金が魅力的だから投資したいと考える人もいれば、好きな会社や経営者を応援したいという「推し活」の一環として投資をする人もいますね。
そういった投資のスタイルを大切にしていいんです。そのうえで、上昇相場が訪れているので経済のことを学びつつ、いわゆる「テンバガー」(株価が10倍になった銘柄やなりそうな銘柄)も狙ってみましょう、と塾生の皆さんにはお話ししています。
- 今後、どういった銘柄が値上がりすると考えますか。
-
日本株に勢いが戻ってきたことで、まずはあらゆる分野の多くの銘柄が値上がりすると思います。
振り返ると、1999年2月には日本銀行が金融緩和を行い、実質ゼロ金利の政策に舵を切りました。外国人投資家の日本株の買い越しが当時の過去最高となり、1999年7月までの5か月間で日経平均株価は15%ほど急上昇しました。
今年も当時と共通点があります。2023年4~5月は外国人投資家が2か月連続で2兆円の買い越しになっています。さらに4月に植田和男氏が日本銀行新総裁に就任した後、6月に大規模な金融緩和の継続を決定しています。これによって日経平均株価は年初から半年ほどで30%ほど急上昇しました。
一方、1998年頃から2000年までの間は、国内外で多くのIT関連銘柄が急騰した「ITバブル」がありました。その後株価を上げたIT関連銘柄の大半は淘汰されましたが、ITを活用して勝ち残ったアマゾン・ドット・コムは株価も上昇し、今や世界的な存在です。
そして今、AIチャットサービスのような生成AIが脚光を浴びています。現時点ではまだ「バブル」を引き起こすほどの決定的な要素には欠けている印象ですが、新技術によって何らかの革新が起こるでしょう。
IT関連銘柄がかつてのITバブルをけん引したように、今後はAIのような革新的技術を活かすことができる銘柄が株価の上昇をけん引するかもしれません。
- 当時のITバブルのような状態が生成系AI銘柄にくるということですか。
-
意外にアナログなものが生成AIによって効率化され、企業の株価が上がる、といったようなことがあるのではないかと見ています。
例えば、コールセンターが生成AIで大きく変貌を遂げて、関連する銘柄が値上がりするといったようなイメージです。AIに関連する銘柄の多くが値上がりする「AIバブル」のような現象がいずれ起きるのではないかと考えています。
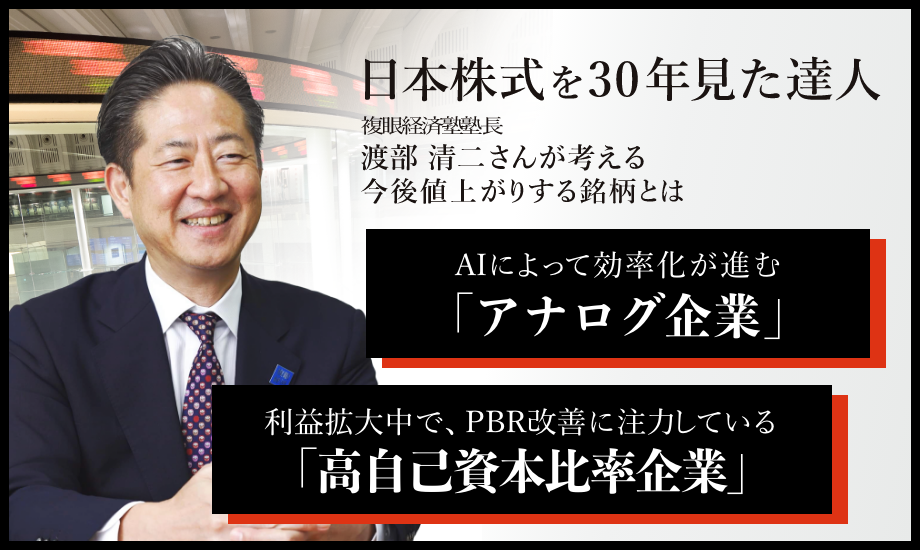
東証のPBR改善要請が「カタリスト」に
- 東京証券取引所が「PBR1倍」を割っている企業に改善を要請しました。このアクションをどう見ますか。
-
東京証券取引所が企業や投資家に、「重大な問題がある」ことを気づかせてくれたという点では、大変よいアクションといえます。
PBR1倍を割っている株式と言うのは「バリュー株」といい、本来の価値から見て割安な株式のことです。企業が資金を成長投資や株主還元に振り向けないと、企業価値は向上せず何年もバリュー株のままになってしまいます。東証のPBR改善要請はそのような銘柄が日本の上場企業の多数を占めている状況を打破するきっかけになるかもしれません。
一方、バリュー株投資について、一部の個人投資家が見落としている点があります。
株式は「値上がりする」と思うから買うものです。しかし一部の投資家は「割安だから買おう」という発想でバリュー株に投資してしまいます。その際、「なぜ値上がりすると思うのですか」と聞いても、答えられない人がいるのです。
「カタリスト」、つまり株価が上がるきっかけが何かを考えられない銘柄の場合、株価もなかなか上がらないものです。東証の要請がカタリストとなり、株価が上がってきているという側面もあると思います。
- カタリストとなるのは、東証の要請以外にどんなものがありますか。
-
企業の資産に関してカタリストとなり得るものは2つあります。1つはインフレです。モノの値段が上がれば資産の値段も上がるのではないかと考えられるためです。もう一つはシンプルで、利益が伸びることです。利益が増えれば結果として企業の純資産が積み上がっていくためです。
企業の純資産に対して、株価が割高か割安かを判断する際に用いる指標がPBRです。まだ株式市場ではPBRが上がり切っていないというのが実情ですが、資産のインフレは進んでいます。東京23区の新築マンションの平均価格が今や1億円を超えるまでになりました。PBRが大きく上昇するタイミングが近いことを物語っていると感じます。
今は東証の要請と、インフレへの流れを踏まえると、PBRを重視する投資戦略は正しいのではないかと思います。PBRを上げる努力をしている企業に注目すべきですが、利益が伸びていることが大前提です。
これに自己資本比率を踏まえるとより確実です。自己資本比率が高いのに、PBRが低いものは明らかに割安と考えられます。
- これからの日本株を占ううえで、2024年からの新NISAはどう影響しますか。「貯蓄から投資へ」の流れは新NISAで本格化するでしょうか。
-
本格化し始めたらあっという間に状況が変わるのではないかと考えています。日本人のマインドは意外なほど早く変化するものです。
新NISAも「貯蓄から投資へ」の流れを強めるきっかけになり得るかもしれませんが、私は2024年に新しいお札が登場するのが転換点になる気がしています。
世間に流通している紙幣の残高は100兆円を超えていますが、私はこのうちかなりの金額が家庭の「タンス預金」として眠っているのではないかと推測しています。
旧札の価値がなくなることはありませんが、新札が登場することで、日常的に旧札が使えない場面が増えると予想されます。旧札から新札へ切り替わるタイミングで、「貯蓄から投資へ」という考えのもと、新たに投資を始める人が増えるのではないでしょうか。
※この記事は、2023年7月現在の情報に基づくものです。
- 「複眼経済塾」塾長
渡部 清二氏 - 筑波大学第三学群基礎工学類変換工学卒業。1990年に野村證券入社、中堅企業や個人投資家向けの資産コンサルティングや機関投資家への日本株セールスに従事し、2013年に退社。翌年、「四季リサーチ」を設立、代表取締役に就任し、国内外の機関投資家へ投資情報の提供を始める。2016年、複眼経済塾設立。代表取締役・塾長として、個人投資家向けの講義やワークショップを実施している。
【関連リンク】
本コラムは渡部清二さんの株式投資に対する基本的な考え方などについて、ご参考としてお送りするものです。また、本コラムで取り上げられた株式投資の基本的な考え方などについては、あくまで渡部清二さん個人の見解によるものであり、野村證券の意見を代表するものではございません。あらかじめご承知おきください。なお、資料の内容等は野村證券において確認したものではなく、また、将来変更される場合があります。銘柄の選択や投資の最終決定にあたっては、ご自身でご判断ください。