2024.02.22 NEW
「新しいNISAで、“売却しない”判断がしやすくなる」行動ファイナンス対談
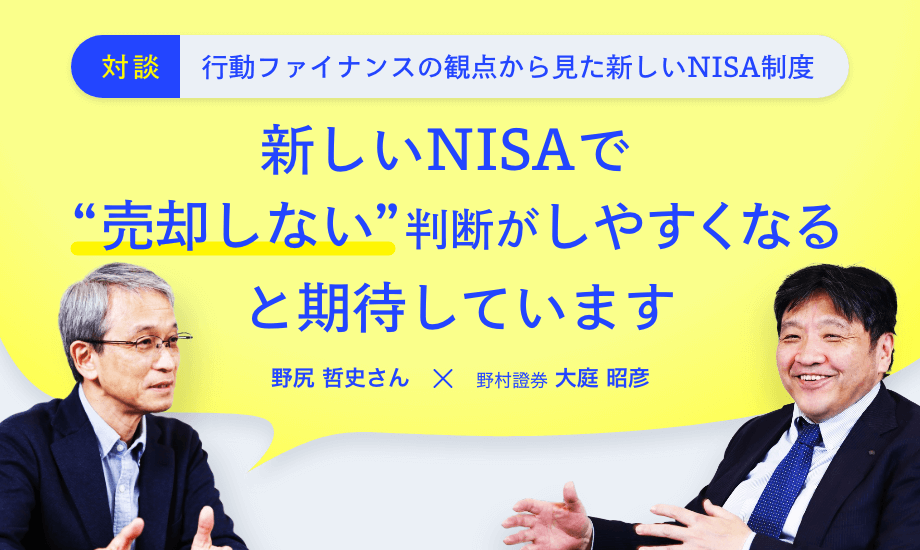
写真/竹井俊晴
新しいNISAが始まって以来、これまで投資をしていなかった人の関心も高まっていると思われます。NISAの制度が変わったことで、人々の投資行動を“合理的な方向”に促すことができるのでしょうか。フィンウェル研究所代表の野尻哲史さんと、行動ファイナンスの研究を専門とする野村證券金融工学研究センター エグゼクティブディレクター大庭昭彦が対談しました(対談日:2024年1月24日)。
行動ファイナンス:人の心理面などの動きに注目し、投資を行うにあたって「人はどのように意思決定し行動するのか、なぜ時として非合理的な行動をするのか」を研究する「行動経済学」に基づく投資理論
新しいNISAで非課税保有期間が無期限になったことの意味
- 新しいNISAは人々の投資行動を“合理的な方向”に促す可能性があるのだろうか?
というテーマを話し合いたくて、野尻さんをお招きしました。大庭昭彦は、野村證券で長く行動ファイナンスを研究しています。お二人は知り合ってから長いそうですね。 -
野尻哲史さん(以下、野尻)
大庭さんと出会ってからずいぶん経ちますね。2011年に野村資本市場研究所が「個人向け投資サービスと行動ファイナンス」を巡る研究会を発足したときに、一緒に委員を担当しましたのをよく覚えています。大庭昭彦(以下、大庭)
そうでしたね。研究会以降もいろいろなところで野尻さんと意見交換しています。野尻
当時、行動経済学に基づく投資理論の行動ファイナンスは、海外では熱心に研究されていました。金融機関の運用部門の運用のためだけでなく、個人投資家の行動の変容が重要なテーマだったのです。当初は投資家の非合理な行動が金融市場に与える影響を分析するという視点だったと思いますが、個人の投資行動を正しい方向に向かわせる研究へと広がりました。当時勤めていたフィデリティ投信で、私はそうしたテーマの海外専門家と議論することがたびたびあり、その知見を広げることができました。
野村資本市場研究所が行動ファイナンスをテーマに研究会を開いていたのは、早かったですね。
大庭
そうかもしれません。我々はかなり早くから、行動ファイナンスに注目していた二人ということになりますね。

- そんなお二人からみて、新しいNISAは行動ファイナンスの観点から、いい制度になったと感じますか。
-
大庭
行動ファイナンスの観点では、投資家にとっては自分の判断で一回一回、有価証券の売買を判断するのはとても大変です。あらかじめどのように投資するのかを決めておけば、その通りに実行しやすくなります。その意味では、積立投資をしやすくするのはいい仕組みだといえます。さらに税制でも有利な点があるので、投資に前向きな姿勢になりやすいですね。野尻
新しいNISAでは、非課税投資枠が広がったことが注目されていますが、私は非課税投資枠よりも重要なのは非課税保有期間が無期限となったことだと思っています。これまでのNISAは、一般NISAは最長5年、つみたてNISAが最長20年と、非課税保有期間に期限が決められていました。このことで、投資家は「いずれ売却するタイミングが来るのだから、株価が上がったら売っておこう」というマインドセットになりやすかった可能性があると考えているんです。
大庭
なるほど。新しいNISAでは非課税保有期間が無期限になったことで、「すぐに売る必要はない」と考えやすくなる、ということですね。
NISA制度が始まって以来「売り」も増えている
-
大庭
行動ファイナンスの観点では、有価証券を簡単に売却するのは合理的とはいえません。例えば投資の目標が老後資金を貯めることだったら、その前の現役世代のときに株価が上がったからといって売ってしまっては、目標を達成しづらくなってしまいます。野尻
実際、旧NISA制度により、多くの人が投資に参加して有価証券の買付金額はどんどん増えました。ところが、実は売りも増えているんです。
金融庁より公表されている「NISA口座の利用状況」データによると、2014年のNISA開始年の年末、NISA口座での買付額は約1兆34億円でした。そして、2022年末までの総買付額は30兆円を超えていますが、残高は13兆円台です。
岸田政権が2022年11月に打ち出した「資産所得倍増プラン」では、「5年間で、NISA 買付額を現在の 28 兆円 から 56兆円へと倍増させる」とされています。しかしこの数字はあくまで買付額。本来は、残高の推移のほうにもっと注目すべきでしょう。

-
大庭
今売らないほうがいいとアドバイスする役割の人がいないと、自分の判断だけでは、早く利益を確保したいという発想になってしまう投資家も多いのではないでしょうか。野尻
特に最近は売買手数料の安いネット証券が増えてきたので、頻繁に売買することへの抵抗が少なくなっているという側面もあるのかもしれません。「株価が上がったからといって売却するのは合理的ではない」(「株価が上がったときの「売りタイミング」とは 行動ファイナンスの観点でまず考えるべきこと」参照)ということを、投資家の皆さんが知らないんじゃないかと思っています。メディアでは、短期間の間に株式が上がって投資金額が倍になったなどというストーリーはよく紹介されますが、「10年20年投資を継続した結果、大きな資産をつくれた」という成功体験を語る人は少ない。もっとそういうストーリーを知る機会があったほうがいいですね。
大庭
例えばNISA制度が始まったのが2014年、10年間、売却せずに投資を継続して大きな資産がつくれている人はいるはずですよね。でも、メディアではなかなか取り上げられません。たとえばGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の運用実績は、Webで誰でもすぐに調べることができます。長期分散投資を行っている代表的な機関で、2001年度から2023年度の累積収益額は132兆円(注)にもなっています。長期分散投資がうまくいっていることには注目しないのに、短期で「何兆円の損失を出した」ということは取り上げられてしまいます。
(注)出典:GPIFウェブサイト
野尻
大庭さん、ぜひ長期投資でうまくいっている人の調査もお願いします。テレビなどでもよく「新しいNISAはお得です!」という言い方を耳にしますが、売却益や配当に対する税金が非課税になるのであって、投資をするとすぐに得するという制度ではありません。そのあたりがちゃんと理解されているか、心配になります。
大庭
得するという言葉に飛びついた人は、株価が下がったときにはびっくりして売却し、「怖いから二度とやらない」というマインドになってもおかしくないですね。そうではなくて長期投資のための手段だと思ってほしいですね。

投資をやめにくくする仕組みがあってもいい
- 新しいNISAが、つみたて投資枠と、成長投資枠に分かれている設計については、行動ファイナンスの観点ではどのような影響がありそうでしょうか。つみたて投資枠の年間投資枠は120万円で、金融機関で積立設定をすると、毎月、定期的に対象の投資信託を買い付けていくという仕組みです。
-
大庭
ゴール・ベースド・アプローチによる、資産形成がしやすくなるといえそうです。例えば、つみたて投資枠では老後資金のために長期で積立投資を設定し、簡単に売らない。一方、成長投資枠のほうはもう少し短期で、「3年後に車を買い替えたい」などの目的で投資をして、売却しながらまた投資をするといった使い分け方です。野尻
本来は、さらに投資をやめにくくする仕組みがあってもいいと思うんですよね。行動経済学では、行動を正しい方向に促す仕組みのことを、肘でつつくという意味のナッジ(Nudge)と表現しますが、私はその逆の概念のスラッジ(Sludge)に注目しています。スラッジとは、泥、ぬかるみという意味で、ぬかるみに足をとられるとなかなか進まないように、人が悪い方向に行くことを遅くする仕組みのことを言います。
大庭
投資をやめる、売却する判断を遅くするという発想ですね。野尻
そうですね。日本のNISA制度のお手本となっている一つが、英国のISAです。私はNISA導入の頃に、何度も英国のISAについての視察に行きました。ISAには「つみたて投資枠」のような区分けはありません。英国は確定拠出年金の枠が大きいので、老後資金のほうはそちらで積み立てている人が多いです。それでも、ISA枠では頻繁に有価証券の売買をする人は少ないようです。大庭
実際に、頻繁に売買をする人は長期投資を続けている人よりもリターンが低くなりがちだというデータがありますから、そういった投資のリテラシーを伝えていくのは重要ですね。
- 投資リテラシーを身に着けていなくても、新しいNISAを機にまずは少額でやってみるというのはありでしょうか。
-
大庭
それは意味があると思います。少額というところがポイントですね。まず始めてみてこういうものかと学ぶことができます。野尻
そうですね。新しいNISAが始まった2024年1月、2月は、株価がかなり上がっています。今後、調整の局面で株価が下がることも考えられるでしょう。そのとき「損してしまった」とショックを受けるのではなく、10年20年またはそれ以上先を見据えて投資を継続するといいと思います。
- フィンウェル研究所 代表
野尻哲史 - 国内外証券会社調査部を経て2006年から外資系運用会社で投資啓発活動に従事。2019年5月に合同会社フィンウェル研究所を設立し代表に。退職後のお金との向き合い方を資産運用だけでなく勤労・移住など多方面から分析する。日本証券アナリスト協会認定アナリスト、行動経済学会等の会員の他、2018年9月より金融審議会市場ワーキンググループ、2022年9月より同顧客本位タスクフォース、2023年10月より同資産運用タスクフォースの委員も務める。『60代からの資産「使い切り」法』(日本経済新聞出版)、「IFAとは何者か」(金融財政事情研究会)など著書多数。
- 野村證券金融工学研究センター エグゼクティブディレクター
大庭昭彦 - CMA、証券アナリストジャーナル編集委員、慶應義塾大学客員研究員、投資信託協会研究会客員。東京大学計数工学科にて、脳の数理理論「ニューラルネットワーク」研究の世界的権威である甘利俊一教授に師事し、修士課程では「ネットワーク理論」を研究。1991年、野村総合研究所へ入社。米国サンフランシスコの投資工学研究所などを経て、1998年に野村證券金融経済研究所に転籍、現在に至るまで、主にファイナンスに関わる著作を継続して執筆している。2000年、証券アナリストジャーナル賞受賞。
※本コラムで取り上げられた投資に関する基本的な考え方などについては、あくまで個人の見解によるものであり、野村證券の意見を代表するものではございません。
【関連リンク】