2024.02.29 NEW
岡崎良介「上昇相場の今こそ高配当株投資」 大型株から選ぶのが鍵

撮影/藤井洋平
新しいNISAの成長投資枠で、配当利回りの高い個別銘柄への投資を考える場合、どのように銘柄を選ぶといいでしょうか。エコノミスト・岡崎良介さんの考えを聞きました。(2024年2月初旬取材)
配当を重視する投資を始めやすいとき
2024年に入り、日経平均株価が高値を更新するというニュースが何度も入ってきていますね。新しいNISAを活用したいという方も増えて、「このような上昇相場で何に投資するべきでしょうか」と、投資初心者の方から聞かれる機会が増えました。
新しいNISAを活用して投資を本格的に始めたい人。それも、金融資産だけで1億円や2億円を持っている富裕層ではなく、「数百万円投資する余剰資金はあるけれども、自分は富裕層とは言えない」という方には、配当収入を重視した投資が向いているのではないかと思います。
具体的には、株価に対して年間の配当金がどのくらいもらえるかを表す「配当利回り」が高い銘柄を選んで、配当をしっかり得るという投資スタイルです。では何を選べばいいのでしょうか。
大型株を選んで、上昇相場の流れに乗る
私の答えはシンプルです。
日本経済新聞社が日経平均株価の構成銘柄から抽出した、予想配当利回りの高い50銘柄から構成される「日経平均高配当株50指数」があります。この構成銘柄(注)から選ぶのは手っ取り早いと思います。または、TOPIX100から配当利回りが高い銘柄を選ぶのもいいでしょう。
(注)日経平均高配当株50指数の構成銘柄は、日本経済新聞社の予想配当を使って、基準日である5月末の予想配当利回りの高い銘柄を定期見直しルールに基づいて選定。年に一回、6月末に入れ替えられています。構成銘柄は、こちらで調べられます。
その意味は、日本株の中でも特に大型で、配当を多く出す割安株に投資するといいのではないかということです。この方法で銘柄を探すと、事業が安定している成熟した企業が比較的多く候補に挙がるでしょう。
大型株がいいと思う理由を説明します。今、日経平均株価を押し上げているのは、外国人投資家の買いであり、外国人投資家が買うのは、TOPIX100などの大型株が中心だと考えています。
なぜ彼らによって日本株が買われているのか。いろいろな要素がありますが、個々に素晴らしい業績を出している企業があるからというよりは、日本の金利水準が主因のひとつです。
日本の金利はこれから上がると予想できますが、それにしても年0.1%程度のゆるやかな上がり方になるでしょう。それに対して米国の金利は、思ったほど急激には下がらず、日米の金利差が大きい状態が続くと見ています。
米ドルで運用している外国人投資家から見ると、日本株を買う際には、為替ヘッジを付けて買うことが増えています。簡単に言うと、米ドルを売って円を買い、日本株を買うと同時に為替リスクをヘッジするために短期のドル買い契約を結ぶという行為であり、その際に米ドルの金利が高く円の金利が安いと、金利差の分が収入となるのです(ヘッジプレミアム)。
こうした自動的に利益が生まれるような金利構造によって、外国人投資家が金利が低い日本の大型株に投資を続ける状態は、しばらく続くと予想しています。10年続くかどうかはわかりませんが、3年くらいは続くのではないでしょうか。
この3年の投資計画として、これから上がるかもしれない成長株を見つけ出して投資するよりも、「外国人投資家が買っている株を買う」という、大きな流れに乗るスタイルが合理的だと思うのです。安定的に配当を得ながら株価の上昇を期待することができるからです。
テンバガー(株価が10倍になった銘柄、なりそうな銘柄)企業などの成長企業は、配当を出して株主に還元するよりも、事業に投資するのが普通です。そして、本当に株価が上がるかどうかというと確率は低く、上がるまでの期間は3年では足りない可能性があります。
十分資産をつくれた富裕層が、将来の楽しみとして成長株投資をするのはいいのですが、これから富裕層になりたいという方は、上昇相場の今こそ、予想配当利回りの高い大型の割安株への投資を選ぶほうがいいのではないかと思います。
ROE、株主還元の方針に注目
配当利回り以外に、見るといい指標を挙げるとしたら、ROE(自己資本利益率)です。資本に対してどの程度の利益を上げているかを表す財務指標で、数値が高いほど経営効率がいいということを示します。高ければいいというものでもないですが、極端に低いものは避けたほうがよく、5%以上はあったほうが良いと思います。
東京証券取引所(以下、東証)が2023年3月、プライム市場及びスタンダード市場の全上場会社を対象に、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を要請したことはご存じのとおりです。
そして東証は、2024年1月、要請に対しての対策を開示している企業を公表しました。
※「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する開示企業一覧表の公表について | 日本取引所グループ (jpx.co.jp)
資本コストや株価を意識した経営の実現のために、自社株買いや配当を増やすことを開示している企業に注目するのも有効です。自社株買いや増配は、成熟した企業にとっては立派な株主還元策です。
東証が公表した資料を見てもいいですし、投資候補の企業のIR情報などを見るのもいいでしょう。
株主還元施策を開示している企業の代表例としては、トヨタ自動車(7203)は2023年3月に、「安定的・継続的に増配を行うように努める」方針を示しています。また、三菱商事は2024年2月に、5000億円を上限とする自社株買いの方針を示しました。
母集団は大型株と決めて、今後の株主還元方針をチェックしながら投資先を選ぶことができるようになれば、立派なストックピッカー(優秀な銘柄選択者)と呼んでいいでしょう。
10%程度の下落は買いのチャンス
TOPIX100などの指数に注目すると、上昇相場であっても一時的に10%くらい下落することは3年くらいのスパンで見ると1~2回はあるでしょう。5%程度ならもっとあると思います。個別株で考えると、20%ほど下落することもあるかもしれません。その原因が、期待にやや届かなかったという意味合いでの業績の小さな下方修正なら心配しなくてもいいでしょう。
興味のある割安大型株について、10%程度の下落があったときは買いのチャンスだと思っています。たとえば、来月、再来月に買おうとしていた計画を変えて、前倒して買うなどの行動をしてもいいかもしれません。
NISAの成長投資枠は、年間240万円が投資金額の上限で、個別銘柄を購入することができます。この枠で投資した銘柄の配当収入には、通常は約20%かかる税金がかからないのがメリットです。
※NISA口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、 証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。
この枠の範囲で買うと決めて複数銘柄を選ぶのもいいですし、金銭的な余裕があれば、NISA口座以外でも株式を購入し、合計で10銘柄程度を持つとさらに分散効果が期待できます。
お話ししてきた上昇相場の投資の考え方は、個別株投資ではなく投資信託やETF(上場投資信託)で投資したい場合も共通すると思います。配当利回りの高い企業や割安大型株を選んで投資するタイプを選ぶといいでしょう。
- エコノミスト 岡崎良介
- 1983年、慶應義塾大学経済学部卒。伊藤忠商事に入社後、米国勤務を経て87年野村投信(現・野村アセットマネジメント)入社、ファンドマネジャーとなる。93年バンカーストラスト信託銀行(現・ドイチェ・アセットマネジメント)入社、運用担当常務として年金・投信・ヘッジファンドなどの運用に長く携わる。2004年フィスコ・アセットマネジメント(現・アストマックス投信投資顧問)の設立に運用担当最高責任者(CIO)として参画。2012年、独立。2013年GAIAの投資政策委員会メンバー就任、2021年ピクテ投信投資顧問客員フェロー就任。
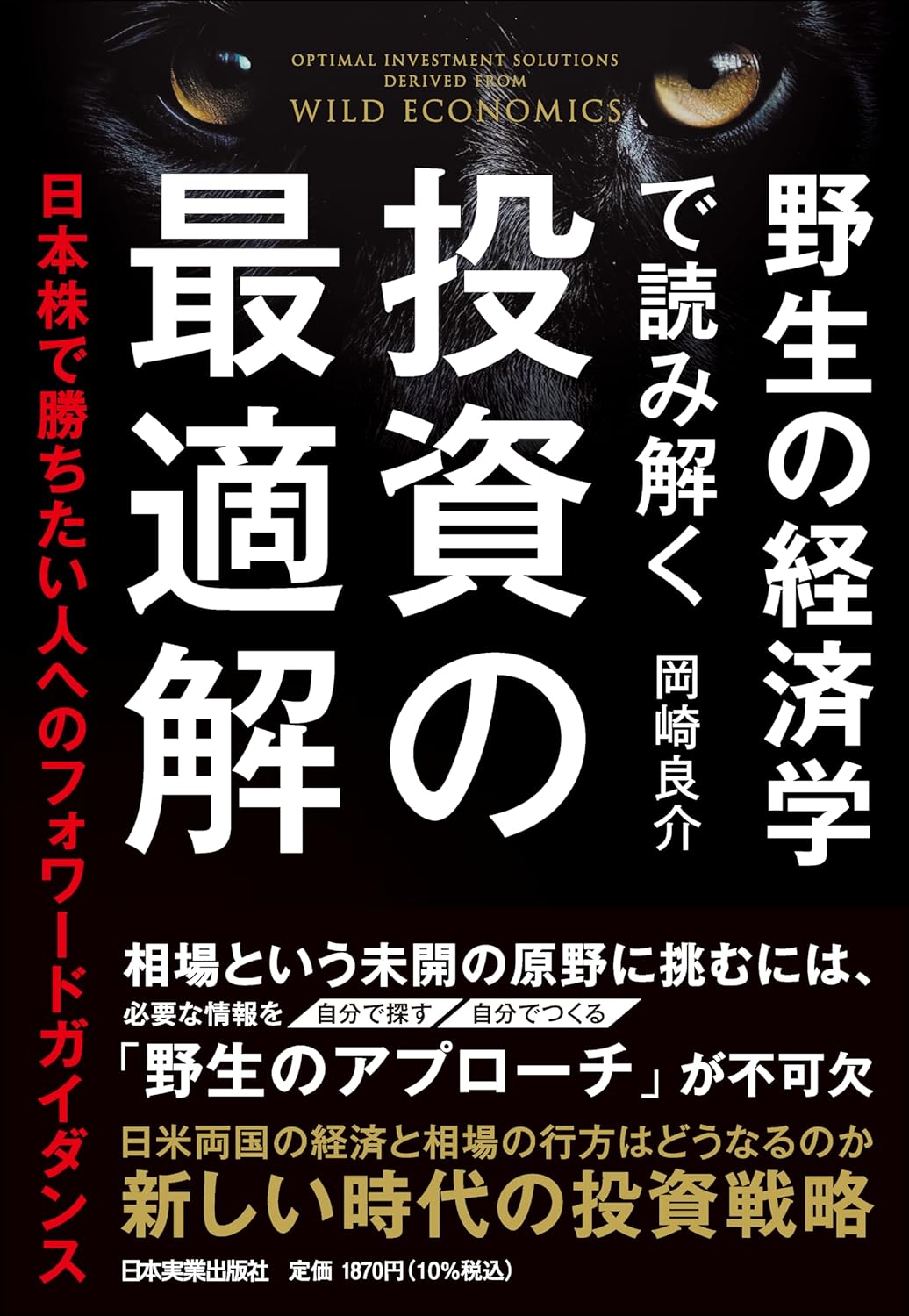
日本株投資の戦略について詳しく解説した近著『野生の経済学で読み解く 投資の最適解 日本株で勝ちたい人へのフォワードガイダンス』(日本実業出版社)。
※本記事は、インタビュー対象者の株式投資に対する基本的な考え方等についてご参考として記載しています。ここで言及している株式投資の基本的な考え方や特定の上場銘柄の解説等は、あくまでインタビュー時点の個人の見解によるものであり、野村證券の意見を代表するものではございません。銘柄の選択や投資の最終決定にあたっては、ご自身でご判断ください。
【関連リンク】