2024.06.03 NEW
コモンズ投信 伊井哲朗社長「議決権行使は長期投資を成功させる一歩」
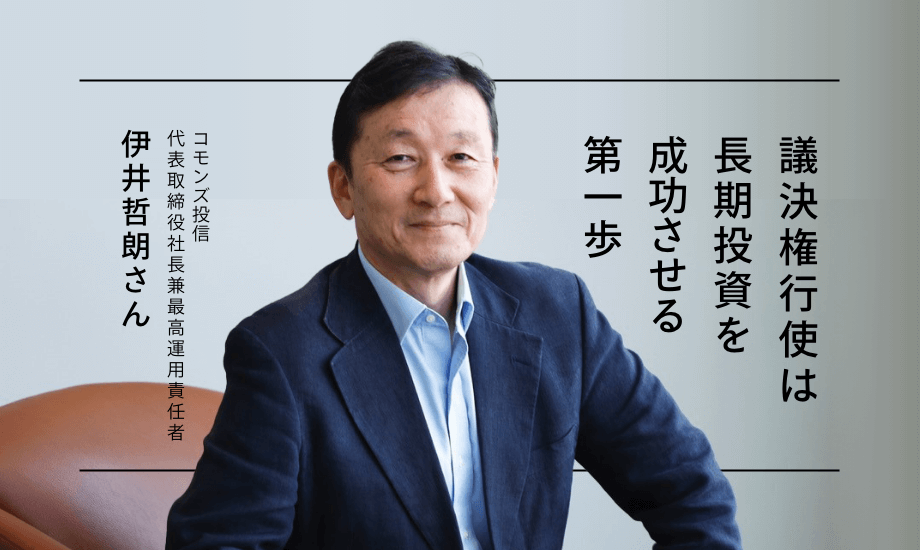
6月は株主総会が多く開催されます。1単元の株式の保有に対し1票の議決権があり、個人投資家も株主である企業の経営方針に対して決議する権利を持っています。議決権行使について、どのように考えるといいでしょうか。企業との対話に詳しいコモンズ投信・伊井哲朗社長に聞きました。(インタビュー日:2024年5月24日)
- 株主総会のシーズンがきました。個人投資家も株主である企業の議決権を持っていますが、そもそも議決権を行使することにはどんな意味があるのでしょうか?
-
私は、これから個人投資家の時代が来るのではないか、と思っています。東京証券取引所(以下、東証)が公表している「2022年度株式分布状況調査の調査結果について」という資料を見ると、日本株にとってのメインの投資家の変遷がわかります。
誰がメインの投資家なのかによって、企業の株主への向き合い方は変わります。1980年代までは、日本株保有者の分類としては「都銀・地銀等、生・損保、その他金融」が最も多かったのです。いわゆる「株の持ち合い」ですね。株主としての金融機関が企業に何を求めるかというと、「融資はわが社で」「従業員の給与振込口座はわが社で」「保険の団体契約をしてください」といった具合でしょう。
株の持ち合いの場合、株主としてはビジネスで恩恵を受ければよくて、値上がりを目的に株式を保有しているわけではありませんから、企業に対して株価を上げる要請をすることもあまりなかったでしょう。バブル期にPERが60倍などの水準になっていても、売却のアクションが起こりにくかったと思います。
ところが金融危機などを経て、金融機関による株の持ち合いは規制されることになりました。金融機関が持つアセットが株式だと、金融危機によって余計お金が回らなくなるからです。1990年代後半からは、金融機関は株主としての存在感を急速に失っていきます。
代わりに台頭してきた株主が、「外国法人等」に分類されている、いわゆる海外の機関投資家です。東証のデータによると、2022年の時点では株主の3割が外国法人で占められています。
海外の機関投資家は、企業に対してガバナンスの強化、ROE(株主資本利益率)の改善、株主還元など、株価上昇に向けてのアクションを求める傾向があります。特にヨーロッパの投資家は、環境にいい経営をしているか、人権問題はないかなど、ESG観点での改善を求めることがあります。この影響は大きく、企業経営の在り方を変えています。
では、これからもこの外国人投資家たちの影響力は増すのかというと、世界のGDPにおける日本企業の割合からいっても、それほど大きくは増えないと思っています。そこで、注目したいのが個人投資家です。
先に示した東証のデータは2022年までしかありませんが、その時点で株主の17.6%が個人投資家です。新しいNISAの影響もあり個人投資家は増えていくと予想しています。
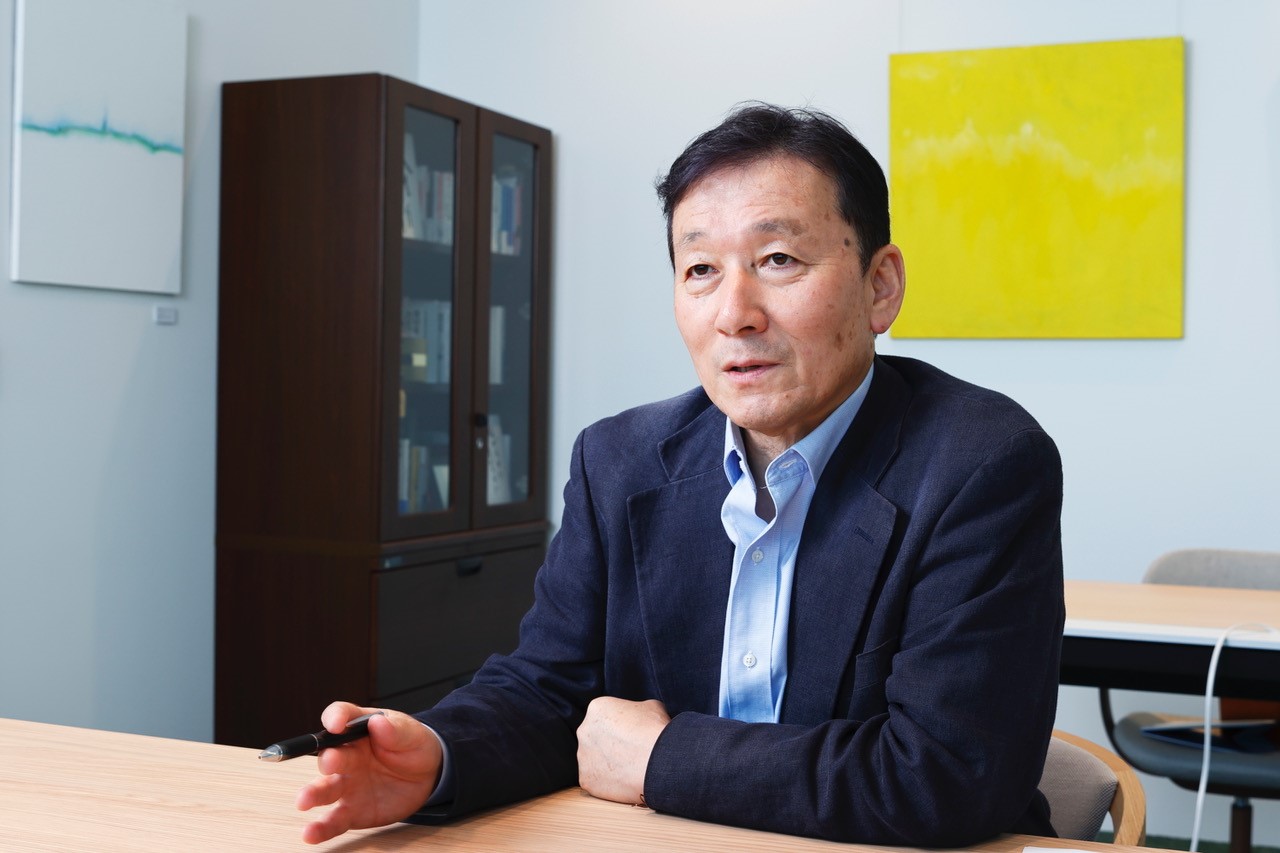
- 個人投資家も株価が上がってほしいと思うわけですが、海外機関投資家との視点の違いはなんでしょうか。
-
個人投資家は、投資家である前に消費者でもあり、同じ社会の一員です。機関投資家と最も違うのが時間軸ですね。海外機関投資家は、株価が上がるまでじっくり待つというスタンスに立つことはできず、企業経営がすぐに改善されないのなら売却します。個人は、消費者として共感できる会社の株を長く持つという選択ができます。
企業側も、個人投資家に長期で株を持ってもらいたいと願っていることが多いと思います。その証左が株式分割です。東証が公表している「投資単位の引下げの状況」というデータによると、1990年時点では投資単位が50万円未満の銘柄はほとんどありませんでした。それが、2024年3月末時点では93.3%の銘柄が投資単位50万円未満となっています。
東証は個人投資家が投資しやすい環境を整備するために望ましい投資単位を50万円未満と明示していますし、企業も個人投資家に株を持ってほしいという思いがあるので、株式分割が進んでいると考えられます。株主優待を充実させる企業がまた増えているのも、個人投資家を意識した施策でしょう。
- 企業にとっても個人投資家が増えることはいいことでしょうか。
-
そうですね。企業は、自社の商品やサービス、取り組みに共感してくれる“ファン株主”を増やしたいのです。個人投資家も、“推し活”として企業を見て、企業がより良くなるための意見を株主総会で議決権行使という形で表明するといいでしょう。選挙と同じで、参加することでさらに企業に興味が湧いてきますよね。
興味が湧いて応援したい気持ちになったら、株価が上がっても下がっても落ち着いていられるかもしれません。価格が理由で買った株は、上がれば売りたくなりますが、応援している企業なら長期で持つ気持ちになれるでしょう。株式投資は長期で行ってこそ意味があると思うので、会社の議案に目を通し議決権行使をして興味を持つことは、長期投資をうまくいかせる一歩であり、個人投資家の利益にもつながるのです。
最近は企業が提出する議案について、賛否を機関投資家に助言する議決権行使アドバイザーの存在感が増しています。企業にとっては、同じ長期投資の目線で考えてくるファン株主の層を厚くすることは大切なのです。

- 株主は、株主総会の招集通知が届いたら、どういうところを見るといいでしょうか。
-
まず、招集通知は大事ですね。個人投資家のほうを向いている企業は招集通知もわかりやすく充実しています。書かれている議案について、ホームページなどで情報収集しながら、自分は賛成できるか否かを考えるのがいいでしょう。
- どんな観点で賛成するか否かを考えるといいでしょうか。
-
いい方向に進んでいると思うことは賛成し、もし「もやっとする」ことがあったら、反対票を投じたらいいと思います。票を入れることですぐに変わらなくても、だんだん変わってくることがあります。その変化に興味がわいてきます。
コモンズ投信は、保有している株式について反対票を投じる議決権行使を行ったときにはそのことを開示しています。議案に反対するよくある例としては、取締役や社外取締役の選任があります。
例えば、取締役に女性がいない場合。消費者の半分が女性であるのに、取締役に女性がゼロなのは偏っていると考えます。社外取締役が少なすぎる場合も、外部の知見を十分生かせていないという意味で反対することがあります。なお、社外取締役として10年以上在任している方がいる場合は、その方の知見はもう十分取り込んだということで、内部の取締役と同じカウントをします。
一定のガイドラインを設けて抵触したら機械的に反対するのではなく、抵触の事実を真ん中に置いて、なぜそうなっているのか、どうしたら解決できるのかを企業と対話することが大切だと思っています。その結果、改善に向けて動いている途中だとか、理想通りにいっていないことに納得できる理由がわかれば、ガイドラインには抵触していても賛成で出すと決めることもあります。
- コモンズ投信のスタンスは、まだ日本では珍しいですか。
-
そうですね。私たちは厳選した企業に長期で投資し、企業とは対話をすることをポリシーとして15年間運用していますが、もう少し仲間が増えてほしいとも思います。長期目線で投資をする機関投資家は、経営者と同じように10年先30年先まで一緒に考える存在として、よい壁打ちの相手になるようです。
- 個人投資家の意見が、企業経営を変えている例は出てきていますか。
-
欧米では例えばコスメの企業がプラスチックを多用する商品を出せば、株主である個人投資家から賛同を得られないので、商品の作り方から変わっています。特にZ世代といわれる20代前後の若い世代は、環境に関心を持っており、企業の姿勢にもそれを求める人が増えていると聞きます。
そういった若い人の風潮は、ネット社会では垣根なく日本に波及してくるので、今後は欧米と同じ流れが出てくると考えています。
- 自社株を持っている場合はどのように考えるとよいでしょうか。
-
一定の自社株を持つのはとても意味があると思います。株主であり消費者であり、社員でもある人が、会社をより良くするアクションを起こせるわけです。忙しい毎日のなかでも、一歩引いて会社のガバナンスや方向性を考えるきっかけになると思います。
株主総会のシーズンを機に、自分が株式を保有する企業の経営について考える習慣をもってほしいですね。
- ありがとうございました。

- コモンズ投信 代表取締役社長兼最高運用責任者
伊井哲朗さん - 山一證券で営業企画部に約10年間在籍し、マーケティングなど担当。その後、機関投資家向け債券営業を経験。メリルリンチ日本証券、三菱UFJメリルリンチPB証券で法人・個人向け営業を約10年経験した。コモンズ投信創業と共に現職。2012年7月から最高運用責任者兼務。
※本コラムで取り上げられた投資に関する基本的な考え方などについては、あくまで個人の見解によるものであり、野村證券の意見を代表するものではございません。