2024.09.04 NEW
成長株投資の祖が創設したティー・ロウ・プライスに学ぶ 米国成長株投資の長期的視点
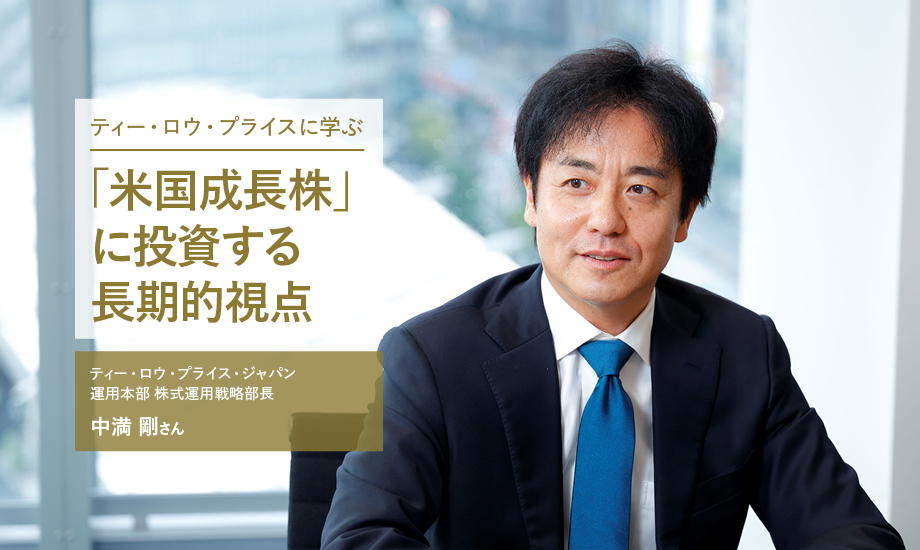
写真/タナカヨシトモ
米国株市場のなかでも、特に長期の値上がりに期待する成長株投資をする際にはどのような視点を持てばいいのでしょうか。ティー・ロウ・プライスは、「成長株投資の祖」と呼ばれるトーマス・ロウ・プライス Jr.が創設した80年以上の歴史を持つ運用会社です。その脈々と受け継がれる成長株投資の投資哲学について、ティー・ロウ・プライス・ジャパン 運用本部 株式運用戦略部長の中満剛さんに聞きました。
- S&P500は2024年7月中旬にかけて史上最高値を何度も更新しましたが、8月上旬には株価急落を経験しました。米国株式市場の好調さが注目される一方、「バブルではないか」という声も聞かれます。現在の米国株式市場をどのようにみていますか。
-
中満剛さん(以下、同)
株価の構成要素とは大きく分けると企業業績とバリュエーション(企業の利益・資産などの企業価値評価)です。そのうち企業業績については、特にAI(人工知能)関連、テクノロジー企業を中心に昨年底打ちし、大きく成長しました。他の業界でもこれから業績が底打ちし、今後もっとよくなるだろうと予想できる局面です。一方、株価のバリュエーションにとってインパクトが大きい要素が金利動向です。利上げ局面においては、企業業績がいいのに株価が下がるということがあったのですが、今後は利下げに向かう局面ですので、金利の影響で株価が大きく下がるという現象は起こりにくいでしょう。
一時的な株価下落はありましたし、確かに、歴史的に見て株価水準はやや割高ですが、これはバブルなのかというと、そのような印象はありません。

- 大型株、特にマグニフィセント・セブン(注1)と呼ばれる7社のテクノロジー企業に投資が集中しすぎているという見方についてはどう考えますか。
-
(注1)アマゾン・ドット・コム、アップル、アルファベット、マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ、エヌビディア、テスラの米国テクノロジー企業7社の総称
確かにマグニフィセント・セブンの平均PER(株価収益率)は、30倍程度です。S&P500の、それ以外の銘柄は平均PERが17~18倍くらいですので、相対的にマグニフィセント・セブンの株価が高いと見ることもできるのですが、一方ROE(自己資本利益率)にも注目すると印象は変わります。
マグニフィセント・セブンのROEは約35%で、S&P500のそれ以外の企業のROEは平均17-18%くらいです。つまり、長期の成長性や収益性とリンクする形で株価が上がっているといえます。今の成長が維持されれば、株価が高すぎるという水準ではないでしょう。また、他の業界の株価は割高ではないから、米国株式市場全体としてもまだアップサイドがあるという見方もできます。
以上の理由により、米国株式市場はまだ伸びる余地があると考えていますが、一方で警戒心を持つことは必要です。特に重要なのは、金利です。
2024年はインフレがピークアウトし、米国の利下げが数回あるだろうという市場の見方もあったのですが、私たちはもともとそう都合よくいかないだろうと予想していました。足元の減速を受けてこれから利下げが早まる可能性もありますが、インフレの後退は思ったよりも緩やかで、金利もコロナ前の水準にはなかなか戻らないと考えています。
金利が下がらないということは、株価のバリュエーションにプレッシャーがかかり、また企業業績にも少なからず悪影響を及ぼします。そのため私たちも、思い切りアクセルを踏むのではなく、警戒しながら運用しているという状況です。
私たちのファンドのうちいくつかは、マグニフィセント・セブンなどテクノロジー企業への投資を早くから開始していたため、良い運用成績を出すことができましたが、それ以外の収益機会もあると見て、バランスの取れたポートフォリオで臨んでいるところです。
- 例えばどんな観点で、マグニフィセント・セブン以外の投資を検討するのでしょうか。
-
ひとつはヘルスケア分野です。肥満症治療のために承認されたGLP-1受容体作動薬などはすでに知名度が高くなっていますが、私たちは早くから投資を開始し、収益機会を得てきました。それ以外にもイノベーションによってアルツハイマー病、がん、遺伝子疾患などの治療法の開発が進んでいます。ロボット手術や電子カルテなどITを活用した医療技術・サービスも発展すると考えています。
また、ソフトウエアやAIによるデジタル・イノベーションに引き続き注目していますが、エヌビディアのような半導体大手企業だけではなく、その周辺にも収益機会が広がっているのです。
例えば、半導体などの需要が増えると、製造過程で欠かせない高純度の水やガスを供給するための装置が重要になってきます。またAI向けの半導体GPUは多量の電力を使用するため、配線や送電の設備や周辺機器を提供する会社にも注目が集まりそうです。一見地味ですが、半導体需要が高まることによる波及効果を得る企業が多くあるのです。
こうした企業の多くは中小型株です。中小型株は大型株に比べると株価上昇が出遅れることが多く、いつ追いつくのかを判断するのは難しいのですが、それだけに収益機会もあり、成長が見込まれる中小型株を選んで投資するアクティブ・ファンドに優位性があると考えています。特に米国株の場合、大型株はグローバル企業ですが中小型株は米国国内事業比率が高く、堅調な米国経済の恩恵を受けやすいともいえます。
私たちは、約200名のリサーチ人員を抱えているため、中小型株まで目が行き届きます。また、未公開企業への投資も行っていますので、有望な中小型企業を早い段階から見出すことが可能になります。中小型株にもいろいろありますが、特に収益の安定性・持続性があり、経営陣の評価が高く、バランスシートが健全であるクオリティ企業と呼ばれる銘柄を選んでいます。米国の中小型企業に投資するファンドのレポートで、組み入れ上位銘柄を見ていただくだけでも発見があると思います。
- ティー・ロウ・プライスは、創始者が「成長株投資の祖」と呼ばれるほど、創業当時から成長株への投資を得意としてきたと聞いています。マグニフィセント・セブンへの投資が早くからできていたのも、運用スタイルによるところが大きいのでしょうか。
-
そう思います。簡単に当社の歴史をお話しましょう。創始者のトーマス・ロウ・プライス Jr.は、1937年に米ボルティモアにてティー・ロウ・プライスを創業し、1950年に初めての投資信託を立ち上げました。当時は、株価をどう評価するかという手法が確立していなかった時代です。
その頃から、トーマス・ロウ・プライス Jr.は顧客利益を第一に考え、予想すべきは株価ではなく企業の将来の業績であるという長期的視点を持っていました。米国の著名な投資家、ウォーレン・バフェット氏が生まれたのが1930年ですから、いかに早くから企業の成長という要素に注目していたかがおわかりいただけるかと思います。
そこから脈々と、企業の成長に注目する企業文化をつないでいます。現在は企業の成長を見越して投資し続けるだけでなく、盤石なリサーチ体制のもと、リスクを適切に管理し、冷静に市場を見ながらファンドを運営する方針をとっています。
- 企業の将来の成長を把握するために、どのようなチーム体制をとっていらっしゃいますか。
-
特徴的なのはコラボレーションという文化です。よく米国系の運用会社というとカリスマファンドマネジャーがいて、運用成績がいいときは莫大な収入を得るが、成績が悪くなると解雇されるという、シビアなイメージをお持ちの方もいるかもしれません。ですが、ティー・ロウ・プライスは、競争ではなくお互い協力しあうことでいい成績を出せるという文化を持っています。
例えば、ある大企業の担当アナリストがいるとします。企業の成長性や業績を調査・分析するのはその人ひとりではありません。前任者も、その前任者も社内にいることが多く、彼等との活発な議論により投資アイデアが洗練されます。
年に一度、歴代のアナリストたちを含めたポートフォリオ・マネジャーやアナリストのグループが揃って米国西海岸の企業を訪問するといった、実地での調査も大事にしています。そこでは大企業ばかりではなく有望な未公開企業も訪問することで、新しい成長分野の発掘や業界の変化を捉えることが可能になります。投資対象の発掘という点でも、企業が上場してから注目するのではなく、上場の何年も前から情報交換を行い、ときにはアドバイザリーボードとして経営にも参加しているので、成長する企業の情報を早くからつかむことができるというメリットがあります。

- そのような体制で見つけることができた成長企業の例はなんでしょうか。
-
エヌビディアもそうですね。まだ株価が低かった2022年終盤頃に、その頃の市場コンセンサスよりも4~5倍の利益規模になることを予想し、投資を判断していました。
2022年に、ChatGPTが出始めた頃、社内のアナリストやポートフォリオ・マネジャーたちの間で熱い議論が繰り広げられていました。「いよいよAIが本格的な離陸期に入っている。生成AIは、世の中で考えられているよりもはるかに大きな規模になりそうだ」という議論です。その恩恵を受ける企業は何かと考えたとき、代表的な存在がエヌビディアをはじめとするテクノロジー企業であるという結論に達し、早い段階で投資行動につなげられたと思います。
また、過去にはメタ・プラットフォームズや旧Twitter社、ARM社にも株式公開前から投資していました。ネットフリックスは、DVDの通販事業の会社でしたが、2007年にストリーミング配信に乗り出しました。その頃から投資していて、10年以上かけて株価が30倍以上になりました。
- 長期的視点を持てる人材育成の工夫もあるのでしょうか。
-
はい。人材が定着しているというのが弊社の大きな特徴で、ポートフォリオ・マネジャーの平均在籍年数は約17年です(2023年12月末時点)。過去40年間近くポートフォリオ・マネジャーは外部から採用したことはなく、すべて内部からの昇格です。
「今新しいファンドをつくったらうまくいきそうだ」という事業アイデアがあったとしても、それに見合うポートフォリオ・マネジャーの人材が社内にいなければ、外部から採用してまで新規ファンドを立ち上げるということはしません。社内で適切な人材が見つかる、もしくは育つまで待ちます。
株式市場の危機のときにも安易に人員整理をすることはありませんでした。また、ポートフォリオ・マネジャーの評価は、純粋にパフォーマンスのみを見ており、一般的に重視される運用残高は評価に入らないというのも特徴です。また長期間のパフォーマンス評価ほどウェイトが高くなっています。
一般的な運用会社では、マネージング・ディレクターという職位の高いポストがありますが、当社はこれを20年以上前に廃止しました。昇進争いによる社内政治を排除し、純粋に顧客のために仕事をする文化が強まったと思っています。
こうした企業文化に共感して入社している社員ばかりなので、安定して運用業務に携われるということもあると思います。
- アクティブ・ファンドにもそれぞれの方針がありますが、運用会社の長期視点での哲学を知ると、自分も長く投資しようという気持ちが高まりますね。最後に、米国株式市場への投資の醍醐味を教えてください。
-
やはり、成長企業の前向きな変化を感じることでしょうか。米国企業は大胆なイノベーションを繰り返し、大きく成長します。そのダイナミックさを感じて、知的好奇心を満たしながらリターンも享受するという運用スタイルを感じていただけたらと思います。

- ティー・ロウ・プライス・ジャパン
運用本部 株式運用戦略部長
中満 剛さん
*本コラムにおいて個別銘柄に言及していますが、当該銘柄を推奨するものではありません。本コラムで取り上げられた投資に関する基本的な考え方などについては、あくまで個人の見解によるものであり、野村證券の意見を代表するものではございません。