2024.10.11 NEW
「今度株価が下がったら投資しよう」と思っている人がずっと投資できない理由
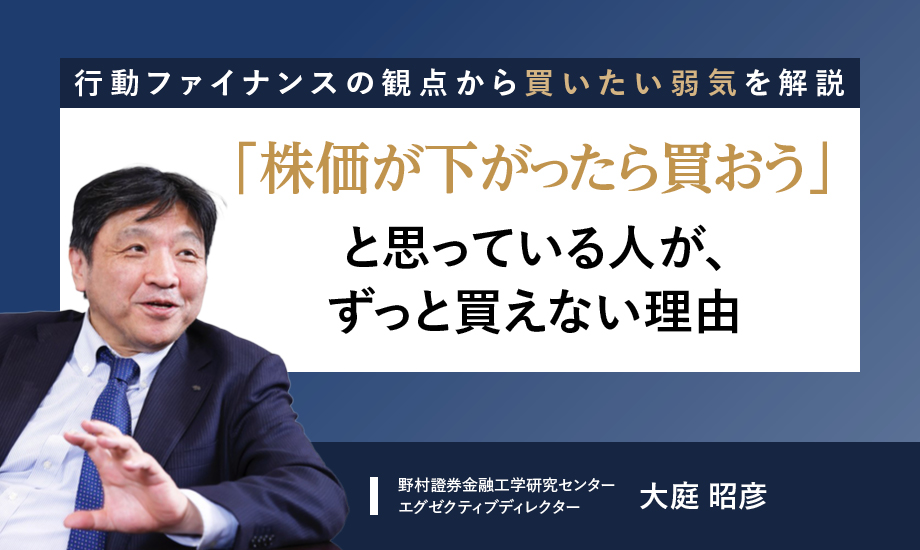
2024年8月5日、日経平均株価は4,451円という過去最大の下落幅を記録しました。翌日には急反発し、上昇幅は3,217円と同じく過去最大を記録。それ以降も、株価のボラティリティが高い状態が続いています。
「次に株価が下がったら今度こそ投資をしよう」と構えている人もいるのではないでしょうか。しかし、実際に株価が下がってもなかなか踏ん切りがつかないという経験をしている人もいると思われます。その裏にある人の心理はなんでしょうか。行動経済学に基づく投資理論である行動ファイナンスを専門とする、野村證券金融工学研究センターの大庭昭彦が解説します。
認知的不協和により、本来の株式投資の目的を忘れてしまう
- 株価を見ながら「もうちょっと下がるのを待って投資しよう」と思っている投資家がいるとします。しかし、株価が下がったと思ったらすぐに上がってしまうなど、なかなかタイミングをつかむのが難しいですよね。
-
そもそも、株式投資をしようと考える方は「これから株価は上がるだろう」と考えているから投資をするわけですよね。しかし、投資を始めるときは、株価が下がれば買いたいという気持ちになる。そこに心の矛盾があります。昔から伝わる相場の格言に、「買いたい弱気」というものがあります。「相場の先高観が高まっても、もう少し安くなってから押し目を拾いたいという心理が支配すること」を表します。
もともとは「上がると思っていたから買いたかった」はずが、株価を見ているうちに「下がることを期待する」、さらには「下がると確信してしまう」のが「買いたい弱気」です。それなのに、実際に株価が下がると「実はもっと下がるんじゃないか」とか、「そもそもなぜ買おうと思っていたんだっけ」と心が揺れて、結局買えなくなるということはありがちです。
逆に、株式を売りたいのに「もっと株価が上がってから売ろう」と思ってしまい売り時を逃す現象を「売りたい強気」という格言で表します。
- まさに株価が下がったらそれはそれで今買っていいんだろうかと迷いが生じる人はいるでしょうね。こういう心理になるのはなぜなのでしょうか。
-
ひとつは、本来の目的である「長期で株価が上がると見ているから今投資する」という考えが薄れてしまって、短期的に株価を見ていることが原因でしょう。人は自然には短期に物事を考えやすいというバイアスです。
もうひとつ、認知心理学的な説明ができます。例えば「株価が上がると思っているのに、株価が下がるのを望んでいる」という矛盾(不協和)があることを認知的不協和といいますが、この矛盾から逃れたくなる感情を認知的不協和バイアスと呼んでいます。
本来は「長期視点では株価が上昇するだろう」という見方については、株価の統計データなどを参考に合理的判断ができていたはずが、「これからもっと下がるかもしれない」「そもそも株式投資をするのは得策じゃない」など、本来と違った見方のほうを正当化し、決定麻痺に陥ってしまいます。認知的不協和から逃れたい心理では、本来持っていた合理的な判断基準を忘れてしまいがちなのです。
この話をするときには、イソップ物語の中の寓話「キツネとすっぱいブドウ」を思い出すといいでしょう。キツネはブドウが食べたいのですが、高いところにあって手が届かないので、「あのブドウはすっぱい」と思い込むようにしてあきらめました。
キツネが「手に入らないものに価値がある」という心理的に都合の悪い状況を解消するため、本当は価値がない(ブドウはすっぱい)という新たな事実を心の中で作り出してしまう話です。
同じことが株式投資において心の中に起きている状態です。
「下がったら買おう」は誰にとっても難しい
- 自分の中の矛盾が、株式市場の見方をずらしてしまったわけですね。そうこうしているうちに数年経ってしまって、投資機会を逸してしまいます。どうしたら投資を始められるようになるでしょう。
-
まず、株価が下がったら買うということは誰にとっても「言うのは簡単だが実行は難しい」ことの典型であることを認識してください。
その上で、本来持っていた「長期で株価が上昇するだろう」という見方が変わっていないなら、初心の長期投資に立ち戻り、その時の株価にはとらわれずにスタートする。スタートするのは早いほうが投資期間を長く取れるという認識をするといいでしょう。一度に資産を株式にうつすのは心理的にハードルが高いので、一部から始めてみるのもいいと思います。
少額でもいったんスタートし、慣れてしまえば判断に要するコスト(大変さ)が低下していくので、続けやすくなると思います。
この先もたびたび認知的不協和に陥るのを防ぐために、自分の将来の行動に制約をかける「コミットメント」という考え方をするといいでしょう。例えば投資方針書をつくり、投資アドバイザーと共有するという方法があります。
投資方針書というのは、自分の資産の何%を投資するか、何%下落したらリバランスするかといった行動規定や、銘柄選択の尺度、モニタリングの方法を細かく記したものです。第三者と共有するためのものですが、自分で持っておくだけでも意味があります。買う段になって、「やっぱりもう少し株価が下がったら…」などの迷いを減らせるでしょう。
特に代表的なコミットメントが自動積立です。これは将来の自分に、「毎月いくらずつ投資信託を購入する」などと約束することを仕組み化したといえます。積立投資は、時間分散によりリスクを低減できることがメリットとして挙げられますが、心理的にも投資を続けやすくする方法なのです。

- 野村證券金融工学研究センター エグゼクティブディレクター
大庭昭彦 - CMA(日本証券アナリスト協会認定アナリスト)、証券アナリストジャーナル編集委員、慶應義塾大学客員研究員、投資信託協会研究会客員。東京大学計数工学科にて、脳の数理理論「ニューラルネットワーク」研究の世界的権威である甘利俊一教授に師事し、修士課程では「ネットワーク理論」を研究。1991年、野村総合研究所へ入社。米国サンフランシスコの投資工学研究所などを経て、1998年に野村證券金融経済研究所に転籍、現在に至るまで、主にファイナンスに関わる著作を継続して執筆している。2000年、証券アナリストジャーナル賞受賞。
※この記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。 また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。