2025.03.27 NEW
米国の経済成長シナリオはトランプ政策で崩れないと見る理由 米国野村證券・雨宮愛知
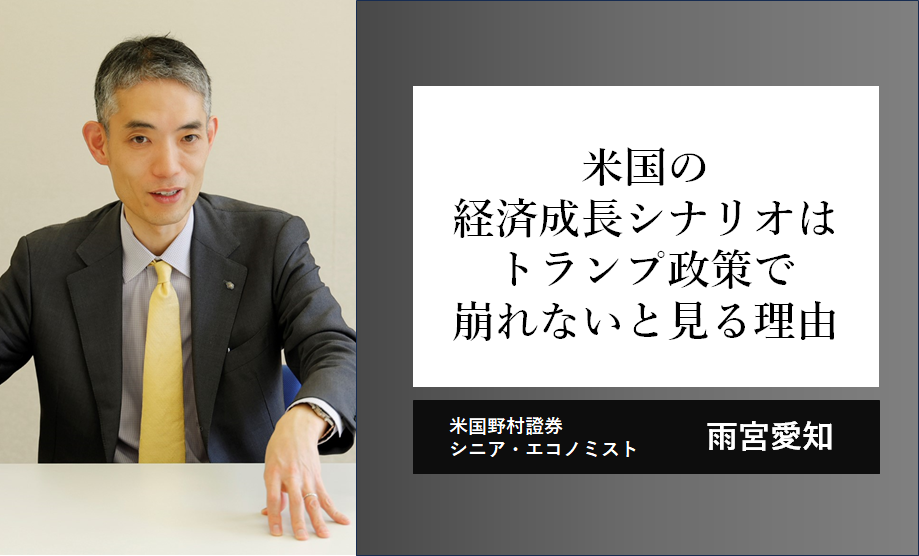
写真/タナカヨシトモ
トランプ第2次政権による関税政策が徐々に明らかになり、2025年2~3月は米国株式市場が大きく下落する場面がありました。市場では米国の景気後退懸念もありますが、野村證券は米国の経済成長は続くと見ています。米国野村證券シニア・エコノミスト雨宮愛知が解説します。

今の米国は、基礎体力は下がっていないが“風邪を引いた”状態
この4年間、新型コロナウイルスのパンデミックの後、米国の“基礎体力”は上がったと思っています。政府が大量に補助金を配った影響で、企業も家計もバランスシートが正常化しました。企業の開業率、労働生産性、潜在成長率などが上がっているなかで、長いタームでの経済成長が予想されていました。
それがトランプ第2次政権スタート後、2025年2~3月は米国の株価が急落する場面が複数見られ、米国の景気後退懸念も聞かれます。
私は今の米国経済の状態を人体に例えると、「基礎体力は上がったけれども、風邪を引いてしまった」状態だと考えています。短期的には“ひどい風邪”を引いているが基礎体力までは失ってはいない、つまり米国の経済成長を裏付けるストーリーが崩れてしまったわけではないと思います。
では、ひどい風邪とはどんな内容なのでしょうか。主に4つあります。
1つ目は関税政策で、これが最も大きいインパクトがあります。トランプ政権が掲げた関税政策が実行されると、第1次トランプ政権の経験からいって輸出業者が自発的に売値を下げて関税分を吸収するとは考えにくく、増税やインフレという形で米国民が負担することになります。
2つ目は移民政策です。移民の流入量を減らすと、米国経済を支える労働力が不足します。これは関税に比べるとインパクトは小さいと考えられます。
3つ目が不確実性です。トランプ政策によりこの先が見通せないため設備投資や広告をやめておこう、という判断が企業側に働くことで経済成長にストップがかかるという見方です。
4つ目が、イーロン・マスク氏率いるDOGE(政府効率化省)です。DOGEは、連邦政府職員の解雇を進めるなどの歳出削減を計画しています。連邦職員だけでなく、政府業務を請け負っている企業でも解雇が発生するなどの話も出ていて、これが失業率の上昇につながるのではないかと警戒されています。
関税政策の痛みはマーケットが過大評価している可能性
2月以降、4つの要素が絡み合って米国の株価が下がったわけですが、マーケットが痛みを過大評価していると思われる要素もあります。
関税政策については、トランプ政権が“高いボール”を投げて、やり過ぎて戻すというケースが見受けられます。例えば、2月4日に対中関税の10%引き上げを宣言した際には、申告額が800ドル以下の少額貨物における「簡易通関制度」を厳格化し少額貨物にも関税をかけるとしました。しかし、貿易実務を担う現場から少額貨物に関税をかけるのは非現実的だという声が上がり、今も無関税の状態が続いています。
3月4日にメキシコ、カナダへの25%の追加関税が発動された際は、3月5日に関税の対象から自動車メーカーを一時的に適用除外すると発表しました。さらに、6日には北米自由貿易協定に代わる「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」の下で出荷される貨物については適用除外とし、関税はいわば骨抜き状態になったわけです。銅や木材の関税については、「調査を開始する」とアナウンスしました。調査には相当の時間を要するため、追加関税開始について事実上延期されることになります。
このようにトランプ政権が勢いで関税政策の強化を宣言した後で緩和したりやめたりすることが続いています。判断に影響しているのは株価の急落だけではなく、自動車メーカーや現場からの「これでは立ち行かない」という抗議の声が大きいと思います。
3月26日(日本時間27日早朝)には、米国が輸入する全ての自動車に一律で25%の関税を課すと発表されました。しかし、メキシコ・カナダからの自動車部品輸入については、米国で加工された付加価値分については関税を免除する規定が盛り込まれるなど、不透明な部分も大きい状況です。4月2日の関税発効日までに自動車業界からの反発も予想され、メキシコ・カナダ関税の時のように、トランプ政権が修正を加えるかどうか注目されます。
これとは別に、4月2日には相互関税に関する全体像が明らかになる予定ですが、今後はマーケットにとってサプライズになる関税政策が急に出てくることは減り、ある程度計算された動きになると思います。相互関税については、パブリックコメントを募集するなど事前調査が実施されており、企業の声も聞くようになっていますので、「これなら持続性がある」と考えられる政策が出てくるのではないでしょうか。具体的には、貿易相手国15位までに、関税10%を課すところから入るのではないかと考えています。この程度ならマーケットも覚悟していると見られ、株価急落を免れると思います。
もう少し政治的に考えますと、来年には中間選挙があります。トランプ大統領としては中間選挙のタイミングでインフレが加速している状態は避けたいはずですので、関税政策を打ち出してくるのは今年の前半がピークでしょう。不確実性の高い状態が1年も2年も続くとは考えにくいです。

野村では米国のリセッションを予想していない
冒頭で米国は「風邪を引いている」と表現したとおり、野村では米国がリセッション(景気後退)入りするという予想はしていません。理由は2つあります。
1つ目は、冒頭で紹介した米国の基礎体力の高まりです。潜在成長率とは、労働力人口の伸びと、労働1時間当たりの生産性の伸びの掛け算で決まりますが、このうち生産性のほうの伸びが加速しています。パンデミックで離職した人が生産性の高い仕事についていて、人が戻ってこなかった業態ではオートメーション化が進んでいます。加えて、生成AIによる生産性を上げる波がこれから来ます。こうしたロングタームでの米国の成長ストーリーは崩れていません。
2つ目は、DOGEによる連邦政府職員の解雇の影響で失業率が上がるという懸念は限定的である可能性です。実は連邦政府が行っている歳出削減は憲法違反になっています。予算を決めるのは議会であり、ホワイトハウスはその予算を執行すると憲法で規定されているにもかかわらず、今は歳出を勝手にやめているのです。そのため、補助金などを一方的に打ち切られた州政府や企業が違憲だと裁判に持ち込めば勝利する可能性が高い、曖昧な状態です。DOGEの歳出削減が正式に議会で承認を得て、今後の予算法案に盛り込まれれば、その影響が大きくなる可能性もあるのですが共和党も一枚岩ではなく、そうなるシナリオの可能性は高くないと考えています。
そして野村では、2025年中の政策金利の引き下げはなく据え置くと予想しています。米国はリセッション入りしないのであれば急いで利下げをする必要はなく、しかもインフレの加速をおさえる必要はあるため、利下げはないだろうという見立てです。
米国の機関投資家はどう見ているか
私は普段、米ニューヨークにて米国の機関投資家と接する機会が多くあります。個人投資家が今の状況に戸惑うように、機関投資家もトランプ政権の不確実性について迷う部分は多くあります。米国の本格的なリセッション入りを想定している人もいますが、多くの機関投資家は、リセッション入りはメインシナリオではないが、そのシナリオもリスクとして考えている、という印象を受けます。とはいえ、大統領選直後の減税や規制緩和を歓迎するムードは、関税政策の厳しさの前に沈静化していると言えるでしょう。
野村では昨年の大統領選後、2025年1~2月の関税政策の加速とそれに伴うインフレの影響で、2025年中は政策金利を据え置くという予想を立てていました。その頃、米国の機関投資家には「野村の予想はとがりすぎている、トランプ政権はビジネス寄りだから、関税政策がそこまで過酷なことにはならないだろう」と見る人が多かったのですが、実際は概ね野村の予想通りになっています。ただ、誤算だったのはDOGEの存在で、野村の予想よりも失業率が上がる懸念が増して、リセッション入りが心配されることとなりました。
もし我々の予想が外れて、リセッション入りしたとしても、その期間は長くないと思います。なぜなら、FRBはすぐに利下げという“特効薬”の投入を決断することができるからです。米国が高金利を維持し、利下げの余地を十分に持っているのも強さの一つといえます。
トランプ大統領は、就任後100日間で、4年の任期でやりたいことをすべて公開し、ニュースフローを埋め尽くす戦略を取っていると思います。私たちはニュースに一喜一憂するのではなく、実際にそれを実行しているかに注目し、長期目線で米国株式市場への投資を続けるのがいいと思います。

- 米国野村證券
シニア・エコノミスト
雨宮愛知 - 2001年野村総合研究所入社。2004年より野村證券金融経済研究所経済調査部。2009年より米国野村證券(ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル)に勤務。
※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。