2025.03.31 NEW
日経平均急落をもたらした 米国「トランプ・プット」「パウエル・プット」への疑念 野村證券・池田雄之輔
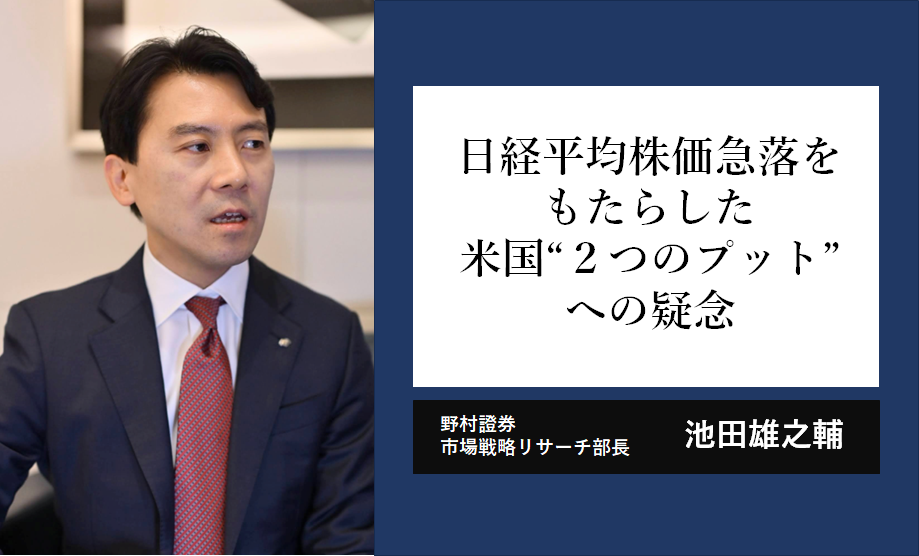
2025年3月31日、日経平均株価は前日比1,502.77円安の35,617.56円と急落し、終値で3万6,000円割れとなりました。この急落の背景には、相場急落時の救済策と期待されていた「トランプ・プット」や「パウエル・プット」が今回は期待できないのではないかとの見方が市場で広がったことが影響している可能性があります。野村證券市場戦略リサーチ部長の池田雄之輔が解説します。
スタグフレーションと関税への不安 米国発の2つのショック
日本株が急落している背景には、米国発の2つのショックがあるとみています。第一に、スタグフレーションに陥るかもしれないという不安が再燃しています。3月28日に発表された米国の指標では、2月の個人消費支出がやや低調な数値となりましたが、それ以上にショッキングだったのは3月のミシガン大消費者信頼感指数です。
「5~10年先のインフレ予想」の数値が、速報値の3.9%から今回の確報値で4.1%まで上方修正されました。速報段階では「調査サンプルが少なく、精度は疑わしい」とあまり真剣に受け止められませんでしたが、「これはまずい」という市場関係者が増えたと思います。
米国の消費者は、とくに民主党支持者が「トランプ政権ではインフレが加速する」と予想しています。インフレ予想が高い状況では、景気が悪化した場合でもFRB(連邦準備理事会)は利下げに躊躇せざるを得ません。「いざとなればパウエル議長が緩和に動く」という安心感(パウエル・プット)が弱まってしまうリスクが意識されています。
第二に、トランプ政権の関税政策に対しても、楽観から悲観への揺り戻しが生じています。4月2日には「相互関税」が発動される見通しですが、「一部の国や製品に絞った措置」という見方から、「全世界への一律20%の関税賦課もあり得る」という警戒に変わってきています。
トランプ大統領が就任してから3月半ばまでは、「自国企業の首をしめるような広範な関税策はない」という評価が広がっていましたが、はしごを外されるかもしれないという悲観論が高まっているのです。ここでも、「株価の軟調が続けば、トランプ大統領が関税措置を縮小・撤回する」という安心感(トランプ・プット)がなくなってきています。
米景気の基調は崩れていないが、雇用統計を見極める必要はある
「2つのプットへの疑念」のうち、前者のスタグフレーション懸念についてはやや行き過ぎとみています。米国の週次景気指標からダラス連銀が算出しているWEIという指数をみると、3月22日の週にかけても「2%成長ペース」を維持しており、大きな基調の悪化は表れていません。トランプ政権の経済運営は、不支持層の消費マインドを悪化させている可能性がありますが、実際の消費減少には至っていないというのが基本感です。
また、インフレ予想の上昇には要注意ですが、雇用は緩やかに減速しているので、利上げを必要とするほどの「予想インフレと賃金の上昇スパイラル」に陥るリスクは低いと考えられます。
目先のイベントとしては4月4日発表の雇用統計がとても重要です。とくに失業率は、イレギュラーな動きが少ないので、金融政策への含意も大きいとみています。3月は4.1%でしたが、4.3%を超えるような悪化だと「リセッション懸念」が本格化するリスクが高まります。一方、市場コンセンサス通りの4.1~4.2%にとどまれば、市場は一安心するのではないでしょうか。
「グローバル一律20%」などトランプ関税の最悪シナリオには要注意
4月2日に公表されるとみられる米国の大掛かりな関税政策については、「トランプ氏のみぞ知る」という側面がありますので、断定的なことは言えません。精査すべきポイントとしては、(1)関税対象となる輸入品の総額規模、(2)税率、(3)適用の時期、(4)交渉余地の有無、となります。最悪シナリオとしてはグローバル一律、つまり全世界例外なしで最大20%の関税というケースも、再度浮上しています(ウォールストリートジャーナル電子版が報道)。楽観は禁物です。
(4)の「交渉余地の有無」の観点は重要になりそうです。結局のところ、高率関税による輸入コスト上昇で米国企業の首をしめてしまい、景気後退を引き起こせば、2026年11月に控える中間選挙に向けて政権に不利となります。トランプ政権は、遅くとも年後半には関税政策の手を緩め、減税や規制緩和に重心を移すと考える方が自然だと思います。
円高・株安の悪循環は加速しにくいポジション状況
今日の東京市場で、円高が限定的であることは重要だと思います。これは2024年7月から8月初旬にかけての相場急落の局面とは大きな違いです。昨年夏場は、日経平均が40,000円を超えていた時点で日経225先物の外国人投資家のポジションはほぼフラットだった一方、ドル円は極端な円ショートになっていました。そのため、円ショートの巻き戻しによる円高が加速し、それが短期目線の投資家の日経先物売りを招くという負のスパイラルに陥ってしまいました。
現状はそのようなメカニズムは作動しにくいといえます。4月2日の米国の関税政策を契機に、グローバル株式市場がさらに動揺した場合、日本銀行は追加利上げのスケジュール感を後ろ倒しにすると予想されます。日本株の下押しを和らげる「植田プット」にはある程度期待できるといえそうです。
当面、日本株にとっての最も重要なチェックポイントは米国景気の行方と、トランプ関税の中身、ということになります。短期的には不透明な要素が多く、楽観は禁物です。一方、長い目で見た場合の日本株の魅力は揺らいでいません。デフレ完全脱却による日本経済のダイナミクスの復活、コーポレートガバナンスへの意識の変化による株主還元の強化というテーマは健在です。

- 野村證券 市場戦略リサーチ部長
池田 雄之輔 - 1995年野村総合研究所入社、2008年に野村證券転籍。一貫してマクロ経済調査を担当し、為替、株式のチーフストラテジストを歴任、2024年より現職。5年間のロンドン駐在で築いた海外ヘッジファンドとの豊富なネットワークも武器。現在、テレビ東京「Newsモーニングサテライト」に出演中。
※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。