2025.04.14 NEW
株価急落後の上昇で、「やれやれ売り」をする前に考えるべきこと 行動ファイナンスで解説
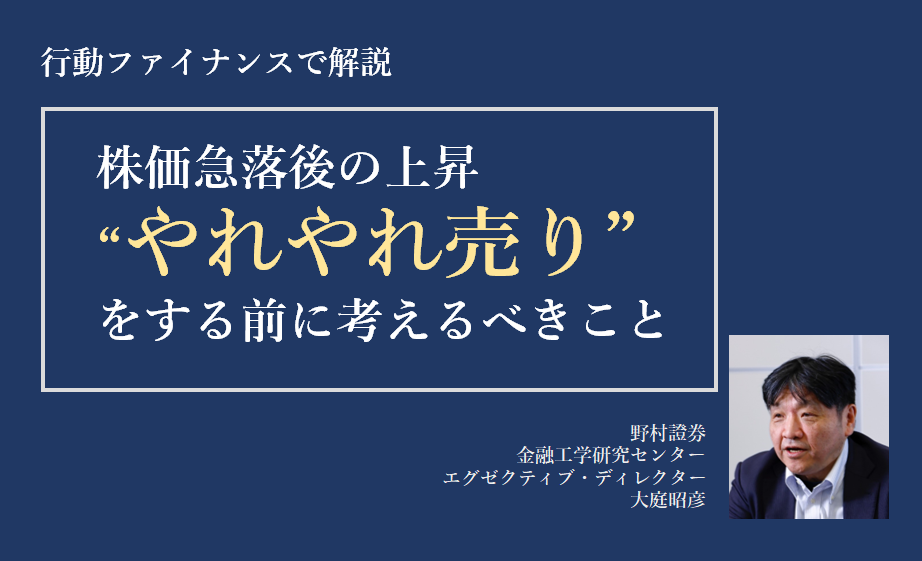
写真/竹井俊晴
4月2日にトランプ政権が相互関税の内容を表明した後、日米の株価は急落しました。4月9日の相互関税発動直後に一部の国・地域の「上乗せ分」の関税について90日間の停止が発表され、やや株価は上昇しましたが、翌日にはまた下落するといった乱高下が続いています。
下落している相場が一時的に回復したり、買値付近まで戻るのを待って売る行動は、「戻り売り」や「やれやれ売り」と呼ばれます。この行動をしたくなる理由と考え方のヒントを、行動ファイナンスの観点から野村證券金融工学研究センター エグゼクティブ・ディレクターの大庭昭彦が解説します。

- 株式市場の混乱が続いています。様々な情報が飛び交うなかで、「米国は景気後退に入り、自分が持っている株式や投資信託はもっと下がるのでは」と考え、「次に買値近くまで上昇したら売ろう」など、通称「やれやれ売り」をしようとしている人もいるかもしれません。さすがにこんなに株価の乱高下が続けばそれも致し方ないでしょうか。
-
気持ちはわかるのですが、その行動には問題があるかもしれません。そもそも、なんのために株式市場に投資しているのかという原点に立ち返ってみましょう。多くの人は1ヶ月後の住宅ローンの支払いに充てるためなどではなく、20年30年後の将来を見据えて、世界経済の拡大の恩恵を享受するために投資をしているのだと思います。
今、足元ではトランプ第2次政権による関税政策が予測のつかない展開となり株式市場が混乱していますが、この政策により、20年30年後の世界経済が壊滅的になることが見えたのでしょうか?
- いや、そこまで見越しているわけではないですよね……。
-
そうでしょう。株式市場はこれまでもリーマン・ショックやパンデミックなど様々なイベントを乗り越えて、総じてみると拡大基調にあるわけですから、投資家の方はそれが今後も続くと思って投資をしているわけですよね。それなのに今保有している有価証券を売ってしまうのは非合理的な行動と言えます。なぜ非合理的な行動をとってしまうのか。行動ファイナンスでは3つのキーワードで説明できます。
得よりも損のほうが痛いというバイアス
-
まず、一つ目のキーワードは、「利益よりも損失のほうが嫌だ」という心理です。例えば関税政策の影響で、保有する株式が10%も下がってしまった!と嘆いている方も、よく考えると昨年、その銘柄の株価が10%上がった時にはそれほど心が動かなかったのではないですか?
- そうですね。上がったのはいつだったかなどは、それほど印象に残っていない人が多いかもしれません。
-
株価の上昇と下落を同じ額で考えたときに、上昇のうれしさよりも下落のダメージのほうが大きいのです。ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンらが提唱する「プロスペクト理論」では、例えば100万円の利益の喜びを1とすると、100万円の損失の場合、同じ金額であっても悲しみは2.25倍になるといわれています。(注1)
(注1)出典:Tversky, A. and Kahneman, D.(1992) “Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty,” Journal of Risk and Uncertainty
合理的に考えると、株価の上昇も下落も同じように捉えるべきなのに、下落のほうばかり反応して行動するバイアスがかかりやすいのです。
- すでに下落したというダメージも大きいのですが、これからもっと下落するかもしれないという市場環境のときに、さらなる損失は絶対に回避したいと思ってしまいます。
-
その「これからもっと下落するかもしれない」という将来の予測自体にもバイアスがあるかもしれません。人は「これから上昇する」情報よりも「これから下落する」情報のほうに重みをかけて反応するのです。メディアも下落の予想に関する情報のほうが人々の反応を得やすいことがわかっているため、そういった不安をあおるような情報が多く出されている可能性もあります。
- 確かに、日本株が上昇していたときには経済ニュースはそれほど見ていなかったのに、今はニュースを頻繁に見ているというのも、下落に反応しやすいということなんですね。
長期よりも短期に目が行きやすい 双曲割引バイアス
-
2つ目のキーワードは「双曲割引」です。人は長期で得る利益・損失よりも、短期で得る利益・損失に目がいきやすいというバイアスを指します。
20年30年後のために余裕資金で投資をしているのであれば、今日明日の株価下落は関係ないはずなのに、短期の損益に関心がいってしまいます。例えば、「将来この会社は伸びる、株価は何倍にもなるだろう」と思って投資しているのに、「今売ればわずかな売却益が出る」または「大底からは少し回復した」というときに、とりあえずすぐに得られる報酬に飛びついてしまうということも考えられます。
- なるほど、大幅下落した後に少し上昇したところで売る「やれやれ売り」は、大底から考えたときの短期で得られる報酬に目がいってしまうということですね。本来はそのわずかな上昇分を得るために投資しているわけではないのに。
-
そうですね。しかし双曲割引バイアスの力は強いので、意識するだけですぐに長期に目を向けられるようになる人はめったにいません。そこで、重要になるのが次のキーワードです。
バイアスを意識するための「リフレーム」
-
「やれやれ売り」には、もともと人の心が持つバイアスが強くかかわるため、意識してコントロールするのが難しいです。そこで心理学でいうフレーム(見方)を変える「リフレーム」というやり方を紹介してみたいと思います。
米国の実験で、こんな例があります。
ある集団を性別や年齢の偏りがないように2つに分けて、1つ目のグループに「収入の20%を貯金できますか?」と聞いたところ、YESが50%、NOが50%でした。2つ目のグループに「収入の80%で生活できますか?」と聞いたところ、YESが80%、NOが20%だったのです。つまり、収入の20%は使えないんだ、という否定的なフレームよりも、収入の80%使っていいんだというプラスのフレームのほうが受け入れやすいという例です。(注2)
(注2)2016年「ゴールベース資産管理入門:顧客志向の新たなアプローチ」(チャック・ウィジャー他、日本経済新聞出版)273頁記載の例参照
長期投資をしているはずなのに、株価の急落であわててしまうという現象については、短期のフレームから長期のフレームへとリフレームするといいでしょう。
つまり、「1ヶ月前の株価と今の株価を比べると下落している」という短期フレームから、「今の株価と20年後の株価はどうなるか」という、長期フレームへと変えるのです。
- つい、直近の最高値からの下落に注目してしまいますが、そもそも数年前から考えると株価は総じて上がっていますよね。どの時間軸で株価の変動を考えるかによって気持ちが変わりますね。
-
はい。とはいっても、これだけ株価が乱高下しているときに、「短期は気にしないように」といっても、気持ちを切り替えられない人も多いでしょう。例えば、米国のファイナンシャルアドバイザー向けの情報で、相場が下落しているときに「言うタイミングを選ぶべきこと」の一つに、「あなたは長期投資家です。短期の動きは無視してください」という言葉がありました。人が感情的になっている最中にこう言っても響きにくいんですね。
もし、今回売ってしまったという人も、また市場に戻ってきて、長期投資を再開することが重要です。そして、人は短期に関心が向いてしまうものなのだと意識したうえで、自分は何を目的として投資をするのかを決める「ゴールベース・アプローチ」へと意識を変えていくといいでしょう。一人では難しい人がほとんどなので、客観的にアドバイスしてくれる第三者の力を借りるのもよい方法です。

- 野村證券 金融工学研究センター エグゼクティブ・ディレクター
大庭 昭彦 - CMA(日本証券アナリスト協会認定アナリスト)、証券アナリストジャーナル編集委員、慶應義塾大学客員研究員、投資信託協会研究会客員。東京大学計数工学科にて、脳の数理理論「ニューラルネットワーク」研究の世界的権威である甘利俊一教授に師事し、修士課程では「ネットワーク理論」を研究。1991年、野村総合研究所へ入社。米国サンフランシスコの投資工学研究所などを経て、1998年に野村證券金融経済研究所に転籍、現在に至るまで、主にファイナンスに関わる著作を継続して執筆している。2000年、証券アナリストジャーナル賞受賞。
※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。