2025.08.05 NEW
野村総研・木内登英さんが語る トランプ政権の「ドル安政策」が次なる焦点
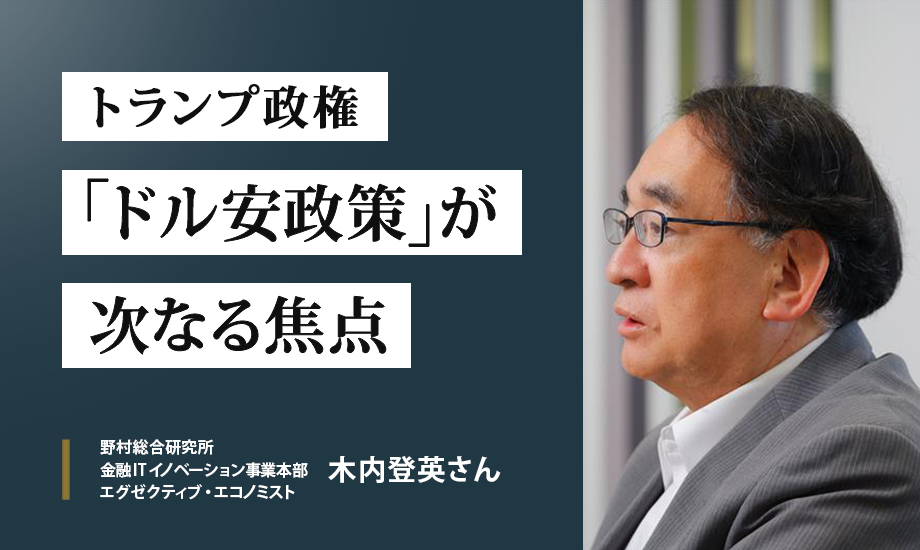
写真/タナカヨシトモ
日本に続き、EU(欧州連合)でも米国との関税交渉は合意に至り、トランプ関税を巡る先行き不透明感は和らいでいます。主要国との関税交渉が一巡した後、トランプ政権の次の一手に関心が集まります。野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミストの木内登英さんは「ドル安政策」を注目点に挙げます。貿易赤字の解消を目指すトランプ政権の狙いや米国経済の見通しについて聞きました。

関税合意も曖昧な対米投資の規模感
- 当初、日本には25%、EUには30%の関税率が予定されていましたが、最終的にはともに15%で合意に達しました。日本政治と米国との交渉結果をどう評価していますか。
「日本は25%の関税が課されるはずだったのが、15%で落ち着き、安堵した」とは言いきれません。トランプ政権が提示していた関税率はもともと根拠のない不当なものです。関税による日本経済への影響については、GDP(国内総生産)に対して0.55%程度の押し下げ効果があると見ており、逆風であることには変わりありません。一旦合意したとはいえ、日本政府は引き続き他国と連携し、関税撤廃を訴えていくべきだと思います。
また、今回の関税交渉について合意文書が公表されておらず、合意内容が非常に曖昧な点も気になります。トランプ大統領は「日本から米国へ5,500億ドルの対米投資を取り付けた」と発言しています。7月22日にホワイトハウスが公表したファクトシートによると、日本が米国に資金を提供し、その資金使途は米国側で決めることができるような誤解を与えるような記載になっています。
実際は日本政府が米国側に資金を提供するわけではなく、日本企業の対米投資を政府系金融機関が5,500億ドル規模の出資や融資、融資保証の形で支援する枠組みです。民間企業が米国への投資を決めなければ、そこまでの規模にはなりません。
- 対米投資については、日米間で合意内容にズレが生まれている可能性があるのですね。日本企業は米国内での生産に切り替えるなど、米国への投資に積極的になるでしょうか。
日本からの輸出品に15%の関税がかかったとしても、米国の人件費は高いため、米国内で生産する方針に変える企業は多くないと考えています。5,500億ドルの投資枠があっても、それほど投資が増えるわけではないでしょう。EUと米国の関税合意において、言及された6,000億ドル相当の対米民間投資についても、同じような状況にあるのではないでしょうか。
このような点は将来的な火種になる可能性があります。関税合意がなされたとはいえ、トランプ政権が不満を感じれば、いつでも関税率を引き上げてくる可能性があります。米国に輸出先、投資先を大きく依存しているのはリスクが高いと捉える企業は、米国から他の地域への分散を考えるかもしれません。そういった意味では新しいサプライチェーン(供給網)が構築される可能性はあります。「ドル離れ」ということもできます。
徐々に「ドル安誘導」に軸足を移す可能性
- 各国との関税交渉が一巡した後、トランプ政権の次の狙いは何でしょうか。
トランプ政権の最終目的は貿易赤字の解消です。戦後の米国はリーダーであるがゆえに他国から不当に過大な負担を押し付けられてきたと解釈しており、その負担のシンボルが貿易赤字と位置付けています。
今回の関税の引き上げ分では、米国の貿易赤字を解消する規模ではありません。当初、トランプ大統領が考えていたよりも、関税政策が上手くいっていないと私は考えています。その最大の要因は中国です。レアアースの輸出規制が対米交渉における重要な切り札となったことで、中国との関税交渉は、米国側が期待する結果にはなりませんでした。
今後は貿易赤字の解消に向けて関税政策中心から、徐々にドル安政策に軸足を移していく可能性があります。トランプ大統領のブレーンであるミラン米CEA(大統領経済諮問委員会)委員長は、関税政策とドル安政策は米国の貿易赤字を解消させるための対となる政策と位置付けており、トランプ大統領やベッセント財務長官も同様に考えているものと推察されます。
- ドル安に誘導するための具体策として、考えられるものは何でしょうか。
やはり、インパクトが大きいのはFRB(米連邦準備理事会)による利下げでしょう。政策金利の引き下げが行われれば、ドル安が進むことが予想されます。そして、ドル安が進むと物価高になる可能性はありますが、関税による物価高に比べインフレの進行には時間がかかります。日本では輸入品のほとんどがドル建てのため、円安になるとすぐに輸入物価が上昇しますが、米国は自国通貨(ドル)建ての輸出入をしているため、ドル安となっても輸入物価はすぐに上昇するわけではありません。
関税率をさらに上げるとなると、急な物価上昇による国民の痛みが伴いますが、ドル安政策ではその影響を小さくすることができます。今後、関税による物価高が表面化し国民から反発の声が出てくると、各国と合意した水準から関税率を引き下げる可能性も考えられます。貿易赤字削減に向けて、行き過ぎたドル高を是正するドル安政策に切り替えていくのではないでしょうか。
具体的にはトランプ政権の息のかかった人物をFRBの議長に送り込むことが最大の介入となり得ます。FRBのパウエル議長の任期が2026年5月に控えており、2025年年末から2026年年初にも後任人事が発表される予定です。しかし、2026年1月まで任期を残してFRBのクーグラー理事が早期退任することになり、トランプ政権がより前倒しでパウエル議長の後任を理事に指名する可能性が生じています。
8月1日に公表された7月の米雇用統計では、7月分の雇用増加数の下振れ、5月と6月分の伸びが大幅下方修正となったことで、金融市場は9月のFOMC(米連邦公開市場委員会)での利下げ期待を大幅に強めています。

米国は関税による物価高で景気後退にはならないと予想
- 個人投資家は米国経済を見る上で、今後、どのような点に注目すべきでしょうか。
やはり注目すべきは、関税による物価高が米国経済と世論に与える影響です。物価がどの程度上がってくるかを見極めるために、7月分の物価関連の指標がポイントになります。
6月分のCPI(消費者物価指数)では衣料品や家具などの価格はやや上がりました。足元では米国小売り大手のウォルマートの値上げも始まっており、7月以降は価格が上昇する品目の幅が広がってくると見ています。例えば、自動車は関税がかかる前に輸入した分の在庫はなくなってきています。7月分のCPIにどの程度、関税による物価上昇の影響が出てくるかに注目しています。
- 関税による物価高が米国の景気に与える影響をどう見ていますか。
米国が簡単に景気後退するほどのインパクトはないと考えています。関税の影響が強く出てくるようになると米国景気の先行きには慎重な見方が広がり、FRBの利下げ観測が強まることで為替はドル安に振れ、それが景気の下支えとなるからです。米国経済は減速するものの、GDPが二期連続でマイナスになる景気後退には至らない「グロース・リセッション」に留まると予想しています。
- グロース・リセッションを予想する中で、リスク要因として考えられるものは何でしょうか。
私は米国経済が抱えるひずみとして、「中小企業の債務問題」に注目しています。リーマンショック以降、低金利で安定した経済環境が継続したことで、中堅銀行やプライベートクレジットファンドが信用格付けの低い中小企業に資金を供給する流れが強くなっており、実はこの金融面でのひずみは解消されていません。 トランプ関税をきっかけとした景気減速が引き金となり、中小企業の債務不履行が増えてくると、銀行やファンドの損失が拡大し、金融危機に発展する可能性をはらんでいます。まずはマクロ経済がしっかりと持ちこたえられるかどうかが重要になります。

- 野村総合研究所 金融ITイノベーション事業本部 エグゼクティブ・エコノミスト
木内登英 - 1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。
※本コラムで取り上げられたマーケットや投資に関する考え方などについては、あくまで個人の見解によるものであり、野村證券の意見を代表するものではございません。本コラムは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。