2025.08.21 NEW
関税問題は終わっていない 米国市場が直面しているニューノーマル 野村證券・吉本元
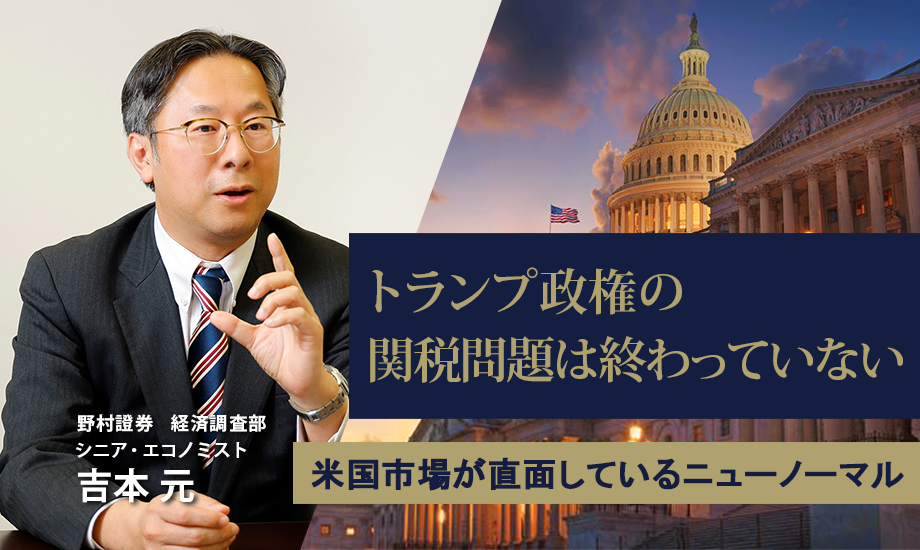
文/斎藤健二(金融・Fintechジャーナリスト) 写真/タナカヨシトモ(人物)
大胆な関税政策、中央銀行への露骨な利下げ要求――トランプ政権の経済政策は一見場当たり的なように見えますが、実は米国の政策決定システムが持つ構造的特徴を浮き彫りにしているとも言えます。これまでに出てきた政策を振りかえり、今後個人投資家が注視しておくといい点について野村證券の吉本元シニア・エコノミストが解説します。

7月の合意は束の間の休息
- トランプ政権の関税交渉がひと段落しつつあります。これまでの政策をどう評価しますか。
-
当初の政策案と比べると、やや穏健化したと言えます。日本に対する関税率は当初の25%から15%に引き下げられ、自動車に対する関税も15%で決着しました。これをもって日本に対する関税は一段落したという見方もありますが、関税問題はまだ終わっていないと見ています。
7月の合意は束の間の休息にすぎません。事故に巻き込まれて命は助かったが、けがは避けられなかった、というのが現状です。引き下げられたとはいえ15%の関税は掛かる訳であり、経済への悪影響は避けられません。
- 関税率の設定にはどのような論理があるのでしょうか。
-
経済学的な根拠はほとんどありません。4月に相互関税率が発表された時は、計算の根拠が示されました。これも計算違いが指摘されていましたが、7月の関税通知の時点で四捨五入のような処理がされています。現在は、米国が貿易赤字の国に対して基本的な関税率は25%を基準としており、通商合意がなされれば15~20%辺り、相手国が米国の要求を拒絶したり報復を用意したりすれば50%、安全保障上の問題もあると見なす強い対応を示したい場合には100%という数値が良く使われています。
7月当初、トランプ大統領はロシアへの制裁として、「ロシア産エネルギーの購入国には100%の2次関税を課す」と宣言した後、8月にインドに対象を絞り関税率を50%に引き下げました。しかし25%までは下げない。これはインドに対する強い通商上の不満があるためと見られます。一方で、ロシア産エネルギーの最大の輸入国である中国には2次関税の発動を見送っており、基準がはっきりしません。少なくとも、関税による税収で財政赤字を埋め合わせたり国内産業を保護したり、貿易赤字を減らしたりするといった目的を実現するために、合理的な基準で算出された関税率を適用しているとは考えられない面があります。
- 関税政策の本来の目的は何でしょうか。税収確保でしょうか、それとも政治的圧力でしょうか。
-
一挙両得を狙っていると見られますが、いずれも詰めが甘いものになっています。関税収入は確かに増加していますが、大規模減税による歳入減を補填するには及びません。今後は過度の関税が輸入減少を招くと見られますが、結果的に税収も減少します。
政治的圧力の手段としても矛盾を抱えています。例えば、エネルギーの6割を依存するカナダ、メキシコに高関税を課せば、米国自身が打撃を受けます。当初高い関税率を発表した後、必需品を除外するなど事後的な調整で影響を緩和しようとします。威嚇と緩和を繰り返すパターンが定着しています。
政策決定に必要な官僚機構が弱体化している
- なぜこのような政策決定がなされるのでしょうか。
-
官僚機構の弱体化があると思います。相手国と政策の詳細を詰めるのは官僚の仕事ですが、米国側には深刻な人材不足があります。同時並行で多数の国と交渉を進めているため、複数の国・地域と合意しても、合意が発効する期日までに詳細な取り決めがなされていないことが多々あります。イーロン・マスク氏主導の政府職員削減もあり、国際合意文書の作成に必要な法曹資格を持つ専門人材が不足していると考えられます。
通常なら官僚が作成する法的文書が決定力を持つわけですが、文書が存在しない以上、合意事項を米国が守らなくても、相手国が指摘しない限りそのまま放置されてしまいます。
- 関税政策には司法による違法判決のリスクがあると聞きますが、それは政策の歯止めになるのでしょうか。
-
相互関税や中国、カナダ、メキシコへの制裁関税は国家緊急経済権限法(IEEPA)に基づいて実施していますが、これは本来有事に対応するために議会の権限を大統領に委ねる法律です。有事と言い難い事象で法の濫用は避けるべきとの批判や、IEEPAは関税発動のための法律ではないとの解釈があります。このため、IEEPAに基づく関税の差し止め訴訟では、一審で政権側が敗訴し二審も旗色が悪い状況です。最終審の最高裁でも敗訴となれば、関税は無効になります。
しかしトランプ大統領は引き下がらないでしょう。IEEPAではなく、通商拡大法232条に基づいて発動された自動車、鉄鋼・アルミニウム製品、銅製品などの品目別関税を引き上げたり、新たに半導体や医薬品などにも関税を発動したりして税収を確保する可能性があります。鉄鋼・アルミ製品関税では、すでに白物家電や缶ビールにも関税を適用するような拡大解釈も行われており、新たに発動される半導体などでも拡大解釈が行われるリスクもあるでしょう。
トランプ政権は人事を通じて影響力行使ができるのか
- トランプ大統領はFRB(米連邦準備理事会)に対して露骨に利下げを要求しています。実際にどこまで介入できるのでしょうか。
-
ある程度の影響は考えられますが、FRBの独立性を奪うような形で法改正でもしない限り不可能です。そうした法改正には民主党が賛成せず、上院での議事妨害で阻止される可能性が高いと見られます。
FRBは7月時点の見通しで年末までに1、2回、0.25%ポイントの利下げを予定しています。年末に近付くにつれ利下げの可能性が高まり、トランプ大統領の要求とFRBの行動が噛み合ってくる時期がやってくると見られます。
とはいえ、どこまで下げるかという水準の問題では意見が中々一致しないでしょう。FRBは中立金利を3%強と見ており、来年から再来年にかけてその水準に近付けるという見通しになっています。一方、トランプ大統領は1%以下にまで政策金利を引き下げるよう要求しています。しかし、これは大幅な景気後退やリーマンショック級の金融危機を想定した水準です。そうした危機を予測しているなら違和感のない政策金利ですが、トランプ大統領自身は自分の任期中に大幅な景気後退や金融危機が起こるとは考えていないでしょう。この自己矛盾が、要求の非現実性を物語っています。
- 人事を通じた影響力行使はどの程度可能なのですか。
-
トランプ大統領は金融政策を決定できる立場のFRB議長やFRB理事を任命できますが、まず、議長も理事も上院の過半数による承認が必要です。そして金融政策を決定するFOMC(連邦公開市場委員会)は12名で構成されます。FRB議長、FRB副議長、FRB理事はこのうち7名です。第1次政権(2017-21年)の時に任命された理事は現在2名です。現在、1名が空席であり、来年5月にはパウエル議長が任期満了で退任する予定ですので、7名中4名がトランプ政権時代に任命されることになります。しかし、FOMCにおいては、12名中4名です。FOMCに参加する5名の地区連銀総裁は大統領が直接選べません。
このため、パウエル議長の後任になる議長は、トランプ大統領の意向に忠実な人物というだけでは上手く役割を果たすことが出来ないでしょう。議長たるもの、FOMCメンバーを説得し、金融政策の決定について意見が分かれる「票割れ」のような事態を避ける必要があります。「票割れ」が続けば、金融市場で米国の金融政策運営が不安視され、ドルの信認が疑われる事態になります。
バーナンキ元議長やイエレン元議長のように著名な経済学者だったり、永年中央銀行に勤めていたボルカー元議長のような経験のある人物だったりすれば、他のFOMCメンバーを説得できると考えられます。しかし上院での承認採決でぎりぎり過半数しか得られないような議長だと、手腕や資質に上院が半信半疑である証左となってしまいます。就任当初からFOMCメンバーに対して説得力を持てず、市場の信認も揺らいでしまうでしょう。民主党上院議員も賛成するような人物である必要があります。

ドルの信認喪失はグローバルな金融システム全体の信頼性に関わる
- なぜFRBの独立性がそれほど重要なのでしょうか。
-
米国は共和党、民主党を問わず、歴代大統領が中央銀行の独立性を保障することで、基軸通貨ドルの信認を維持してきたと言えます。
仮に政策金利を大幅に下げた場合、本来なら景気刺激で株価上昇が期待されます。しかし「FRBが政治的にそんたくして金利を下げた」という場合には、景気、雇用、インフレの状況を反映した本来のあるべき政策金利になっていないという疑念が市場で生じてしまいます。
つまり、政治の介入によって決定された政策金利では、景気、雇用、インフレをうまくコントロールできないことになります。ドルの信認が低下し、ドル安が進行します。政策金利は下がっても、インフレを抑えられないだろうという市場の懸念を反映して長期金利はなかなか下がらず、米国債から資金が逃避します。最終的には株式市場からも外国人投資家が逃避しかねません。
ここ数年の例では、トルコで、エルドアン大統領が次々と中央銀行総裁を解任したり、利下げを要求したりした結果、海外投資家の資金逃避を招き、大幅なトルコ・リラ安、トルコ国債利回り上昇、株安を招き、インフレが悪化した事例があります。
トルコ・リラはあくまでもエマージング通貨の一つですが、基軸通貨ドルの場合は動揺が大きくなり、金への資金逃避も視野に入ってくるでしょう。ドルの信認喪失は、単純な金融緩和による株高という話ではなく、グローバルな金融システム全体の信頼性に関わる問題となります。
市場と政治の相互作用
- 市場はトランプ政権の政策リスクをどのように消化しているのでしょうか。
-
現時点の経済指標はまだら模様というところで、景気、雇用、インフレの方向性がはっきりしているわけではありません。したがって、市場は楽観と警戒の間で揺れています。
関税の影響は急激に起こるのではなく、徐々に物価や消費に現れると見られます。さらに物価が徐々に上昇する場合、消費者は同じ商品でも高価格品から低価格品に乗り換えて節約を試みると見られます。目立ったインフレや消費の落ち込みではなく、購入物の質の低下、言うなれば消費の質が低下している可能性があります。
米国の大手ファストフードチェーンの売上は落ち込んでいないと言われています。しかし本来は低所得者層が利用する店なのに、最近は中所得者層が顧客になっていると報告されています。つまり全体的に物価が上がり、中所得者層が安価な外食を選択していると見られています。こうした消費の質の低下はマクロ経済指標には表れにくいですが、水面下では進行しています。
もっとも、ファストフードからはじき出された低所得者層は、食費を節約する余地が無くなっていることになります。給与では支出をまかない切れず、クレジットなどの債務が膨らみその返済が滞るようになってくるでしょう。そうした形で、じわじわと消費の落ち込みが表面化してくると考えられます。
- 長期的に見て、米国市場をどう捉えるべきでしょうか。
- 中央銀行の信認が揺らぐというリスクは、従来は新興国市場でしか見られない現象でした。根拠が明確ではないうえに朝令暮改を繰り返す関税政策も、自由貿易を原則としてきた従来の先進国の経済政策とは異質のものです。先進国市場への投資だと考えていても、実際には新興国市場並みに政治リスクに左右されてしまう。それが現在の米国市場が直面している新常態(ニューノーマル)と言えるでしょう。
- 個人投資家にとって重要なのは、この市場が「読めない」ということを認識することです。関税がいつ発動されるか分からない。政治的介入によって中央銀行への市場の見方がいつ暗転するか分からない。予期せぬタイミングで市場の急落に巻き込まれる可能性があります。米国市場に関しては株高こそニューノーマルと安住するよりも、リスク分散を意識した投資を心掛けることが肝要と見られます。

- 野村證券 金融経済研究所経済調査部 シニア・エコノミスト(政治・地政学調査) 吉本 元
- 1993年に野村総合研究所に入社し、経済調査部配属。1999年、東京大学大学院経済学研究科入学、2001年に経済学修士号取得。野村證券金融市場情報管理部、米国野村證券、野村證券金融経済研究所経済調査部を経て、2009年に外務省に出向し、在英国日本大使館に着任。2011年、野村證券金融経済研究所に帰任。国内外のリスク分析(政治政策、地政学リスク、政治動向など)を担当。
※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。