2025.08.26 NEW
エコノミスト・上野泰也さんに聞く 基軸通貨「ドル」の地位は揺らぐか?
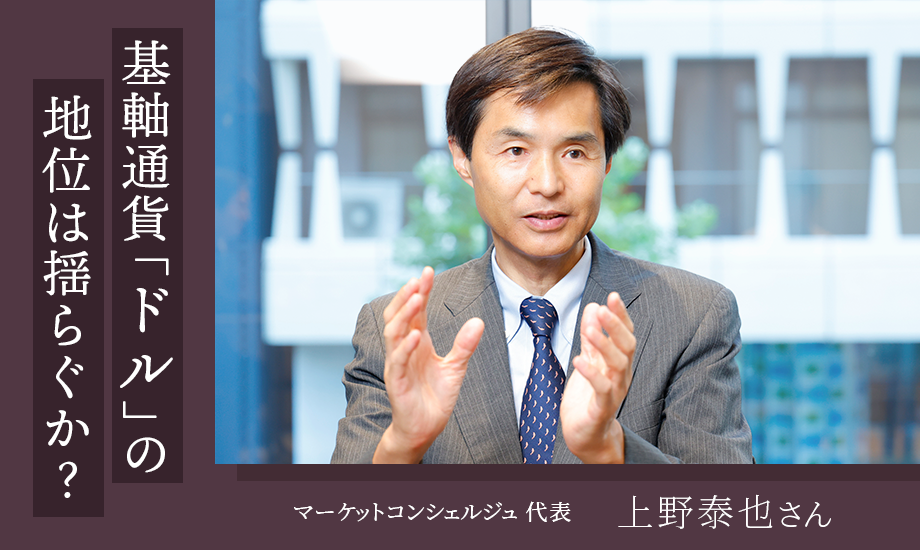
写真/タナカヨシトモ
トランプ政権による関税政策やFRB(米連邦準備制度理事会)への政治圧力などから、基軸通貨であるドルへの信認が揺らぎ、投資家がドルや米国資産から他の通貨、資産へと投資マネーをシフトさせる「ドル離れ」の動きが本格化するのではないか、と不安視する声があります。今後、米国に集中していた投資マネーの行方はどうなるでしょうか。
長年、証券会社などでマーケットエコノミストとして、マーケットの最前線で経済やマーケットに関する情報発信を手掛け、2025年7月に独立したマーケットコンシェルジュ代表の上野泰也さんに、QUICKナレッジコンテンツ本部の中山桂一さんが聞きました。
 左からQUICKの中山さんとマーケットコンシェルジュの上野さん
左からQUICKの中山さんとマーケットコンシェルジュの上野さん
楽観論と悲観論の間で揺れ動くトランプトレード
中山桂一さん(以下、中山)
第二次トランプ政権発足後、2025年4月の「トランプ関税ショック」で株式相場は大きく下落しました。その後、欧米や日本の株式市場では史上最高値を更新しています。ここまでのマーケットの動きをどう見ていますか。
上野泰也さん(以下、上野)
第二次トランプ政権発足後、市場では減税政策への期待感などから楽観論が出ていましたが、4月2日に突如、相互関税が公表されると、一気に悲観論に転じました。ここまで高い関税率を課すことは誰も想像していませんでした。
その後、トランプ大統領はディール(取引)を行うために高い関税率を課しており、必ず最後は妥協するという「TACO(Trump Always Chickens Out、トランプはかならずヒヨって逃げる)」と言われるようになり、再び楽観論に切り替わりました。
足元では、膨らむ米国の財政赤字やトランプ政権の政策の先行き不透明性などから、一方的に楽観論に走るのはどうかと、日々、迷いが生じている状況にあると思います。
中山
短期間での変動の大きさをみると、マーケットの反応もより早くなっているように感じます。
上野
そうですね。カネ余りが要因だと思います。もちろん、米国の金利水準をみると金融引き締め気味ではありますが、FRB (米連邦準備制度理事会)のバランスシートは非常に大きいですし、米国企業も日本企業と同じようにキャッシュリッチでお金が余っています。
中山
日本もそうですが、2025年4-6月期の企業決算をみると、自社株買いが増えていて株価の下支えになっています。事業法人以外の機関投資家もカネ余りのなかで資金の振り向け先を考えているなかで、運用先を求める短期的な資金の循環が早くなっているということですね。
ドルに代わる基軸通貨はなく、「ドル離れ」は長続きしないと予想
中山
トランプ大統領の言動に振り回される中、米国への投資を継続して良いのか、資産をどこかに避難させたほうがいいのか、といった不安もあると思います。いわゆる、「ドル離れ」の動きについてはどう見ているでしょうか。
上野
ドル離れは長続きしないだろうと考えています。基軸通貨として、ドルに代わり得る通貨、米国債に代わり得る金融資産は出てきていないと思います。基本はやはりドルを主軸として、世界経済は今後も動き続けるでしょう。
ドルに代わる基軸通貨の候補として、ユーロが挙げられます。金融政策はECB(欧州中央銀行)に一元化されていますが、財政政策は各国バラバラというのは制度的には大きなデメリットだと思います。ドイツが財政拡張に舵を切ったことで、ドイツ国債と他の欧州の国債との金利差は縮小し、バラツキは軽減されていますが、一つの経済システムとしてみると、財政政策はバラバラで、極右政党の台頭による通貨統合参加国の政治の不安定化などを踏まえると、ドルに匹敵するほどのポテンシャルはないでしょう。
ただし、同盟国にも平気で相互関税を課すなど、トランプ大統領の政策運営の不安定さには、ドルに対する信認を傷つけている面があります。基軸通貨としてのドルの存在感は変わらないものの、その信頼感、ドルへの集中度合いは弱まる方向でしょう。

中山
これまでドルや米国資産に集中していた投資マネーの一部が他に分散していくイメージですね。その場合、運用先がドル建て資産中心の個人投資家は、運用方針を見直すタイミングに来ているでしょうか。
上野
個人投資家については、それ以外の通貨にも分散して運用していく方がベターだと思います。分散先の候補として挙げられるのは、ユーロやスイスフランなど欧州の通貨でしょう。
通貨以外の分散投資先として、実物資産を考えるのもありだと思います。近年、金は飛躍的に価格が上がっています。ロシアによるウクライナ侵攻以降、以前に比べれば核戦争のリスクが高まっており、金の高騰につながっていると思います。またビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)については、裏付けとなる資産はなく、信用力は乏しいですが、過去に比べ一定の存在感があるのは事実です。価値の変動は激しいですが、ポートフォリオに占めるごく一部の対象として、暗号資産を考えるのも一考に値しそうです。
中山
円については挙げられませんでしたが、分散投資を考えるうえで、円はどうでしょうか。
上野
短期的には円高のリスクが高まっていますが、私は個人的に長期的な見通しでは円安になると、以前より見ています。人口減・少子高齢化、広い意味での人口問題の重みは、長年、エコノミストとして強調してきました。少子化対策は中途半端なままで時間が過ぎ去り、事実上、もう手遅れに近い状況になっています。
外国人の受け入れについては、特定技能制度の整備やインバウンド政策による外国人観光客の増加で、実態としてかなり進みましたが、国内では摩擦も生まれています。7月の参議院議員選挙では外国人の居住、資産の取得などが焦点になり、排外主義的な主張が目に付く場面がありました。しかし、日本は無策でいると国力が落ちていくことになります。
国内政治についても、参院選後、自民党が衆参両院で過半数を割り込んだことで、2大政党制は幻になりました。多党制の時代に入ると、当然、政治は不安定化します。
このような点からすると、外国人投資家としては、円を保有する比率を格段に引き上げるのは難しいでしょう。円の将来性について考えると、強い見通しは立ちにくいです。
ただ、日本に住み、円で稼ぐ日本人には、当然、母国通貨である円を保有するメリットがあります。資産運用の中では、日銀の利上げで金利がかなり上昇した国債に投資妙味があるほか、株式や社債などの円建てのリスク資産を一定の比率を持つことも検討対象です。
FRBの利下げペース次第で「1ドル=139円台」割れの可能性も
中山
引き続き先行きが見通しづらい環境が続くことになりそうですが、今後の金融市場の注目点はどこになるでしょうか。
上野
ウクライナ戦争問題を含めたトランプ政権の動きとパウエル議長の後任人事、FRBの金融政策の動向がポイントになります。国内に目を向けると、日本銀行の利上げと石破政権の行方になると思います。日米ともに政治が絡み、金融政策においても不透明感が漂うことになるでしょう。その中でどういう結末になるかで、マーケットは手探りの状態が続くと思います。

中山
そういった見通しですと、秋から年末にかけては荒れやすい相場環境になるでしょうか。
上野
このまま何もなく今年が終わるとはとても思えない状況です。何がきっかけになるか分かりませんが、再びマーケットのムードは悲観的になってもおかしくありません。
中山
足元では日本株の強さが目立っています。日経平均株価は8月12日に約1年1か月ぶりに史上最高値を更新しました。その後も最高値更新を続けていますが、過熱感は出てきているでしょうか。
上野
私は日経平均株価の予想PER(株価収益率)で17倍台というのは、やはり割高だと思います。若いころから、PER15倍が基準だと教え込まれた世代からすると、17倍まで到達するとさすがに収益の向上を先食いしている印象があります。
グローバルにポートフォリオを組んでいる海外投資家は、米国株や欧州株の株価がこれだけ上昇すると、日本株だけ時価ベースでウェイトが下がります。その結果、リバランスで日本株を買い増すことになります。そういう意味で、米国株が大きく上昇したときに、日本株は出遅れ感を取り戻す形で上がっていくこと自体は、常に起きるパターンなので違和感はありません。ただ、そのリバランスが終わったときにふと見てみると、本来の日本の企業収益見通し対比で買われすぎてしまっている可能性があります。
また、為替相場がこの先はカギになります。当然、円高になると輸出関連企業、グローバル収益の比率が高い企業の収益見通しは悪化します。円高が進んだときに、日本株は上がりすぎた分の調整はあってもおかしくないと思います。
中山
日本株においてもドル円の水準が重要になるのですね。市場では9月にFRBの利下げが織り込まれている中で、日米金利差の縮小からドル安円高方向に進みやすい局面かと思います。
上野
そうですね。2025年のドル円相場の年間値幅は約19円(8月18日時点)で、夏場までの期間ですでに変動の激しい年となっています。2025年1月には1ドル=158円台まで円安が進みましたが、2025年4月には1ドル=139円台まで円が買われる局面がありました。139円台は2024年9月にもドル安円高方向の動きに歯止めかかった水準です。このあたりを抜けていくかがポイントになります。
為替市場でも見方は割れており、FRBの利下げのペース次第でしょう。9月に利下げした後、インフレ動向を見極めるためにさらなる利下げはしばらく手控えるケースも考えられます。一方、米国のインフレ関連指標が市場予想よりも下振れ、FRBが10月、12月のFOMC(米連邦公開市場委員会)を含め、年内3回の利下げまで踏み切る場合、139円割れの可能性は高いと思います。

中山
まだ第2次トランプ政権が始まって1年目ですが、トランプ大統領の言動にマーケットが振り回される状況は、2期目の任期(2029年1月)が終わるまで辛抱する必要があるでしょうか。
上野
トランプ大統領の2期目の任期が終わっても、「トランプの時代」は必ずしも終わるとは言えません。共和党がバンス副大統領やルビオ国務長官を後継者に立て、次の大統領選に臨む場合、トランプ氏の影響力が残ることも考えられます。第2次トランプ政権後の米国の政治状況は読みにくいところがあります。
振り返ると、2016年が歴史の大きな転換点だったと考えています。2016年6月には英国の国民投票でEU(欧州連合)離脱派が勝利した「Brexit(ブレグジット)」が起き、同年11月の米国大統領選挙では、トランプ氏が次期大統領に当選しました。それまで自由貿易が長く推し進められてきた中で蓄積された経済のグローバル化への不満の噴出・副作用とでもいうような、一時的な揺り戻し現象だととらえる見方もありました。
ただ、その後の流れをみると、トランプ氏が再選した米国に限らず、このトランプ的な現象は各国でも見られるため、一過性のものとは言えません。私は2016年からグローバル化と反グローバル化がぶつかり合い、しのぎを削る時代に突入していると考えています。
中山
トランプ現象が拡散することで、世界経済のバランスが変わってしまいますね。米中対立など大国間の争いには影響しないでしょうか。
上野
非常に長い目でみると、米中覇権国家争いについて、米国の勝ちと言い切るのは難しいでしょう。トランプ政権は移民の受け入れを拒んでいます。移民は米国経済の原動力の一つで一番の強みです。
米国のIT関連企業のトップはインド出身の経営者が多くいるなど、さまざまな出自を持った方がいます。外から人を受け入れることで、人口の増加という需要面だけでなく、サプライサイド(供給側)に刺激が加わり、技術革新や新しい企業の出現につながっていますが、トランプ政権の政策はこの強みを抑え込んでいます。
では、中国に投資をするかというと投資規制の問題などもあります。米国の対中投資規制を意識して、中国の代わりに日本に投資マネーが流入し、日本の株価を押し上げている面もあるわけです。国際的な金融面の規制も含めバランスを考えて投資をしていかないといけないタイミングにあるかもしれません。
※本コラムで取り上げられたマーケットや投資に関する考え方などについては、あくまで個人の見解によるものであり、野村證券の意見を代表するものではございません。本コラムは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。

- マーケットコンシェルジュ 代表
上野泰也(うえのやすなり)さん - 会計検査院、富士銀行(現みずほ銀行)、富士証券(現みずほ証券)、みずほ証券チーフマーケットエコノミストを経て、25年7月に独立して、マーケットコンシェルジュを設立。専門は、内外経済・金融市場・中央銀行および政府の政策動向の調査・分析・予測。日本経済新聞電子版の有識者コメント欄「Think!」担当、日経ビジネスオンラインやロイターなどへの定期寄稿、テレビ番組への出演、各種セミナー講師など、幅広く活動中。

- QUICK ナレッジコンテンツ本部 コンテンツグループ 副部長
中山桂一(なかやまけいいち)さん - 2008年QUICKに入社。2013年に日本経済新聞社商品部(当時)に出向し記者職に就く。日経QUICKニュース社への2度の出向を経てQUICKデリバティブズコメント、エクイティコメントでマーケット記事の執筆業務に携わる。