2025.09.16 NEW
2026年末の日経平均株価予想を46,000円に引き上げ 相場レンジが上方シフトか 野村證券ストラテジストが解説
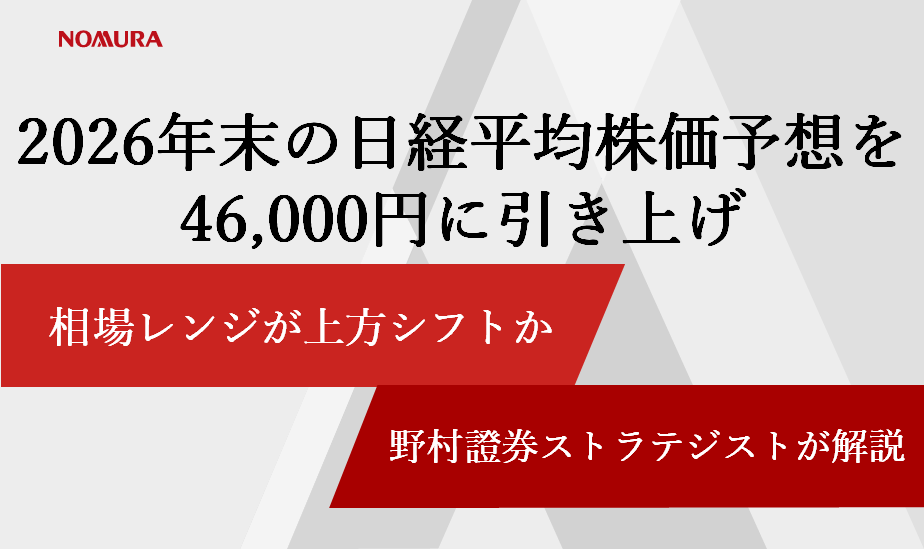
7月後半以降の日中時間帯における日本株の底堅さ
2025年7月後半に日米関税について大筋合意がなされた以降、日本株は場中(取引時間中)において強さ、底堅さが目立つようになりました。8月18日以降は、株価指数のピークアウト感が出てきたことで、日中に弱含む場面が増えていますが、従来のような場中での下落が常態化する傾向は減少しています。さらに、2025年9月8日以降は「高市トレード」への期待(自民党新総裁の下での財政拡張期待)が高まり、主要株価指数が大幅上昇し、高値を再度更新しました。
このような日本株の底堅さの背景には、石破茂首相辞任後の政局に対する財政拡張期待が一因となっていますが、主な要因は企業業績の回復期待と考えられます。2025年7月後半の日本株の上昇と連動し、アナリストの業績予想の方向感を示す「リビジョン・インデックス」がV字回復しています。
また、従来ほど「国内投資家による売り」が見られなくなっている需給構造も、日本株の底堅さに寄与している可能性があります。過去数年のTOPIX(東証株価指数)上昇局面では、通常、国内株式投資信託の資金フローが流出に転じるパターンが一般的でしたが、2025年7月後半以降の株高局面では大きな流出が見られませんでした。さらに、8月最終週には個人投資家が買い越しに転じたことも意外な動きです。従来は日経平均株価が4万円を超えた場面で売りが出ていましたが、今回は4万2千円を割り込む場面で買いが入るなど、相場レンジが上方にシフトした可能性があります。

(出所)NRI、JPX総研より野村證券市場戦略リサーチ部作成
金融・財政政策は基本的に景気を支援
2025年10月4日の自民党総裁選挙に向けて、当面は(1)財政政策、(2)野党との連携・連立の2つが、株式市場の期待値の変動要因となりやすいとみられます。次期自民党総裁が臨時国会で首班指名を受けて首相に就任する可能性が高いと見られますが、保証はなく、衆参いずれも少数野党である点は石破首相時代と変わりません。
次期自民党総裁の有力候補として高市早苗氏、小林鷹之氏、茂木敏充氏らが挙げられています。これらの候補が就任すれば、財政刺激への期待から株高・金利上昇が意識されやすいものの、すでに株高・金利上昇が進行していることから、株式市場が早期に様子見に転じる可能性があります。一方、小泉進次郎氏や林芳正氏が総裁となれば、政策の継続が意識され、市場へのインパクトは限定的と考えられます。
安定政権となれば経済政策の予見可能性が高まり、海外投資家にとって魅力となりやすいです。過去には政権交代後の内閣支持率上昇に伴い株高が進行した例もあり、これは構造改革期待(2001年、小泉純一郎政権)や財政刺激期待(2012年、第2次安倍晋三政権)など、経済政策への期待が株高要因となったとも考えられます。
9月7日の石破首相辞任表明においては、賃上げと同時に消費税の重要性が強調されました。麻生太郎氏、岸田文雄氏など自民党重鎮も消費税維持の姿勢を見せており、高市氏が主張する大規模な財政刺激策が実現するかは不透明です。ただし、参院選の結果を踏まえると、誰が首相になっても財政拡張志向は続きやすく、名目経済成長率(G)が長期金利(R)を上回る「G>R」局面は維持されやすいと考えられます。「G>R」局面では株式投資の優位性が意識されやすい傾向にあります。

(出所)内閣府、ブルームバーグより野村證券市場戦略リサーチ部作成
コーポレートガバナンス(企業統治)改革やNISA(少額投資非課税制度)の拡充も維持される見込みで、自社株買いやTOB(株式公開買い付け)を通じて株式需給は引き締まる傾向が続くとみられます。以上から、日本株はまだ利益確定のタイミングではなく、底堅い上昇相場が続くと予想しています。
業績見通しと株価指数見通しを引き上げ
円安や価格転嫁、米景気の底堅さなどを反映し、マクロトップダウンでの業績見通しの想定を見直したことに加えて、株式数の減少率について2025年度は2%、2026年度以降は1.5%とし、従来比で2026年度以降を0.5%引き上げました。これを踏まえ、TOPIXのEPS(1株当たり利益)変化率について、2025年度は前期比-1.1%から同-0.2%へ微減益に上方修正し、2026年度は同+7.5%から同+10.4%へと引き上げます。2025年度、2026年度の利益の上方修正には、主に為替と価格効果(値上げ)が貢献しています。
2026.3期のTOPIX EPS予想の引き上げを主因として、メインシナリオにおける2025年末のTOPIXは3,000から3,200、日経平均株価は42,000円から44,500円、2026年末のTOPIXは3,150から3,350、日経平均株価は44,000円から46,000円へ、それぞれ上方修正します。2027年末のメインシナリオはTOPIX 3,500、日経平均株価 47,500円と予想しています。これらの数値は日本株の期待リターン(配当込みで年率6%前後)とも整合性があります。
国内株指数見通し概要
| 2025年12月 | 2026年6月 | 2026年12月 | 2027年6月 | 2027年12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メインシナリオ | TOPIX | 3,200 | 3,250 | 3,350 | 3,400 | 3,500 |
| 日経平均株価 | 44,500 | 45,000 | 46,000 | 46,500 | 47,500 | |
| 上振れシナリオ | TOPIX | 3,500 | 3,600 | 3,700 | 3,800 | 3,900 |
| 日経平均株価 | 48,000 | 48,500 | 49,500 | 50,500 | 51,000 | |
| 下振れシナリオ | TOPIX | 2,700 | 2,750 | 2,850 | 2,900 | 3,000 |
| 日経平均株価 | 38,000 | 38,500 | 39,500 | 40,500 | 41,000 | |
| 従来のメインシナリオ | TOPIX | 3,000 | 3,100 | 3,150 | 3,250 | - |
| 日経平均株価 | 42,000 | 43,500 | 44,500 | 45,500 | - |
(出所)野村證券市場戦略リサーチ部作成
10月4日の自民党総裁選挙にかけては、政局への期待感から株価指数が大きく変動する場面が予想されます。その後は経済対策の具体化を見極めつつ、次期自民党総裁や首相が誰であっても「G>R」の状態が継続しやすい点が意識されるでしょう。10月末以降の2025年度中間決算では、2026年度以降の業績回復見通しが確認されること、株主還元策やTOBなど需給タイト化要因が再認識されることも、年末にかけて株価の支援材料になるとみています。2026年度は二桁増益が下支えし、株高基調が継続すると見込まれます。
株価見通しレンジの上限は大規模な財政刺激策の実施やコーポレートガバナンス改革の進展などを想定しています。一方、レンジ下限は、従来は景気後退時を想定した水準でしたが、現時点で野村證券では日米景気後退を予想していないため、景気減速やコーポレートガバナンス改革の停滞時などに見直しています。
(編集:野村證券投資情報部 デジタル・コンテンツ課)
編集元アナリストレポート
日本株投資戦略(9月号) – 意外にしぶとい日本株上昇相場(2025年9月12日配信)
(注)各種データや見通しは、編集元アナリストレポートの配信日時点に基づいています。
※この記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。