2025.04.09 NEW
日米株価の乱高下が続く FRBが“米国緊急利下げ”を決める可能性はあるのか 野村證券・美和卓
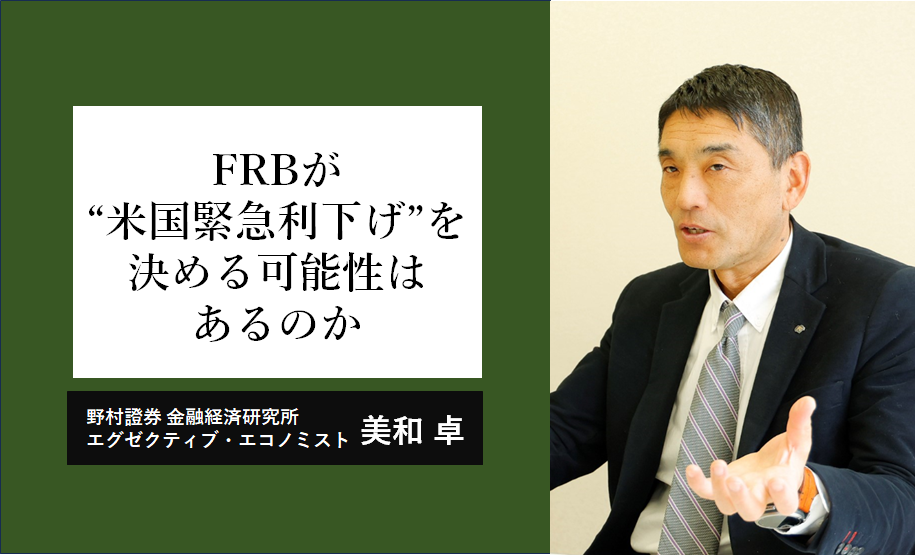
写真/タナカヨシトモ
米トランプ政権が4月2日に相互関税の発表を行って以来、世界で同時に株価が急落する事態に陥っています。4月8日の米株式市場では、NYダウが一時前日比1400ドルを超える上昇を見せましたが、米中通商摩擦への懸念からその後下落し、最終的に前日比320.01ドル安となり4営業日続落で取引を終えました。日本株式市場では、前日8日の日経平均株価が過去4番目の上げ幅となる1,876.00円高を記録しましたが、翌9日は寄り付きから大幅に下落する展開となりました。
トランプ大統領は4日、SNSでFRB(連邦準備理事会)のパウエル議長にとって、「今は利下げに絶好のとき」と投稿しました。では、FRBが米国の政策金利引き下げを決定するにはどんな条件が必要でしょうか。野村證券金融経済研究所
エグゼクティブ・エコノミストの美和卓が解説します。
FRBが利下げをすぐに決定できない理由
- 日米の株価は相互関税の発表以来急落しており、関税政策が変わらない以上、下落相場がずっと続くのではないかと恐れる投資家はいると思います。こうなるとFRBが利下げを決定することに期待する声が高まってくると思いますが、その可能性はどうでしょうか。
-
今のところ、FRBから利下げを急ぐ“シグナル”は出てきていません。4日、パウエル議長は講演で、雇用統計は強く経済は依然として好調であり、政策変更を急ぐ局面ではないと発言しています。関税政策については、「インフレ率を押し上げる可能性がある」と発言し、景気対策よりもインフレ対策が重要であると感じさせる発言が目立ちました。
ただし、マーケットの状況としては、FRBが利下げを決断せざるをえない可能性が出てきたと思います。株式を中心にリスクアセットの水準が切り下がってきており、関税が実態として景気へマイナスの作用を持つ可能性は高まっています。
野村證券はFRBが利下げを再開するのは2025年12月という予想を置いていますが、マーケットの動向によってはこれが早まる可能性はあります。
- FRBが利下げをすぐに決断しないのは、関税によるインフレを抑え込むために高い金利が必要だからでしょうか。
-
その通りなのですが、実は関税によりインフレが起きるというのは、本来は正しくありません。インフレとは、物価上昇が連続的に起きることを意味します。関税の引き上げは理論的には物価水準の上昇を招きますが、それは一度だけであり、物価上昇が継続するイベントではないはずです。
ただし、実際にはそんな風に物価が決まるわけではありません。物価が一度上昇すると労働組合が賃上げを要求する、賃上げされると購買力が高まる、すると関税と関係のない品目まで“便乗値上げ”がされる……といった物価上昇のスパイラルが起きる可能性があります。
これと似た現象について、パウエル議長率いるFRBは手痛い失敗をした経験があります。2021年、コロナ禍の影響で物価上昇の傾向が明らかになったときに、FRBはこれを「一時的」とみなし、利上げ開始を見送ったのです。しかし先ほど言及したような現象で物価上昇が連続して起きてインフレが収束せず、2022年以降に大幅に利上げをせざるを得ない事態となってしまいました。結果、2022年は米国の企業業績が堅調だったにもかかわらず大幅な株安となり、S&P500株価指数は年間で19%下落しました。
FRBはこれを教訓として、今回の関税についても、一時的な物価上昇にとどまらず持続的なインフレに繋がらないかどうかを慎重にみていると思われます。
FRBが“利下げを決定しなかった失敗”とは
- では、今回はこれだけ株価が下がっても米国の政策金利の引き下げはできない、ということになりますか。
-
現在とアフターコロナの経済情勢は似ているように見えますが、明らかな違いもあります。アフターコロナでは、コロナ禍で人々の経済活動が止められていた分、“強制貯蓄”と呼ばれる、通常よりも多くの余裕資金を持つ状態になりました。そしてコロナ禍で止まっていた生産の回復を上回るリベンジ消費が起き、供給よりも需要が上回る期間が長く続きました。物価が高くても買える、買いたい、だからさらに物価が上がるという循環です。
今は過剰な貯蓄が概ね解消しており、FRBの金融引き締め策により景気にブレーキがかかりやすい状態になってきています。そのため人々は「そんなに物価が高いと買えない」と判断するようになり、需要が供給を下回って物価上昇に歯止めがかかる可能性があります。こうした環境を考えると、コロナ禍後よりも利下げを決断しやすいのではないかと期待できます。
もうひとつ、FRBが「利下げを決断しなかった」失敗もあります。2024年8月の歴史的株価下落は、7月末のFOMC(連邦公開市場委員会)でFRBが政策金利の据え置きを決定した後でした。そして次の9月のFOMCには、4年半ぶりの利下げを決定しただけでなく、7月に利下げしなかった分を埋め合わせたという名目で一気に50ベーシスの利下げを決定しました。2つの失敗も、FRBが今後利下げを決断する上での教訓になりえると思います。
FRBは2024年9月のFOMCから3会合連続で利下げを行いましたが、それ以降は据え置きが続いています。次にFRBが利下げを決定するときが、今回の株式市場が底を打つきっかけになる可能性はあります。5月6~7日のFOMCがその最初の機会となりますので、注目したいところです。それまでに株価下落がずっと続くような事態になれば、もっと早く緊急利下げを決定する余地もあるでしょう。
日銀は利上げ方針を変えるのか
- 日銀はこの株価下落をふまえてどう動くでしょうか。日本は米国とは逆に利上げが予想されています。
-
今全世界で利下げが検討される事態なのに、日本だけが利上げという逆方向の政策を取っているのが、際立っていますね。しかし日銀で関税政策を受けて金融政策の変更が検討されているかというと、その兆候はありません。日銀があくまでフォーカスしているのは、国内で賃金と物価の上昇の好循環が生まれているかどうかです。賃金は上がっていることが確認できているので、政策金利を引き上げたいという方向性は変わらないでしょう。
ただ、客観的には利上げを決定できる余地は狭まってきたといえます。日銀が注視している地域経済報告、通称「さくらレポート」で直近4月7日に上がってきたレポートでは、ほぼすべての地域で、中小企業にもゆるやかに景気回復が見られるという報告がありますが、これには関税の影響は織り込み切れていません。今後、早ければ5月にも国内の一部製造業が生産を米国に切り替えるなどの変化が出てくることも予想されます。
リーマン・ショックの後も協調的に全世界で利下げが行われたのに対し、日本は逆方向でした。日本だけ株価の回復に関してダメージが残るという懸念は否定はできませんので、そうならないように慎重さは強めていると思います。野村證券は7月の日銀金融政策決定会合で、政策金利の追加引き上げが決定される予想を変えていませんが、マーケットを注視しながら、7月は据え置く可能性もあるでしょう。

- 野村證券 金融経済研究所 エグゼクティブ・エコノミスト
美和 卓 - 1990年野村総合研究所入社。東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了。2004年野村證券に転籍。2024年4月より現職。国内・海外のプロの投資家に対して、日本と世界の経済に関する分析、見通しを提供する一方、一般向けに経済、金融の仕組みを分かりやすく解説。著書に『金利「超」入門』(日本経済新聞出版社)など。
※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。