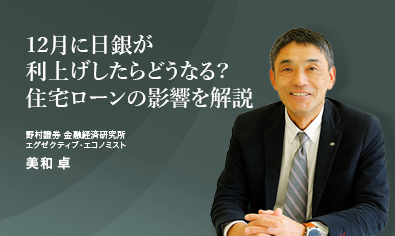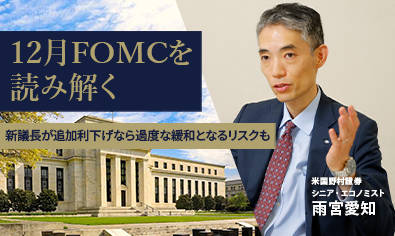2025.03.17 NEW
春闘の賃上げ率の上昇が、金利上昇にすぐつながるわけではない理由 野村證券エコノミストが解説
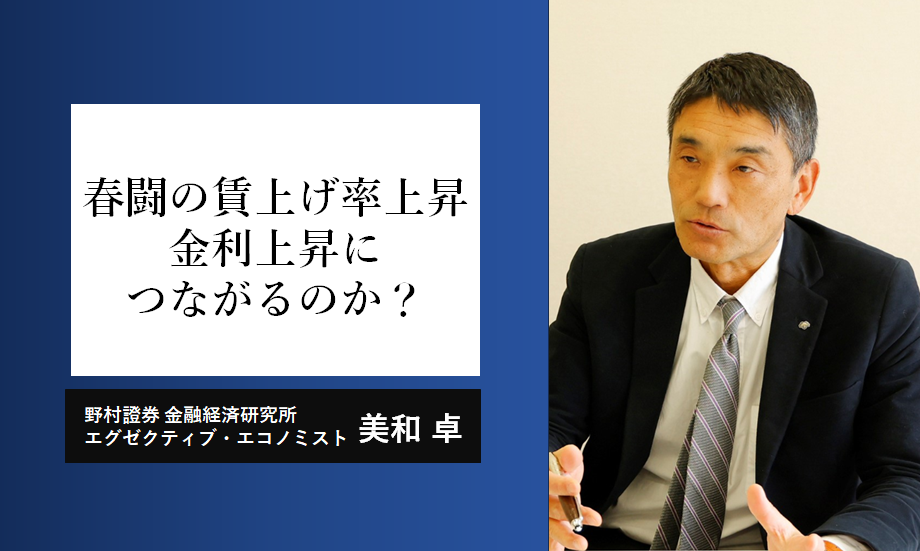
写真/タナカヨシトモ
上昇し始めた日本の金利がこれからも上がるのか。今後の金利動向を考えるうえで重要なファクターとなるのが賃金の上昇です。2025年3月14日に、春闘の第1回回答集計が発表されました。そこからわかることと今後の注目点を、野村證券金融経済研究所エグゼクティブ・エコノミストの美和卓が語ります。

日本労働組合総連合会(連合)が3月14日に、2025年春季労使交渉、いわゆる春闘の第1回回答集計を発表しました。基本給の底上げを意味するベースアップ(ベア)と定期昇給を合わせた賃上げ率の平均は5.46%と、昨年の5.28%からやや上がりました。一般的に大手企業よりも低い数字が出がちな中小企業の賃上げ率も、5.09%と33年ぶりに5%台に乗りました。これは、日本企業の業績が比較的良く、一方で人手不足を背景に採用難は深刻であり、賃金上昇圧力が高まっていることを反映しているでしょう。
春闘の賃上げ率には、日本の雇用者全体の賃金上昇率のペースセッターといった意味合いがあり、マクロ的な賃金上昇率を推しはかるために重要な指標であることは間違いありません。特に2024年あたりからは、日銀が政策金利の引き上げを決定していくうえで賃金と物価の好循環が重要だと発言しており、賃金への注目度は今も引き続き高いです。日本市場に詳しい海外の機関投資家からも注目される指標です。
ただし、春闘の賃上げ率が高いからといって、日銀は利上げを決定できるわけではありません。
重要なのは中小企業の賃上げ
日銀関係者の発言を表面的にとらえる限りでは、春闘の賃上げ率は政策決定に大きく影響していると考えられます。ただ、昨年から春闘の賃上げ率は高水準で今年もそれが継続しているなかで、日銀の関心事は中小企業の賃上げ率のほうに移ってきているといえるでしょう。
業績が良くキャッシュを貯めている大企業が賃上げするのは当然であるとして、その流れに中小企業がついていけなければ、賃金の上昇と物価の上昇の好循環が崩れてしまうということです。
中小企業まで考えると、賃上げについては企業間格差が広がっているという側面はあるかもしれません。なかには満額回答を上回る企業もあるなかで、野村證券の調査では春闘の満額回答率はむしろ下がっているという見方もあり、おしなべて賃金上昇圧力が高まっているわけではない可能性があります。
春闘の賃上げ率の傾向としては、集計が進むにつれて中小企業の割合が大きくなってきますので、数字はだんだんと下がっていくのが普通です。それを加味しても、今後の賃上げ率の数字が大きく下がらないかどうかは重要です。
また、この集計は連合が行っているものであり、賃金交渉をしている組合が連合に加盟していなければ集計に反映されません。中小企業のなかでも特に規模が小さくなればなるほど連合に加盟している企業は少なくなりますから、その実態は集計を見てもわからないということになります。
そのため、日銀が特に注目しているのは四半期に一度の支店長会議の前段として行われる、各支店へのヒアリングです。中小企業において賃上げをするという声が上がっているか、という定性的な評価が各支店から上がってきます。こちらのほうが今、政策決定には大きく影響すると思われます。
春闘の賃上げ率に含まれない層
では、中小企業も含めて賃上げ率が上昇すれば、金利上昇につながるのでしょうか。
論点は二つあります。まず、春闘のベースアップが、実質賃金の計算につながるマクロ全体の賃金上昇に結び付くのかどうかです。春闘の賃上げ率は5%を超えていても、現金給与総額という統計でみた一人当たりの賃金上昇率は5%には全く届かず、直近では前年比2%台です。賃金上昇率に物価上昇率を加味した実質賃金がプラスにならないのは、全体の賃金上昇率が低いからです。
春闘の賃上げ率の数字が示しているのはあくまでも組合員の賃金であり、ここには管理職が含まれません。総じて管理職のほうが高い賃金を得ているので、この層の賃金が上がらないと、若い層の賃金をかなり上げたとしても全体の賃金上昇率は上がりません。そして、組合員に含まれないもうひとつの層は非正規雇用の従業員です。この層の賃金が据え置きになってしまうと、やはり実質賃金の上昇にブレーキがかかります。
物価が高い実感があっても、日銀の目標は達成されない
もうひとつの論点は物価の上昇です。今、足元でコメ価格などの物価は上がっているんだから、日銀が目指す物価上昇率2%を達成し、利上げできる環境になっているのだろうと思いがちなんですがそうではありません。物価が上がっているという情報を得ると、消費活動が抑えられてしまうのです。
特に鍵になるのが年金生活者です。年金は年金財政の持続性を保つために、マクロ経済スライドという仕組みを取って、金額が上昇していきます。しかし、現役世代の賃金上昇と比べると、年金の上昇率は必ず割引されてしまいます。年金はそれほど増えないというのがわかっているため、年金生活者はコメなどの生活必需品の値段が上がると、もっと支出を絞ろうとしてしまうでしょう。
実際に消費動向はどうなっているかというと、先週発表されたGDPの二次速報による10-12月期の実質民間消費の増加率は前期比0%となりました。同じ日に発表された1月の家計調査によると、一世帯当たりの消費額は実質ベースで前月比マイナス2.5%です。今後どうなるかははっきりしませんが、1-3月の家計調査を反映したGDPは、前期比マイナスになる恐れもあります。
これらのデータは、米価の上昇を受けて実質所得がマイナスとなり、生活防衛のために支出を減らす傾向が強まっている証左ともみることができます。
日銀が賃上げを重要視し、春闘で高い賃上げ率が見られたとはいえ、これが景気回復を裏付けて金利上昇につながるわけではないことを強調しておきます。賃金が上がり日本全体の消費者の所得が実質上がって、その結果消費需要が伸びることが最も重要です。消費需要がないと、企業は値上げができないからです。

- 野村證券 金融経済研究所 エグゼクティブ・エコノミスト
美和 卓 - 1990年野村総合研究所入社。東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了。2004年野村證券に転籍。2024年4月より現職。国内・海外のプロの投資家に対して、日本と世界の経済に関する分析、見通しを提供する一方、一般向けに経済、金融の仕組みを分かりやすく解説。著書に『金利「超」入門』(日本経済新聞出版社)など。
※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。
- 手数料等およびリスクについて
-
当社で取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料(換金時手数料)および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、年金保険・終身保険・養老保険・終身医療保険の場合は商品ごとに設定された契約時・運用期間中にご負担いただく費用および一定期間内の解約時の解約控除、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の委託保証金または委託証拠金をいただきます。信用取引、先物・オプション取引には元本を超える損失が生じるおそれがあります。証券保管振替機構を通じて他の証券会社等へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、移管する銘柄ごとに11,000円(税込み)を上限額として移管手数料をいただきます。有価証券や金銭のお預かりについては、料金をいただきません。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。