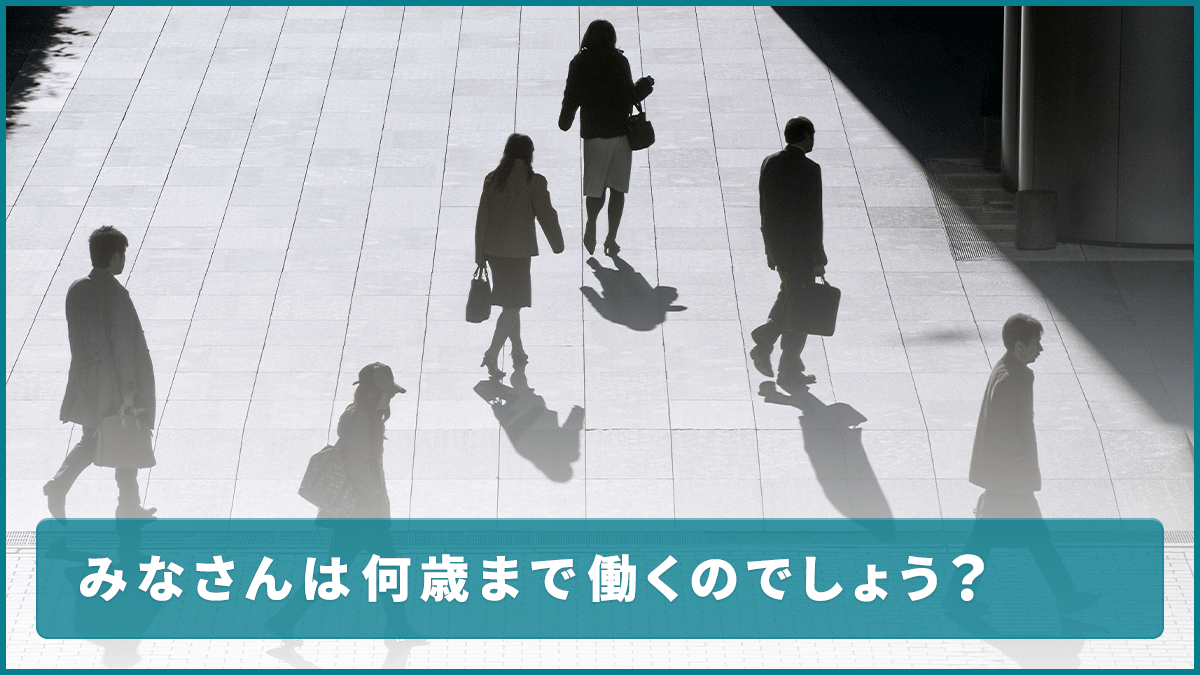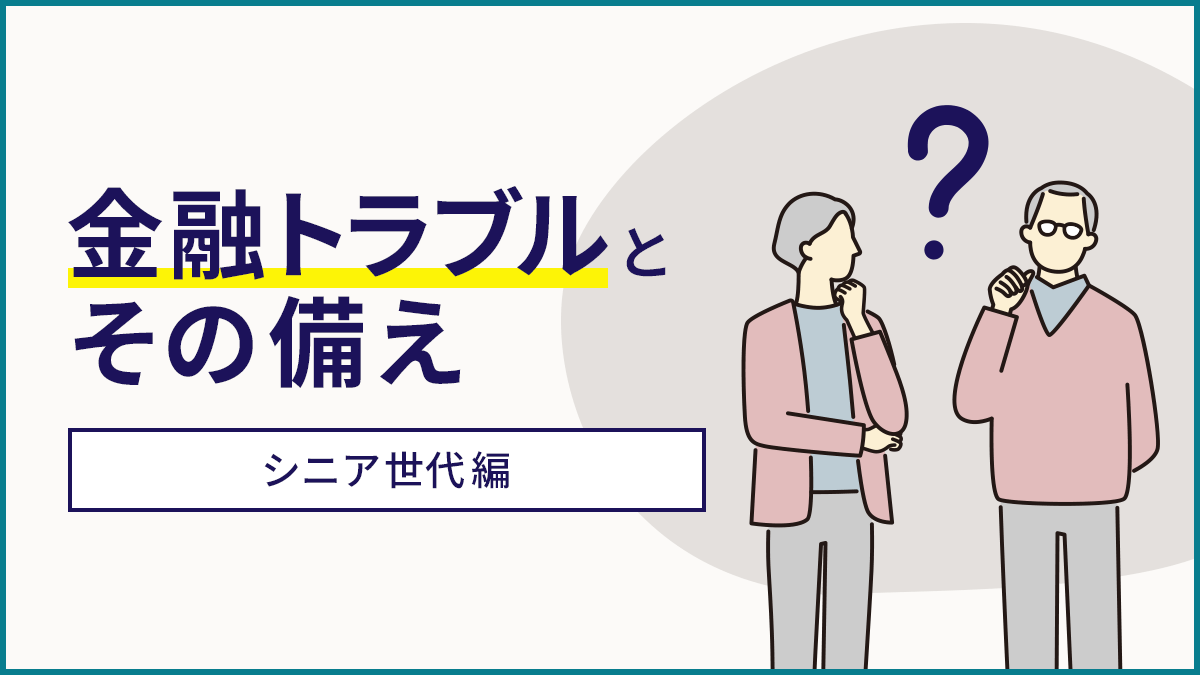定年退職と再雇用の手続きとポイント<退職時に必要な手続きとは?>
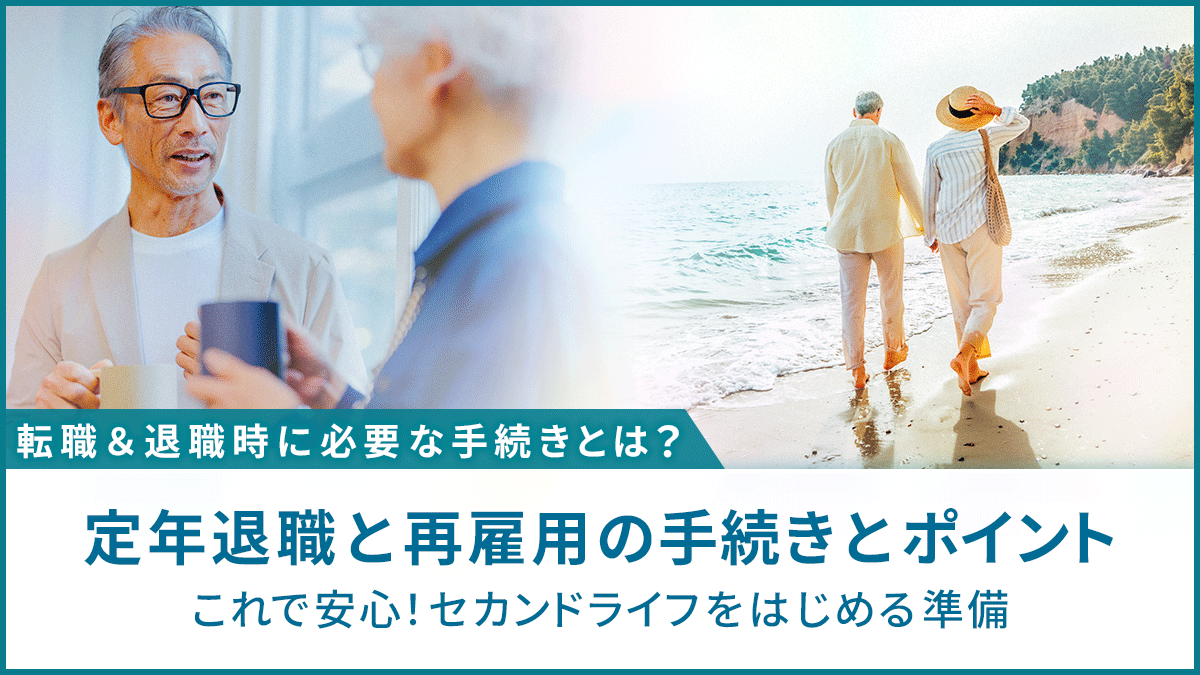
定年退職する方へ
はじめに
定年退職、再雇用の期間を満了して職場を離れるという節目は、多くの方にとって「働く人生の一区切り」と言えます。「退職後の健康保険はどうなるの?」「年金はいつから、どうやってもらえるの?」「税金や手続きに抜けがないか心配」という不安を感じるのも当然です。安心してセカンドライフを始めるために、年金制度と手続き方法を理解して、必要な準備を整えておくことが大切です。
このコラムでは、定年退職、再雇用の終了時に必要な手続きや注意点をわかりやすく説明して、退職金や高齢者給付など大切なポイントをチェックリスト形式で整理しています。
定年退職を迎えた時の3つの選択肢
それでは、定年退職にともなう準備や手続きを、3つのパターンに分けて整理していきます。
1. 定年を迎えて退職(定年退職)
2. 定年後に再雇用で働く(再雇用)
3. 再雇用が満了し退職(満了退職)
記載する年齢は一般的な会社員のモデルケースを参考にしていますが、定年延長や定年廃止するケースも増加しており、実際の退職年齢や再雇用期間、必要な手続きは所属先や個々の事情によって異なります。ご自身の状況にあわせてご確認ください。大切なことは、スムーズに移行ができるよう事前に必要な情報を整理し、余裕をもって準備しておくことです。
チェックリストの項目は主なものを取り上げています。年齢はモデルケース。
1. 定年退職を迎えるとき(60~65歳)
ここでいう「定年退職」は、労働契約の区切りを迎え、勤務先を完全に離れるケースです。
健康保険
退職すると在職中の健康保険は使えなくなりますが、次に加入する健康保険を選択します。現在、家族を扶養しているか、任意継続保険と国民健康保険(以下、国保)どちらの保険料が安いのか、またはサービスが充実しているかを検討して決めましょう。
| 勤務先の健康保険任意継続制度の利用(最大2年間) 1 | |
| 国保への加入 | |
| 家族の扶養に入り、家族の健康保険に加入する(但し、収入要件あり) | |
| 再就職先の健康保険に加入 |
1 任意継続の申請期限は退職日の翌日から20日以内、国保の申請期限は14日以内
国民年金
国民年金への切り替えは原則不要です。保険料の未納期間がある場合は、任意加入制度を利用し、将来受け取る年金額を増やすことができます。また、扶養している配偶者が60歳未満の場合は、国民年金の第3号被保険者(会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者に扶養される配偶者の方)から国民年金の第1号被保険者(自分で保険料を納付する方)への切り替えが必要となります。
| 配偶者(第3号被保険者)が60歳未満の場合、第1号被保険者への手続き | |
| 国民年金納付期間が40年に達しない場合、「任意加入」して年金額を増やせる可能性あり | |
| (再就職する場合)新しい勤務先の厚生年金に加入 | |
| 年金の繰り上げ受給の手続きをする(ひと月あたり年金受給額0.4%減額 2 。繰り上げ請求した場合、生涯減額した年金額のまま) |
2 2025年10月時点
雇用保険の失業手当
定年退職した後、再就職する意思があれば、失業手当を受けることができます。定年退職は原則「会社都合退職」として扱われますので、失業保険の受給資格が認定した日から7日間の待機期間後、翌日から支給されます。
| 「離職票」を事業主から発行してもらう | |
| 「雇用保険被保険者証」を発行してもらう | |
| ハローワークにて求職の申し込み、失業手当の申請 | |
| (再就職し、賃金が再就職前の75%未満の場合)「高年齢再就職給付金」の対象(但し、条件あり) |
税金・その他の手続き
| 勤務先から「源泉徴収票」を必ず受け取り、保管する(確定申告が必要な場合) | |
| 住民税の支払い方法の確認(1~5月事業主が一括徴収/6~12月個人で納付書払い) | |
| 財形貯蓄や持株会、企業型確定拠出年金(以下、企業型DC)など勤務先の福利厚生制度の手続きを確認 |
2. 定年後に再雇用で働く場合(60~65歳)
定年を迎えても、就業を希望すれば、再雇用制度のある企業や団体が多くなっています。雇用形態が変わるため、新たな契約を結びます。ほとんどの手続きは勤務先からの案内があると思いますが、ご自身でも契約内容をしっかり確認しましょう。
健康保険・厚生年金の資格
| 同日得喪(どうじつとくそう)の確認(退職日と再雇用開始日が同日である。社会保険料の再計算のため) | |
| 健康保険・厚生年金の再加入 |
高年齢雇用継続給付金
| 60歳時点の賃金より給与が75%未満に減額された場合は「高年齢雇用継続給付」の対象になる(但し、条件あり) | |
| 所属先に申請後、事業主がハローワークに手続き(通常は勤務先から案内あり) |
詳細の条件については、ハローワーク等でご確認ください
在職老齢年金
年金を受け取りながら働いている場合に、(年金+給与)>基準額(51万円・令和7年度)の場合、年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
| 65歳未満は、在職中の給与により老齢厚生年金が減額される可能性あり、要確認 |
その他、税金関連
| 労災や雇用保険の適用 | |
| 福利厚生の確認(住宅手当、通勤手当ほか) | |
| 源泉徴収票を受け取る(確定申告が必要な場合) | |
| 住民税の支払い方法の確認 | |
| 財形貯蓄や持株会、企業型DCなど勤務先の福利厚生制度の手続きを確認 |
3. 再雇用満了で退職するとき(65歳以降)
再雇用期間が終了し、本格的にリタイアする場合やさらに仕事を続ける際にも、重要な手続きがいくつかあります。
健康保険
| 勤務先の健康保険任意継続制度の利用(最大2年間) 3 | |
| 国保への加入 | |
| 家族の扶養に入り、家族の健康保険に加入する(但し、収入要件あり) |
3 任意継続保険の申請期限は退職日の翌日から20日以内、国民健康保険の申請期限は14日以内
国民年金
扶養している配偶者が60歳未満の場合は、国民年金の第3号被保険者(会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者に扶養される配偶者の方)から国民年金の第1号被保険者(自分で保険料を納付する方)への切り替えが必要となります。
| 配偶者(第3号被保険者)が60歳未満の場合、第1号被保険者への手続き | |
| (65歳以降さらに再就職する場合)新しい勤務先の厚生年金に加入(70歳まで) |
雇用保険
| 「高年齢求職者給付金」の申請(65歳以上で再就職の意思あり・被保険者期間が1年以上の場合50日分) | |
| 64歳11か月で退職する場合、失業手当が受け取れる | |
| 65歳以上で退職する場合、高年齢求職者給付金が受け取れる |
在職老齢年金
年金を受け取りながら働いている方が、(年金+給与)>基準額(51万円・令和7年度)の場合、年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
在職定時改定制度
厚生年金に加入中で、老齢厚生年金を受給している65歳以上70歳未満の方が、毎年1回基準日の9月1日において被保険者であるときは、翌月の10月分の年金額から見直されます。
65歳未満の方は繰上げ受給をされている方であっても在職定時改定の対象外
税金・その他の手続き
| 老齢年金から住民税が特別徴収で引かれることを確認 | |
| 確定申告が必要な場合は、源泉徴収票と公的年金の源泉徴収票などを準備する |
特に注意したいポイント・手続き漏れに注意
定年退職や再雇用満了のタイミングは、手続きや確認事項が多く、想像以上に慌ただしくなりがちです。知らなかった、うっかり忘れていた…という小さな見落としが、のちのちご自身の負担や損失につながることも少なくありません。たとえば、健康保険を任意継続保険に切り替える申請期限は、退職翌日から20日以内と決まりがあります。公的年金を受給するためには、申請が必要で、手続きを忘れると、受給が遅れるケースもあるため注意が必要です。また、高年齢求職者給付金などの「もらえるお金」も申請しないと受け取れません。それぞれ年齢のステージで住民税の納付方法が変わる点や、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付、退職時の持株会や財形貯蓄の手続きなども含め、事前の確認をしっかり行いましょう。
さらに意外と見落としがちなのが退職金の税金です。退職所得控除という税制優遇措置がありますが、「退職所得の受給に関する申告書」を所属先に出していないと、高い税率がかかることもあるので、注意が必要です。通常、この申告書は退職手続きの際に所属先から渡され、必要事項を記入して提出すると、所属先が上記の優遇された方法で税金を正しく計算し、源泉徴収してくれます。もし、この申告書を提出し忘れても、確定申告をすれば、払い過ぎた税金は全額戻ってきますが、一時的に手元に残るお金が減り、確定申告の手間もかかってしまいます。これらは、しっかり確認しておきたいポイントです。
定年後のライフプラン
定年を迎えるタイミングは、「働き方」だけでなく「生き方」そのものを見つめ直す大きな節目です。人生100年時代、これからの暮らし方・お金の使い方・時間の過ごし方が、ますます多様化しています。定年を迎えて完全退職した場合は、自由な時間を送ることができるかもしれません。定年後再雇用期間は、同じ職場に勤めたとしても収入が大きく変動する方も多いでしょう。現役時代と同じお金の使い方ではなく、家計の見直しや高年齢雇用継続給付など制度の情報収集を行い、老後資金が枯渇しないようしっかりと資金計画を見直しましょう。定年後の再雇用満了以降は、本格的なリタイア生活に入る方が多いと思います。リタイア以降も、家計管理をしっかり行い、今後の人生を楽しむために健康面も留意していきましょう。
定年を迎えた後の生き方はご自身が選択することです。「あなたらしいこれから」を、自分の価値観や人生のテーマにそって描けることが大切です。そのために「どう暮らしたいのか」を軸に、今後のライフプランを考えてみてください。
まとめ
定年退職後は、働き方も暮らし方もさまざまです。定年という区切りを迎えるタイミングは、自分自身や家族の未来を見つめ直す大きなチャンスです。定年まで頑張ってきた自分に「これから、どう生きていきたい?」と問いかけながら、心豊かなセカンドライフを描いていきましょう。そのためには、情報収集を行い、しっかりとセカンドライフの準備をすることで、将来への不安が和らぎ、新しい一歩を踏み出せるのではないでしょうか。
編集協力:寺澤真奈美 2級ファイナンシャル・プランニング技能士編集/文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部
記事公開日:2025年10月2日