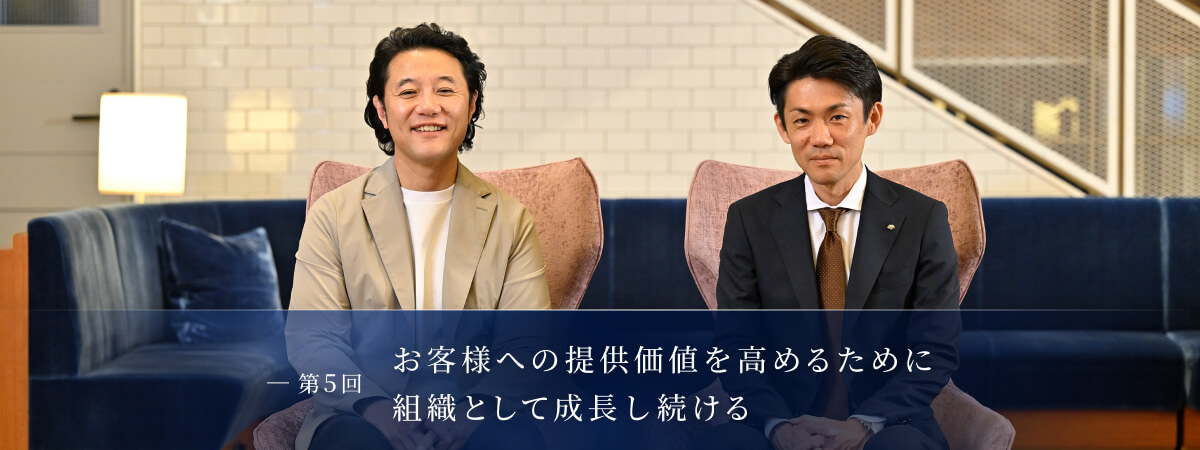
- (写真左から)
-
入山 章栄 氏
早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授
-
藤井 宏樹
営業企画部長
この記事は、日経ビジネス電子版に2025年7月11日から掲載した広告記事を日経BPの許諾を得て掲載しております。
連載最終回となる第5回は、野村のビジネスモデルの変革と組織カルチャーについて迫る。野村は、10年以上前からビジネスモデルの変革に取り組み、ウェルス・マネジメント(以下、WM)ビジネスに注力している。無形のコンサルティングビジネスであるWMを提供して、お客様との信頼関係を構築し、人生に寄り添いながら長期にわたって伴走する。早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授の入山章栄氏が営業企画部長の藤井宏樹氏に、なぜお客様一人ひとりからの期待に応え続けるために、野村の人が成長し続けることができるのかについて聞いた。
入山章栄氏(以下、入山)野村の戦略や具体的なサービス展開について教えていただけますか。

藤井宏樹氏(以下、藤井)野村では、10年以上かけてブローカレッジ型(金融商品を売買する際に手数料をいただくモデル)からストック型(お客様からお預かりする資産に対して手数料をいただくモデル)へのビジネス移行を進めてきました。先が読みにくい時代となる中で、お客様の「資産」に関する悩みも多様化しており、金融の枠に捉われない包括的な資産管理サービス、すなわちWMサービスを提供することで、お客様の課題を解決しています。
入山非常に大切な変革ですね。多くの日本人は、日々の収入や支出といったフローで物事を見ており、資産全体、いわゆるストックの感覚が希薄なんですよね。本当に豊かになるためにはストックをうまく活用すべきで、考え方を変えていきたいですよね。
藤井おっしゃる通りです。私たちは単純に資産を増やすことだけにフォーカスするのではなく、これまでの資産運用の枠を超えて、お客様のかなえたい未来を実現するための最適な解決策を提供し続けています。

入山野村ではそうしたサービスを実践されているのですね。ビジネスモデルの変革を行う中で、営業手法も変わってきたのでしょうか?
藤井評価指標を変え、目指す方向性を根気強く発信することで、社員の意識改革は進み行動が変わっています。また、お客様と同じ方向を向くことができる体制を数年かけて整備してきました。特に、2023年には、お客様一人ひとりに寄り添う時間が不足することがないように、1人の営業担当者(パートナー)が受け持つお客様の数を適正化すべく、対面パートナーの数を1.5倍に増やしています。
ビジネスモデルは変わりましたが、証券会社としてマーケットの変動に長年対峙してきた経験を活かし、変化を読むことができるのは、昔から受け継がれる野村の強みだと考えています。
入山確かに、証券会社である野村ならではの価値ですね。
藤井はい。そして、WMの本質は、課題解決ではなく課題設定です。なぜ資産を形成し、管理するのかを、お客様と共に考え続けるからです。そのため、お客様が豊富な金融知識をお持ちであっても、私たちが必要ないということはなく、対話を通じて、ご自身も気づいていない課題を浮き彫りにし言語化することで、お客様一人ひとりの未来像を一緒に明確にしていきます。私たちは、お客様と共にその考えを練り上げ、伴走し続けます。
入山野村の強みは、マーケット等の変化に対応しながら長期伴走できる圧倒的な知見を持つ社員がいることですね。お客様からすると「なんでも相談できる」と感じるのだと思いますが、お客様から寄り添う存在と認めていただくためには、相当な時間がかかるでしょう。
藤井私たちのビジネスは、前提として信頼関係の構築が必要です。お客様からの小さな宿題を確実にこなし、こつこつと信頼を積み上げていくことで、本当の意味で寄り添える存在になれるのです。
入山信頼してもらうことが大事ということですね。まさに、人間力が問われますね。お客様から信頼されるための人間力を組織として高めていくためには、人によって信頼の得方が異なるので、経験させるしかありません。まさに経営者を育てることと同じで、経営者も経営することを経験しないと育ちません。時にお叱りを受けたとしてもお客様に寄り添う経験を重ねていくことで、お客様から信頼される人間が育っていくのでしょうね。
藤井私たちのお客様は、大切な資産を長期にわたりお預けいただくため、私たちに対する期待が非常に大きいです。お客様の期待に応えるためには乗り越えなければならない壁も高く、その結果として、「もっとこうした方が喜ばれるのではないか」と真剣に考える機会も増え、お客様に寄り添うことを経験する機会も多くなります。さらに、マーケットは想定とは異なる動きをします。そんな時こそお客様にとことん向き合い、何があっても逃げない姿勢が問われます。そのため、お客様一人ひとりにしっかりと寄り添い考えるカルチャーが、野村には脈々と受け継がれていますし、こうした経験やお客様に教えていただく様々なことが、私たちの成長の大きな糧となっています。
入山なるほど。
藤井お客様の価値観まで理解したうえで人生に伴走し、期待に応え続けることが、社員の成長や組織としてのサービス開発体制の強化につながり、結果、お客様への提供価値が向上する循環が生まれていると感じています。
入山これからAI時代が本格的に到来し、肉体労働はロボットに、頭脳労働はAIに、それぞれ置き換わる可能性があります。最後に残る仕事は感情労働だといわれています。先ほど伺った、WMの本質である課題設定の領域は、AI(人工知能)には代替されにくいでしょうね。金融分野でいえば、金融ポートフォリオだけが欲しいならAIが担うでしょう。ですが、人生観を踏まえたうえで感情に訴えられることに頼りたい人もたくさんいます。やはり証券会社にとっては、人材が非常に重要な資産だと思います。
藤井まさにその通りです。私たちは能力・専門性だけで信頼を勝ち取ることはできません。お客様の価値観や感情に寄り添い、もっと豊かな人生を送っていただくために伴走し続けることで、共に歩む存在と認めていただけます。現在は、全国の部店長が集まり、こうしたWMを体現できる人材をどのように育てていくことができるか等を議論する場を設けたりしています。
入山そうした暗黙知を形式知化して共有していく取組みは非常に大事です。実際にパートナーにも集まってもらい、成功事例や失敗事例などを共有すると、社内でも熱気が生まれていくのではないでしょうか。
藤井はい。お客様に寄り添って期待に応え続けることで得られる学びや経験が成長につながり、モチベーションも向上するため、野村には、成長意欲が高い社員が育つ風土があります。個人の学びや経験を共有し言語化して、お互いに学びを深めていくことで、社員たちはさらに成長していきます。コミュニケーションの時間をあえて取ることで、成長していく仕組みを組織として作っています。
入山いいですね。藤井さんのお話を伺って、僕もWMの相談をお願いしたくなりました。




