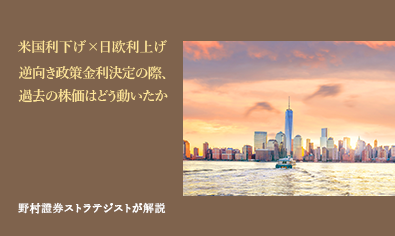2025.07.29 NEW
野村総研・木内登英さんが語る 参院選後の日本政治 今後の注目点は「消費税減税」議論の行方
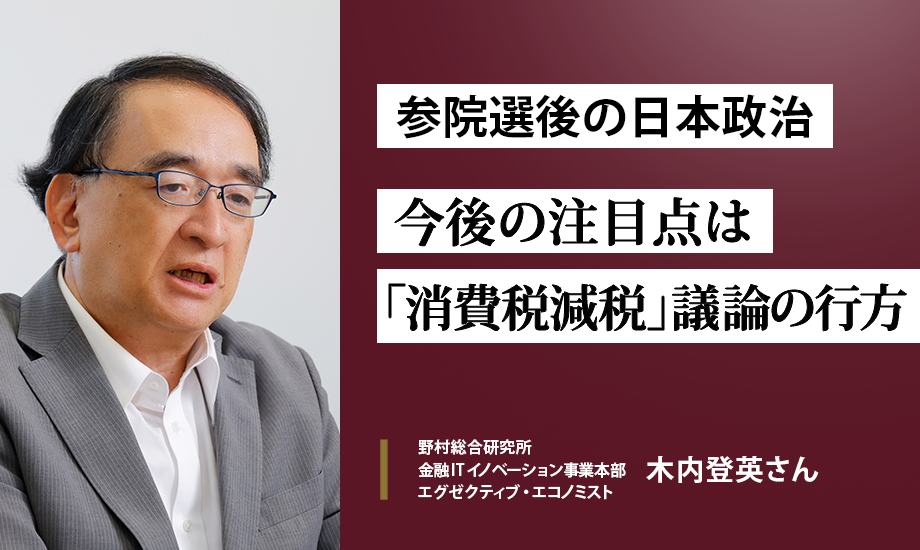
写真/タナカヨシトモ(人物)
7月20日の参議院議員選挙で与党は大敗し、衆参両院で過半数を割る厳しい結果となりました。国内政治の混乱は金融市場にどのような影響をもたらすでしょうか。野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミストの木内登英さんに、参院選後の金融市場、財政政策や金融政策の見通しについて聞きました。

衆参過半数割れで財政政策は拡張傾向に
- 参議院議員選挙で与党の自民党と公明党は大敗し、衆参両院ともに少数与党になりました。政局の不安定化は金融市場や財政・金融政策にどう波及するでしょうか。
政治の不安定化は一般的に経済活動にはマイナスに働きます。与党が参議院でも、議席の過半数を失ったことで政策を進めていくのはより難しくなります。より野党の意見も取り入れなければならなくなると、財政政策は拡張的になりやすい。金融政策については、野党の影響力が強まったことによって、日本銀行が利上げしにくくなる可能性があります。
財政拡大は短期的にはもしかしたら、景気にはプラスかもしれませんが、金融市場の反応次第によっては必ずしもプラスではありません。注意しなければならないのは、すでに足元でも表れてきている金利上昇と円安です。例えば、日本では債券市場は長らく財政環境に反応しない動きでしたが、日本銀行の利上げとともに債券市場の機能が少しずつ戻ってきています。金融市場の動きが財政環境に対して敏感になっており、積極財政政策に対して警鐘を鳴らすかもしれません。
悪いシナリオとしては、行き過ぎた財政政策によって大幅な長期金利の上昇で金融市場の混乱を招く可能性があります。また、財政赤字拡大によって円安が進むと、物価高を助長し、個人消費にはマイナスになってしまいます。良いシナリオとしては長期金利の上昇を市場の警鐘として、政治が受け入れれば、財政拡張に歯止めがかかるという可能性があるでしょう。
- マーケットはどこまでの財政政策を織り込んでいるでしょうか。
参院選後、ある程度の積極財政は避けられないことは市場も織り込んでいると考えています。秋に控える補正予算の議論では、自民党が掲げた給付金が焦点になります。給付金については立憲民主党も掲げているので、立憲民主党の協力で秋には実施される可能性はあると考えています。野党が足並みを揃えるガソリンの暫定税率の廃止もあります。
最大の注目は消費税減税までいくかどうかです。これについてはまだ分かりません。参院選で野党はすべて消費税減税を掲げましたが、各党の中身はバラバラなので簡単にはまとまらないというのがメインシナリオです。例えば、立憲民主党は原則1年間の食料品の消費税0%への引き下げを掲げましたが、財政規律を維持する姿勢を示しており、赤字国債発行で大型の消費減税を掲げている他の野党も少なくないなかでは一線を画しています。ただし、消費税減税が成立の方向に進む場合には、日本国債の格下げも意識されやすくなり、金融市場には一定の影響はあるでしょう。
- 市場の焦点となっている消費税減税の議論は、石破茂首相の進退が影響する面も大きいと思います。
今後、石破政権がどうなるかはわかりません。市場は半分程度、退陣を織り込んでいるのではないでしょうか。ただ、世論も、自民党内も意見は分かれています。自民党内の旧派閥間の対立も残っており、単純に選挙結果だけで退陣が決まるわけではないでしょう。
後任者が財政拡張的な考えである場合には、野党と連携して、積極財政傾向に強く進んでしまいます。例えば、有力な候補の一人である高市早苗氏は同じく候補となりえる小泉進次郎農林水産大臣や林芳正官房長官よりも、財政拡張路線が強く、野党と一体となって消費税減税に動く可能性が出てきます。
物価高対策の先は労働生産性の向上
- 今回の参院選での国民民主党や参政党の躍進をどうみているでしょうか。
自民党や立憲民主党などの既存政党の新鮮味はなくなっているなかで、国民民主党や参政党が選択肢になりました。ただ、選挙ごとの一種のブームで終わってしまう側面もあると考えているため、本当に持続性があるかどうかは見極めなければなりません。右派政党が今後も勢力を伸ばしていくかは分かりません。右派勢力が持続的に影響力を高めている米国や欧州とは日本の国民性は異なるのではないでしょうか。
生活自体が物価高で圧迫されているなかで、誰かのせいで自分の生活が悪くなっているという意見が通りやすくなります。給付金、減税、社会保険料の引き下げといった政策が出てくるのは、限られた資源の分配を変えるとの主張が受け入れられやすいからです。しかし、本来目指すべきなのは所得を他の人に不当に奪われているというストーリーにとらわれるのではなく、全体のパイを大きくする、つまり成長戦略を地道にやっていくことに尽きます。
減税か、給付金かという目先の政策論に注目が集まってしまい、本質論に目が向けられなかったのが今回の選挙です。長期的な視点でどういう国にするのか、本来、有権者が選択すべきことが選択されていないという問題はあります。
- 長期的な視点で議論を行うためには、どのような議論に目を向けるべきでしょうか。
足元のように急激に物価が上がるときは、労働分配率が下がるので、確かに企業に分配が偏ってしまいます。普通は物価が急激に上がっても一時的だが、今回は円安の影響やコメや野菜の高騰で息が長い物価高になっている。企業による賃上げにも限界があるなかで、米価対策など物価自体を下げることは重要です。さらに行き過ぎた円安を修正できるのであれば、物価高対策につながります。
それで物価高が収まったとしても、長い目でみた実質賃金の上昇率は、今度は労働生産性を高めていかないと実現できませんし、将来、良い生活ができるという期待も高まりません。短期的な物価高対策に加えて、どうすれば労働生産性のトレンドが上がるのかの議論をする必要があります。

日米合意後も日銀は関税の影響を見極める姿勢は変わらず
- 国内政治の不透明感が増す一方で、米国との関税交渉は合意に至りました。今後の日本銀行の金融政策の見通しはどうみているでしょうか。
日米関税交渉の合意によって、日本銀行の利上げ時期が若干早まる可能性はありますが、すぐに利上げに動くわけではないでしょう。日本銀行の内田眞一副総裁は「(日米合意は)非常に大きな前進であり日本企業にとっては不確実性が低下した」と評価しつつも、「世界経済全体、日本経済全体にとっての不確実性は引き続き高い」と見ています。
今までより高い関税率が課されることで経済にどのような影響を与えるかを見極めている段階にあるのは変わらないでしょう。私は日本銀行の利上げ時期は2025年12月と見ています。日本銀行が利上げが可能なときに利上げをしておきたいという意識が強くなる場合には、利上げ時期が早まるリスクはあります。その場合は最短では2025年9月になりますが、可能性が高いとまでは言えません。
- 日本銀行の最終的な政策金利の到達点と長期金利をどう見通しているでしょうか。
日本銀行の政策金利が到達するところとしては1%、上振れたとしても1.25%と予想しています。食費などの表面的なインフレ率は上振れているとはいえ、基調的なインフレ率はほとんど高まっておらず、日本銀行が目指している「賃金と物価の好循環」はほぼ起こっていません。サービス価格や、生鮮食品とエネルギーを除く「コアコアCPI」は1%半ばで推移しており、おそらく市場のインフレ期待もその程度でしょう。
予想するターミナルレートに基づくと、足元の長期金利は少し上振れているという見方ができます。そこは財政リスクプレミアムが乗っているからだと考えています。
債券市場が、消費税減税による財政悪化をどの程度織り込んでいるのかにもよりますが、日本国債の格下げリスクが出てくるような悪い金利の上昇にならなければ、長期金利はどこかのタイミングで1.5%よりは低い、1%前半の水準で落ち着いてくると見ています。

- 野村総合研究所 金融ITイノベーション事業本部 エグゼクティブ・エコノミスト
木内登英 - 1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。
※本コラムで取り上げられたマーケットや投資に関する考え方などについては、あくまで個人の見解によるものであり、野村證券の意見を代表するものではございません。本コラムは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。
- 手数料等およびリスクについて
-
当社で取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料(換金時手数料)および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、年金保険・終身保険・養老保険・終身医療保険の場合は商品ごとに設定された契約時・運用期間中にご負担いただく費用および一定期間内の解約時の解約控除、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の委託保証金または委託証拠金をいただきます。信用取引、先物・オプション取引には元本を超える損失が生じるおそれがあります。証券保管振替機構を通じて他の証券会社等へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、移管する銘柄ごとに11,000円(税込み)を上限額として移管手数料をいただきます。有価証券や金銭のお預かりについては、料金をいただきません。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。