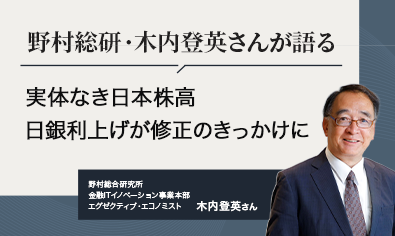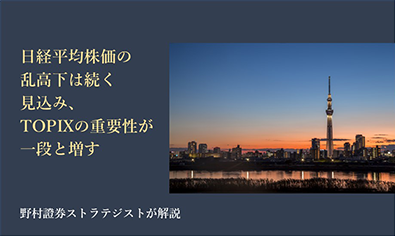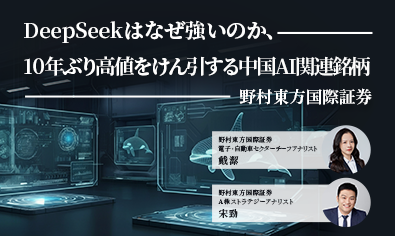2025.11.10 NEW
野村総研・木内登英さんが語る 実体なき日本株高、日銀利上げが修正のきっかけに
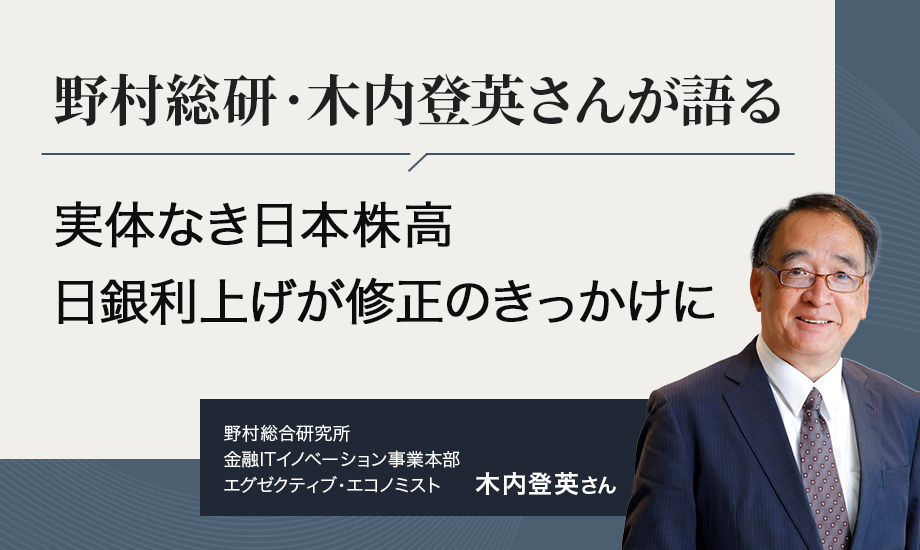
撮影/タナカヨシトモ
日経平均株価は10月31日に終値で52,411円まで上昇し、史上最高値を更新しました。11月1日以降は不安定な動きが続いていますが、5万円台を維持しており、高値圏で推移しています。野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミストの木内登英さんは、株価上昇の背景として外国為替市場での円安と国内のインフレ高進を挙げ、過去の株高局面とは経済環境が異なると分析。「実体経済の改善を伴わない株高」だと懸念を示し、日本銀行の利上げなどを背景に、今後1年程度をかけてゆっくりと調整が進むと分析しています。詳しく解説します。

円安とインフレは株価に追い風、家計に逆風
- 日経平均株価が高値圏にあります。何が理由でしょうか。
-
これまで長く続いた日銀の金融緩和策による円安とインフレ高進の影響が大きいです。資産価格の押し上げ効果はもちろんですが、それ以上に、円安もインフレも進んだことで名目ベースの企業業績が拡大しています。株価も名目値であるため、インフレを加味した実質ベースでは企業業績がそれほど改善していなくても、株価の上昇要因となります。
一方で、モノを買う側の消費者から見れば、インフレによって実質賃金が下がり、これまでよりも消費にお金をまわしにくくなっています。そのため株価が上がる中で消費者の生活が苦しくなるという、非常に大きな二極化が進んでいると考えています。
過去の株高局面ではほとんどの場合、国内経済全体も実質ベースで成長しており、その結果、株価も持続的に上昇していました。今回はそうしたケースとは違っており、実体経済の改善を伴わない「水ぶくれの株高現象」という要素があると言えます。日銀の金融政策の正常化を背景に足元の円安とインフレ高進が修正されれば、株式市場でも少し調整の動きが出るかもしれません。
今後1年で0.50~0.75%の追加利上げか
- 日銀の金融政策が正常化するタイミングはいつでしょうか。
-
政策金利の到着点、いわゆるターミナル・レートは1.00~1.25%と予想しています。現在の政策金利が0.50%ですので、向こう1年かけて0.50~0.75%程度の利上げが行われる見込みです。利上げのタイミングは2025年12月と2026年後半になるでしょう。
- 金融市場は日銀の利上げに対してどう反応すると予想していますか。
-
家計や企業のインフレ期待がいったん高まると、簡単には下がりません。インフレ期待と強く結びついている円安も同様です。そのため、今後1年程度をかけて金融政策の正常化が進む中で、ゆっくりと円高が進み、インフレ圧力が和らいでいくでしょう。米ドル円相場に関しては、2026年は1ドル=140円前後まで円高・ドル安が進むと予想しています。
そうした動きに歩調を合わせ、名目値で計算される株価や企業収益、不動産価格などの上昇(増加)ペースが時間をかけて緩やかになる、または下がる(減少する)のではないかと考えています。
ただし、外部環境の悪化が重なれば、急激な調整が起こる可能性はあります。米国景気の減速やトランプ米大統領の米ドル安政策、株高をけん引したAI(人工知能)ブームの終焉など、米国発で投資家のリスク回避姿勢を強めるようなニュースがあれば、調整幅が大きくなるかもしれません。
米中間選挙に向け、関税政策はドル安政策にシフト
- ドル安政策について、詳しく教えてください。
-
米国では2026年秋に米連邦議会の中間選挙が控えています。関税政策が米国のインフレ高進を招き企業収益を悪化させている上、米政府閉鎖も長引いたことで、トランプ政権への批判の声が強まっています。11月4日のニューヨーク市長選では民主党候補が勝利しました。こうした動きを受けて、トランプ大統領も中間選挙に向けて軌道修正が必要になるでしょう。
そのひとつが関税政策です。貿易赤字是正のためにトランプ政権が導入した関税政策は、米最高裁でその正当性が疑われ始めています。自身が敗訴した場合の「第2プラン」も伝わっていますが、関税政策が個人消費や企業業績の重荷となっている現状を踏まえれば、縮小せざるを得ません。代わりとして取りざたされているのがドル安政策で、その手段はFRB(米連邦準備理事会)への一段の政治介入です。パウエル議長が退任するタイミングである2026年5月からは、FRBの支配を強めていくのではないでしょうか。
米国が明確なドル安政策をとった場合、円高・ドル安が急激に進行する可能性があります。とはいえ、そこまで強引な手段に踏み切った場合は米国資産に対する信認が落ち、米国株や米国債、ドルがすべて値下がりする「トリプル安」に見舞われるリスクもあり、ドル安政策が長期化しないことも十分想定されます。
日本政府は積極財政も、金融政策は静観
- 日本でも以前、高市早苗首相が金融政策について「政府が責任を持つ」などと述べていました。
-
高市政権の経済政策に対する考え方は、積極的な財政政策と金融政策という、「アベノミクス」の第1、第2の矢を受け継いでいるように見えます。具体的には明言を避けているものの、防衛力強化や教育などについて「新しい財源調達の在り方」を検討しており、積極財政の姿勢は強まるでしょう。
一方で、日銀に対する積極的な介入は予想しにくいと考えています。首相就任以降の発言を見る限り、そもそも金融政策への言及が限られているほか、国会の代表質問でもこれまでの政権が踏襲してきた想定問答を繰り返しています。日銀への政治介入の姿勢は後退しており、2026年末にかけての複数回の利上げを妨げるものではないでしょう。
そのため、トランプ政権のように高市政権が日銀に介入して円への信認低下を招き、円安・インフレ高進を加速させるというシナリオは、あくまでテールリスク(発生確率は低いが、発生した場合の影響が大きいリスク)であり、メインシナリオとしては想定しにくいです。
国内政治は依然として不安定、政策実現性を注視
- 第3の矢である成長戦略については、どうでしょうか。
-
高市政権の成長戦略は政府主導による投資です。そこには防衛産業や防災・国土強靭化、AI・半導体など幅広い分野が含まれていますが、政府が主導する投資や補助金の給付といった政策は往々にして非効率で民間需要の増加も一時的にとどまり、波及効果は大きくありません。需要の先食いをしたり、民間投資の活力を奪ってしまったりする可能性もあります。
それよりも、規制改革などを通じて民間投資を引き出したアベノミクスのような経済政策を期待します。社会保障や税制の改革、医療費などの分野でも、政府がやるべきことは多いはずです。
- 個人投資家はどんな点に注意すれば良いでしょうか。
-
日本の株式市場は高値圏で推移していますが、円安やインフレ高進、またはインフレ期待の高さが名目値である企業業績や株価を押し上げたり、下支えしたりしている面が大きい、という点を認識する必要があります。実体経済の改善を伴わない「水ぶくれ」の株高は日銀の利上げなどを理由に、今後1年ほどをかけてゆっくりと修正されていくはずです。そのため、ポートフォリオの分散はますます重要になるでしょう。
また、国内の政治情勢については、依然として不安定です。連立政権の結びつきは、以前と比べて弱まっている印象を受けます。高市政権が掲げるさまざまな政策の実現性や高市政権そのものの持続性については、注意深く見ていく必要があります。

- 野村総合研究所 金融ITイノベーション事業本部 エグゼクティブ・エコノミスト
木内 登英 - 1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。
※本コラムで取り上げられたマーケットや投資に関する考え方などについては、あくまで個人の見解によるものであり、野村證券の意見を代表するものではございません。本コラムは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。
- 手数料等およびリスクについて
-
当社で取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料(換金時手数料)および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、年金保険・終身保険・養老保険・終身医療保険の場合は商品ごとに設定された契約時・運用期間中にご負担いただく費用および一定期間内の解約時の解約控除、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の委託保証金または委託証拠金をいただきます。信用取引、先物・オプション取引には元本を超える損失が生じるおそれがあります。証券保管振替機構を通じて他の証券会社等へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、移管する銘柄ごとに11,000円(税込み)を上限額として移管手数料をいただきます。有価証券や金銭のお預かりについては、料金をいただきません。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。
- 株式の手数料等およびリスクについて
-
国内株式(国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は2,860円(税込み))の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。国内REITは運用する不動産の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。国内ETFおよび国内ETNは連動する指数等の変動により損失が生じるおそれがあります。国内インフラファンドは運用するインフラ資産等の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。
外国株式(外国ETF、外国預託証券を含む)の売買取引には、売買金額(現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対し最大1.045%(税込み)(売買代金が75万円以下の場合は最大7,810円(税込み))の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等は国や地域により異なります。外国株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。