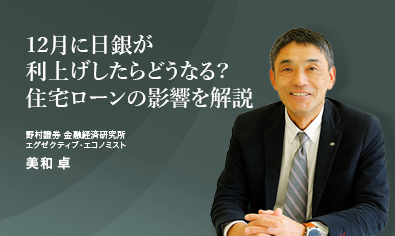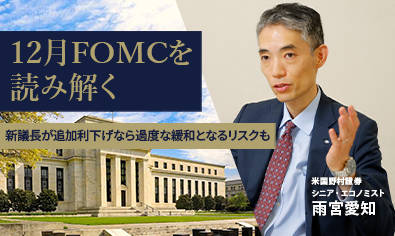2024.12.19 NEW
相続対策としてのタワマン投資は、2024年の税制改正でどう変わったのか税理士が解説
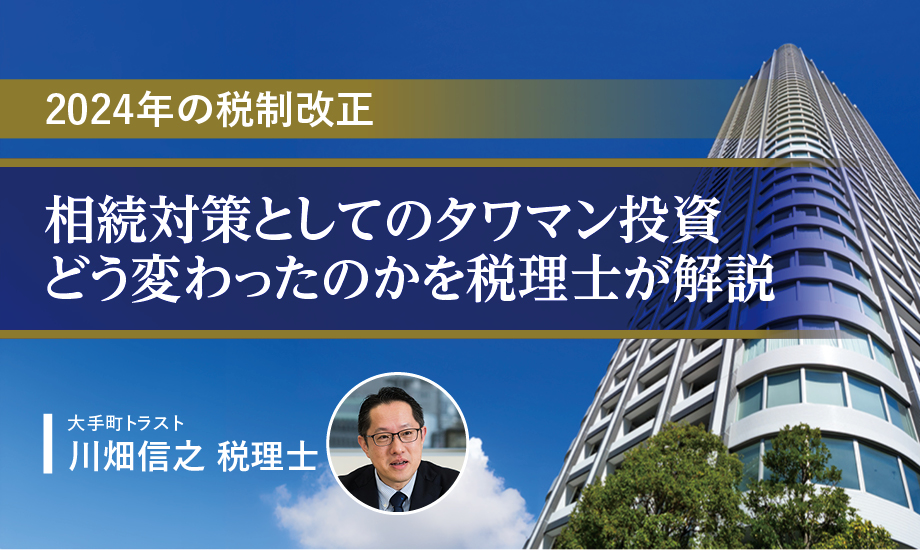
不動産投資をしている場合、2024年1月以降の相続発生分から居住用の区分所有マンションの相続税評価額の算定ルールが見直されたことは大きな関心事です。実際に相続が発生するとどのような評価額になるのでしょうか。都内のタワーマンションに投資をしているケースを参考に、不動産の相続や贈与の相談を受けることが多い大手町トラストの川畑信之税理士が解説します。
相続税評価の算定ルールの見直しはタワマンの高層階ほど影響を受ける
- 居住用の区分所有マンションの相続税評価の算定ルールが見直されたことで、タワーマンションなどの高層階の購入・投資にどのような影響が出ているのでしょうか。
-
川畑信之さん(以下、同)
2024年1月1日に施行された税制改正によって何が変わったのかといいますと、算定ルールの見直しはタワーマンションなどの高層階ほど影響を受け、従来よりも相続税評価額が引き上げられることになりました。マンションの相続は、土地(共有持分)と建物に分けて考える必要があります。まず、土地についてですが、マンションは高層になるほど総戸数が増えるため、一戸建てに比べて一戸当たりの敷地面積は小さくなります。簡単に説明すると、タワーマンションのように総戸数が多いマンションは、敷地全体の相続税評価額を総戸数で割ることになるため、一戸にかかる相続税評価額は低くなる傾向があります。
建物について、相続税評価額の算出時に使用される固定資産税評価額は、建物の材料や施工方法、専有面積などに応じて決まるため、同じ専有面積であれば、低層階でも高層階でも同じになります。しかし、高層階は眺望の良さやステータス性などの魅力から人気が高く、市場価格も高い傾向があります。つまり、市場では高層階ほど高く売買されるにもかかわらず、相続税評価額は一定のため、相続を考えると高層階の物件を買った方が有利という状況になっていました。
国税庁の資料によると、平成30年における市場価格と相続税評価額の乖離率(市場価格÷相続税評価額)の平均値は、マンション1室が2.34倍(市場価格の43%)であるのに対し、一戸建ては1.66倍(市場価格の60%)と開きがありました。
このような土地と建物ともに相続税評価額が低くなるマンションの評価方法を是正するために、一戸建てとのバランスを考慮し、相続税評価額が市場価格理論値の60%(乖離率1.67倍)未満の場合、市場価格理論値の60%になるよう相続税評価額を補正するように改められました。この補正には、築年数、総階数、所在階、敷地持分狭小度(自分が所有しているマンションの敷地部分とマンションの床面積との比率)が加味されています。
 撮影/齋藤大輔
撮影/齋藤大輔
賃貸マンションが自用マンションより相続税評価額が低い理由
- 相続税評価が引き上げられたのであれば、投資目的でタワーマンションを購入する魅力はなくなったと考えられるのでしょうか。
-
賃貸収入が得られる賃貸マンションには、居住用の自用マンションよりも相続時の評価額が下がる仕組みがあり、相続税評価額が市場価格の60%以下になることも少なくありません。
賃貸マンションの場合、相続人と被相続人だけでなく、借主が存在します。借主は所有者から建物を借りる「借家権」などを有しています。そのため、相続人は自分が所有する土地と建物であっても、売却や増改築などが自由に行えないなど、自用マンションに比べて制限がある状態といえます。
こうした理由から、賃貸マンションの相続税評価額は、自用マンションの相続税評価額から「借地権割合」と「借家権割合」に応じた額が差し引かれた金額になります。借家権割合は一律30%と定められており、借家権割合には実際に賃貸されている面積の割合がどれだけあるかを示した「賃貸割合」も加味されます。
なお、過度な投資目的でのタワーマンション購入には注意が必要です。過去には明らかな節税目的と判断されたことで、国税庁側から否認されたということも起きています。
賃貸用のタワーマンションを相続した場合、どれだけ変わるのか
- 居住用の区分所有マンションの相続税評価の算定ルールの見直しによって、賃貸用のタワーマンションは具体的にどれだけ相続税評価額が変わるものでしょうか。
-
以下の都内タワーマンションAを賃貸用として購入した場合、算定ルールの見直し前と後でどれだけ相続税評価額が変わったのかをシミュレーションしてみましょう。
都内タワーマンションA
総階数:33階 所属階:33階
路線価:1,815,000円/㎡
登記地積:7,812.45㎡ 専有面積(公簿):85.88㎡
持分:100,000,000分の259,948
借地権割合:70%
築年数:16年
建物固定資産税評価額:9,311,500円
売買価格:1.5億円
-
算定ルールの見直し後だと、相続税評価額は約6,930万円になります。算定ルール見直し前は、相続税評価額が約3,564万円(売買価格の約24%)だったことを考えると、不利になったと感じるかもしれません。しかし、賃貸マンションであるため、相続税評価額は売買価格の約46%となり、マンションの状況によっては、引き続き有利な点はあるといえるでしょう。
| 算定ルールの見直し | 賃貸用タワーマンションA 相続税評価額 |
|---|---|
| 前 | 約3,564万円 |
| 後 | 約6,930万円 |
試算:大手町トラスト
-
今度は相続税がどれだけ変わったのかをシミュレーションしてみましょう。以下の男性Bさんは賃貸用に、自己資金から売買価格1.5億円の都内タワーマンションAを購入したとします。その都内タワーマンションAを長男に相続し、長女には現金1.5億円を相続すると仮定します。また、今回のシミュレーションでは、配偶者はすでにまとまった金額の資産を保有しているため、相続税評価額7,000万円の持ち家を一次相続すると仮定します。なお、持ち家には小規模宅地等の特例(※後述)を適用しないと仮定します。
男性Bさん60歳
配偶者58歳、子ども2人(32歳長男、28歳長女)
総資産3億円+持ち家(相続税評価額7,000万円)
-
算定ルールの見直し前だと相続税は約3,026万円でしたが、見直し後だと相続税は約4,052万円になります。今回のシミュレーションでは、算定ルールの見直しによって相続税に約1,026万円の差があることが分かります。これからタワーマンションを購入する人だけではなく、すでに所有している人も一度、算定ルールの見直しによって相続税がどれだけ変わったのか確認しておいた方がいいでしょう。

小規模宅地等の特例で貸付事業用宅地の評価額が50%減額に
- 賃貸マンションは自用マンションよりも相続税評価額が低くなることは分かりましたが、ほかに、投資目的でタワーマンションを購入した時に有利になることはないのでしょうか。
-
小規模宅地等の特例は引き続き利用できます。この小規模宅地等の特例を適用できれば、賃貸マンションの土地部分に対する評価額を50%減額することができます。
小規模宅地等の特例とは、個人が相続や遺贈により取得した財産の中で、その相続の開始の直前まで被相続人等が自宅として住んでいたり、事業に使用されていたりした宅地があった場合、一定の条件のもと限度面積までの部分について、相続税の評価額の一定割合が減額される特例のことです。住むための土地(特定居住用宅地等)の場合、限度面積330㎡に対して80%減額されます。一方で、賃貸アパートなど貸していた土地(貸付事業用宅地等)の場合、限度面積200㎡に対して50%減額されます。
前述の賃貸用に購入した都内タワーマンションAでシミュレーションをしてみましょう。土地の持分が約20.3㎡※で200㎡以下のため、小規模宅地等の特例を適用することは可能です。賃貸用のため土地の相続税評価額は50%削減され、相続税評価額は約4,099万円(売買価格の約27%)になります。
※登記面積7812.45㎡×持分259,948/100,000,000今度は相続税をシミュレーションしてみましょう。賃貸用に購入した都内タワーマンションAに小規模宅地等の特例を適用した場合、男性Bさんの財産の分割案ですと、相続税は約3,187万円になります。小規模宅地等の特例を適用しなかった場合、相続税は約4,052万円だったため、小規模宅地等の特例を適用できると、今回のシミュレーションでは相続税が約865万円減ることになります。
参考までに、タワーマンションAを購入せずに現金3億円を子どもに相続した場合(長男に1.5億円、長女に1.5億円)、配偶者の税額軽減の特例を適用し、相続税は約6,624万円(配偶者が0円、長男が約3,312万円、長女が約3,312万円)になります。
つまり、賃貸用タワーマンションAの相続を受ける長男の相続税は、現金だけを子どもに相続する場合に比べると、約2,628万円減ることになります。一方、相続財産の全体の額が減ったので、現金を相続する長女も相続税が約809万円減っています。
| 財産 | 分割案 | タワマンAへの 小規模宅地等の特例 |
相続税 (各相続人) |
相続税 (総額) |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家 現金3億円 |
配偶者:持ち家 長男 :1.5億円 長女 :1.5億円 |
― | 配偶者:0円 長男 :約3,312万円 長女 :約3,312万円 |
約6,624万円 |
| 持ち家 賃貸用タワーマンションA 現金1.5億円 |
配偶者:持ち家 長男 :タワマンA 長女 :1.5億円 |
適用なし | 配偶者:0円 長男 :約1,280万円 長女 :約2,772万円 |
約4,052万円 |
| 適用あり | 配偶者:0円 長男 :約684万円 長女 :約2,503万円 |
約3,187万円 |
試算:大手町トラスト
(注)配偶者の税額軽減の特例を適用
-
確かに、居住用の区分所有マンションの相続税評価額の算定ルールが見直されたことで、将来的に相続をする際、単純に高層階の物件を買った方が有利とはいえなくなりました。それだけを聞くとインカムゲイン目的でタワーマンション投資を考えている人は不安に感じてしまうかもしれませんが、賃貸マンションは自用マンションよりも相続税評価額が低くなり、賃貸マンションに対しても小規模宅地等の特例を適用できる可能性もあります。これからタワマン投資を考える人は、そのことも念頭に入れて資産計画をしてみるといいでしょう。
- 賃貸マンションに小規模宅地等の特例を適用するために、事前に把握しておくべきことはありますか。
-
2018年度の税制改正により、相続開始前3年以内に新たに貸し付けられた宅地等は貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例の適用対象外となりました。この要件は、亡くなる直前に賃貸不動産を購入することによる相続税の租税回避を防止する観点から設けられました。
相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っていた場合には、新たに3年以内に貸し付けられた宅地等も適用対象となりますが、この事業的規模とは、所得税の不動産所得に係る事業的規模の判定基準と同等の、5棟10室基準(一戸建てなら5棟、アパート・マンションなら10室)が想定されています。将来的に相続することを考えている場合は、早いタイミングで検討を始めることが好ましいといえるでしょう。

- 大手町トラスト/税理士
川畑信之(かわばた・のぶゆき) - 1972年生まれ。東京理科大学理学部卒業。主に証券会社の顧客の相続に関する税務申告、相続対策、事業承継対策(非上場株式等の納税猶予)などを担当している。相続対策や事業継承についてのセミナーも多数行っており、富裕層に対する資産承継や事業承継に関するコンサルティング対応を得意とする。
※本コラムで取り上げられた不動産・相続税に関する基本的な考え方などについては、あくまで個人の見解によるものであり、野村證券の意見を代表するものではございません。本コラムは2024年12月現在の法律に基づいて作成しています。個別の税務の詳細につきましては、税理士等にご相談ください。
- 不動産関連のご留意事項
-
お客様の個別の不動産のご相談に関しましては、提携不動産会社または当社の宅地建物取引業の免許を取得している部署がお受けいたします。
- 野村證券株式会社 宅地建物取引業者 国土交通大臣免許(3)第8197号