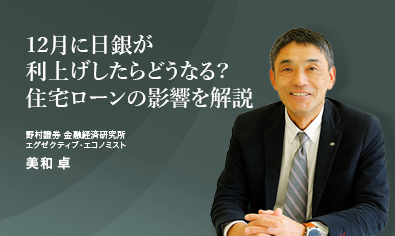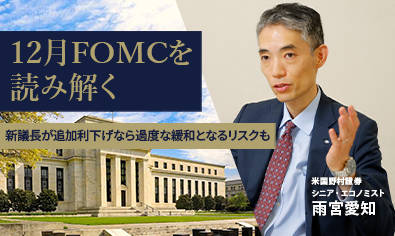2024.12.06 NEW
「103万円の壁」引き上げへ 日本経済の持続的な成長に寄与するのか 野村證券エコノミストが解説
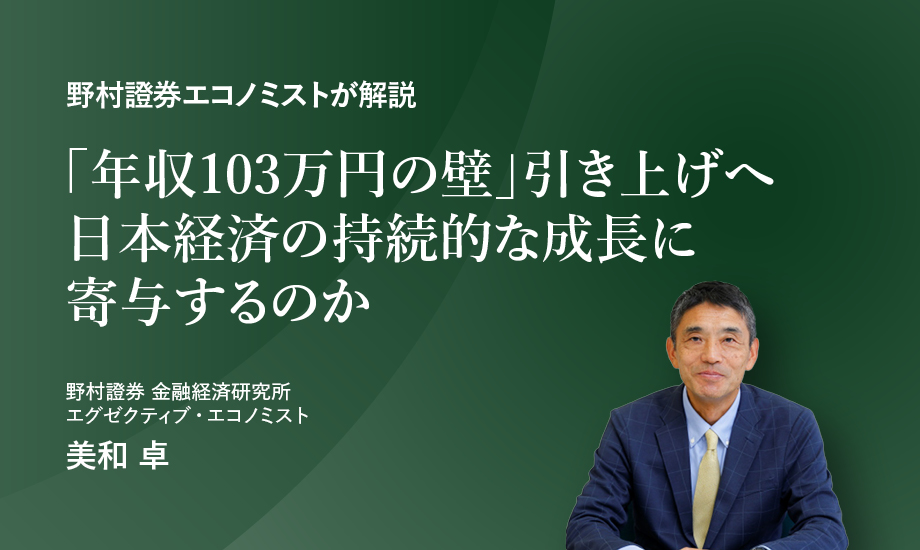
2024年10月の衆議院議員選挙で躍進した国民民主党が打ち出す看板政策が、所得税の基礎控除等を103万円から178万円へ拡大する、いわゆる「年収103万円の壁」の引き上げです。自民、公明、国民民主の3党が「壁」の解消を検討することで合意したと報道されました。給与所得者にとっては減税となりそうですが、日本経済全体にはどのような影響を与えるのでしょうか。マクロ経済学が専門で、野村證券金融経済研究所 エグゼクティブ・エコノミストの美和卓に聞きました。
日本経済にとってはプラスの政策
- 国民民主党は、課税所得を計算する際に差し引かれる基礎控除48万円と給与所得控除の最低額55万円の合計額を178万円に拡大するという政策を打ち出しています。非課税枠の引き上げ幅などは未定ですが、与党と実現に向けて検討することで合意しました。給与所得者にとっては大きな減税となりそうです。どう受け止めていますか。
-
美和卓(以下同)
ある程度はポジティブな政策として受け止めていますが、完全には賛同できない点もあります。まずプラスの面から考えてみます。国民民主党は1995年からの最低賃金の上昇率1.73倍に基づき、基礎控除等の合計を103万円から178万円に引き上げ、減税を行うという政策を掲げます。同党の玉木雄一郎代表は、税収の減収分はインフレに伴う税収の上振れ分で賄えると主張します。
たしかに、近年の物価の上昇傾向、景気回復により国の税収は増えています。また、コロナ禍以降、頻繁に大規模な補正予算が組まれている一方で、予算の使い残しも発生しています。消化できないような予算ならば、減税をして、国民が個人で使えるようにする。このような理屈は理解できるものです。
今回の政策が実現した場合、政府試算によると減税額は7.6兆円に上ります。実質的な減税効果により、消費需要の拡大が喚起されることは確実なので、日本経済にとってプラスかマイナスかでいえばプラスでしょう。
さらに、実は「103万円の壁」があるばかりに、働くのを一定の時間で止める人がいます。こういう人たちにかかる制限を引き上げることで、より長時間働いたり、高収入の仕事に就いたりするチャンスが生まれます。これは個々の人々の収入がプラスになるだけでなく、経済にとってもプラスになるという面もあります。
現役世代に恩恵が大きい政策
- 国にとっては大きな税収減となる政策です。社会保障などどこかに悪影響がありそうでしょうか。
-
この政策が実現したとして、どこかに目に見えて悪影響が出てくるかというと、そんなことはありません。しかしながら、懸念点はいくつかあります。まず、政策のプラス効果が、税収減、さらには財政不安定化のリスクを踏まえても十分であり、そのデメリットを上回るものであるかどうかという点です。
そもそも、この政策の恩恵は主に給与所得者にしか及びません。日本の人口動向から考えると、今後は年金生活者が多数派になっていきますが、この層に及ぼす恩恵が限られたものになります。ここは見逃されている論点だと思います。一方で、もしこの減税が財政悪化を引き起こすと、そのしわ寄せがいくのは給与所得者ではなく、年金生活者である可能性があります。なぜなら、財政の悪化が、間接的にではありますが年金財政の悪化につながり、年金額が引き下げられるスピードが速まるかもしれないからです。
このように、現役世代への恩恵に過度に配慮しすぎている面が、今の日本の社会構造、人口構造を考えるとマイナスになるかもしれないというのは課題です。
減税効果の持続性に課題
-
また、政策の効果の持続性にも問題があります。「年収103万円の壁」が一度限りで引き上げられ、消費需要が喚起されても、厳密に言えば、持続的な経済成長にはつながりません。もちろん、減税分の一部は消費に向かうでしょう。しかしながら、次の年にもさらに消費が増えるかというと増えません。つまり、翌年以降の消費の増加=経済成長には寄与しないので、減税の効果は一時的ということになります。
ポジティブな期待ができる点があるとすると、減税を行った最初の年に需要が拡大し、企業の売上が上がり、企業が投資に前向きになり、より良い商品やサービスが世に出て需要が喚起されると減税分以上の効果は出るかもしれません。ただ、それは保証されたものではありません。
今回の「壁」の引き上げにより、それ以降の需要の持続的な増加を喚起できるのかどうか。例えば、持続的需要拡大を促すその他の施策をセットで打ち出せるか、というのも一つのポイントだと考えます。

消費に回るのは減税分すべてではない
- 7.6兆円が減税されても、消費に回るのは一部であると言う主張もあります。例えば、野村の試算によると、減税分の7.6兆円の可処分所得が増加しても、消費増加効果は1.3兆円程度と予想されています。
-
そうですね。家計が所得の増加分のうち消費に回す割合を限界消費性向と言いますが、一般的に減税などによって得られた追加的な所得の限界消費性向は非常に低いです。局面やタイミングによってばらつきはありますが、所得増加分のうち、消費に回るのはおよそ20~40%とされます。さらに、これは所得が高くなるにつれて低下することが実証的に示されています。
限界消費性向の低さにはいろんな理由があるのですが、高所得者ほど今の消費で満足してしまっていて、手取りが増えても、新たな消費をしてもしなくてもいい、という人が多い。さらに、今は減税されても、将来的にそれが財政悪化につながり、何かの形で取り返されるのではないか、もらった分は取っておこうというインセンティブが働き、消費に回らないという点もあります。
実際に、今回の「103万円の壁」の議論に呼応して、厚生労働省からは一定の条件下で社会保険の加入を義務化する「106万円の壁」を引き下げるか検討するという案が出ています。これまで、中小企業などには社会保険料の徴収を免除していたのを、逆に「壁」を撤廃し、徴収する範囲を広げましょうと言い出しているわけです。
もちろん、働き方を抑制するというインセンティブを排除するためには、「壁」を撤廃するという手段もありますが、基本的に働く人の負担は増加します。このような動きがある限り、せっかく減税が行われても、別のところで取られるかもしれないから貯金しておこうという心理は働くでしょう。
この観点からも、(減税政策は)ワンショットではだめで、毎年いくらかは所得が増えるという期待を、確からしい形で与える。ちゃんと国には財源もあるし、毎年いくらかの減税があると信じられれば、この限界消費性向はもっと上がるはずです。
「壁」の引き上げ、撤廃を議論する上での4つのポイント
- 今回は「103万円の壁」が議論されていますが、これ以外にも税制や社会保険に関するいくつかの「壁」が存在します。これらの引き上げや撤廃を考えるときに必要な議論のポイントはどこにありますか。
-
はい、所得税基礎控除額の「年収103万円の壁」以外にも、厚生年金、国民年金の保険料発生の有無を分ける「106万円の壁」、「130万円の壁」の存在が知られています。「壁」の存在が経済に与える影響については、以下の4つの視点から議論する必要があると考えています。
まず一つ目は、これらの「壁」によって発生する税金や社会保険料の負担を回避するため、「働き控え」を誘発してしまうという問題です。特に、現在のように少子高齢化によって人手不足が深刻化している中では、労働力の供給不足により、経済成長の抑制要因として作用してしまうことが考えられます。
二つ目は、現在のようにデフレを脱却し、一定の物価上昇が生じる局面では、所得税の控除額を低い水準に据え置いてしまうと、労働者が賃金上昇の恩恵を受けにくくなるという問題です。
三つ目はプラスの効果ですが、「壁」を引き上げることで減税となり、家計の支出が増えることによって、経済全体が活性化するという視点です。さらに四つ目は、「壁」を引き下げたり、撤廃したりすることで発生する税金と社会保険料の減少分を、どんな財源でまかない、財政の持続性を担保するのかという点です。
今、国民民主党と財務省という対立構図で議論されているのは、主に二つ目から四つ目の論点です。国民民主党は、「壁」の引き上げによって手取りが増加するため、経済活性化のメリットが大きく、「壁」の引き上げは正当化できると主張しています。一方で、財務省は大幅な税収減を理由に反対の姿勢ですが、国民民主党はインフレによって税収が増えていることを根拠に、財源問題はクリアできると反論しています。
もちろん、これからの論点をトータルで見て、財政全体にとってプラスなのか、マイナスなのかは丁寧に検証されるべきでしょう。一方で私は、日本経済が直面する最大の課題は人口減少であるのに、働き控えによって経済成長が抑制されてしまうという一つ目のポイントについての議論が重要で、この部分が希薄なのではないかという懸念を覚えています。
- 野村證券 金融経済研究所 エグゼクティブ・エコノミスト
美和 卓 - 1990年野村総合研究所入社。東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了。2004年野村證券に転籍。2024年4月より現職。国内・海外のプロの投資家に対して、日本と世界の経済に関する分析、見通しを提供する一方、一般向けに経済、金融の仕組みを分かりやすく解説。著書に『金利「超」入門』(日本経済新聞出版社)、『図解 いちばんやさしく丁寧に書いた金利の本』(成美堂出版)など
※この記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。
- 手数料等およびリスクについて
-
当社で取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料(換金時手数料)および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、年金保険・終身保険・養老保険・終身医療保険の場合は商品ごとに設定された契約時・運用期間中にご負担いただく費用および一定期間内の解約時の解約控除、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の委託保証金または委託証拠金をいただきます。信用取引、先物・オプション取引には元本を超える損失が生じるおそれがあります。証券保管振替機構を通じて他の証券会社等へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、移管する銘柄ごとに11,000円(税込み)を上限額として移管手数料をいただきます。有価証券や金銭のお預かりについては、料金をいただきません。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。