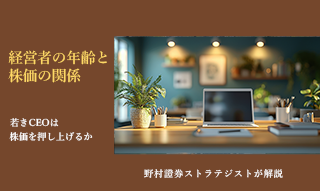2025.03.05 NEW
長期金利は誰が決める? 急上昇の背景と投資の考え方を野村證券エコノミストが解説
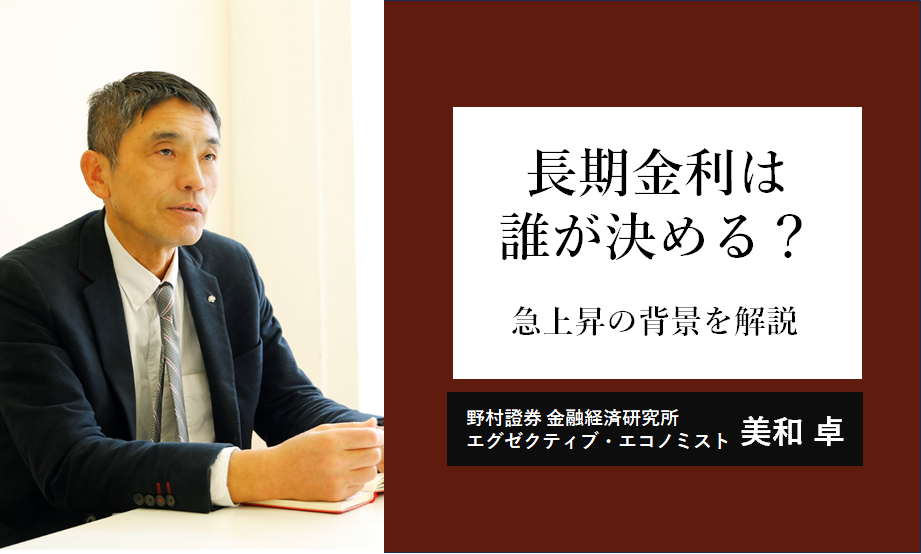
写真/タナカヨシトモ 文/斎藤健二(金融・Fintechジャーナリスト)
日本の長期金利が上昇し「金利のある世界」が戻ったともいえる今、投資家はどのような発想の転換が必要でしょうか。日本銀行の政策金利引き上げを背景に、日本の長期金利は一時1.4%台まで上昇しました。野村證券金融経済研究所エグゼクティブ・エコノミストの美和卓氏が、長期金利上昇のメカニズム、一般投資家への影響について解説します。住宅ローンと定期預金の金利上昇、債券や株式などの資産価格への影響、そして今後の見通しについて、ポイントを整理します。

長期金利が上昇した背景とメカニズム
- 日本の長期金利は2025年2月21日には一時1.4%半ばまで上昇しました。これは日銀が政策金利を引き上げたからですよね。
-
最近の長期金利の上昇は、2025年1月に日銀が政策金利を0.5%に引き上げたことが影響しているのはもちろんですが、日銀が長期金利を決めているわけではないんですよ。政策金利はあくまで短期の金利です。
長期金利の水準は、大きく分けて2つの要素で決まります。1つは短期金利の将来に向かっての予想の積み重ねです。例えば10年の金利であれば、今から1年後までの金利、1年後から2年後までの金利を予想したものを、10年分積み重ねたと考えられます。分かりやすく言うと平均のようなものです。
もう1つは、期間の長さから来る不確実性を反映した“おまけ”が上乗せされます。これはタームプレミアムと呼ばれるリスクプレミアムの一種です。つまり、1年後や2年後、10年後の金利がどうなっているか分からないからこそ、その予想が外れる危険性に対して上乗せされる部分があるのです。
最近の長期金利の上昇は、日銀が政策金利を0.5%に引き上げたことだけでなく、それ以上に、1月に続いて将来も利上げが続いていくだろうという予想が以前より強まったことが影響しています。
また、2月に発表されたCPI(消費者物価指数)が高かったことも、日銀がより利上げを行うという予想を強めました。物価上昇が続けば、日銀はそれに対応してさらに利上げをするだろうと市場が予測したわけです。
- 日銀のイールドカーブコントロール(YCC)の緩和は影響していないのでしょうか?
-
YCCが発動されている世界では、長期金利の決定メカニズムは通常とは異なり、金利決定の理論的な仕組みは当てはまりません。端的に言うと、それは日銀が長期金利を決めるということであり、日銀が長期金利を0%程度に持っていくと宣言し、それを実現するために国債を買うという手段を取っていました。
つまり、本来は市場の需給や将来の金利予想で決まるはずの長期金利が、人為的に設定されており、国債の需給関係も歪んだ状態でした。今の長期金利の急騰は、本来の金融政策のあり方、つまり金融政策は基本的に短期の金利しか決めないという普通の状態に戻ってきたということでもあります。
- 日銀は実際、今後も利上げに積極的なのでしょうか?
-
日銀は、今後の利上げにも意欲的だと思います。
市場では、もともとITバブルの時やリーマンショック後など、過去の利上げ局面では日銀の利上げは0.5%が限界だったという歴史があり、今回も0.5%が限界ではないかという見方が強かったのです。ところが最近は、日銀が0.5%の壁を簡単に突破できそうだという印象を与えています。さらに1%の壁も突破するかもしれません。日銀が考える中立金利(景気を上げも下げもしない金利)は1%程度と言われていますが、それを超える可能性もあるでしょう。
ただし、長期金利が上昇しすぎることは多少抑えたいという姿勢も見られます。長期金利が上がりすぎると、日本の経済成長を阻み、ひいては日銀が目指している2%のインフレ目標達成を妨げるリスクにつながるからです。
住宅ローンのリスクをどう考えるか
- 長期金利が上昇することで、一般投資家にはどのような影響があるのでしょうか?
-
主に2つの影響を受けます。1つは定期預金の利息です。長期金利が上昇すれば、銀行がそれに連動させる形で定期預金の利息を上げてくる可能性があり、これは受け取りが増えるという恩恵になります。
一方で、住宅ローンなどの借入に関しては、マイナスの影響を受ける恐れがあります。特に固定型の長期住宅ローンの金利設定に影響します。例えば、短期の変動型から固定型に切り替えようと考えていた矢先に長期金利が上昇すると、金融機関が固定型住宅ローンの金利設定を引き上げることになり、当初より高い金利で借りなければならなくなります。
ところが、長期金利の上昇とともに、必ずしも住宅ローンの金利がおしなべて上がるわけではありません。最近も、一部の住宅ローンの優遇金利がさらに有利に適用されているのを見かけるでしょう。
ひとつには、金利が上がると住宅ローンの需要が減り、金融機関の住宅ローン残高の伸びが鈍化します。それを防ぐためのプロモーションとして優遇金利を設定しているケースがあります。
また、金利局面が変わる中で、金融機関にとってどの商品を貸した方が有利かという判断も関わってきます。多くの人が固定金利を選ぶ流れを食い止めるために、変動金利の商品を割り引いて提供することもあります。金融機関としては変動金利で貸した方が、金利上昇局面では有利になるからです。
- 金利上昇が続くと、住宅ローンの返済が困難になる人も出てくるのではないでしょうか?
-
リスクはあると思います。特に一部の金融機関では、経営戦略として貸出残高の維持・拡大を重視するあまり、通常なら審査で落とすような所得水準や資産水準の方にも貸し出していたケースがあります。そうした方々が金利上昇の影響を最も早く受ける可能性があります。金融庁や日銀もこのリスクを警戒しているでしょう。
ただ、すぐにバブル崩壊時のような社会不安につながる状況にはならないと思います。賃金も上昇傾向にあり、借り手の返済能力も向上しています。また、最近はペアローンが一般的になり、共働き世帯が増えていることも安心材料です。
- 不動産価格への影響はどうでしょうか?
-
長期的には、金利上昇によって不動産価格が下落するリスクは考えられます。バブル崩壊時には担保評価額が下がり、借りていた額に対する担保評価が割れたため、金融機関から早期返済を求められるケースがありました。これが問題を悪化させました。
しかし、現状では地価やマンション価格は上昇傾向にあり、まだ現実の不安にはなっていません。今後も注視は必要ですが、すぐに問題が顕在化する可能性は低いでしょう。
高い金利が得られる金融資産へのシフトを
- 金利のある世界では、投資家はどのように資産運用を考えればよいでしょうか?
-
大原則としては、金利のある世界になれば、高い金利が得られる金融資産にシフトしていくことが重要です。普通預金でおいておきたいお金はそれよりも定期預金が有利になりますし、個人向け国債なども選択肢になります。
個人向け国債の変動10年は現在0.83%程度で、定期預金の0.5%程度と比べると利回りは高いです。ただし、個人向け国債は期間が長いというデメリットがあります。定期預金ならペナルティを払えば解約できますが、個人向け国債は原則として満期まで持ち切ることが前提です。早期換金も可能ですが、それなりのペナルティが発生します。
個人の判断で、おまけの高さと自分の資金が長い期間凍結されても大丈夫かを天秤にかけての判断になります。また、変動型の個人向け国債であれば、今後金利がさらに上昇していくなら、利払いも増えていくというメリットがあります。
- 社債はどうでしょうか?
-
社債も金利上昇によってクーポン収入が増えるという点で有利になります。ただし、国債との違いは、金利上昇はすなわち企業にとっての金利負担が上がる点です。中には高い金利負担に耐えられない財務体質の企業もあります。
そのため、金利が上がれば上がるほど有利かというと、必ずしもそうではありません。金利上昇によって企業の破綻リスクが高まる可能性もあるのです。投資する際は企業の事業特性や財務状況を見ていく必要があり、格付けも参考にするべきです。「投資適格債」を選ぶのも一つの判断基準です。
- 社債と個人向け国債、どう選ぶといいでしょう。
-
社債の上乗せ金利は妥当な水準にあると思います。選択のポイントは金利の先高感をどう見るかです。金利がさらに上がると判断するなら個人向け国債の方が有利でしょう。今がピークだと考えるなら社債が有利になります。
- 日本の金利上昇と米国の金利を比較すると、米ドル建ての債券に投資した方が良いのでしょうか?
-
債券という商品性だけを考えると、金利の先高感があるよりも先安感がある場合の方が有利です。日本は金利先高感があり、米国は金利先安感がある状況です。為替を無視すれば、米ドル建て債券の方が商品性としては有利です。
ただ、日本の金利先高感と米国の金利先安感がある時、為替は円高に動きやすいという点も考慮する必要があります。為替オープンで米国債を買った場合、債券の値上がりと為替の円高という双方の要素が効いてきます。
数年後の使い道が決まっている資産など、為替変動の影響を考えずに安全に持っておきたいと考える資産については、円建ての債券も選択肢になると思います。
- 株式への投資はどう考えればいいでしょうか?
-
単純に考えると、金利上昇は株式にマイナスの面があります。株と債券は配当と利息で勝負しているため、金利の魅力が高まると株が不利になりがちです。
ただし、金利が上がる時は通常、景気が良く企業の売上や収益も増加する傾向にあります。これにより配当の成長期待も高まるので、一概に株が不利とは言えない面もあります。
現在の日本株については、実体経済は悪くなく、企業の値上げもしやすい環境になっているため、業績は底堅いと思います。ただし、日本の金利先高感と米国の金利先安感で円高に向かうと、特に輸出関連企業やグローバル展開企業の収益にはマイナスの影響が出る可能性があります。
- 金利上昇が業種別に与える影響はどうでしょうか?特に金融機関への影響はプラスと言われていますが。
-
金融機関、特に銀行については、金利上昇局面では一般的に収益にプラスになります。金利上昇局面では通常、長期金利が先に上がりやすく、短期と長期の金利差が拡大します。短期でお金を集めて長期で運用する銀行のビジネスモデルではこれが有利に働きます。
- マイナスの影響を受ける業種はありますか?
-
典型的にはREITや不動産業で、これらは金利上昇でマイナスの評価を受けやすいです。借入残高が大きい業種として小売業や商社も同様にネガティブな影響を受ける可能性があります。
- 今後も金利上昇が続くと予想されますが、投資家はどのような心構えを持つべきでしょうか?
-
これまで株式を中心にポートフォリオを組んでいた投資家は、金利のある世界への移行を意識して資産配分を見直す必要があるでしょう。株と債券は配当と金利で勝負している面があるため、金利が上がれば債券の相対的な魅力が高まります。
ただし、投資判断は個人のリスク許容度や将来の見通しによって異なります。金利先高感をどう見るか、円高・円安の動向をどう予測するかによっても最適な資産配分は変わってきます。
バランス型商品でアロケーション変更に対応するのは方法の一つです。ご自身の金利見通しによって、安全型や低リスク型の配分を増やすことも検討されるとよいでしょう。

- 野村證券 金融経済研究所 エグゼクティブ・エコノミスト
美和 卓 - 1990年野村総合研究所入社。東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了。2004年野村證券に転籍。2024年4月より現職。国内・海外のプロの投資家に対して、日本と世界の経済に関する分析、見通しを提供する一方、一般向けに経済、金融の仕組みを分かりやすく解説。著書に『金利「超」入門』(日本経済新聞出版社)など。
※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。
- 手数料等およびリスクについて
-
当社で取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料(換金時手数料)および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、年金保険・終身保険・養老保険・終身医療保険の場合は商品ごとに設定された契約時・運用期間中にご負担いただく費用および一定期間内の解約時の解約控除、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の委託保証金または委託証拠金をいただきます。信用取引、先物・オプション取引には元本を超える損失が生じるおそれがあります。証券保管振替機構を通じて他の証券会社等へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、移管する銘柄ごとに11,000円(税込み)を上限額として移管手数料をいただきます。有価証券や金銭のお預かりについては、料金をいただきません。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。
- 個人向け国債の手数料等およびご留意事項について
-
個人向け国債を募集によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。
個人向け国債は発行から1年間、原則として中途換金はできません。個人向け国債を中途換金する際、原則として次の算式によって算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれます。
(●変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685、●固定5年、固定3年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)
ご購入にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。
- 債券の手数料等およびリスクについて
-
債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。債券の価格は市場の金利水準の変化に対応して変動しますので、損失が生じるおそれがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。加えて、外貨建て債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。