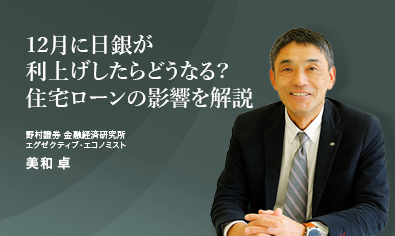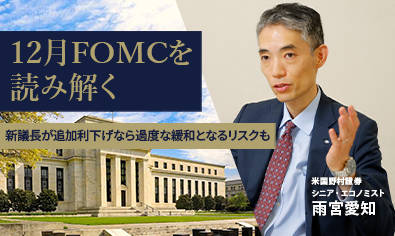2025.03.10 NEW
株安・円高がじわり進行 それでも4月後半以降の株高を想定する理由 野村證券・池田雄之輔
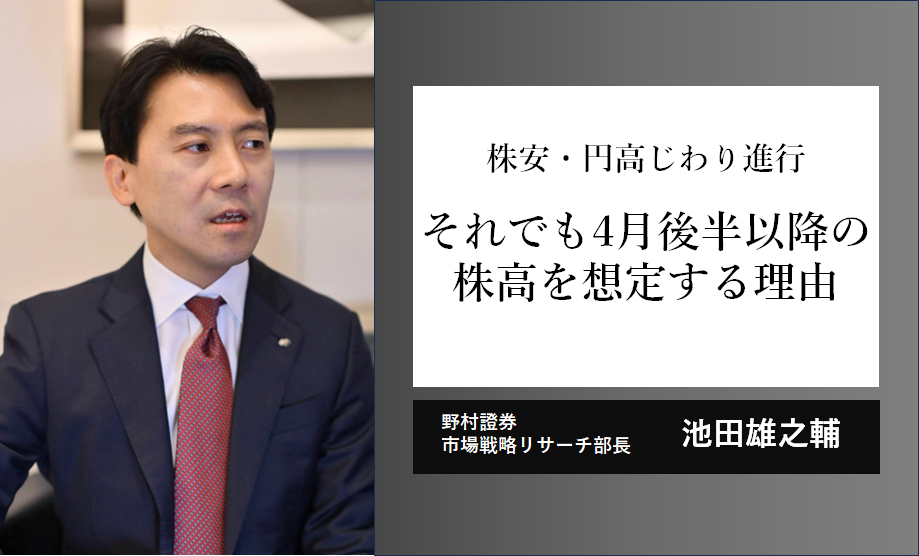
写真/稲垣純也
日経平均株価は2025年3月に入り、乱高下を繰り返しています。先週末3月7日の終値は、前日比817円安の3万6,887円となり、年初来最安値を更新しました。3月10日の終値は、前日比141円高の3万7,028円と上昇したものの、外国為替市場では円高・ドル安が進行しており、3月10日15時30分時点では1ドル=147円台での推移となっています。この背景にある要因を整理したうえで、今後の日本株の見通しについて、野村證券市場戦略リサーチ部長の池田雄之輔が解説します。
日本株の弱さの国内要因は、日銀の追加利上げに対する警戒感
このところの日本株の弱さには国内要因1つ、海外要因4つが重なっていると思います。まず国内要因としては日本銀行の追加利上げに対する警戒感と、それに伴う円高です。年初の時点で、市場が織り込んでいた2025年12月末の政策金利は約0.7%でしたが、1月の追加利上げを経て、0.8~0.9%まで高まってきました。7月までに追加利上げがあることを約8割織り込み、さらに12月までに政策金利が1.00%へと引き上げられることを5~6割織り込んでいるという状態です。
海外投資家は3月19日の日銀金融政策決定会合後の植田和男総裁会見で、「早ければ5月1日の金融政策決定会合での利上げへの示唆があるのではないか」と警戒を強めています。2024年7月31日の日銀の利上げから間もない、8月初旬には強烈な株安・円高が発生しました。海外投資家はその連想から「日銀タカ派化に向けて日経平均先物をショートする(下落すると予想し、売り建てる)」という動きを強めている面があると思います。
米国の要因は、米国景気懸念、トランプ関税の不透明感など
海外要因の1つ目は、米国景気に対する不安感です。2月はたとえば、消費者マインドの指標や製造業の新規受注に下振れが目立ちました。米国株は、国内景気への依存度の高い中小型銘柄で構成されるラッセル2000指数がとくに大きく下落しています。「米景気悪化」が意識される局面は、日米同時株安と円高がセットで進行しやすいというのは、これまでにも経験済みです。
2点目は「トランプ関税」に対する不透明感です。トランプ政権は中国との関税引き上げ合戦を始めている一方、カナダ・メキシコへの関税賦課については二転三転しています。日本に対しては円安批判と見なされる発言もあり、円高の加速要因になりました。
以上が株安・円高の背景ですが、株式市場ではさらに、海外要因の3点目としてAI関連についての期待の揺り戻しが加わっています。中国産AIのDeepSeek(ディープシーク)が台頭したことにより、米国ハイテク産業の独走態勢や、日本の関連セクターへの恩恵についての懐疑的な見方が出てきています。
4点目は、欧州株の急回復です。年初来、グローバル投資家はウクライナ停戦がもたらす欧州景気への浮揚効果に注目してきました。そこに加え、3月4日にはドイツの次期首相への就任が見込まれるメルツ氏(キリスト教民主同盟党首)が国防費の拡大に意欲を示したことが同国財政政策の重大な転換点と見なされています。結果的に、海外投資家の関心が日本株に向きにくい状況が続いています。
日銀追加利上げは経済の強さの証でもある
日本株の弱さについて5つの要因を挙げましたが、いずれも株安が長引く決定打となるものではないと思っています。
まず、日銀の追加利上げについては、市場が実施を織り込む段階で株安圧力が作用する可能性があります。短期的には要注意要因です。また、コメ価格の予想外の高止まりが消費者のインフレ期待を押し上げ、さらには日銀のタカ派化を後押ししているという「悪いインフレ」の色彩を多少帯びてきている面もあります。
ただし、今のところは企業が資本財などを適正価格に引き上げることで利益率を高めているというプラスの側面が勝っていると思います。「日銀が利上げを進められる=日本経済の足腰が強くなっている証拠」という基本観は変わっていません。
米国景気減速は深刻なレベルではない
海外要因としては、たしかに米国指標には弱いものも散見されます。しかし、3月7日に発表された雇用統計では2月の非農業部門の雇用者数は15.1万人増とまずまずで、失業率も4.1%(前年比+0.2%)と低水準にとどまっています。前年比で0.5%以上の上昇ペースになると景気後退入りが濃厚、という経験則(サーム・ルール)が2024年夏の株価急落を招きましたが、それに比べ現状はかなり緩やかな減速です。むしろ、週次の小売売上で前年比の伸び率を見ると、1月半ばに4%台へと大きく落ち込みましたが、V字型で回復しており、2月後半には6%台まで回復しています。
トランプ関税は予想困難で複雑です。しかし、米国が関税を引き上げる相手国としては、優先順位がかなり明確になっていると思います。つまり、中国、次にカナダ・メキシコ、次いでEU(欧州連合)、という順番です。日本は米国の貿易赤字に占めるシェアが5.7%(2024年)まで低下している一方、直接投資の出資国としては「最大の投資家」という立場です。石破首相はトランプ大統領との2月7日の首脳会談で、この2点を強調し、理解を得ています。もちろん、自動車関税にはリスクがつきまといますが、カナダ・メキシコに対して発動された関税も、自動車などUSMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)の枠組みにのっとって非課税となってきたものは、今回の関税からも除外されています。北米で生産される自動車(部品)に関税がかかる最悪の事態は回避されています。カナダドルやメキシコペソが大きく崩れていないことも、「関税シナリオは不透明だが最悪回避」の証と言えます。
「DeepSeekショック」は、AI関連ビジネスが従来想定していた米国一強の図式を覆す可能性があり、「AI恩恵銘柄」への強気の見方はなかなか回復しない可能性もあります。一方で、AIを利用するユーザー側の事情で考えれば、低コストAIの普及は大きなメリットになります。具体的には、情報通信や金融セクターには中長期でプラス要因になるでしょう。
欧州株に対する見劣りという点は、しばらく続く可能性があります。欧州株は2022年2月のロシア軍によるウクライナ侵攻以来、エネルギー価格の高騰という足かせをはかされてきました。また財政規律が日米などに比べ厳しすぎることも、「グローバル景気の減速に対して脆弱」という評価につながっていました。しかしこれらの中長期の弱点を克服することへの期待が当面高まることはあり得ると思います。一方、日本もバブル崩壊から30年超続いたデフレを完全脱却するという、重大な転換点を迎えています。私は先週、ニューヨークで多数の投資家にお会いする機会がありましたが、日本株への中長期の期待感は根本的には変わっていないと感じました。
株高に転じる時期としては4月後半以降を想定
日本株が再度上昇に転じる時期としては、2025年4月後半以降を想定しています。理由は3点あります。
第一に、「次の日銀追加利上げ」を株式市場がしっかり受け止められる時期としては、5月1日の会合間近になるのではないかと予想しています。春闘の集中回答が3月12日にありますが、野村では昨年並みの強い結果になると見ています。3月19日の会合では植田総裁が次の利上げに前向きなトーンを打ち出すでしょう。しかし株式市場では「企業業績を確認するまでは楽観的になれない」という雰囲気が続くのではないでしょうか。
第二に、企業業績としては、4月後半から本格化する2025年3月期決算の発表が重要です。とくに、マクロ環境に不安を抱えている中で、企業の2026年3月期の業績見通し(ガイダンス)に注目が集まると見られます。日銀短観によれば、企業の想定為替レートは146円でしたので、現状の147円程度の円高であれば、円高による業績下振れリスクは大きくないと言えます。野村では5~10%の増益基調が続くと見ています。
第三に、個人消費の回復です。ここまでの消費の停滞は、賃金上昇率が高まっている一方で、インフレ率がなかなか下がらないという図式によってもたらされていました。とくにコメ価格が前年比7割という過激な上昇率(1月の全国消費者物価指数)になったことにより、CPI(消費者物価指数)が0.4%ポイント高まってしまいました。これが丸々消費余力を奪ったわけです。先行きは、備蓄米の放出などによりコメ価格の上昇に歯止めがかかれば、春先以降、賃金上昇が素直に消費拡大につながりやすい局面に移行すると想定しています。
野村證券は、2025年12月末の予想値としてはドル円:140円、日経平均:42,000円を維持しています。デフレ完全脱却にともなう日銀の追加利上げをこなしながらも、景気拡大にともなう企業の増益、株価の上昇は続くというシナリオは不変です。足下の株価調整は、長期投資家にとっては買いの好機をもたらしていると見ています。

- 野村證券 市場戦略リサーチ部長
池田 雄之輔 - 1995年野村総合研究所入社、2008年に野村證券転籍。一貫してマクロ経済調査を担当し、為替、株式のチーフストラテジストを歴任、2024年より現職。5年間のロンドン駐在で築いた海外ヘッジファンドとの豊富なネットワークも武器。現在、テレビ東京「Newsモーニングサテライト」に出演中。
※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。
- 株式の手数料等およびリスクについて
-
国内株式(国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は2,860円(税込み))の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。国内REITは運用する不動産の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。国内ETFおよび国内ETNは連動する指数等の変動により損失が生じるおそれがあります。国内インフラファンドは運用するインフラ資産等の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。
外国株式(外国ETF、外国預託証券を含む)の売買取引には、売買金額(現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対し最大1.045%(税込み)(売買代金が75万円以下の場合は最大7,810円(税込み))の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等は国や地域により異なります。外国株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。