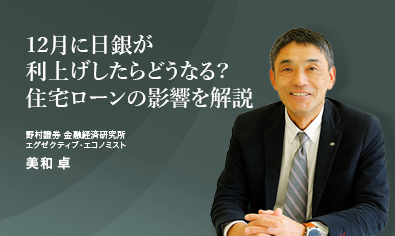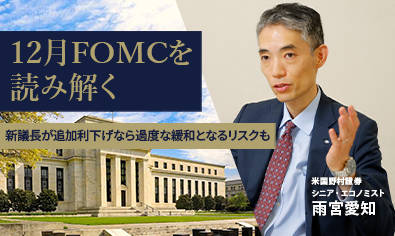2025.04.11 NEW
日経平均株価が再び急落 トランプ関税を巡る次の論点は 野村證券・吉本元
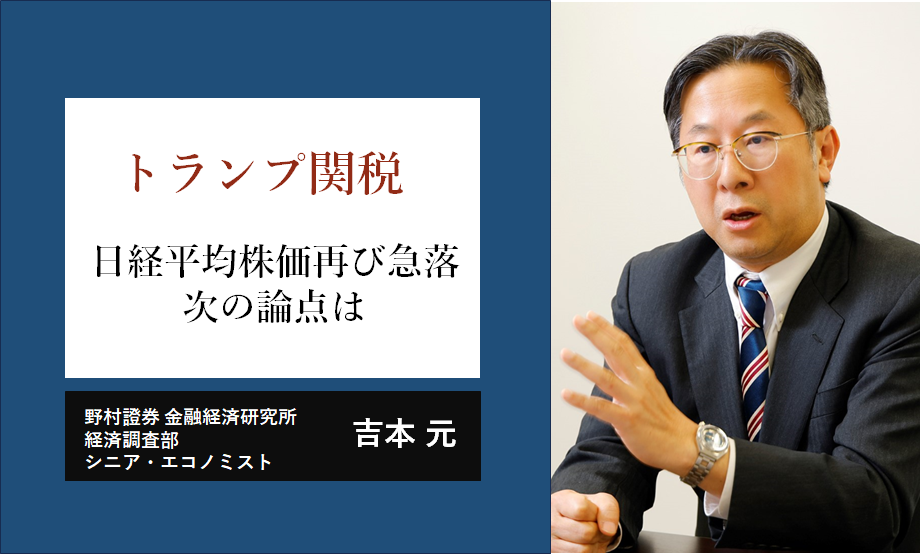
写真/タナカヨシトモ 文/斎藤健二(金融・Fintechジャーナリスト)
トランプ政権の「相互関税」政策により株価が世界的に急落しました。しかし、4月9日に一部の国・地域に対する上乗せ分の関税発動が延期されると決定され、その日のNYダウは前日比2,962.86ドル高と史上最大の上昇幅を記録しました。翌10日の日経平均株価も同2,894.97円高となり、歴代2番目の上昇幅となりました。ところが4月10日のNYダウは反落し、一時2,100ドル以上下落し、終値は同1,014.79ドル安となりました。これを受け、日経平均株価も11日は大幅安で寄り付き、終値は同1,023.42円安となりました。関税をめぐる不透明感は依然として強く、株式市場は不安定な動きを続けています。相互関税の狙い、今後の関税政策の行方について、野村證券シニア・エコノミストの吉本元が解説します。

相互関税3つのサプライズ
- 相互関税の発表後、世界的な株価急落が起きました。なぜ市場はここまで大きく反応したのでしょうか?
-
三つの理由があります。まず、すぐに実行された点です。本来、通商法や通商拡大法に基づく関税発動では事前調査が必要で、発動までに一年程度かかるものです。しかし今回は全く違う法律で実施されました。国際緊急経済権限法(IEEPA)を使ったのです。これは本来、戦争中の敵国、平時でも米国と敵対する国(テロ支援国家)、テロ集団や犯罪組織に制裁する権限を大統領に付与する措置として適用される法律です。大統領の権限を大幅に拡大することになるため、非常時に限る法律です。このため、第1次トランプ政権時(2017-21年)は、大統領の権力の濫用を避けるため、IEEPAの適用は見送られました。まさか、現在の政権になって、この方法を採るとは思いもよりませんでした。全世界が米国を脅かしているという危機的状況を理由にIEEPAを適用するのは、かなり強引と言えます。
二つ目は、対象が全世界に及ぶとは想定していなかった点です。当初は貿易赤字の大きな国だけが対象になると見られていました。「ダーティー・フィフティーン」とラトニック商務長官が言及していたように、15カ国程度が対象になると予想されていたのです。しかし実際には基礎部分10%の関税はほぼ全世界に課され、超過分も60カ国・地域に及びました。
三つ目は、相互関税のコンセプト自体が当初の予想と異なっていました。本来の相互関税は、相手国の税率が高いから同じ分をかけるというコンセプトのはずですが、貿易黒字国に対しても10%の基礎関税をかける理由が不明確でした。
こうした予想外の展開に市場は驚き、不安視したのです。
繰り返しになりますが、相互関税は二段構えになっています。一つは10%の基礎部分で、これはほぼ全部の国に対してかけるものです。もう一つは米国の貿易赤字が大きな国に対して、10%超の税率を上乗せするものです。上乗せ分を含めた相互関税の税率の算定方法は、相手国の関税率や消費税率、規制などの非関税障壁を税率換算したものを個別に査定し、積み上げたものではありません。貿易赤字額を輸入額で割り、それに2分の1を掛け合わせた、機械的なものになっており、米国の不満の具体的内容が税率からは分かりません。
- 日本にとっては24%の関税を突き付けられたのに、9日に関税が発動になった直後にその上乗せの14%分は発動が90日間延期されました。これは市場としてもホッとしていいことですよね。
-
そうとは言えません。24%から10%というと大幅に下がったように感じますが、錯覚です。従来は数%だった関税が10%になるだけで打撃です。日本だけではなく、米国がWTO(世界貿易機関)加盟国に対して今までかけてきた関税は平均で3.3%でした。これを一気に10%に引き上げるだけでも大きな影響が出るでしょう。4月11日に株価が下落したのは、中国に対する相互関税率について9日に発表された段階では、その他の関税率を含めて125%だったはずなのに、計算違いということで145%に修正されたことがきっかけです。もちろん、税率が引き上げられ、経済や物価への悪影響がさらに懸念されたためですが、税率の根拠があやふやで、いつ引き上げられるか分からないためでもあります。
- 日本が最初の交渉国になった背景と、交渉における課題は何でしょうか?
-
トランプ政権は約60カ国・地域と交渉する方針ですが、その先陣を切ることになったのは日本です。これは4月2日に相互関税が発表されて早々に、石破茂首相がトランプ大統領と電話会談を行い、協議開始で合意したためです。日本は安全保障面で米国の恩恵を受けており、同盟関係を重視する立場から交渉に応じるだろうと米国側も期待しているのでしょう。
そして、日本が米国に有利な条件を提示すれば、それが他の国と交渉する際も駆け引きの材料になります。「日本がここまで受け入れたのに、あなたの国は受け入れないのか?」と交渉が出来るからです。ですから、米国側は、なるべく、日本から有利な条件を引き出そうとするでしょう。
交渉において気がかりなのは、米国側の窓口が財務長官となっている点です。本来、関税問題は通商政策の一環であり、ラトニック商務長官が担当するのが自然なのですが、ベッセント財務長官が交渉役を務めることになっています。ベッセント財務長官はラトニック商務長官程強硬ではないとの観測もありますが、これは第1次トランプ政権時の日米交渉とは異なる態勢です。米国側の要求が多岐にわたるかもしれません。
- 日本はどのような交渉戦略をとると予想されますか?
-
それでも、日本側の戦略は、第1次トランプ政権時の通商交渉の経験を踏まえて立案されると見られます。
第1次トランプ政権時に合意した日米貿易協定の未決事項や、3月31日にUSTR(米通商代表部)が発表した外国貿易障壁報告書を踏まえると、米国側は、農産物に関して、関税引き下げや非関税障壁を取り下げ、輸入を拡大するよう求めてくると見られます。しかし、日本は参議院選挙を7月に控えており、農業関連の票田と、農産物分野での譲歩の兼ね合いを図らないといけません。
農産物以外で考えると、石破首相が米国訪問時に提案した、対米投資を1兆ドルに増やす提案、LNG(液化天然ガス)のアラスカからの輸入拡大や防衛装備品の購入などの提案が主な柱になるでしょう。トランプ大統領は目に見える成果を重視する傾向があるため、日本企業による米国への具体的な投資計画や、投資を増やすための支援策などを見せる必要があるでしょう。
交渉には二つの時間的制約があります。一つは90日の猶予期間内(7月7日まで)に合意を目指す必要があること、もう一つは日本側の事情として7月の参議院選挙の存在です。選挙結果次第では政権の枠組みが変わる可能性もあるため、日本側としては選挙前に一定の決着をつけたいという思惑があるでしょう。
具体的なスケジュールとしては、6月15-17日のG7首脳会談(カナダで開催予定)が重要な節目になると考えられます。トランプ大統領が出席すれば、石破首相との二国間会談の機会が設けられ、そこまでに早ければ大筋合意、少なくとも暫定合意を目指すことになるでしょう。
主要国の対応と今後の関税政策
- 中国やEUなど、他の主要国・地域はどのような対応をしていますか?
-
中国も交渉する姿勢は示していますが、まだ、米中双方の関税の応酬が止まりません。関税引き上げが収まったとしても、通商交渉は第1次トランプ政権時と同様に長期化するでしょう。2018年から交渉しましたが、合意に至ったのは1年以上後の2019年12月。しかも関税引き下げは限定的なものでした。
今回の両国の関税率とも100%を超えており、交渉の結果、大幅に引き下げられるかは視界不良です。現実的な対策として、迂回輸出の動きが活発になると思います。第1次政権時代にも、中国製品をメキシコ経由で米国に輸出するという迂回輸出が行われました。メキシコ経由の迂回輸出はバイデン政権の時代に指摘されましたが、今後は、メキシコ以外の地域、例えば、相互関税率が10%のシンガポールなど、中継貿易国や租税回避地を用いた別のルートを探ることになると見られます。
EU(欧州連合)も報復関税を発表しました。これは鉄鋼・アルミニウムの制裁関税に対する報復で、約210億ユーロ分の米国からの輸入品に25%の関税をかける方針です。米国の相互関税上乗せ分の発動延期を受けて、報復措置を90日間保留することになりましたが、同盟関係にありながら、報復という比較的強硬な姿勢に出たのは、ウクライナ紛争に関する米国の対応への不満があるからだと思われます。トランプ政権が欧州の安全保障に積極的でないため、通商面で譲歩する理由が乏しいと考えているのでしょう。
- 今後、トランプ政権の関税政策はどのように展開すると予想されますか?
-
関税政策はまだ終わりではありません。国別の相互関税に一段落ついたように見えても、次は品目別の関税が控えています。すでに木材や銅製品については調査を命じており、トランプ大統領は医薬品への関税も検討していると発言しています。
特に注目すべきは、以前、トランプ大統領が言及していた半導体関税です。日本、韓国、台湾などが主要な輸出国ですが、これらの国に対する相互関税率がすでに高いため、半導体関税はそれを上回る必要があります。これはかなり強硬な措置になるでしょう。
ただ、半導体は一つの国だけで製造できるものではありません。製造装置や素材も含めて国際的なサプライチェーンで成り立っています。関税で国産化を促そうとしても、短期間で切り替えることは不可能です。関税によって半導体の輸入品が値上がりすれば、防衛産業などの生産にも支障を来すことから、政権内でも様々な意見があるのでしょう。木材、銅製品、医薬品のようにいち早く出てこないのは幸いと言えるでしょう。
金融市場と世界経済への影響
- 関税政策は、金融市場と世界経済にどのような影響を与えますか。
-
関税がインフレを引き起こす一方で、景気も悪化させるという複雑な状況が生まれています。現在米国の短期金利と長期金利で異なる動きが見られるのはこのためです。
関税によるインフレ懸念から、FRB(米連邦準備理事会)は政策金利を引き下げにくくなり、短期金利は高止まりしています。一方、関税による景気減速懸念から、長期金利は低下する傾向にあります。これは、金融機関にとっては、「逆ザヤ」になるため、収益上はよろしくありません。
トランプ大統領は金利引き下げを強く望んでいます。不動産業のビジネスパーソンだったので、低金利のほうが、仕事がしやすいという経験則もあるのでしょう。2026年11月の中間選挙を前に、インフレ抑制よりも、景気浮揚を急ぎたいのでしょう。2026年5月には、中央銀行のFRBのトップ・パウエル議長の任期が切れるため、自分の意向に沿った人物を次期議長に据えようとするでしょう。しかし単純に金利を下げれば景気がよくなるわけではありません。所得格差の大きい米国において、インフレがひどくなれば、所得の低い層では、家計が赤字になり、借金を返せなくなる人が増え、金融機関の不良債権が増えてしまいます。FRBが最も避けなければならないのは、その結果金融危機が起きることです。関税政策を完全に撤廃しない限り、FRBは、金利の上げ下げという一つの手段で、景気後退とインフレと金融危機の三つのリスクを回避するという難しいかじ取りを続けることになります。
- 投資家はこの状況をどのように見るべきでしょうか?
-
フリーフォール(急落)状態はいったん収まると思いますが、関税政策が転換せず、五月雨式に発表が続く限り、市場では警戒感が解かれず、V字回復は期待しにくい状況です。しばらくは底這いの状態が続きつつも、値動きの大きいボラティリティー(変動率)の高い相場になるでしょう。
特に警戒すべきは、市場が落ち着いたタイミングで再び関税政策が持ち出される可能性です。トランプ大統領は相互関税の猶予を発表した際に、「みんな騒ぎすぎたからちょっとやめてやった」と発言しています。裏読みすれば、市場が落ちつけば、また次の関税を検討し始める可能性が高いと見ています。
現状では、投資家にとって重要なのは、資産や地域についてリスク分散を図ることでしょう。

- 野村證券 金融経済研究所経済調査部 シニア・エコノミスト(政治・地政学調査)
吉本 元 - 1993年に野村総合研究所に入社し、経済調査部配属。1999年、東京大学大学院経済学研究科入学、2001年に経済学修士号取得。野村證券金融市場情報管理部、米国野村證券、野村證券金融経済研究所経済調査部を経て、2009年に外務省に出向し、在英国日本大使館に着任。2011年、野村證券金融経済研究所に帰任。国内外のリスク分析(政治政策、地政学リスク、政治動向など)を担当。
※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。
- 手数料等およびリスクについて
-
当社で取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料(換金時手数料)および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、年金保険・終身保険・養老保険・終身医療保険の場合は商品ごとに設定された契約時・運用期間中にご負担いただく費用および一定期間内の解約時の解約控除、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の委託保証金または委託証拠金をいただきます。信用取引、先物・オプション取引には元本を超える損失が生じるおそれがあります。証券保管振替機構を通じて他の証券会社等へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、移管する銘柄ごとに11,000円(税込み)を上限額として移管手数料をいただきます。有価証券や金銭のお預かりについては、料金をいただきません。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。
- 株式の手数料等およびリスクについて
-
国内株式(国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は2,860円(税込み))の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。国内REITは運用する不動産の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。国内ETFおよび国内ETNは連動する指数等の変動により損失が生じるおそれがあります。国内インフラファンドは運用するインフラ資産等の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。
外国株式(外国ETF、外国預託証券を含む)の売買取引には、売買金額(現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対し最大1.045%(税込み)(売買代金が75万円以下の場合は最大7,810円(税込み))の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等は国や地域により異なります。外国株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。