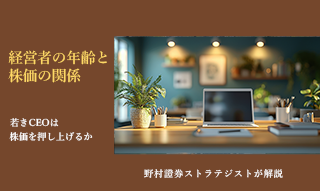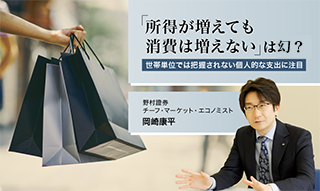2025.05.07 NEW
「含み益が出ているうちに売却」は合理的な投資行動か? 行動経済学で考える 野村證券・大庭昭彦
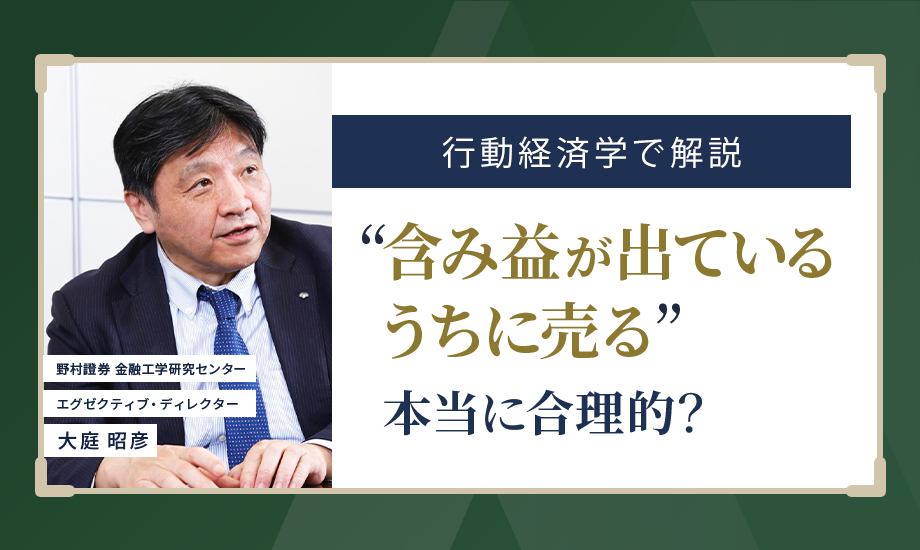
写真/竹井俊晴
トランプ第2次政権の関税政策などの影響により、株式市場に様々な混乱が生じています。日米の株価はやや切り返したものの、2024年の最高値の水準には戻っていません。なかには株価が戻ったことで「含み益が出ているうちに」売却したいという気持ちになっている投資家もいるかもしれません。この行動は合理的なのでしょうか?行動経済学に基づく投資理論である行動ファイナンスに詳しい野村證券 金融工学研究センター エグゼクティブ・ディレクターの大庭昭彦が解説します。

買値という「参照点」を意識しすぎて投資がうまくいかない例
- 前回の記事(株価急落後の上昇で、「やれやれ売り」をする前に考えるべきこと 行動ファイナンスで解説)で、株価が急落した後、買値近くまで上昇したときに売る「やれやれ売り」は合理的とは言えない、という話を聞きました。人の心理には得よりも損のほうが痛いというバイアスがあり、株価が下がった時のつらさから早く逃げたくなるということですよね。
-
そうですね。今も株式市場の軟調は続いているので、嘆いている人も多いかもしれませんね。
- 仮に、株価低迷時に投資を始めていて、買値よりは今の株価は高いとします。2024年よりは下がったとはいえ、「含み益」が出ているなら売って、その売却益で次の投資を考えるという考え方は妥当ではないでしょうか?
-
なるほど、売却益が出るうちに売りたいというわけですね。よく投資に関して、「含み益」「含み損」という言葉を使いますが、普通の個人にとっては誤解を招きやすい概念だと思います。株式や投資信託を持っているなら、その時の株価や投資信託の価格により資産額が決まります。今の株価が高すぎるのか安すぎるのか、という議論には意味がありますが、過去のある時点の株価でしかない買値と比べてどのくらい乖離があるかにとらわれる必要はないんです。
しかし、実際には含み益、含み損を気にする人はたくさんいますね。そして、保有している有価証券の含み益を得る行動は急ぐのに対し、含み損を確定するのは躊躇しがちです。これは前回も紹介したプロスペクト理論の主張の一つである、損が得よりも痛いというバイアスからきていると思います。得は少しでも早く確定したいのに、損失のほうは認めるのが心理的につらいからです。
含み益を気にする意味が本当にあるのか、もう少し突っ込んで考えてみましょう。あなたは老後資金の足しにしたくてA社とB社の株式投資を始めました。どちらも1,000円のときに買ったとします。A社の株価は2,000円まで順調に上がりましたが、ある金融市場のイベントにより一時1,500円まで下がりました。一方B社はそのイベントまで株価は変わらず、750円に下がりました。あなたはどうしますか?
- A社は500円も儲かっているのだから、売りたいですね。2,000円の時に売れれば良かったんだと思いますが、そんなうまくいきませんし、贅沢はいいません。B社は、今売ると損なので、もうちょっと待ちたいです。A社の売却益で他の株式を買いたいです。
-
なるほど。でもよく考えてみてください。A社は一時、2,000円まで上がっている時を基準とすると、B社と同じく3/4に下がっています。なのに、なぜA社だけ売るのでしょう。もし、この金融イベントが大変深刻なものでもう株価が上がらないと思っているなら、B社も売ったほうがいいことになります。
- うーん、言われてみるとそうですね。なぜかA社だけ売ろうと思ってしまいました。
-
もしこの金融イベントは一過性で、また株式市場の水準は元に戻ると思っているのなら、株価がずっと上がらなかったB社より、それまで順調に株価が伸びたA社のほうが成長性のある企業ということで保有を続けるのが妥当かもしれませんよ。買値と比較して儲かった、儲からない、という点だけを気にすると、企業の成長とともに利益を得ることができる株式投資の意味を失ってしまいます。
買値を強く意識するあまり、判断が歪んでしまう現象を「参照点の依存性」と言います。人は買値を参照点として記憶し、そこからどのくらい変化したかに敏感に反応する傾向があります。その参照点よりも上だから儲かるという感覚で売却するのが合理的とはいえません。有価証券を持っていれば、株価が上がったら上がっただけの資産を持っているということになりますから、買値だけをずっと覚えているというのは不合理なのです。
もうひとつの参照点として強く意識されるのは、過去の高値です。「高値覚え」という言葉がありますが、これは過去の高値が忘れられず、相場が下落してもまたすぐに上昇すると思い込んでしまうこと。相場が下降基調に入っているのにもかかわらず高値との比較をしてしまい、売却ができない、というのもよくある現象です。
お金に色をつける「メンタルアカウンティング」を活用
- では合理的に考えるための参照点はどこにすればいいんですか?
-
本当に合理的な参照点は、「今」なのです。今、その企業の株価に対して、今後の成長が見込めない大きな変化が起きているなら、売却を検討するのもありですが、そうではなく過去の自分の買値を強く覚えているだけなら、売却は待った方がいいかもしれません。
本来はその株は上がったらすぐ売ろうと思って投資したのではなく、長期にわたって成長が見込めて老後資金としたいと思って投資したはずですから、その成長ストーリーに陰りがないのであればまだ老後ではないのに売却するのは不合理なのです。
- 株価が下がったときも、常に今の株価に立ち返ってこの投資対象はこれから成長するか?と考えるということですね。ついついそれを忘れて、投資に関しては1円も損したくないと思ってしまうんですよね。
-
それはとてもよくわかります。合理的な考え方に自分を導くためにも、行動ファイナンスは有効です。お金に関して特徴的な行動のひとつに、「メンタルアカウンティング」があり、日本語訳では「心の会計」とも呼ばれます。行動経済学の権威でノーベル賞を受賞したリチャード・セイラー氏が提唱した理論のひとつです。
本来お金とは、どんな手段で手に入れたお金でも1万円なら1万円の価値をもっているはずですが、人は心の勘定科目によって色分けしがちです。例えば、苦労して働いて得たお金は大事に使うのに、ギャンブルで得たお金はパッと使ってしまう、といった具合です。
その心の勘定科目をあえて活用し、「これは老後資金のための投資」という色を明確にするのです。つまり、ある投資対象について「これは定年退職までは売却しない」と決めて運用を継続する。そのほうが、株式市場の乱高下のたびに不合理な売却・購入を繰り返すよりも安定的に資産を増やせる可能性が高いでしょう。これを仕組み化しているのが事実上60歳まで引き出すことができないiDeCoなどの制度です。
- なるほど、「老後資金のための投資」という色をつけて、足元の株式市場の動きには翻弄されない、と決めるということですね。
-
株式市場が乱高下しているときにこれを言っても、人はなかなか実行には移せません。大事なのは平常時に自分の投資ルールを決めることですね。

- 野村證券 金融工学研究センター エグゼクティブ・ディレクター
大庭 昭彦 - CMA(日本証券アナリスト協会認定アナリスト)、証券アナリストジャーナル編集委員、慶應義塾大学客員研究員、投資信託協会研究会客員。東京大学計数工学科にて、脳の数理理論「ニューラルネットワーク」研究の世界的権威である甘利俊一教授に師事し、修士課程では「ネットワーク理論」を研究。1991年、野村総合研究所へ入社。米国サンフランシスコの投資工学研究所などを経て、1998年に野村證券金融経済研究所に転籍、現在に至るまで、主にファイナンスに関わる著作を継続して執筆している。2000年、証券アナリストジャーナル賞受賞。
※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。
- 株式の手数料等およびリスクについて
-
国内株式(国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は2,860円(税込み))の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。国内REITは運用する不動産の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。国内ETFおよび国内ETNは連動する指数等の変動により損失が生じるおそれがあります。国内インフラファンドは運用するインフラ資産等の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。
外国株式(外国ETF、外国預託証券を含む)の売買取引には、売買金額(現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対し最大1.045%(税込み)(売買代金が75万円以下の場合は最大7,810円(税込み))の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等は国や地域により異なります。外国株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。