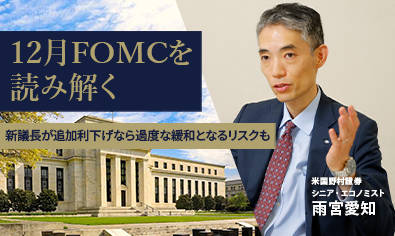2024.12.12 NEW
フリーアナウンサー・大橋ひろこさんの投資スタイル 「マクロ経済を学ぶと投資がもっと理解できた」
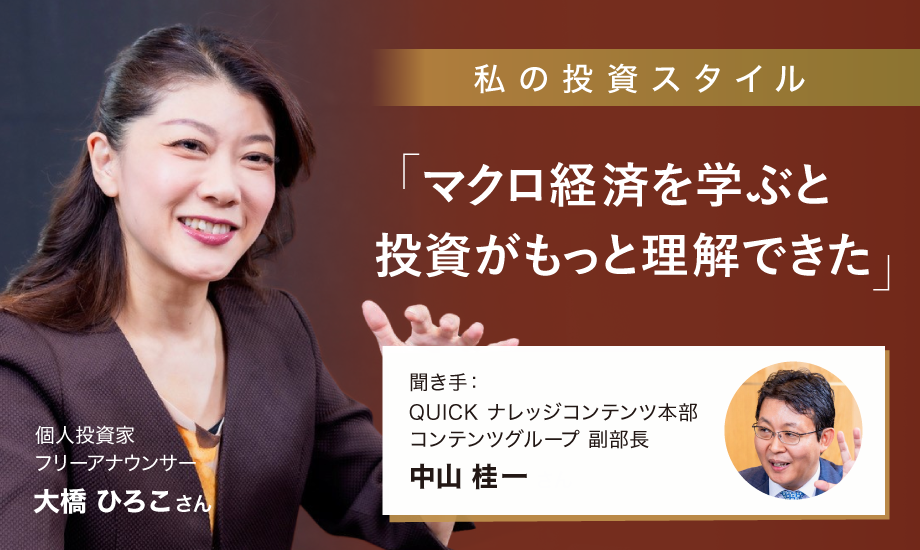
文/中城邦子 撮影/竹井俊晴
ラジオ番組で投資を一から勉強
中山桂一さん(以下中山)
大橋さんはどんなきっかけで投資を始めたのですか。
大橋ひろこさん(以下大橋)
駆け出しの頃、昔のラジオたんぱ、今のラジオNIKKEIの投資情報番組のアシスタントとして、先物の情報番組を2年間、そのあと1時間の帯番組を3年間担当したことがきっかけです。
中山
いきなり先物ですか。まず株式じゃないところから入ったのですね
大橋
そうなんです。チャートなどテクニカルの見方も知らなかったので、出演されている方のお話も、パーソナリティの言っていることもわからず、必死に勉強しました。そのうち、テクニカル分析のコーナーを担当するようになったのですが、当時は相場の強弱を表すテクニカル分析の指標であるオシレーターの数値を、毎日手計算していた時代でした。わずか25年ほど前なのですが、投資環境は大きく変わりましたね。
中山
そうですね、私もその時代を知っています。ファンダメンタルズはどんな風に勉強されたのですか。
大橋
出演するコメンテーターやパーソナリティの話を聞いて、毎日メモしていました。金や原油は地政学で動くのだとか、何をおいても金利が大事なんだとかということを、番組を通して学べたことはすごくラッキーでした。
全て独学でしたが、エコノミストやストラテジスト、経済学者の方とお会いする前には、ご本人の著書や関連する本を読んでおかなければいけないので、当時の金融政策のあり方や中央銀行の役割、為替などについて、いわゆる学術本も事前に読み込み、インタビューしていました。
給料の大半を投信積み立てに
中山
1998年に改正外為法で、個人が為替取引を行えるようになり、FX(外国為替証拠金取引)がスタートしました。FXはそのころから始めたのですか。

大橋
FXについても、まずは番組を担当することになり、そこでまた勉強させていただきましたね。24時間、ドル/円だけでなく、ポンドやユーロ、ニュージーランドドル、豪ドルなどあらゆる世界の通貨を、少ないスプレッド・手数料だけで、個人が取引できる時代が来たことが衝撃的でした。そこで自分も口座を作りました。
中山
投資家デビューされたわけですね。最初に買ったのはどんな金融商品でしたか。
大橋
最初に株式の取引口座を開きました。番組で勉強したのはどちらかというとデリバティブ(金融派生商品)だったので、株式取引は素人でした。当時は色々な情報を見ながら、インターネット上で人気の銘柄を買ったりして、失敗したこともありました。
中山
2000年代初頭は米国でITバブルがありましたよね。日本でもITベンチャーが渋谷に集積し、「シブヤ・ビットバレー」などと呼ばれ、IT企業の株式公開も相次ぎました。
大橋
私の周りにも、「ビットバレー界隈の株を買っておけばいい」と、信用取引で買っている人たちもいました。私は、株式のトレーディング成果は全然上がらなかったので、このやり方では駄目だと感じ始めていました。そこで、色々な投資商品を見渡してみると個別株ではなくて投資信託が良いのではないかと気が付きました。ちょうど「草食投資隊」の方々が本を出されたころです。
中山
コモンズ投信会長の渋澤健さん、セゾン投信社長の中野晴啓さん、レオス・キャピタルワークス代表取締役社長の藤野英人さんが、「草食投資隊」を結成し、「運用のプロが教える草食系投資』(日本経済新聞出版)という長期投資を勧める本を出されたころですね。
大橋
そういう方々のお話を勉強して、とりあえず投資信託の積み立てをやろうと考えました。最初は新興国株式の投資信託2、3本から始めました。当時はBRICSなどが話題で、米国株式がこんなに強くなるとも言われてなかったので。入ってきた収入のうち生活費以外、ほぼ全額を投信の購入に充てていました。
当時、積立設定した銘柄は今に至るまで15年近く積み立てを続けています。最初の2、3年は全く資産が増えている感覚はなかったのですが、複利の効果もあって大相場で大きく増え、資産の核になってくれました。今では日本の連続増配株やインド株の投信など10本以上を少しずつ積み立て、たまに銘柄の見直しをしています。
投資信託で積み上げた資産があるという安心感があるので、FXやコモディティ、あるいはデリバティブもやれるのだと思います。もちろん天才的なトレーダーの方もいらっしゃるのですが、普通の人は、やはり核となる資産を確実性の高い商品で積み上げて、余力で個別銘柄を買ったり、売ったりしたほうがよいと思っています。

相場に何が織り込まれているかを考える
中山
大橋さんは、為替や金利などの動きについて日常的にSNSで情報発信されるなど、マクロ経済に強いですよね。
大橋
そうですね。これまで勉強を続けてきたから、例えば、今はドル金利が高く、円金利が低いため日米金利差から円安になるのは仕方ない、日銀が介入してもまた円安方向に行くよねと理解できます。ギリシャ発の債務危機が起きた時は、ユーロが売られるだろうとか、その危機を乗り越えるための金融政策はなんだったか、ということを覚えておくと、新たな危機が起きた時に為替がどう動くか捉えることができるようになってきます。
例えば、雇用統計のデータが悪くなったら利下げは急ぐべきだとか、投資家は金融政策の次の一手を予測してマーケットに織り込みに行きます。行き過ぎた織り込みが失望に変わる時の変動は大きくなる、そういう投資家心理を自分で考えられるようになったことは大きいと思います。
中山
著書やセミナー、ブログなどを通じて、様々な発信をされています。アナウンサーという相手から言葉を引き出す仕事から、自分の言葉で発信する側になったのは、どんなタイミングだったのですか。
大橋
ブログに関しては、現在は「note」に移行しましたが、日曜から木曜までほぼ毎日書いてアップすることを2007年から17年間続けていました。自分の投資トレードの履歴も書いているのですが、当初は損切が苦手で、コメント欄に「もうやめた方がいい」などと書かれたりしました。読者に叱咤激励され、損切りができるようになったのです。番組やブログをご視聴下さる皆様に育てられた側面も大きかったと思います。
ブログには、「今日の日銀の発表は」「FOMCが」など、自分なりにニュースで調べたことや自分の思いを書いたり、このニュースを見て私はドルを買ったよと報告したりしています。そうやって日々発信を積み重ねたことが、少しずつ教える側の活動につながっていったのだと思います。
投資によって経済的な自由を獲得してほしい
中山
今の投資環境をどう見ていますか。
大橋
NISAが為替市場を動かすほどのインパクトを持ったことに、本当にびっくりしています。どうして政府は、NISAの投資対象を日本株に限定しなかったのだろうと思うぐらいに、S&P500や全世界型のインデックスファンドに人気が集中していますよね。仕事でお会いする若い方もみんなNISAをやっておられます。投資環境が変わるときは本当に一瞬で変わるのだなと実感しています。
中山
投資初心者の方にはどんなことをアドバイスしますか。
大橋
NISAをきっかけに今年から始められた方には、まずは長期的に考えてほしいですね。投資の世界で短期的に成功しようと思うと、信用取引などでレバレッジをかける、なけなしのお金をつぎ込むなど無理をしがちです。そうではなくて、長期的に自分の資産を複利で運用していくという概念をまず覚えてほしいです。最初から“10倍株を探せ”みたいな本を買って鵜呑みにするのは、お勧めできません。
複利の効果を使う方法は、誰もが時間を味方にして、実践しやすい資産形成だと思います。どの銘柄を買おうかと悩んでいるうちに時間は過ぎていくので、まずは投信をやってみましょう、とアドバイスしたいですね。
特に女性の方こそ、投資によって経済的な自由を獲得してほしいです。経済的に独立できていたら、家庭でも職場でも理不尽なことに対して言うべきことを言えます。いざとなったら別の人生もあると思える強さを得るためには、資産形成はすごく重要だと思います。

大橋流、投資情報の集め方、定点観測のすすめ
中山
大橋さんが日々チェックされている情報やルーティンにされていることを教えてください。
大橋
まず真っ先にチェックするのは、あらゆる金融商品のチャートが見られる「TradingView」というサイトです。無料で見られるものと有料で見られるものとがあるのですが、米国、日本を始め世界の主要株価インデックス、あらゆる通貨、金利、コモディティ、個別株のチャートも見ることができます。それでまず株価、金利、為替の値動きを見て、なぜこんな動きになったのか、違和感のあるものをチェックして、その後に市況概況を見ます。
ニュースサイトはブルームバーグ、ロイター、日本経済新聞などをチェックします。誰でも見ることができるメディアのニュースを見ていますが、報じるメディアによって同じニュースでも温度差がある時もあり、そんな時はやはりマーケットの値動きが最も信頼できる情報というわけです。
中山
ニュースより、まずはチャートを見た方がいいですか。
大橋
そうですね。今日は日経平均株価が700円下がったといっても変動の連続性がわからないですが、チャートで見れば値動きが一目でわかります。私のルーティンとしては、帰宅してチャートやニュースをチェックしたら、夜中にnoteを書いて寝ます。
中山
情報を整理して、書いてから寝るのは良い習慣ですね。一般の方なら新聞や経済ニュースチェックをして、整理する感じですね。
大橋
経済は日々つながっていることを感じるために、毎日の習慣として、これとこれだけはチェックしてメモをするということをやっていただけるといいですね。定点観測を続けていると、スポットでしか理解できなかった経済政策や金融政策の意味がつながって見える時が来ます。スポット的に人に聞いただけの情報と違って、自分は継続的に勉強しているから大丈夫なのだという自信につながりますし、マクロのお金の動きが見えてくると、面白いと思えるようになるのでおすすめです。
定点チェックをするのは、新聞でもウェブサイトのまとめ記事でも、あるいはテレビの経済報道番組でもいいと思います。コンパクトに重要事項を伝えてくれているものを毎日見て、ちょっとメモを取る。色々な方と仕事をさせていただいていますが、みなさんちゃんと記録をされています。手書きのノートでもスマホのメモ機能でも、形態はご自身の好きなスタイルでいいと思いますし、今日こんなニュースがあったとかだけでもいいのだと思います。

- 個人投資家、フリーアナウンサー
大橋ひろこさん - アナウンサーとして経済番組を担当したことをきっかけに自身も投資をスタート。現在は幅広い投資活動のほか、経済講演会のモデレーターとしても活躍。ラジオNIKKEI「マーケット・トレンドDX」、TBSラジオ「水谷隼の投資&ヘルスケア」、WEB動画「なるほど投資ゼミナール」などのレギュラー番組多数。近著に『無敵の日本経済! 株とゴールドの「先読み」投資術』(エミン・ユルマズ氏との共著)
- QUICK ナレッジコンテンツ本部 コンテンツグループ 副部長
中山桂一さん - 2008年QUICKに入社。2013年に日本経済新聞社商品部(当時)に出向し記者職に就く。日経QUICKニュース社への2度の出向を経てQUICKデリバティブズコメント、エクイティコメントでマーケット記事の執筆業務に携わる。
※本コラムで取り上げられたマーケットや投資に関する考え方などについては、あくまで個人の見解によるものであり、野村證券の意見を代表するものではございません。また本コラムは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。
- NISAのご利用にあたり、ご留意いただきたい事項
-
- 日本にお住まいの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方)が対象です。
- すべての金融機関を通じて、同一年内におひとり様1口座に限り利用することができます。
- 特定預り、一般預りで保有している上場株式等をNISA預りに移管することはできません。
- NISA預りとして保有している上場株式等をNISA預りのまま、他社に移管することはできません。
- 年間投資枠はつみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円です。また非課税保有限度額(総枠)は、成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円、そのうち成長投資枠は最大で1,200万円までとなります。なお、非課税保有限度額については、NISA口座で上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた分だけ非課税保有額(NISA口座で保有する上場株式等の残高)が減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
- NISA預りに係る配当金等や売却損益等と、特定預り、一般預りとの損益通算はできません。また、NISA預りの売却損は税務上ないものとみなされ、繰越控除はできません。
- NISA預りから払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。
- NISA預りとして保有している公募株式投資信託の分配金は非課税となります。ただし、当該分配金を再投資する際、当社ではNISA預り以外のお預り(特定預りや一般預り)でのご購入となります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、NISA預りでの保有であるかどうかにかかわらず非課税であるため、NISA預りにおける非課税のメリットは享受できません。
- お客様のご住所・お名前・お取引店が変更となる場合、または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。
- 成長投資枠、またはつみたて投資枠で買付けた投資信託について、原則として年1回、信託報酬等の概算値を通知いたします。
- 成長投資枠のご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項
-
- 当社が成長投資枠で取扱う金融商品は、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託、公募株式投資信託等の他、国外の取引所に上場する当社所定の株式等(ただし上場新株予約権付社債、外国籍の公募株式投資信託等、整理・監理銘柄に該当する上場株式、信託期間20年未満またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等、もしくは毎月分配型の投資信託等を除く)です。
- 国内の上場株式等の配当金等は、株式数比例配分方式を利用して受領する場合のみ非課税となります。株式数比例配分方式のお申込みはお取引店にお申付けください。
- つみたて投資枠のご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項
-
- 当社がつみたて投資枠で取扱う金融商品は、当社で選定した、法令等の要件を満たす公募株式投資信託等になります。
- つみたて投資枠のご利用には、積立契約(累積投資契約)を締結いただく必要があります。この契約に基づき、定期かつ継続的な方法で買付けが行われます。
- 法令により、当社は、NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日、及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における、お客様のお名前・ご住所について確認させていただきます。確認ができない場合は、新たに買付けた金融商品をNISAへ受入れることができなくなります。
- つみたて投資枠を利用した投資信託のお取引について
-
購入時手数料はございません。なお、換金時には基準価額に対して最大2.0%の信託財産留保額を、投資信託の保有期間中には信託財産の純資産総額に対する運用管理費用(信託報酬)(最大1.65%(税込み・年率))等の諸経費をご負担いただく場合があります。
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の価格や為替の変動等により基準価額が変動することから、損失が生じるおそれがあります。個別の投資信託ごとに費用やリスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
- 手数料等およびリスクについて
-
当社で取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料(換金時手数料)および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、年金保険・終身保険・養老保険・終身医療保険の場合は商品ごとに設定された契約時・運用期間中にご負担いただく費用および一定期間内の解約時の解約控除、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の委託保証金または委託証拠金をいただきます。信用取引、先物・オプション取引には元本を超える損失が生じるおそれがあります。証券保管振替機構を通じて他の証券会社等へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、移管する銘柄ごとに11,000円(税込み)を上限額として移管手数料をいただきます。有価証券や金銭のお預かりについては、料金をいただきません。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。
- 投資信託の手数料等およびリスクについて
-
投資信託のお申込み(一部の投資信託はご換金)にあたっては、お申込み金額に対して最大5.5%(税込み)の購入時手数料(換金時手数料)をいただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大2.0%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、国内投資信託の場合には、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用(信託報酬)(最大5.5%(税込み・年率))のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。外国投資信託の場合も同様に、運用会社報酬等の名目で、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。従って損失が生じるおそれがあります。投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。また、上記記載の手数料等の費用の最大値は今後変更される場合がありますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。