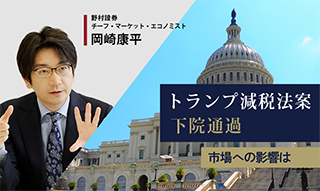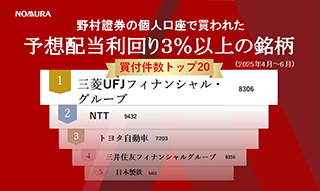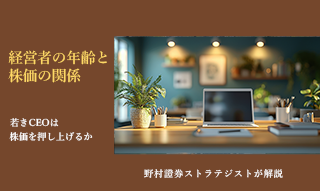2025.02.25 NEW
トランプ相互関税の「有りうる」含意 日本株マクロへの影響は 野村證券ストラテジストが解説
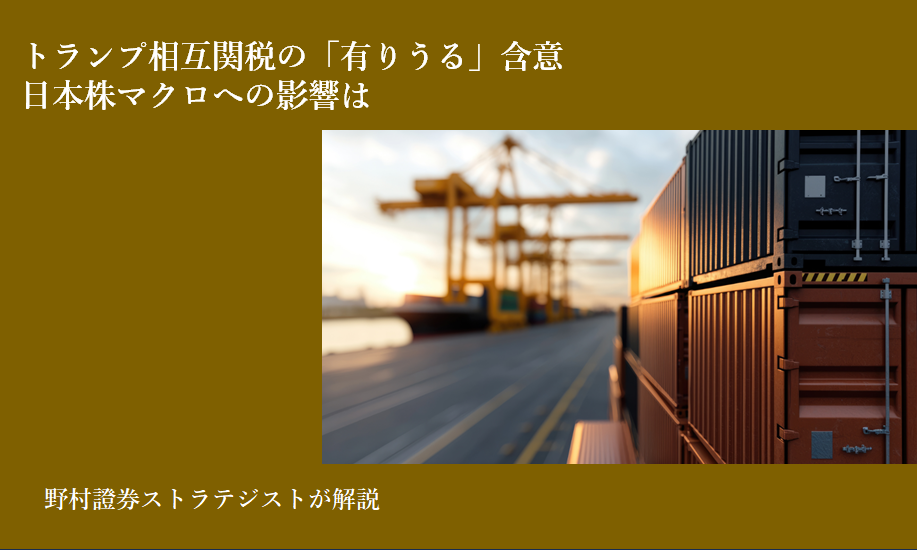
トランプ大統領が相互関税の実施に向けて動き始めました。具体的な制度設計が不明であるため、現時点で相互関税が日本株マクロに与える影響ははっきりしません。しかし、これまでに判明した情報から「ありうる」含意を想定することは可能です。野村證券ストラテジストが、日本株マクロへの「ありうる」含意を4つ挙げます。
第1の「有りうる」含意:相互関税は物品単位で検討か
第1に、関税率の格差が個別品目を単位として検討される可能性があります。米大統領府の「ファクトシート」によると、エタノールに関する米国とブラジルの関税率格差が具体例として挙げられています。また、インドに対してはオートバイ、EUに対しては自動車が具体例として示されています。これらの例からも分かる通り、貿易額全体での平均関税率ではなく、特定の品目における関税率の格差が焦点になる可能性があります。
この観点から見ると、日本が相互関税を通じて影響を受ける度合いは相対的に小さいと考えられます。2019年に当時のトランプ政権が公表した報告書によれば、米国よりも高い関税率を課している品目の比率では、日本は132ヶ国中123位と下位に位置しています。
非相互関税の主要国と名指しされた6ヶ国に比べ、日本株へのマクロ的な影響は限定されやすいでしょう。ただし、関税率格差が大きい一部の品目が影響を受ける可能性には注意が必要です。
第2の「有りうる」含意:付加価値税率が考慮される可能性も
第2に、各国の付加価値税が議論の対象となる可能性があります。これは、米大統領府が公表した文書で付加価値税が言及されているためです。日本の消費税と各国の付加価値税は厳密には異なるものとされる場合もありますが、トランプ政権の意向を踏まえると、日本の消費税も相互関税の検討に含まれると考えられるでしょう。
一方で、国際的な比較をすると、日本の消費税率は相対的に低いと言えます。米国連邦レベルでは消費税自体が存在しないため税率はゼロ%ですが、州政府および地方政府レベルでは消費税の一種である売上税が広く導入されています(45州とコロンビア特別区)。米国のシンクタンク「タックス・ファウンデーション」による調査では、2024年1月時点で米国の売上税率(州政府と地方政府を合算した税率)の中央値は7.0%とされています。そのため、実質的に見ると、日米間の付加価値税率の差はそれほど大きいとは言えないでしょう。
第3の「有りうる」含意:非関税障壁も関税賦課の材料に
第3に、非関税障壁や補助金、規制などが関税賦課に影響を及ぼす可能性があります。日本の非関税障壁について米国がどのように認識しているかを確認するには、USTR(米通商代表部)の2024年版報告書が参考になるでしょう。輸入政策に関する指摘は、コメ、小麦、豚肉、エタノールといった特定の品目に集中していますが、全般的には自動車を含めた幅広い分野が取り上げられています。ただし、これらの指摘の中には長期間にわたり継続されているものも少なくありません。相互関税という新たな状況に直面しても、容易に解消されるのは難しいと考えられます。
第4の「有りうる」含意:日本政府が賃上げ促進を加速する可能性
第4に、為替レートや賃金水準が問題視される可能性があります。米政府の公表文書では、「為替レートを市場価値から乖離させる政策・措置」、「賃金の抑制」、および「そのほか米国の競争力を削ぐ重商主義的な政策」が相互的でない政策・措置として挙げられています。
この記述は主に中国や新興国を念頭に置いたものと見られますが、日本に対する批判の材料にされる可能性もあります。現在のドル円相場が152~153円程度と円安水準にあり、さらに日本では長年にわたり賃金の伸びがほとんど見られなかったためです。これらは日本政府が意図した結果ではありませんが、トランプ政権が関税賦課の理由として取り上げる可能性は否定できません。
こうした状況を踏まえれば、日本政府としては円高を容認する姿勢を取る可能性があるほか、これまで以上に賃上げ促進に注力する展開も予想されます。
終わりに:関税政策が日本株マクロに影響しやすい状況が続く
第2次トランプ政権による関税政策は、まだ始まったばかりの段階です。4月1日頃には、この相互関税に関する米国政府の調査報告書が提出される予定であり、トランプ大統領は4月2日頃にも自動車への関税を導入する意向を示しています(ブルームバーグ報道、2月15日付)。また、半導体や医薬品についても追加関税を課す姿勢を見せています。関税政策が日本株マクロに影響を及ぼしやすい状況は、当面続くと考えられます。
(編集:野村證券投資情報部 デジタル・コンテンツ課)
編集元アナリストレポート
野村マクロレビュー – トランプ相互関税の「有りうる」含意(2025年2月17日配信)
(注)各種データや見通しは、編集元アナリストレポートの配信日時点に基づいています。
※この記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。
- 手数料等およびリスクについて
-
当社で取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料(換金時手数料)および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、年金保険・終身保険・養老保険・終身医療保険の場合は商品ごとに設定された契約時・運用期間中にご負担いただく費用および一定期間内の解約時の解約控除、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の委託保証金または委託証拠金をいただきます。信用取引、先物・オプション取引には元本を超える損失が生じるおそれがあります。証券保管振替機構を通じて他の証券会社等へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、移管する銘柄ごとに11,000円(税込み)を上限額として移管手数料をいただきます。有価証券や金銭のお預かりについては、料金をいただきません。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。
- 株式の手数料等およびリスクについて
-
国内株式(国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は2,860円(税込み))の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。国内REITは運用する不動産の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。国内ETFおよび国内ETNは連動する指数等の変動により損失が生じるおそれがあります。国内インフラファンドは運用するインフラ資産等の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。
外国株式(外国ETF、外国預託証券を含む)の売買取引には、売買金額(現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対し最大1.045%(税込み)(売買代金が75万円以下の場合は最大7,810円(税込み))の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等は国や地域により異なります。外国株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。