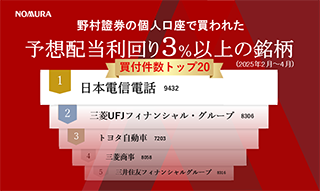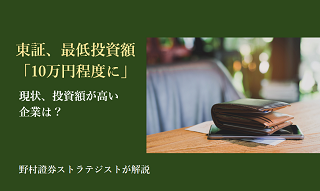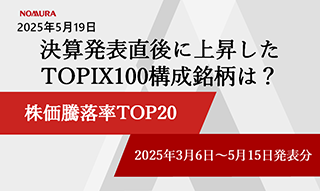2025.05.23 NEW
日本の超長期金利上昇に絡む3つのファクター 財政への不安は高まっている 野村證券・美和卓

写真/タナカヨシトモ
トランプ政権の関税政策以降、世界経済の不確実性が高まっているなかで、日米欧の超長期金利が上昇しています。5月20日には日本の30年国債利回りが3%を突破し、上昇し続けています。日本の超長期金利が上昇しているファクターについて野村證券金融経済研究所エグゼクティブ・エコノミストの美和卓が解説します。

- 日米ともに超長期金利が上昇しています。日本の政策金利は引き上げが検討されている状況とはいえかなり低金利に留まる一方、米国の政策金利は高止まりしています。両国の超長期金利が同時に上昇しているのはどのような背景でしょうか。
-
超長期金利の上昇とはどのような状況かというと、30年などの長い年限の国債の値段が下落し、利回りが上昇していると理解できます。超長期の国債を個人が保有しているケースは少なく、多くは機関投資家が保有しています。超長期国債を買う機関投資家が減り人気が下がっているので、値段が下がり利回りが上昇しているということです。つまり超長期国債であっても、他の債券と同じく需給バランスで値段と利回りが決まります。
米国と欧州の超長期金利が上昇しているそれぞれの理由
- なぜ、機関投資家にとって日本の超長期国債の人気が下がっているのでしょうか。
-
今回、超長期国債の値段が下がっているファクターは3つあると思います。1つ目は米国をはじめ世界の超長期金利が上昇している、つまり超長期の米国債の人気が下がっていて、その影響を受けていることがあります。
例えばグローバルでアロケーションしている機関投資家が、国内債券と外国債券を1対1で保有する方針を持っているとします。その前提で外国債券の値段が下落すれば、国内債の比率が高まりすぎてしまいますよね。そのため、国内債を売却するというリバランスをすることになります。外国の債券と日本の債券が連動して動くというのは、機関投資家の調整が起きて需要が減るからなのです。
- イメージがよくわかりました。では、なぜ米国債の人気が下がったのでしょうか。
-
今回米国の超長期金利が上昇したのは、ある民間格付け会社が米国債の格付けを引き下げたことがきっかけと報道されることもありますが、需要が減る根本的な原因としては、米国の財政への不安があります。
- トランプ関税政策が強硬だったため、今後の米国景気に不安が高まったということでしょうか。
-
関連はあります。トランプ関税政策により米国景気後退の懸念が高まっており、トランプ政権がその対策として次に減税政策を打ち出すのではないかとの期待が高まっています。実はこれが超長期金利に大きく影響しています。減税を行うということは将来の米国財政の規律性を損なうのではないかという懸念が生まれるからです。
米国だけでなく、欧州の超長期金利も上昇していますが、こちらは違う要因があります。トランプ政権がNATOへの資金援助をやめる可能性を示唆しており、欧州の防衛費の負担増が現実になり始めたことが財政悪化の原因となっています。これまでも欧州全体では財政問題を抱える国が多くありましたが、ドイツだけは財政の健全性を守ってきました。それが防衛費増加というやむを得ない事情により、ドイツですら財政拡張を決定しました。もともと不景気だったドイツでは財政拡張が求められていて、それが今回の件で堤防が決壊したような状態となり、欧州全体の財政不安が高まっているのです。
それぞれの国で事情は異なりますが、将来の財政健全性に疑問符が付く状態が続いており、それが日本の超長期金利の上昇につながるということです。
日銀の政策金利引き上げへの期待が影響
-
2つ目の理由は日本固有の事情で、日銀の政策金利の行方です。
トランプ関税政策は先述したように、米国景気悪化の懸念を生みましたが、GW(ゴールデンウイーク)後はその懸念はやや後退しています。引き上げが強行されていた対中関税も一部は停止され、関税の影響は思ったより少ないのではないかという楽観論が市場に生まれつつあります。
日本が関税の影響を受けている間は、日銀が政策金利の引き上げを簡単に行えないと思われていたのですが、関税がそれほど深刻ではないのなら、政策金利の引き上げを行えるのではないかと市場は期待します。つまり、金利の先高感が生まれます。
- 政策金利の引き上げが期待されるから、先に超長期金利が上がっているということですか? 単純に考えると先に超長期金利が上がっているなら国債の人気は上がりそうな気がするんですが……。
-
そうはならず金利の先高感があるときは、債券の需要が弱まります。日本はゼロ金利政策から脱却し、政策金利の引き上げを段階的に行っています。金利上昇局面では、機関投資家はそれまで保有していた債券の価格が下落し、含み損を抱えていることになります。
過去に投資した債券の含み損を抱えている機関投資家の立場で考えて、「超長期金利は上昇して、魅力があるので投資しよう」と思えるでしょうか。それよりは、「これからもっと金利が上がったら含み損がさらに増えてしまう」という思いのほうが大きくなると想像できます。
- なるほど、トランプ関税政策により米国景気の不安が生まれたことも、関税政策がやや和らいで楽観論が広がったことも、両方超長期金利の上昇につながるのですね。3つ目の要因とはなんでしょうか。
-
3つ目の要因は、これも日本固有の話で、7月の参議院選挙を前に消費税減税の議論が出ていることです。2022年に英国で財源の根拠のない大型減税策が出され、市場の混乱を引き起こした「トラス・ショック」のようなことが起きるのではないかと、日本の財政への不安が高まっています。参議院選挙まではこの議論はおさまることはなく、むしろ盛り上がるでしょう。そのため、20年30年後の日本がどうなっているかわからないという不確実性は高まり、超長期国債はますます買いづらい状況にあります。
- 世界からの影響と日本固有の事情があることがわかりました。今後、3つの要因に変化があると状況は変わるのでしょうか。
-
そうですね、消費税減税がなくなったり、日銀の政策金利引き上げが当面行われなさそうだという見方が優勢になったりすると、状況が変わってくるでしょう。例えば、米国FRBが利下げを行うというメッセージを出すようになると、円高ドル安の傾向がはっきりして、日本の利上げ期待が薄れる状況になります。
- 個人投資家には超長期金利上昇はどのように影響するでしょうか。
-
実は個人投資家が直接購入する機会が多い個人向け10年国債は変動金利ですし、固定金利型の個人向け国債は満期が3年、5年であるため、その影響は波及しにくくなっています。住宅ローン金利に超長期金利上昇がすぐに反映されるということも考えにくく、直ちに何かアクションを起こさなくてはならないということはないでしょう。トランプ関税政策などの影響が複雑に絡み合って超長期金利が上昇しているということを知っておくと、金融市場への理解が進むと思います。

- 野村證券 金融経済研究所 エグゼクティブ・エコノミスト
美和 卓 - 1990年野村総合研究所入社。東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了。2004年野村證券に転籍。2024年4月より現職。国内・海外のプロの投資家に対して、日本と世界の経済に関する分析、見通しを提供する一方、一般向けに経済、金融の仕組みを分かりやすく解説。著書に『金利「超」入門』(日本経済新聞出版社)など。
※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。
- 手数料等およびリスクについて
-
当社で取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料(換金時手数料)および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、年金保険・終身保険・養老保険・終身医療保険の場合は商品ごとに設定された契約時・運用期間中にご負担いただく費用および一定期間内の解約時の解約控除、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の委託保証金または委託証拠金をいただきます。信用取引、先物・オプション取引には元本を超える損失が生じるおそれがあります。証券保管振替機構を通じて他の証券会社等へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、移管する銘柄ごとに11,000円(税込み)を上限額として移管手数料をいただきます。有価証券や金銭のお預かりについては、料金をいただきません。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。