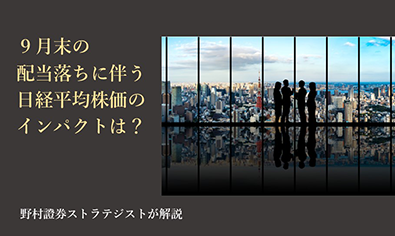2025.09.25 NEW
[特別対談]森永康平さん×野村證券エコノミスト 今後も続くであろうインフレに私たちはどう備えるか
![[特別対談]森永康平さん×野村證券エコノミスト 今後も続くであろうインフレに私たちはどう備えるかのイメージ](/wealthstyle/article/0448/images/a_0448_01.png)
撮影/齋藤大輔(人物・左)、タナカヨシトモ(人物・右)
仕事や子育てなどに忙しいビジネスパーソンの中には、落ち着いて資産形成について考える余裕がない方もいらっしゃるのではないでしょうか。日本が久しぶりに「金利ある世界」へと転換し、インフレの実感が増しているなど現役世代を取り巻く市場環境は変化しており、先行きが見通しにくい状況になっています。今、ビジネスパーソンに必要なお金の新常識について、マネネCEOで経済アナリストの森永康平さんと野村證券チーフ・マーケット・エコノミストの岡崎康平が対談しました。
(この記事は野村證券の動画対談をもとに構成しています。動画対談はこちら。収録日:2025年8月14日 視聴期限:2025年11月30日)
![[特別対談]森永康平さん×野村證券エコノミスト 今後も続くであろうインフレに私たちはどう備えるかのイメージ](/wealthstyle/article/0448/images/a_0448_02.jpg)
「ゆとりある老後生活」を送るためにはいくら必要か?
- インフレが進み物価が上がっていることから、老後にお金が足りるのか、心配になっているビジネスパーソンもいらっしゃるのではないかと思います。老後資金をどう考えたらいいか、インフレは個人の生活をどう変えるか、意見を聞かせてください。
森永康平さん(以下、森永)
そうですね。私のもとにも老後が不安だという方の相談はよくきます。老後資金をいくら貯めれば良いか全然分からず、不安になっているビジネスパーソンの方も多いと思います。まず、具体的な数字を考えることから始めてみましょう。
必要な老後資金は人によって違いますが、例えば65歳で定年退職し、夫婦で90歳まで25年間の老後生活を送るケースで考えます。「ゆとりある老後生活」を送るためにはいくら必要か試算してみましょう。
25年間、ゆとりある老後生活を送るために必要な生活費(1億1,400万円)から、年金支給額(6,600万円)と退職金(2,400万円)を差し引くことで、準備する必要がある資金を導き出します。下の図の通り、この試算では2,400万円が不足する計算になります。
![[特別対談]森永康平さん×野村證券エコノミスト 今後も続くであろうインフレに私たちはどう備えるかのイメージ](/wealthstyle/article/0448/images/a_0448_03.png)
(注1)老後の最低日常生活費(平均23.2万円/月)と老後のゆとりのための上乗せ(平均14.8万円/月)の合計が38万円。
(注2)高齢夫婦無職世帯の社会保障給付(平均22万円/月)
(注3)民間企業と公務員の平均退職金(約2,400万円)
(出所)生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」、総務省統計局「高齢夫婦無職世帯の家計収支2022年度調べ」、人事院「民間の退職金及び企業年金の実態調査の結果並びに国家公務員の退職給付に係る本院の見解について(令和4年)」を基にマネネ作成。
ただ、老後資金がいくら不足するかはどの時点のデータを使うかで結論が変わってしまいます。面倒かもしれませんが、毎月自分がいくら使っていていくら貯金ができているか、このペースでいくと自分はいくら貯めないといけないということをまず見極めてほしいと思います。
岡崎康平(以下、岡崎)
おっしゃるとおりですね。これから長期間に渡ってまとまった老後資金を貯めなければならないビジネスパーソンの方は、インフレについても考慮する必要が出てくるでしょう。ただ、これまでの日本経済を振り返ると「ずっとデフレだったじゃないか」と考える人も多いと思います。現在の物価上昇は一時的なものか、長く続くかどうかが問題になります。
そのカギを握るのは「人口減少」です。人口減少で働き手の数が減っていくと、人材確保のために賃上げが必要になります。自動化やIT化が進んでいるとはいえ、モノ・サービスを提供するには人が必要になる場合が多いわけです。人口減少は2、3年で終わるものではありませんから、インフレは長引く可能性があります。
「人口減少はデフレ要因ではないか」と思う方もいらっしゃるかもしれません。確かに、人口減少でモノの買い手が減るとデフレになる、という見方は私もその通りだと思います。2000年代や2010年代の日本経済はその状況にあったと言えるでしょう。
しかし、ここ2~3年で状況に変化が見られます。モノの買い手が減るのみならず、働き手も増加から減少に転じる曲がり角に到達したのです。経済の中の需要面だけが縮小する人口減少から、供給面も縮小する人口減少になったと言えるでしょう。これが今、起きている大きな構造変化です。
このような点を踏まえると、数年で終わるインフレではなくて、しつこいインフレ圧力として覚悟しなければいけません。
森永
岡崎さんが指摘された「しつこいインフレ圧力」は、老後資金を考えるうえで重要視する必要があります。一般論として、インフレになると現預金の価値が目減りするため、投資に回しなさいとよく言われます。物価上昇によって、現金の価値がどれだけ目減りするのかを試算したものが次のグラフです。
![[特別対談]森永康平さん×野村證券エコノミスト 今後も続くであろうインフレに私たちはどう備えるかのイメージ](/wealthstyle/article/0448/images/a_0448_04.png)
(出所)マネネ作成
-
政府の発表によると、昨年1年間の物価全体の上昇率はおよそ2.7%でした。分かりやすいように、四捨五入して3%の物価上昇率が継続した場合で考えると、1,000万円の価値は10年後には737万円、20年後には544万円と半額程度になってしまいます。30年後に401万円まで目減りしてしまいます。
例えば、老後資金として2,000万円必要な人が現役のうちに頑張って2,000万円を貯めたとしても、仮に毎年3%物価が上がってしまうと自分がその資金を必要とする30年後のタイミングには貯めていたはずの老後資金の価値が6割も減ってしまいます。
貯めるお金を全額投資しなさいとは言いませんけれども、私はその一部を投資に回したほうがこのようなインフレによって現預金の価値が目減りするリスクを抑えられるのではないかと思います。
「配当の力」で収入を複線化する
![[特別対談]森永康平さん×野村證券エコノミスト 今後も続くであろうインフレに私たちはどう備えるかのイメージ](/wealthstyle/article/0448/images/a_0448_05.jpg)
岡崎
そうですね。インフレによって現預金の価値が目減りするリスクは頭に入れておく必要があります。その上で物価上昇にしっかりとキャッチアップするために、収入を複線化していくことも重要だと思います。ビジネスパーソンは企業から給料が支払われているわけですが、企業から「配当」を得ることも選択肢になります。
これまで日本企業は配当の原資となる現金をため込んでいましたが、近年、この状況が変わってきました。下のグラフの赤い線が企業における資金の過不足を表しています。1998年頃を境に、企業は資金不足から資金余剰(カネ余り)の主体に転じています。その年に稼いだお金の一部を、企業が貯めこむようになったわけです。ある意味では、「経済の血液」ともいわれるお金がなかなか巡らなくなったことを示しています。
![[特別対談]森永康平さん×野村證券エコノミスト 今後も続くであろうインフレに私たちはどう備えるかのイメージ](/wealthstyle/article/0448/images/a_0448_06.png)
(注)過去基準計数を用いたため、1979年と1980年、及び1993年と1994年の間が厳密には接続しない点に注意。
(出所)内閣府資料より野村證券作成
-
ところが2015年頃から、この数字は下がっています。直近はやや上昇していますが、大きな流れで見ると「カネ余り」が緩和されているのです。その背景の1つが、配当の支払いです。企業がお金をため込まず、配当として株主に払うようになったというのが2015年くらいからの大きな変化でした。
もう一つ、配当に関連して注目していただきたいグラフがこちらです。配当を日経平均株価に再投資した場合のリターンを示した、配当込み指数の推移を表しています。
![[特別対談]森永康平さん×野村證券エコノミスト 今後も続くであろうインフレに私たちはどう備えるかのイメージ](/wealthstyle/article/0448/images/a_0448_07.png)
(注)日経平均株価(価格指数)と日経平均株価(配当込み指数)のデータは月次、2002年1月末から2025年7月末までの期間。日経平均株価(配当込み指数)は1979年12月28日から算出されており、その時点では日経平均株価(価格指数)と計数が一致する。
(出所)ブルームバーグ資料より野村證券作成
-
2025年に入り日経平均株価は再び4万円を突破しましたが、配当込み指数でみると7万円を超える水準にあります。この過去10年くらいで日経平均株価に投資をしていたら、持っていたお金が2倍、3倍になったと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には「配当の力」でさらに増えたことがこのグラフから分かります。
森永
岡崎さんが紹介された日経平均株価の配当込み指数は昔からある指数ですが、これからより重視されていくのではないかと思っています。なぜかと言うと、やはり東京証券取引所が上場企業に対して、株主還元や資本効率を良くした経営をしなさいと要請しているからです。
最近では海外から、いわゆる「物言う株主」と呼ばれる投資家たちがどんどん日本の株式市場に入ってきています。配当を増やさずただお金をため込んでいる企業の経営陣に対して、物を言うのが時代の流れになってきています。今まで以上に、配当込み指数は上昇しやすい傾向になってくるのではないかと考えています。
岡崎
一方、「『金利がある世界』になって預貯金に金利が付くようになったのだから、預貯金で十分ではないか」と思う方もいらっしゃると思います。確かに、15年前だったらそうだったかもしれません。ただ、今は状況が変わっています。
下のグラフの通り、銀行の普通預金金利と定期預金金利(10年)は2022年以降に上がってきました。とはいえ、日経平均株価の配当利回りと比べると大きな差があります。2000年代までは定期預金金利(10年)と株式配当利回りは概ね同じぐらいでしたが、日本企業のガバナンス改革等もあり、配当の利回り水準が一段と高くなったのです。「金利がある世界」においても、実は配当利回りの方が金利よりも高い。このことは、少し意識しておくべきと思います。
![[特別対談]森永康平さん×野村證券エコノミスト 今後も続くであろうインフレに私たちはどう備えるかのイメージ](/wealthstyle/article/0448/images/a_0448_08.png)
注)普通預金金利は、日本銀行の取引先のうち国内銀行(整理回収機構等を除く)、信用金庫および商工組合中央金庫が調査対象。
定期預金金利(10年)は、日本銀行と取引のある国内銀行の銀行勘定の計数。ただし、整理回収機構、紀伊預金管理銀行、日本承継銀行、第二日本承継銀行、ゆうちょ銀行を除く。
銀行預金と株式は異なる性質の金融商品であることをご承知おきください。株式等の有価証券は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。また、元本の保証はありません。記載の金利・利回りは過去の実績であり、将来の金利・利回りを示唆あるいは保証するものではありません。
(出所)日本銀行、野村総合研究所、ブルームバーグ資料より野村證券作成
ビジネスパーソンが労力をかけずに運用するコツ
- 外部環境や日本企業の変化も踏まえ、ビジネスパーソンが資産運用をする際のポイントを教えてください。
森永
まず、ビジネスパーソンが資産運用をする場合は、専業の投資家ではないということが大前提です。あくまで仕事という本業があり、それをおろそかにしてしまっては本末転倒です。ただ、「投資には学ぶ時間をそれなりにかけないと危ないのではないか」と思われる方もいらっしゃると思います。
本業をメインにしつつ、なるべく労力をかけずにうまく資産運用するための方法は、3つあります。まず1つ目は「長期」で運用することです。
このグラフは毎月3万円を30年間投資した場合を試算した結果です。年率2%で運用できた場合を緑の線、年率4%を青の線で示しています。オレンジの線は、年率0.01%の利息が得られる銀行預金を利用していたケースを仮定しています。30年後どうなっているでしょうか。
![[特別対談]森永康平さん×野村證券エコノミスト 今後も続くであろうインフレに私たちはどう備えるかのイメージ](/wealthstyle/article/0448/images/a_0448_09.png)
(注1)上図は毎月3万円をそれぞれの投資収益率(年率を月次換算)で複利運用した場合の試算。
(注2)運用期間中の値動き、税金・手数料等は考慮していない。
(出所)マネネ作成
-
7年目ごろまではそんなに大きな差は出ません。ただ、その後は徐々に差が開いていきます。30年経つと年0.01%と年4%では、大きな差になります。このような複利効果を活用し、時間を味方につけて欲しいです。「今日、これだけ儲かった」「1週間でこれだけ損した」という話になってしまうと、値動きが気になってしまって本業の仕事に支障が出ます。そうではなく、30年後どうなるのかというスパンでぜひ考えていただきたいです。
続いて2つ目の資産運用のポイントは「積立」です。自分のお金で投資を始めると、誰しも安い時に買い、高い時に売りたいと思います。それがベストですが、プロでも「今日の株価が一番安い」と断言することはできません。
スマートフォンやパソコンで相場を見ることに時間をかけるよりは、例えば、毎月15日に投資信託を3万円分積立てるなど、機械的に行動を決めましょう。投資にかける時間を最大限抑えるために、積立という仕組みをぜひ使っていただきたいと思います。
分散投資でリスクを調整し、運用成績の波を抑えられる可能性
森永
最後に3つ目のポイントは「分散」です。下の図表は2012年から2024年にかけて、どのアセットクラスの成績が良かったかを色分けしてまとめたものです。一目で各年によって成績が良かった順の色がバラバラであることが分かると思います。つまり、特定の資産に資金を投入していれば、必ず勝てるということはなく、良い年も悪い年もあるということです。
![[特別対談]森永康平さん×野村證券エコノミスト 今後も続くであろうインフレに私たちはどう備えるかのイメージ](/wealthstyle/article/0448/images/a_0448_10.png)
(注)国内株式はTOPIX、国内債券は野村BPI総合インデックス、国内REITは東証REIT指数、先進国株式はMSCIコクサイインデックス、先進国債券はFTSE世界国債インデックス、先進国REITはS&P先進国REIT指数(日本除く)、新興国株式はMSCI新興国指数、新興国債券はブルームバーグ新興国債券指数、新興国REITはS&P新興国REIT指数。いずれもトータル・リターンかつ日本円建ての計数。上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。
(出所)ブルームバーグ資料より野村證券作成
-
株式だけに投資するのではなくて、債券や金、不動産投資信託(REIT)といった複数の資産に分散して投資ができるバランスファンドが良いのではないかと思います。昨今、新NISA(少額投資非課税制度)が始まってから、全世界株や米国株を投資対象としたインデックス型投資信託を選ぶ個人投資家が多いですが、これらはすべて海外株に投資をしていることになります。ご覧のように、海外株の成績は良い時も悪い時もあります。リスクを多く取りたくない方は、複数の資産に投資をするバランスファンドを購入することで、その波を抑えることができるのではないかと思います。
岡崎
分散という意味では、為替の視点も重要です。日本はエネルギーや食料の供給を輸入に依存している国ですから、外貨換算でも自身の資産価値が保全されていることの価値は大きいと思います。すべてのバランスファンドがそうとは限りませんが、国内外の様々な資産に投資するバランスファンドであれば、為替の観点でも分散できるという隠れた魅力があると思います。
森永
そうですね。為替の変動については注意が必要です。円安が進んでいる局面では外貨建て資産を持っていてラッキーだと思うかもしれませんが、為替の動きが逆転して円高方向に行くと、米国株などの海外株は上がっているのに、為替で同程度の損が発生してしまい、運用成績は上がらないということが起こり得るわけです。海外株に投資をするなと言っているわけではなく、日本株も投資対象に加える、株式だけでは少しリスクが高いと思う人は債券を組み入れるなど、ご自身に適したリスクの調整をしていただきたいと思います。
やはりビジネスパーソンは仕事が本業で、投資はメインではないです。長期で積立投資を続けて、対象は分散していくというポイントを意識してほしいです。肩ひじ張らずに資産運用しながら、このインフレの世界を乗り越えていただきたいと思っています。
※本コラムで取り上げられた森永氏によるマーケットや投資に関する考え方などについては、あくまで個人の見解によるものであり、野村證券の意見を代表するものではございません。本コラムは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。
当コラムで使用している指数について
・ 国内株式はTOPIX、国内債券は野村BPI総合インデックス、国内REITは東証REIT指数、先進国株式はMSCIコクサイインデックス、先進国債券はFTSE世界国債インデックス、先進国REITはS&P先進国REIT指数(日本除く)、新興国株式はMSCI新興国指数、新興国債券はブルームバーグ新興国債券指数、新興国REITはS&P新興国REIT指数を使用しています。いずれもトータル・リターンかつ日本円建ての計数です。
・ MSCI 株価指数使用上の注意点:本資料中に含まれるMSCIから得た情報はMSCI Inc. (「MSCI」)の独占的財産です。MSCIによる事前の書面での許可がない限り、当該情報および他のMSCIの知的財産の複製、再配布あるいは指数などのいかなる金融商品の作成における利用は認められません。当該情報は現状の形で提供されています。利用者は当該情報の利用に関わるすべてのリスクを負います。これにより、MSCI、その関連会社または当該情報の計算あるいは編集に関与あるいは関係する第三者は当該情報のすべての部分について、独創性、正確性、完全性、譲渡可能性、特定の目的に対する適正に関する保証を明確に放棄いたします。前述の内容に限定することなく、 MSCI、その関連会社、または当該情報の計算あるいは編集に関与あるいは関係する第三者はいかなる種類の損失に対する責任をいかなる場合にも一切負いません。MSCIおよびMSCI指数はMSCIおよびその関連会社のサービス商標です。
・ FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、FTSE Fixed Income LLCが有しています。
![[特別対談]森永康平さん×野村證券エコノミスト 今後も続くであろうインフレに私たちはどう備えるかのイメージ](/wealthstyle/article/0448/images/a_0448_11.jpg)
- マネネ CEO/経済アナリスト
森永康平(もりなが・こうへい) - 証券会社や運用会社にてアナリスト、ストラテジストとして日本の中小型株式や新興国経済のリサーチ業務に従事。業務範囲は海外に広がり、インドネシア、台湾などアジア各国にて新規事業の立ち上げや法人設立を経験し、事業責任者やCEOを歴任。日本証券アナリスト協会検定会員。経済産業省「物価高における流通業のあり方検討会」委員。著書は『親子ゼニ問答』(角川新書)、『スタグフレーションの時代』 (宝島社新書)など多数。
![[特別対談]森永康平さん×野村證券エコノミスト 今後も続くであろうインフレに私たちはどう備えるかのイメージ](/wealthstyle/article/0448/images/a_0448_12.jpg)
- 野村證券 チーフ・マーケット・エコノミスト
岡崎康平 - 2009年に野村證券入社。シカゴ大学ハリス公共政策大学院に留学し、Master of Public Policyの学位を取得(2016年)。日本経済担当エコノミスト、内閣府出向、日本経済調査グループ・グループリーダーなどを経て、2024年8月から、市場戦略リサーチ部マクロ・ストラテジーグループにて、チーフ・マーケット・エコノミスト(現職)を務める。日本株投資への含意を念頭に置きながら、日本経済・世界経済の分析を幅広く担当。共著書に『EBPM エビデンスに基づく政策形成の導入と実践』(日本経済新聞社)がある。
- 手数料等およびリスクについて
-
当社で取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料(換金時手数料)および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、年金保険・終身保険・養老保険・終身医療保険の場合は商品ごとに設定された契約時・運用期間中にご負担いただく費用および一定期間内の解約時の解約控除、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の委託保証金または委託証拠金をいただきます。信用取引、先物・オプション取引には元本を超える損失が生じるおそれがあります。証券保管振替機構を通じて他の証券会社等へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、移管する銘柄ごとに11,000円(税込み)を上限額として移管手数料をいただきます。有価証券や金銭のお預かりについては、料金をいただきません。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。
- 株式の手数料等およびリスクについて
-
国内株式(国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は2,860円(税込み))の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。国内REITは運用する不動産の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。国内ETFおよび国内ETNは連動する指数等の変動により損失が生じるおそれがあります。国内インフラファンドは運用するインフラ資産等の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。
外国株式(外国ETF、外国預託証券を含む)の売買取引には、売買金額(現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対し最大1.045%(税込み)(売買代金が75万円以下の場合は最大7,810円(税込み))の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等は国や地域により異なります。外国株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。
- 債券の手数料等およびリスクについて
-
債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。債券の価格は市場の金利水準の変化に対応して変動しますので、損失が生じるおそれがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。加えて、外貨建て債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
- 投資信託の手数料等およびリスクについて
-
投資信託のお申込み(一部の投資信託はご換金)にあたっては、お申込み金額に対して最大5.5%(税込み)の購入時手数料(換金時手数料)をいただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大2.0%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、国内投資信託の場合には、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用(信託報酬)(最大5.5%(税込み・年率))のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。外国投資信託の場合も同様に、運用会社報酬等の名目で、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。従って損失が生じるおそれがあります。投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。また、上記記載の手数料等の費用の最大値は今後変更される場合がありますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。


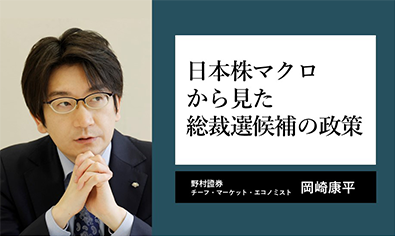
![[特別対談]森永康平さん×野村證券エコノミスト 今後も続くであろうインフレに私たちはどう備えるかのイメージ](/wealthstyle/article/0448/images/a_0448_thm.png)