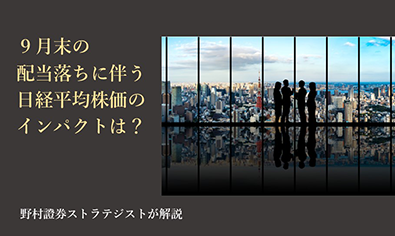2025.09.26 NEW
日本株マクロから見た総裁選候補の政策、「内需刺激も市場かく乱は回避」 野村證券・岡崎康平
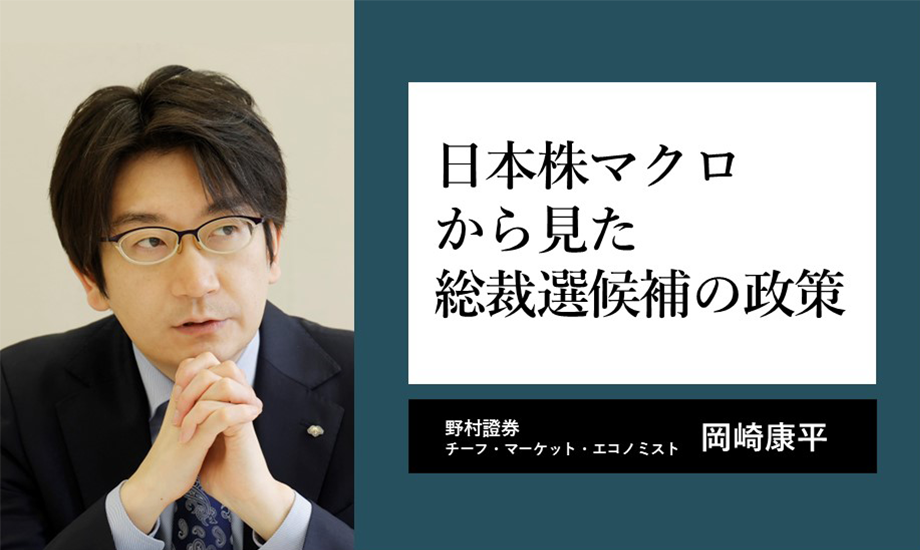
撮影/タナカヨシトモ
9月22日に自民党総裁選が告示日を迎えました。今回の総裁選で出馬するのは茂木敏充前幹事長、小林鷹之元経済安保相、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保相、小泉進次郎農相の5氏(出馬表明順)です。それぞれの候補者における日本株マクロの重要論点を野村證券チーフ・マーケット・エコノミストの岡崎康平が解説します。なお、野村證券では選挙結果そのものについての予想は一切行っていません。

「内需刺激も市場かく乱は回避」という点で5氏は共通
各候補の政策を俯瞰すると、候補者を二分するような大きな論点は見当たりません。候補者ごとに政策の重点に違いはあるものの、あくまで「どこまで踏み込むか」の違いに止まっています。
日本株マクロの観点で最大公約数的にまとめると、「緩やかな財政拡張で内需(消費・設備投資)を刺激するものの、極端な政策で市場を攪乱する展開は避ける」姿勢と言えるでしょう。具体的な政策としては、
(1)物価高対策(需要刺激策)
(2)供給力強化政策
(3)金融政策
(4)財政政策
(5)防衛費
(6)外国人政策
(7)与野党連携・連立
が各候補におおむね共通する項目です。以下、各候補が最優先と位置付ける政策を抜粋して解説します。
茂木候補:物価高対策を最優先と位置付ける
茂木候補は、2年で経済再生の道筋をつけるとしました。最優先と位置付ける物価高対策では、数兆円単位の「生活支援特別地方交付金」を主張しました。地方自治体が地域の実情に合わせて使える交付金との位置づけですが、国も推奨メニューとして交付金使途のモデルケースを示す内容です。同様の施策はコロナ禍でも導入されました。ガソリン等の暫定税率については、2026年度税制改正で対応して段階的に廃止する意向を示しています(この場合、実際の減税時期は26年4月以降になるとみられます)。
物価高対策よりやや長い時間軸では、日本経済の成長力強化に向けた供給力強化を訴えています。具体的には、(A)企業設備の即時償却、(B)地方経済の活性化、(C)労働移動の支援・働き方改革の見直しです。このうち(B)では、AI・半導体、データセンター、グリーン産業の成長が企図されており、関連分野の研究機関・スタートアップ・教育機関について地方への立地を推進する構えです。脱炭素電源の重要性も認識し、原子力・再エネを最大限活用する姿勢も見せました。
これら施策を実現することで、実質経済成長率は+1.5%、名目賃金は+3.5%成長、年収は3年で1割増える(平均年収を前提に50万円の年収増)と茂木氏は主張しました。
小林候補:日本を再びテクノロジー大国へ
小林氏は、日本を再びテクノロジー大国にするとしました。AI・量子・宇宙などの分野が主眼です。目先の施策としては、ガソリン等の暫定税率を速やかに廃止するほか、期限および減税額の上限を定めた定率減税を行う意向です。定率減税では、所得税額の一定割合が減税されます。具体的な減税規模は未定としつつも、過去の実施例として1999年~2006年に行われていた20%の減税(1人当たり上限は25万円)で規模が3兆円程度だったと述べました。
やや長い時間軸では、新しい所得税制を構築する意向です。所得税の控除額や税率構造の見直しなど、1年程度の時間をかけて新税制の内容を固めます。野党が求める「年収の壁」議論のスコープを広げたかたちと言えるでしょう。
経済の供給面では、各種の安全保障政策が強調されました。まず防衛費については、名目GDP比2%まで予算を拡大する現行方針では不十分として、予算規模を積み増す方針を明らかにしました。5名の候補者の中でも、防衛費の増額方針は小林氏が最も明確とみられます。
経済安全保障では、クラウドの外国依存低減や、外資による企業・土地購入規制の強化を主張しています。外国人政策も強化する意向です。エネルギー安全保障では、他国依存度の高い再エネに否定的な姿勢を見せました。特に、太陽光発電の導入は限界として、これ以上の導入に難色を示しました。一方、原子力発電については再稼働・新増設を進める意向です。
林候補:コンテンツ産業振興に意欲
林候補は、自身が岸田・石破政権で官房長官を務めてきた立場も踏まえ、これら政権を引き継ぎつつ新たな政策を追加するスタンスです。経済政策では、実質賃金の1%成長定着を目指します。省人化や価格転嫁の促進に加え、企業の稼ぐ力強化策として、GXやDX、スタートアップ政策を推進する意向です。経済構造の面では、デジタル赤字縮小に向けたコンテンツ産業の振興や、人材育成のため公教育の充実を掲げました。
やや時間軸の長い政策としては、2040年代に団塊ジュニア世代が後期高齢者になることを踏まえた社会保障制度の改革が挙げられます。欧州を参考とした日本版ユニバーサルクレジット制度(日本版UC)の導入を目指します。日本版UCでは、税負担のみならず社会保険料負担を含めた個人の公的負担を把握し、国民の負担を可視化することが前提となります。
その他の政策(防衛費、財政規律、年収の壁、外国人政策など)には、目立った主張は見られません。現職の官房長官という立場もあり、現政権の方針が明確な政策領域では新政策を打ち出しにくいとみられます。
そのなかで林候補の独自性において目立つのが、行政・選挙制度改革です。林候補は、現在の1府12省庁による行政機構がすでに30年近く経過しているとして、省庁再編の検討を始める意向を示しました。その狙いは明確にされていませんが、経済・社会の変化を踏まえた最適化とみるのが自然でしょう。
高市候補:消費税率引下げは取り下げも、ハト派的な金融政策観は残存
高市候補は、日本をもう一度世界のてっぺんに戻す、と掲げました。外交力・防衛力・経済力・技術力・情報力・人材力いずれも重要としつつ、経済成長を強く追い求めるスタンスです。最も意欲を燃やす政策としては、危機管理投資の拡充と、成長投資の促進が挙げられました。
物価高対策としては、ガソリン等の暫定税率の廃止、就労時間調整の緩和(「年収の壁」の引上げ)、自治体向けの速やかな重点支援交付金の交付が掲げられました。また、導入には「数年かかる」としながらも、給付付き税額控除の制度設計に着手することも明らかにしました。
供給面の取り組みでは、経済安全保障の強化と関連産業の育成が掲げられています。分野としては、AI・半導体、ペロブスカイト型太陽電池、全固体電池、デジタル、量子、核融合、マテリアル、合成生物学、バイオ、航空、宇宙、造船、創薬、先端医療、送配電網、港湾ロジスティクスなどが挙げられました。分野ごとに投資フレームワークを設けて推進される模様です。
このほか、経済安全保障では、対日外国投資委員会を設けて、海外からの投資に対する体制を強化することが明らかになりました。食料安全保障では、国産ドローンの活用やロボット農機、衛星技術の活用が訴えられました。エネルギー・資源安全保障では、原発の稼働を進めるほか、次世代革新炉の振興、2030年代に向けたフュージョン・エナジー推進が主張されています。ただし、外国製の太陽光パネル導入には「猛反対」とし、ペロブスカイト型太陽電池や全固体電池(酸化型)の導入に力を入れる方針です。なお、国産資源開発・国産資源「共同」開発にも積極投資するとされました。
金融政策について、高市候補は、2024年9月に利上げを強くけん制する発言を行ったことから、金融市場からは明確なハト派志向とみられています(日本経済新聞 2024年9月23日付)。出馬会見では金融政策への言及はありませんでしたが、9月22日公開のインターネット番組では、2024年9月ほど直接的ではないものの、住宅ローンを抱えている家計や企業の設備投資に対する影響などを踏まえて、政府と日銀がコミュニケーションを密にする必要性を強調しています。高市候補は、引き続き金融政策に対してハト派的な志向を有すといえます。
小泉候補:外国人問題のアクションプランを年内策定へ
小泉候補は、自民党が下野した2009年の衆院選で初当選した経験を踏まえ、党再生こそ自身の原点であるとアピールしました。
経済政策では、インフレ時代の新たな経済運営を構築すると述べ、早期に経済対策を策定する方針を明らかにしました。そこではガソリン等の暫定税率の廃止に加え、物価・賃金の伸びに合わせた基礎控除の引上げなどが盛り込まれるようです(基礎控除の引き上げは、2026年度以降も引き上げていく意向が示されました)。社会保障の現場(医療・介護など)で働く人の処遇改善にも取り組む模様です。
こうした物価高対策を通じて、実質賃金のプラス成長を通じた消費主導の景気回復をまず実現し、それに合わせて経済の供給面も拡大する方針です。供給力の拡大では、グローバル化が世界的に逆転していることを踏まえ、自国生産力の拡大を訴えました。「市場まかせ・企業まかせ・個人まかせ」ではなく、国家もリスクを取って、企業の大胆な投資を引き出す構えです。具体的な方策としては、設備投資の即時償却の拡大などの税制改革が念頭に置かれています。
マクロ的には、国内投資135兆円・平均賃金100万円増が2030年の目標とされました(実質賃金は年1%成長を目指し、インフレ2%と合わせて名目賃金は3%上昇が目標。設備投資目標も含め、骨太方針2025年に明記された石破政権の方針と同一)。
地方創生への取り組み加速も掲げられました。農林水産業については、生産者の所得を守るセーフティネットを整備するほか、特にコメでは水田の大規模化・集約化、スマート農業の推進などを主張しました。2030年までに、農林水産物輸出を5兆円まで拡大、同じく訪日外国人数を6,000万人まで増加という地方創生に係る政府目標(インバウンド消費額は15兆円が目標)も堅持する構えです。
外国人政策については、オーバーツーリズムや不動産取得などにふれつつ、外国人問題の司令塔を設置して総合対策を策定します。不法滞在や不法就労の防止、医療・児童手当等の不適切利用の是正、土地・不動産取得の透明化などが意識されているようです。2025年内にもアクションプランを作成するとも述べました。
防衛費については、現行計画通りに名目GDP比2%まで引上げると明言しました。エネルギー政策については、再エネ・原子力を最大限活用する方針です。原子力については、リプレースを含めて、できることは進めるとしました。
なお、2024年の総裁選で主張した解雇規制については、進めないことを明確にしました。ただ、成長分野への労働力移動は大切な課題と認識し、ジョブ型雇用やリスキリングの推進に努める姿勢を示しました。
以上、9月22日の公示時点の各候補の重要論点を確認しました。今後の論戦が、これら政策の優先順位付けに終わるのか、新たな論点が出てくるかに注目したいところです。

- チーフ・マーケット・エコノミスト
岡崎康平 - 2009年に野村證券入社。シカゴ大学ハリス公共政策大学院に留学し、Master of Public Policyの学位を取得(2016年)。日本経済担当エコノミスト、内閣府出向、日本経済調査グループ・グループリーダーなどを経て、2024年8月から、市場戦略リサーチ部マクロ・ストラテジーグループにて、チーフ・マーケット・エコノミスト(現職)を務める。日本株投資への含意を念頭に置きながら、日本経済・世界経済の分析を幅広く担当。共著書に『EBPM エビデンスに基づく政策形成の導入と実践』(日本経済新聞社)がある。
※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。
- 手数料等およびリスクについて
-
当社で取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料(換金時手数料)および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、年金保険・終身保険・養老保険・終身医療保険の場合は商品ごとに設定された契約時・運用期間中にご負担いただく費用および一定期間内の解約時の解約控除、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の委託保証金または委託証拠金をいただきます。信用取引、先物・オプション取引には元本を超える損失が生じるおそれがあります。証券保管振替機構を通じて他の証券会社等へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、移管する銘柄ごとに11,000円(税込み)を上限額として移管手数料をいただきます。有価証券や金銭のお預かりについては、料金をいただきません。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。


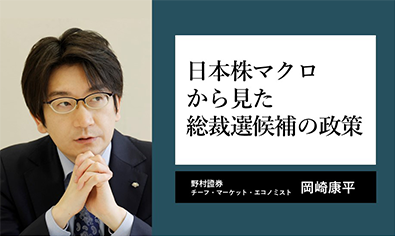
![[特別対談]森永康平さん×野村證券エコノミスト 今後も続くであろうインフレに私たちはどう備えるかのイメージ](/wealthstyle/article/0448/images/a_0448_thm.png)