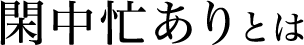ベストセラーをもう一度(第1回) 村上春樹『風の歌を聴け』
2019年7月10日

かつて時代を彩ったベストセラーのページを、あらためてめくってみる――。そこで出会うのは、懐かしい思い出か、それとも……。まずは、60年代生まれの作家/書評家・印南敦史(いんなみあつし)さんが語る2度目の読後感に耳を傾けてみましょう。
第1回でとりあげる作品は、村上春樹氏のデビュー作である『風の歌を聴け』(1979年初版発行)。20代最後の年を迎えた主人公の「僕」が、大学生だった1970年の夏の日々について記した形式をとる小説作品です。
いまこそ青春時代を振り返ってみよう
「青春」といえば聞こえはいいが、多くの人にとってそれは、人間的に未成熟だった時期であったといえる。勢いはあるが、常識はずれで不器用で、いろいろなことがうまくいかず、思い出すだけで顔から火が出るような失敗もあったはずだ。
だが、人生も後半にさしかかったいまだからこそ、あえてそんな時期の記憶を呼び戻してみるのも悪くない。そうすれば、いまの自分を少しだけ誇らしく思えるかもしれない。なぜなら未成熟な時期を経てきた結果として、いまの自分があるのだから。
ところで青春時代を振り返ってみると、その時期の自分に対してなんらかの影響を与えてくれた文学作品があったことに気づく。
読んでみたら衝撃を受けたという作品が記憶に深く刻まれている一方、気にはなっていたものの、結局は読まずじまいになってしまったものもあるかもしれない。
あるいは、読んだ結果、当時の自分についての痛いところを突かれたような気がして、よい印象が残らなかったという作品もありそうだ。
かように印象はさまざまであろうが、いずれにしても青春時代に通り過ぎてきた文学作品には、なんらかの“引っかかる部分”があったのではないかということである。
青春時代を綴った村上春樹のデビュー作
さて、思い浮かべてみてほしい。具体的な「忘れがたい作品」を挙げるとしたら、誰のなんという作品にたどり着くだろう? 当然のことながらそれもまた人それぞれだろうが、個人的には村上春樹の『風の歌を聴け』を思い出す。
1978年の春に神宮球場で野球観戦をしているときに「小説を書こう」と思い立ち、少しずつ書き進めたという処女作。しかも最初は、冒頭部分を書きたかっただけだったのだという。
つまり、強い意気込みをベースに書かれたわけではなく、日常生活の延長線上で創作されたものだと表現したほうがいいのかもしれない。しかし、だからこそよかったのではないか。だからこそ第22回群像新人賞を受賞しただけでなく、結果的には村上を代表する名作となってしまったのではないか。
いいかえれば、必要以上に肩肘を張っていないからこそ、“結果的に”この小説にしかない空気感が誕生したのだ。いま改めて、そう感じる。歴史的な名作というのは狙ってできるのではなく、このように“ふっと”誕生するものなのだ、おそらくは。
1978年に29歳になった主人公の「僕」が、1970年の8月8日から8月26日までのことを振り返る物語。いうまでもないことだが、サスペンスのように派手な展開があるわけではない。それどころか、一貫して淡々とした、ちょっと淡い色のついた空気が流れ続けているような印象がある。
つねに景色があり、景色の邪魔をしないように会話がある。そして、会話の背後に音楽が流れている。音量は、サードウェーブ系コーヒーショップのBGMよりも少しだけ大きく、でも騒がしくはないといったニュアンスだ。そうしたことまでが、文脈から伝わってくる。
ストーリーは……あるようで、ない。しかし、ないように見えて、ある。汽車に乗っていて、窓の外の景色が変わっていくこともストーリーであるとすれば、ここに描かれている静かな世界もまた、ひとつのストーリーだ。
ただし、そこに取ってつけたようなイベントのようなものは皆無だ。しかし、ないからこそ、静かなのに強烈な印象を残すのだ。
自分自身の青春時代を思い起こしてみると、少なからずその空気感を思い起こせるに違いない。あのころ、必ずしもエキサイティングな事件ばかりが起きていただろうか? そうとは限らなかったはずだ。
それどころか、「すべてが漠然としたこの状態がずっと続くのではないか」というような思いを抱えながら、変化に乏しい毎日を送っていたといったほうが近いのではないか。
そういう意味で、友人である「鼠」とのやりとりが重要なファクターとなっているこの小説には、不思議なリアリティがあるのだ(ちなみに、同じように鼠が登場する『1973年のピンボール』『羊をめぐる冒険』は「鼠三部作」と呼ばれている)。
端的に言えば、青春時代の風景を切り取ったものであり、過度なメッセージ性があるわけではないのだ。しかし、その淡々とした、心地よいような、しかし生々しくもあり、ときおりヒリヒリと皮膚に染み入るような感覚が、読む者を無理なく作品の内部に引きずり込む。
その結果、読者ひとりひとりが無意識のうちに「僕」と自分とを重ねあわせようとすることになるのである。
とはいえもちろん、現実の自分自身と「僕」との間には大きな距離があるだろう。「『僕』は実際の僕にそっくりだ」と感じた人がいないとは言わないが、実際問題として、そういう人のほうが少ないと思う。
なぜならここに描かれている「僕」は、きわめて抽象的だからだ。どこにでもいそうな印象があるのだけれども、突き詰めて考えてみると、どこにも存在していなさそうな感じなのである。
だから、「僕」の言動や行動、思考が自分のそれときっちりと重なり合う可能性は低いのではないかと考えるのである。しかし、そうでありながら、そうだとわかっていても、なぜか「共感」を生み出してしまう力が、この作品にはある。
それは、とても曖昧な感覚だ。例えるなら、歳月を経ていい感じにくすんだポップ・アート作品のような印象。手に届くようで、少し遠い。近くで見たいのだが、そのテクスチャーを実感しすぎたくないという気持ちもある。なのに、またじっくりと見てしまう。そんなイメージだ。
だから、涙が抑えられなくなるほど感動するわけでない。にもかかわらず、読んだあと何年も心のどこかに引っかかったままになる。そこに心地よさを感じる。
いまだからこそ感じられる本書の魅力とは
私の場合も、最初から深く感動したわけではなかった。高校生のころに読んだのだが、文学に詳しい友人に無理やり勧められて読んだにすぎなかったので、その時点では感銘を受けるようなことはなかったのだ。
そもそも、この作品のなかで描かれている1970年、私は大阪万国博覧会のことしか頭にない8歳児だった。だから、そこに描かれていた光景は自分とはあまり関係のない、遠い世界の出来事のように感じた。少なくとも、その当時は。
にもかかわらず、時が経つにしたがって、記憶の奥底のほうからじわじわと浮き出てくるような印象が大きくなっていった。その証拠に、初めて読んだときから40数年を経たいま、改めてこの作品に描かれた風景を思い出すことがよくある。
しかも思い出したからといって、大きな感動に包まれるというわけではないのだ。少なくとも私はそうだ。だが、それでも近くにいたいような、そんな包容力がこの作品にはある。
ただしそれは、この原稿を書くにあたり、数十年ぶりに読みなおしてみた結果として感じたことである。おそらく青春期のあのころは、そこまで考えてはいなかったような気がする。
だが、いまだからわかる。『風の歌を聴け』のなかには、生き方がよくわからなくて、なにをやってもうまくいかなかった、20代前半の私がいたのだ。いや、私を含む、すべての読者がそこにいたといったほうが適切だろう。つまり、読者の多くがこの作品に引き込まれたのだ。
だとしたら私は自分のことを、この小説のなかの「僕」に投影していたのだろうか? おそらくそうではないだろう。しかし、誰に似ているとか誰に近いとか、そういうことはどうでもいいのだ。
『風の歌を聴け』は、誰のなかにもあるストーリーなのである。そして、誰のなかにもないストーリーなのである。
改めてこの作品を読み返した結果、ここまで深いインパクトをいまになって感じたのはなぜだろうか。それは私という人間が、それなりに人生経験を重ねてきたからなのだと思う。
別な表現を用いるなら、「いまだからこそ」わかることに価値があるのだ。それが、いま私たちがこの作品と接する価値だ。
そこで提案したい。いまこそ『風の歌を聴け』を手にとって、読んでみてはいかがだろうか? そこには、経験を重ねてきた人間にしか感じることのできないなにかがあるはずだからだ。そしてそれは、自分自身が成熟したことの証明にもなるのだろう。
【作品インフォメーション】
村上春樹『風の歌を聴け』
1979年、講談社より単行本発行。1982年に文庫化され、2004年に文庫新装版発行。
評者プロフィール
印南 敦史(いんなみ あつし)
1962年、東京生まれ。作家、書評家、音楽評論家。広告代理店勤務時代にライターとして活動開始。最新刊は『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)。他にも、ベストセラーとなった『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)など著作多数。書評家として数々のサイトに寄稿。
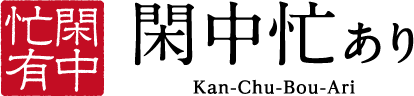 人生100年時代を粋でお洒落に
人生100年時代を粋でお洒落に