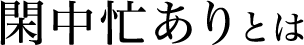ベストセラーをもう一度(第2回) リチャード・バック『かもめのジョナサン』
2019年10月23日

かつて時代を彩ったベストセラーのページを、あらためてめくってみる――。そこで出会うのは、懐かしい思い出か、それとも……。まずは、60年代生まれの作家/書評家・印南敦史(いんなみ あつし)さんが語る2度目の読後感に耳を傾けてみましょう。
第2回でとりあげる作品は、アメリカの飛行家/作家であるリチャード・バックが1970年に発表した『かもめのジョナサン』(1974年日本語訳発行)。
「餌をとる」という目的のために飛ぶのではなく、ただひたすらに飛ぶことそれ自体を追求し飛行技術を磨き続けた「異端」のかもめ、ジョナサンを主人公とする小説作品です。
当時の自分には「まだ早かった」作品を読みなおしてみる
1970年にアメリカで出版されたリチャード・バックによる『かもめのジョナサン』の日本語版が発行され、爆発的なヒットとなったのは1974年のことだ。
私は当時12歳だったが、小学生でも知っている有名作家の五木寛之が「創訳(創作翻訳)」を手がけたその本が、日常的に出入りしていた近所の中規模書店にずらりと並んでいた光景は、いまでもはっきり記憶に残っている。
表紙は写真集のようにおしゃれだったし、なにより多くの大人たちが飛びついていたのだ。だから読まなければいけないような気がして(でないと乗り遅れるような気がして)、店頭で手にとってみた。
ところが残念ながら、小学生にはやや理解しづらかった。写真が多くて文字は少なく、しかも書かれていたことは詩のようでもあり、散文のようでもあり、端的にいえば実態が見えなかったのだ。
つまり、あの時点での自分には「まだ早かった」のだろう。そのため初版から44年後の2014年に、ずっと封印されていた第4部が公開され、「完全版」としてふたたび世に出たときにさえ、さして興味は惹かれなかった。
読みなおしてみようと思い立ったのは本当につい最近で、知人と1970年代の文学作品について話したことがきっかけだった。
「あのころ、こんなのが流行ったよね」というような他愛もない会話の筆頭に、『かもめのジョナサン』が登場したのである。
そしてそのとき、「あれはいったい、どのような作品だったのだろう? なぜ、あれほど話題になったのだろう?」と純粋な疑問が湧き、当時さんざん見慣れた表紙と、数十年ぶりに対面したというわけだ。
「個」をつらぬき続けた主人公の姿から見えてくること
本作はかもめの、ジョナサン・リヴィングストンを主人公とした物語である。
ジョナサンは、なんの迷いもなくただ餌をとるだけの生き方に満足できないかもめだった。母親から「かもめらしく生きろ」と言われても、飛行技術の向上にしか関心が持てない。
かくして、努力と工夫により卓越した飛行能力を身につけるのだが、この時点でジョナサンがかなりの変わり者であることがわかる。
彼は、自身以上の飛行技術を持つ2羽の輝くかもめに導かれ、さらに高次の世界へ向かう。彼と同じく飛行に取り憑かれたかもめたちが暮らすその世界ではより高度な飛行技術を学び、チャンという名の老いたかもめからは究極の「瞬間移動」を学び取る。
そうした経緯を経たジョナサンは、その時点でさらに上の世界を目指すことをやめ、かつていた世界に戻る。自分と同じようなかもめを見つけ、教育しようと決めたからだ。
ところが弟子の数は増えていったものの、卓越した能力を持つ彼を悪魔呼ばわりし、敵視するかもめも数多く現れることになる。だが、そんななかで弟子たちが力をつけていくと、ジョナサンは姿を消すことになる。
よくも悪くも目立つ存在であった彼は、その段階で偶像化したともいえよう。
1972年の時点で明らかにされた第3部は、こうして幕を閉じる。前述したように2014年になって第4部が加えられるわけだが、そこで明らかになることを書いてしまっては読む楽しみが半減してしまう。だから、ここでは黙っておくことにしよう。
とはいえ第3部まで読んだだけでも、この作品が1970年代に支持された理由は多少なりともわかるはずだ。当時のアメリカのヒッピー文化の内部で支持され、数年を経て大ヒットしたというが、たしかに根底には、禅の影響があるように思えるからだ(ヒッピー文化は仏教や東洋思想に大きな影響を受けていた)。
しかし、この作品からは、そうした捉え方とはまた違った次元の価値を見出すこともできる。それは、ジョナサンの立ち位置だ。
大多数が「かもめらしい生き方」に疑問を感じることなく、集団の一員として生きるなか、ジョナサンだけが飛行に執着し、技術の習得に集中し続ける。
いわば、団体行動からは距離を置き、「個」であり続けたのだ。しかし当然のことながら、団体行動を前提とした集団において個を貫けば、それは軋轢につながっていく。だからジョナサンも孤立し、それでも我が道を進み続けた。
それが個の確立、ひいては偶像化につながっていくわけだが、いうまでもなくこの図式は人間社会にもぴったりとあてはまる。たとえば、かもめの群れを企業と考えればわかりやすいだろう。
どんな集団のなかにも、集団行動が苦手な人がいるものだ。というよりも、心のなかでは絶対的多数の人が「自分は集団が苦手だ」と考えているといっても過言ではないかもしれない。
とはいえ、働くこと自体は生き甲斐でもあった。だからこそ、つまり生き甲斐を守るため、多くの人は苦手なものも我慢しながら会社へ向かっていたのではないだろうか。
そんな状況下、“自分にはできないこと”をしてみせてくれたのがジョナサンだった。好むと好まざるとにかかわらず周囲を意識しなければ生きていけないからこそ、自分の意思を最優先して飛行訓練に集中するジョナサンに、多くの読者が我が身を投影させていたのだ。
現代にも通用する本作の価値とは
そう考えると、我が国における『かもめのジョナサン』現象が高度経済成長期の終わりとリンクしたことに、単なる偶然を超えたなにかを感じることもできる。いわば、あの時代だからこそ訴えかけたなにかがこの作品にはあったのだ。
ちなみに当時の社会について思い出すのは、漠然とした閉塞感、終末感だ。『かもめのジョナサン』が我々の前に登場する前年の1973年を言い表すキーワードは「不景気」であり、オイルショックの影響でトイレットペーパーを買い漁るという主婦たちの不可解な行動に気味の悪さを感じていたのである。
また、同じ年に話題となった『ノストラダムスの大予言』も、子どもたちを絶望の淵まで追い込んだ(私も、1999年に37歳で死ぬのかもしれないと思っていた)。
だから、その翌年も、人々は相変わらず“漠然とした閉塞感”を肌で感じつつ、でも、それを“なかったこと”であるように考えていた。
そんななか、『かもめのジョナサン』が現れた。アメリカでのヒットから数年遅れて登場したわけだから、日本での受け止められかたを現地のそれと比較することはできないだろう。
また、それ以前に(当時の私がそうだったように)「流行ってるらしいから」という単純な理由で興味を示した人も多いはずだ。
だが、そうした事情を差し置いても、1974年の日本で『かもめのジョナサン』が出版され、支持されたことには相応の意味があると感じるのである。
おそらくそれはこの作品が、多くの人々の内部にあった“漠然とした閉塞感・終末感”を一時でも忘れることのできる媒体として機能してくれたからだ。
ヒッピーたちを魅了した宗教的な意味がどうであれ、高度経済成長期の終わりにあった日本を生きる我々にとっては、なにか別の意味を持ったのではないかということだ。
ところで先ほど、時代の閉塞感と本作との接点について触れた。もしもその考え方が当たっているのだとしたら、それは同様の閉塞感を持つ現代にも通用するのではないだろうか?
だとすれば、いまこの作品を読み返すことにも相応の価値があるだろう。集団から離れて個を貫くジョナサンの姿が、そうした閉塞感を忘れ、残りの人生を好きなように生きていくための勇気を与えてくれるかもしれないからだ。
【作品インフォメーション】
リチャード・バック『かもめのジョナサン』
1970年にアメリカで出版。1974年、新潮社から五木寛之の訳による日本語訳が発行され、のち文庫化。2014年に封印されていた第4部を含めた「完成版」が発行。
評者プロフィール
印南 敦史(いんなみ あつし)
1962年、東京生まれ。作家、書評家、音楽評論家。広告代理店勤務時代にライターとして活動開始。最新刊は『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)。他にも、ベストセラーとなった『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)など著作多数。書評家として数々のサイトに寄稿。
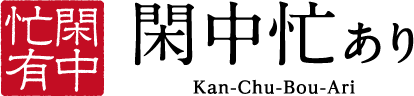 人生100年時代を粋でお洒落に
人生100年時代を粋でお洒落に