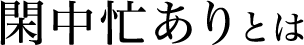ベストセラーをもう一度(第3回) 星新一『ボッコちゃん』
2020年1月29日

かつて時代を彩ったベストセラーのページを、あらためてめくってみる――。そこで出会うのは、懐かしい思い出か、それとも……。まずは、60年代生まれの作家/書評家・印南敦史(いんなみ あつし)さんが語る2度目の読後感に耳を傾けてみましょう。
第3回でとりあげる作品は、星新一の『ボッコちゃん』(1971年初版発行)。国内SF界きっての名短編として名高い1958年発表の表題作をはじめ、同氏の選りすぐりの短編をおさめた文庫作品です。
SF人気高まる時代にあらわれた“超短編”の名手
中学1年生のころ、星新一のSF小説に心を奪われた。我が家にも著作がたくさんあったので、なんとなく読んでみたら、見事にハマッてしまったのだった。
あっという間にファンになり、その年の冬には年賀状まで出した。返事が来るだろうとは思ってもいなかったが、出さずにはいられなかったのだ。
小松左京、筒井康隆と並んで「SF御三家」と呼ばれてもいた、SF界の大御所である。SF人気が高まっていた当時の時代状況を、見事に泳ぎ抜いてみせた人物であるといえよう。
ちなみに星の父親である星一(ほし はじめ)は、星薬科大学の創立者で、星製薬の創業者だ。そのため彼も父の死後、短期間ながら星製薬の社長を務めた。そればかりか母方の大伯父は森鴎外であり、端的にいえばお坊ちゃんである。
などといってしまっては身もふたもないが、それはともかく、星作品の魅力はどこから来るのか。それを考えるとするならば、3つの要因が思い浮かぶ。
まず1つめは“品”だ。お上品ぶっているという意味ではなく、簡潔で読みやすい文章からは、さりげない品のよさがにじみ出ているのである。もしかしたらそれは育ちのよさ、あるいは生まれ育った環境の影響なのかもしれない。
2つめは、随所に生かされている数学的な感覚だ。むしろ、こちらの価値が大きいのではないかと思う。
ご存知のとおり、星の作品の大半は「ショートショート」と呼ばれる“超短編”である。一編が3,000字程度、ページ数でいえば5、6ページ前後のものも多い。短時間で読むことができるので、そんな親しみやすさも人気の理由だったに違いない。
そして、ここに見逃してはいけないポイントがある。
文字数の少ないショートショートだと聞くと、「なんだ、だったら簡単に書けるじゃないか」と思われるかもしれない。だが考えてみてほしい。それは、たかだか5、6ページ程度の文章ですべてを完結させなければならないということなのである。
しかも、それは想いをつらつらと綴った随筆のようなものではなく、ましてや抽象的な純文学でもなく、れっきとした小説だ。
だとすれば、その5、6ページのなかで明確に起承転結を成り立たせなければならない。ましてやSFは、特に星の書くそれは、娯楽小説的な意味合いが非常に高い。読み終えたとき、読者が「あー、おもしろかった」と感じることのできるようなクオリティが求められるということだ。
それは決して簡単なことではなく、(推測の域を超えないが)きわめて端的かつ明快な構造のようなものが必要であるように思われる。膨大な作品数を考えると、そのひとつひとつに緻密なプロットが用意されていたとは考えにくいが、少なくとも原稿用紙に向かう星の頭のなかには、なんらかの数学的な設計図があったのではないだろうか?
つまり、数学的なそれを感覚的に言語化していったからこそ、緻密でありながらも軽快なショートショートを生み出すことができたのではないかと感じるのだ。
そういえばあのころ、星がウイスキーの広告に登場したことがあった。書斎でウイスキーグラスを傾ける星の写真に、文章に関することばが添えられた広告だ。40年以上前の話なので細かいところまでは憶えていないが、最初の一行が難しく、そこで大いに悩むが、その一行さえ書ければ、あとは大した苦労ではないといった内容であった気がする。
「なるほど、そうかもしれないなぁ」と大いに共感した。たしかに星作品の決め手は冒頭部分である。15篇すべてが「ノックの音がした」で始まる『ノックの音が』が最たるものだが、最初の一行目でエンジンをかけ、その勢いで残り数ページを数学的に、かつ感覚的に書き進めていたのではないだろうか?
そう考えると、星作品特有の簡潔さ、スピード感にも納得できる気がするのだが、いかがだろう?
ロボット・AIと共にある日常を予見
さて、3つめの要因は、なんといっても発想力である。軽妙な文章力もさることながら、やはり最大の魅力はアイデアの斬新さなのだ。そのいい例が、本書の表題作であり、星の代表作である「ボッコちゃん」である。
まず際立っているのは、ひとかけらの無駄もないオープニングの描写だ。
そのロボットは、うまくできていた。女のロボットだった。人工的なものだから、いくらでも美人につくれた。あらゆる美人の要素をとり入れたので、完全な美人ができあがった。もっとも、少しつんとしていた。だが、つんとしていることは、美人の条件なのだった。
星新一著「ボッコちゃん」(新潮文庫刊『ボッコちゃん』所収)より
わずか百数十文字で、読者へ的確な情報を投げかけている。「そのロボットは、うまくできていた。女のロボットだった。」と言われれば、まずいロボットではなく、うまくできていることを嫌でも実感せざるを得ない。
それどころか「いくらでも美人につくれた」となると、「ロボットなんだから、そうだろうなぁ」と思うしかない。ツッコミどころがないのである。そのため読者は必然的に、「美人でつんとした、完璧なロボット」をイメージしてしまう。これは重要なポイントだ。
これがもし同時代の純文学だったとしたら、もっと回りくどい表現で描写するだろう(純文学を否定するわけではなく、しかし、純文学とはそういうものでもある)。だが、ここに一切の無駄はない。
ボッコちゃんは、バーテンダーとして客に酒を提供するのみならず、簡単な「会話」だってこなしてみせる。家庭向けにロボットが販売され、人間と「会話」をするAIも現実のものとなったこの現代において、私たちは「ボッコちゃん」で描かれた光景をありありと想像することができる。しかし忘れてはならないのは、この作品が書かれたのが1958年であるという事実である。いまから半世紀以上も前に、「ボッコちゃん」は「日常にロボットがいる光景」を、そこから生まれる物語を予言していたのだ。いや、「ボッコちゃん」に限らず、星作品にはおしなべて先進性があるのである。
ここに収録されている、他の話にしても同じだ。読む楽しみを減らすようなネタバレはできないが、たとえば「おーい でてこーい」では原発の廃棄物処理問題を取り上げ、「生活維持省」では官僚の体質を皮肉り、「鏡」ではいじめ問題の本質を突き……と、現代社会においても十分に通用するトピックを持ち出しているのである。そこに驚かされる。
いま読むことで感じられる醍醐味とは
なお、これは肯定的な意味なのだが、そんなところも含め、星作品は「漫画」である。簡単に読めて、難しいことを考えさせず、それでいて、刺すべきところはさりげなく、チクッと刺す。その洗練されたスタンスこそ、誰にも真似のできない魅力なのだ。
少し前に出張をした際、『ボッコちゃん』の文庫本を持っていった。なにか持って行こうと思ってなんとなく選んだだけだったのだが、結果的には正解だった。サラッと読めるので、旅のお供に最適なのだ。
そう感じたからこそ、ひとりでも多くの方に、ふたたび星作品を読んでみていただきたいと思う(もちろん、読んだことがない方も)。少年時代を思い出すかもしれないし、少年時代には気づかなかった粋な仕掛けに気づくことになるかもしれないからだ。
さて最後に、冒頭の年賀状の話の後日談を書いておきたい。
もちろん、正月の三が日を過ぎても返信はなかった。なにしろ向こうは売れっ子作家なのだから当然の話だし、別に期待もしていなかった。
ところが、それからしばらくして忘れかけたころ、返事が届いたのだ。たしか2月下旬のことである。
「賀 星新一」
サインペンで縦書きされていたのは、たったそれだけ。しかし、まさかの展開に驚き、そして深く感動した。
ウイスキーグラスを手に微笑んでいたあの書斎で、この4文字を書いてくれたのかと考えると、思わず笑みがこぼれてしまった。うれしさを隠すことなどできなかったのだ。
【作品インフォメーション】
星新一『ボッコちゃん』
1971年、新潮社より初版発行。なお表題作を含む最初の短編集は『人造美人―ショート・ミステリイ』として1961年にて刊行されているが、本書とは収録作品を異にしている。
評者プロフィール
印南 敦史(いんなみ あつし)
1962年、東京生まれ。作家、書評家、音楽評論家。広告代理店勤務時代にライターとして活動開始。最新刊は『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)。他にも、ベストセラーとなった『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)など著作多数。書評家として数々のサイトに寄稿。
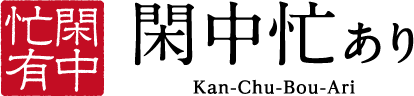 人生100年時代を粋でお洒落に
人生100年時代を粋でお洒落に