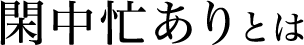コロナショックを予見していたかのようなリアルさ―小松左京の名作パンデミック小説
2020年10月28日

正体不明の感染症が流行し、世界中の人々が混乱に陥ってしまう――。こうした類のテーマは、これまで幾多の小説、映画で取り上げられてきました。それゆえ、新型コロナウイルスが拡大していく様を見て、「これは本当に現実なのだろうか?」「SFの世界に迷い込んだようだ」と感じた方も多いのではないでしょうか。
そうした中、あらためて世間の注目を集めているのが、人類と感染症との戦いを描いたSF小説『復活の日』(小松左京 KADOKAWA/角川文庫)。コロナショックを彷彿とさせる展開もさることながら、作品の発表が東京五輪開催年でもある1964年だったというのも、なにか因縁めいたものを感じます。今回は同書をピックアップし、作家・書評家の印南敦史(いんなみ あつし)さんに、作品としての魅力や「いまだからこそ読むべき理由」について、解説していただきましょう。
小松作品の背景には「不安」がある
去る5月25日に緊急事態宣言が解除された際、無意識のうちにそれを“収束”と結びつけて捉えようとしていた方は、決して少なくないのではないだろうか?
もちろんそこに根拠はなく、現実的に考えればそんなことはありえない。そもそも、新型コロナウイルスがそれほど脆弱なものではなさそうだということは誰もが理解しているはずだ。
つまり「収束するのかも」というような思いは、あくまで希望的観測、もしくは単なる楽観にすぎない。なのに、そうだとわかっていてもなぜ、そんなことを考えてしまうのか?
言うまでもない。不安だからである。
3年弱の歳月を経るなか、世界で5億人が感染したとされる1918年のスペインかぜのようなことになるのか? もしもそうだとすれば、生き残ることができるのか? 少し前までなら「そんなのSFの世界の話だよ」と笑い飛ばされたかもしれないことが、いまや現実になっている。
小松左京『復活の日』がここにきて再評価を受けているのも、現代人がいま、そんな状況と対峙しているからなのだろう。文字どおりのSF作品であるが、そこに描かれている情景には、いま私たちが目の当たりにしている現実と重なり合う部分があるということだ。
ご存知のとおり、1973年の作品『日本沈没』で知られる小松左京は、筒井康隆、星新一と並ぶ“日本のSF御三家”のひとり。
1931年生まれの彼に大きな影響を与えたのは、思春期に体験した第二次世界大戦だった。14歳で終戦を迎えたため自身は徴兵されずに済んだものの、同年代の少年たちが沖縄戦で命を落としたことを知り、「生き残ってしまった者の責任」を痛感するのである。
しかも戦争が終わり、ようやく平和な時代が訪れるかと期待を抱いたのも束の間、1950年には朝鮮戦争が勃発する。さらには1954年にはビキニ環礁で大規模な水爆実験が実施され、第五福竜丸が死の灰を浴び、それが地球規模の深刻な大気汚染、海洋汚染につながる。また、1962年のキューバ危機は米ソ核戦争の一歩手前まで進むことにもなった。
つまり当時は、第三次世界大戦も絵空事とは思えないような漠然とした不安感が社会を覆っていたわけである。小松も戦争体験とその後の社会状況のなかから多くのことを感じ取り、それが結果的にはSFを書くことにつながっていくことになったのだ。
「人類の危機」のリアリティはどこから生まれたのか
『日本沈没』と並ぶ代表作として名高い『復活の日』は、1964年8月に書き下ろし作品として世に出た。同年3月、ひと足先に出版された『日本アパッチ族』に次ぐ、2作目の長編である。
1963年、創立直後だった日本SF作家クラブが、「日本SFシリーズ」というプロジェクトを立ち上げる。当時はまだ黎明期にあった日本SFの地盤を固めることを目的とした長編書き下ろしシリーズで、そのトップバッターとして選ばれたのが小松左京。かくしてこの作品が生まれたのだ。
未知のウイルスによって人類が滅亡の危機にさらされるなか、南極基地で懸命に生きようとした人々の姿を描いたもの。ストーリーは、強い吹雪のアルプス山中で遭難機が発見されるところからスタートする。
遭難機の残骸の傍に、露出した岩にぶつかって、蓋がとび、ひきさかれ、ねじまがったジュラルミン製のトランクの破片がころがっていた。なかのものは全部もえてしまったらしかったが、そこから十数メートルもはなれた雪の中に、ブルーのプラスチック塗料のはげた薄い鉄板が、かろうじてもとの円筒形をたもってころがっており、付近の雪や、岩の上には、銀メッキされたガラスの粉々になった破片が、キラキラかがやきながら散乱していた。(p.58)
つまりはそのトランクのなかに、未曾有の感染症を引き起こす“MM菌”が入っていたのだ。
その結果、春になり雪が溶けると、ヨーロッパ各地で不可解な死亡事案が確認されはじめる。そしてその波は全世界に広がっていき、人類は滅亡の危機と直面する。
プロットが緻密に練り込まれた作品であり、予知のできない展開が魅力であるだけに“ネタ明かし”をするわけにはいかない。したがって、残念ながらこの場で明かすことができるのはここまでだ。あとは実際に読んでいただきたいと思う。
そこでここからは、この作品の価値について言及したい。
まず驚くべきは、その「情報収集力」である。それは小松左京という作家ならではのポテンシャルだとも言えるが、ここでも彼は作品の完成に向け、並々ならぬ努力をしているのである。
その点については、文庫版解説を手がけられている次男・小松実盛氏の文章に詳しい。
本作品は、最新の生物学、軍事情報などが溢れんばかりに盛り込まれ、南極を含む世界各地がリアルに描写されています。けれど、当時の小松左京は、まだ一度も海外旅行の経験はなく、当然、インターネットなど影も形もない時代でした。物語に関する情報は、普通に入手した書籍や雑誌に加え、大学、研究所関係の図書館にも入れてもらい、関係文献や研究資料、レポートなどを閲覧し、さらにアメリカ文化センターで、「サイエンス」や「サイエンティフィック・アメリカン」といった雑誌にも眼を通すことで蓄えたようです。(p.445)
そもそも最初の段階では、まだ物語の形は見えていなかったのだという。「日本SFシリーズ」を取り仕切っていた「SFマガジン」編集長から電話で内容を問われるまで、作品のテーマもタイトルも決まっていなかったそうだ。
まさに“無”からスタートしたわけだが、にもかかわらずこの作品には、あたかも自分の目で見て、体験してきたかのようなリアリティが貫かれている。そして実盛氏も指摘しているように、最も重要なポイントは、「風邪で人類が滅亡の淵まで追いつめられてしまう事態」を、いかにリアルに描くかだ。
その点について一切の妥協なく、とことん突き詰め表現しているからこそ、発表から56年後の現代においても強いインパクトを投げかけるのだ。
危機を前にして、いかに振る舞うか
ところで本書の解説には、1964年版『復活の日』のあとがきに掲載された小松の言葉が引用されている。とても興味深い内容なので、ここにも引用しておきたい。
――偶然に翻弄され、破局におちいる世界の物語を描いたところで、私が人類に対して絶望していたり、未来に対してペシミスティックであると思わないでいただきたい。逆に私は、人類全体の理性に対して、――特に二十世紀後半の理性に対して、はなはだ楽観的な見解をもっている(それはおそらく現代作家の誰にも共通のことだと思う)。さまざまな幻想をはぎとられ、断崖の端に立つ自分の真の姿を発見することができた時、人間は結局「理知的に」ふるまうことをおぼえるだろうからである。(p.451~452)
小松は、窮地に追い込まれた人類に対して楽観的な見解を持っていた。しかし実際にコロナという「断崖の端」に立ったいま、はたして人類は小松の予想した通り「真の姿」を発見し、然るべきふるまいをなすことができているだろうか?
いま『復活の日』から学べることは少なくない。その点に注目しつつ現実と照らして読むことで、より多くの学びを得ることができるのではないだろうか?
そういう意味においても、「いまだからこそ」改めて読んでみるべき作品であると断言できるのだ。
ちなみに本作は発表から16年後の1980年、深作欣二監督によって映画化されている。当時の金額で25億円の製作費がかけられ、劇場公開映画世界初の南極ロケが行われた超大作。
国内の名優たちに加え、ハリウッドスターまでが出演していることも大きな話題となった。
小松左京作品は『日本沈没』などいくつかが映画化されているが、本人も「一番好きなのは『復活の日』だと語っていたそうだ。ネットで気軽に観ることができるので、チェックしてみるのもいいかもしれない。
ただし、まず最初に読了することをお勧めする。
【作品インフォメーション】
『復活の日』小松左京 KADOKAWA/角川文庫
感染症による人類滅亡の恐怖と、再生への模索という壮大なテーマを描き切ったSF小説。1964年に書き下ろしで発表された。
評者プロフィール
印南 敦史(いんなみ あつし)
1962年、東京生まれ。作家、書評家、音楽評論家。広告代理店勤務時代にライターとして活動開始。最新刊は『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)。他にも、ベストセラーとなった『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)など著作多数。書評家として数々のサイトに寄稿。
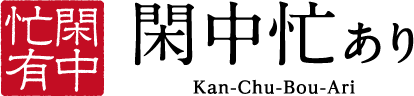 人生100年時代を粋でお洒落に
人生100年時代を粋でお洒落に