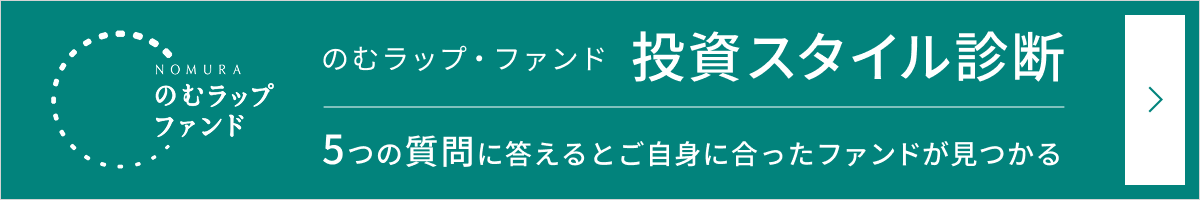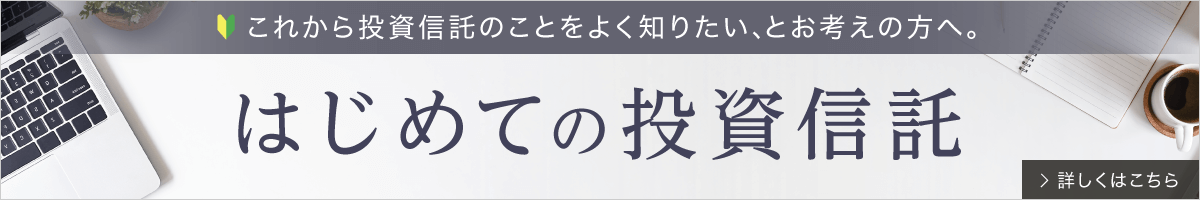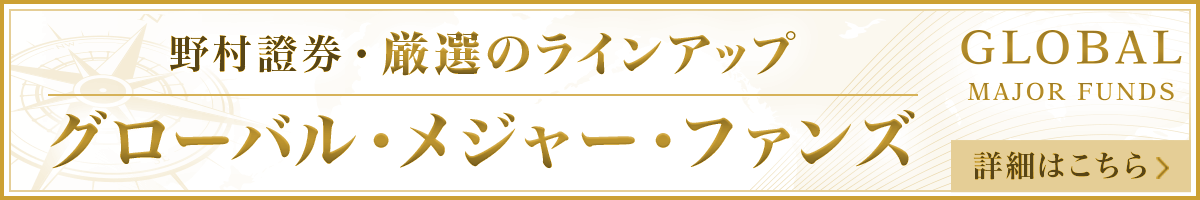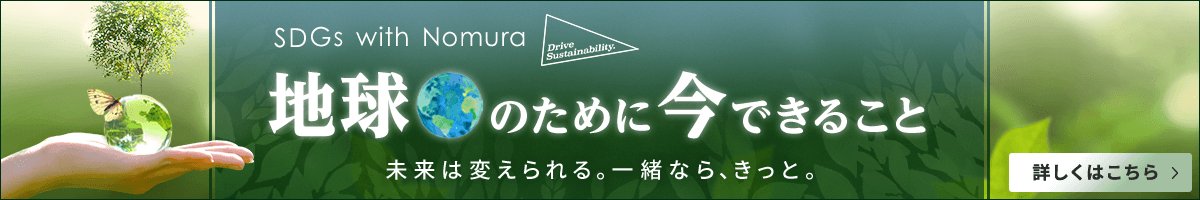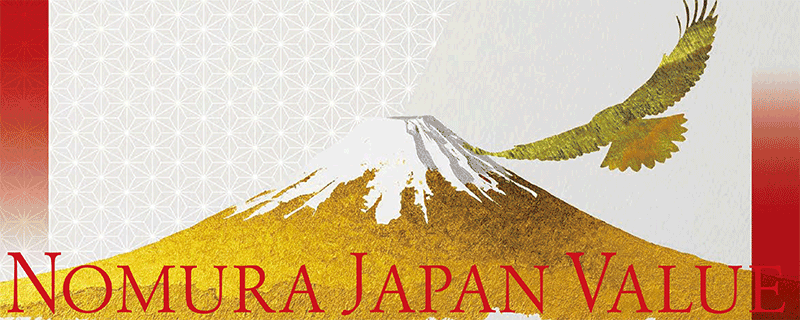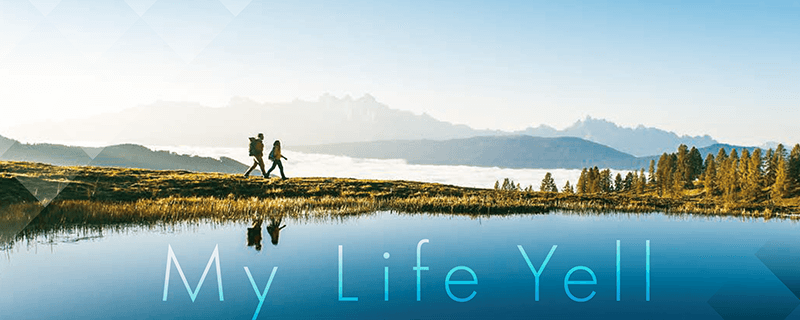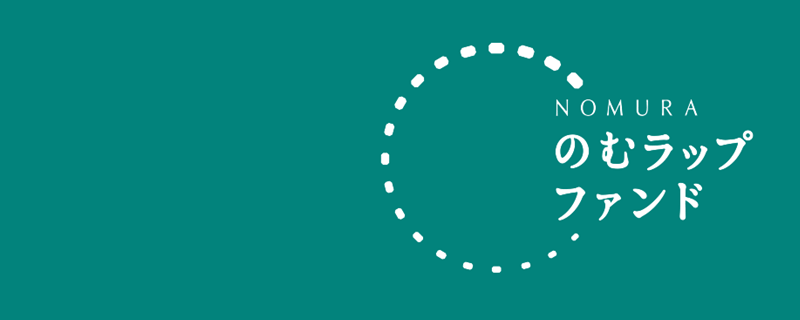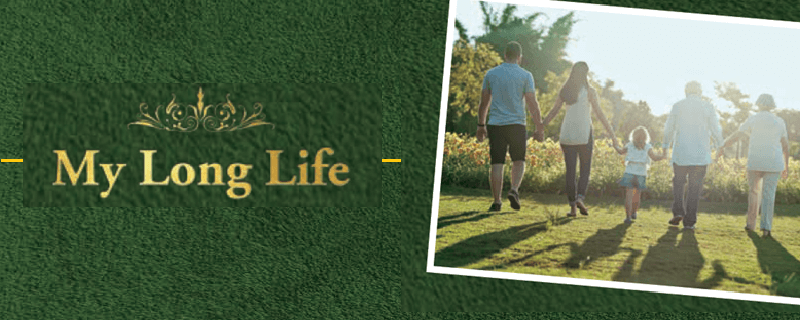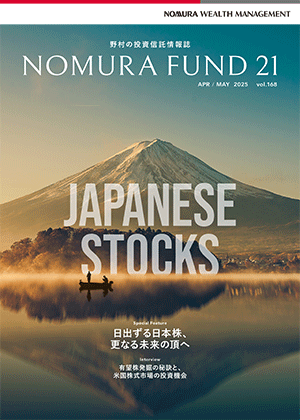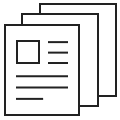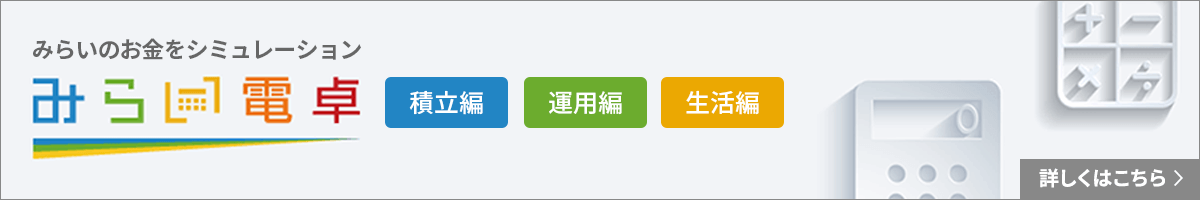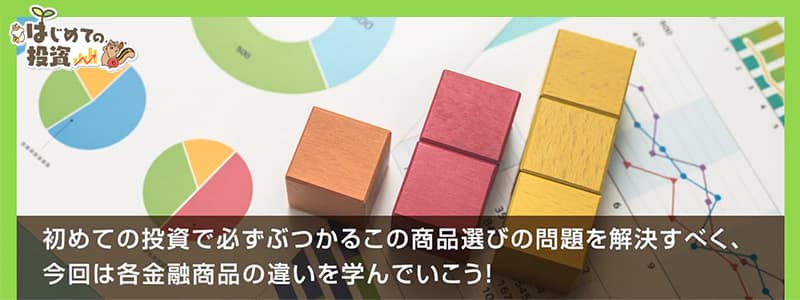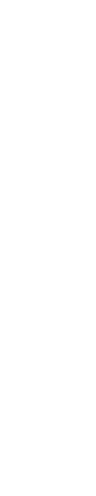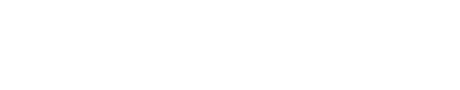各ファンドの投資リスク・手数料等については、リンク先の目論見書・商品説明資料等でご確認ください。
-
-
注目商品
野村のインデックスファンド:Funds-i
-
注目商品
マイライフ・エール
国内外の様々な資産への分散投資によってリスクを抑えた運用を行い、人生100年時代の資産運用を応援します。
-
注目商品
フィデリティ・世界割安成長株投信
テンバガー(株価が10倍になると期待される銘柄)を発掘します。
-
注目商品
目的・スタイルで選ぶ5商品:のむラップ・ファンド
リスク水準が異なる5つのファンドから自分に合ったファンドを選べます。
-
注目商品
人生100年時代を楽しむために:野村ターゲットインカムファンド(愛称:マイ・ロングライフ)
-
注目商品
野村スリーゼロ先進国株式投信【オンライン限定】
信託報酬0%のファンドが登場!
投資信託(ファンド)を探す
投資信託(ファンド)ランキング
オンラインサービスの
ランキングを見る
オンラインサービスは、口座をお持ちのお客様がご利用いただけるサービスです。
オンラインサービスで表示されるランキングは、
オンラインサービスで購入可能なファンドが対象です。
オンラインサービスの
ランキングを見る
オンラインサービスは、口座をお持ちのお客様がご利用いただけるサービスです。
オンラインサービスで表示されるランキングは、
オンラインサービスで購入可能なファンドが対象です。
オンラインサービスの
ランキングを見る
オンラインサービスは、口座をお持ちのお客様がご利用いただけるサービスです。
オンラインサービスで表示されるランキングは、
オンラインサービスで購入可能なファンドが対象です。
オンラインサービスの
ランキングを見る
オンラインサービスは、口座をお持ちのお客様がご利用いただけるサービスです。
オンラインサービスで表示されるランキングは、
オンラインサービスで購入可能なファンドが対象です。
投資信託業界の潮流や変化、最近の投資戦略やトレンドなどが理解できる情報を掲載
特集
Multi-Private Asset 資産を守り育てる分散の力
投資信託を野村ではじめる魅力
-
野村の資産運用アプリ
「NOMURA」

-
スマートフォンさえあれば、いつでもどこでも資産状況をまとめて管理でき、保有資産に関する情報やマーケットニュースを一つのアプリで簡単に把握、そのまま取引を行うことができます。
-
国内最大級の証券会社
ならではのサポート力

-
預り資産の規模は円※。野村は国内最大級の証券会社です。オンラインでのお取引だけでなく、コールセンターや全国の店舗でお客様をサポートいたします。
投資信託とは?~初心者でもよくわかるはじめての投資信託
「投資信託」とは、少額から投資でき、幅広く分散投資できることが魅力の金融商品です。基礎から選び方、お取引の方法まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。
投資信託のお取引
お取引の流れ(オンラインサービス)
STEP 1投資信託(ファンド)を選ぶ
購入するファンドを選びます。
投資地域、投資対象、運用方法、分配金などに着目するなど、さまざまな観点があります。ファンドごとにご提供している目論見書、月次レポート、商品説明資料などをご確認の上、お客様の投資目的やリスク許容度にあったファンドをお選びください。
オンラインサービスにログインすると、各種ランキングや検索機能など、銘柄選びの機能をご利用いただけます。
STEP 2投資信託説明書(交付目論見書)を確認する
目論見書でファンドの目的・特色、投資リスク、運用実績、手数料等の費用(コスト)等を必ずご確認ください。
STEP 3資金を入金する
投資信託を購入する前に、野村證券の口座にあらかじめお買付けに必要と想定される資金(概算金額)をご入金ください(ご入金方法)。
STEP 4お申し込み
銘柄、買付方法(分配金受取/分配金再投資/積立)、買付単位(口数/金額)、NISA口座の選択の有無等を指定して、買付注文(申し込み)します。
買付注文時に数量(口数)、概算購入単価・約定金額・受渡金額※、約定日、受渡日をご確認ください。
- 受渡金額は、口数指定の場合は「約定代金(口数×ファンドの基準価額)+購入時手数料」が概算金額となり約定後確定します。金額指定の場合は「指定する金額」です。
STEP 5約定
投資信託の売買注文が成立(約定)します。
約定日の基準価額によって約定代金や手数料などが確定します。約定日は投資信託によって異なります。
STEP 6受渡し
受渡日に商品や資金の受渡しをおこないます。約定日の2~5営業日後が受渡日になるケースがほとんどですが、投資信託によって異なります。
STEP 7注文状況を確認する
「注文照会/訂正/取消」画面から、注文状況や結果を確認します。
注文が成立(約定)すると、注文状況が「約定済」となります。
約定日の翌日以降は「取引履歴」画面からご確認ください。
- ●売却したいときは?
- 買付時と同様、売却対象のファンドを選択し、お申込み、約定、受渡しのステップを踏みます。
お申込み時に、売却単位(口数/金額/全額)の指定が必要です。
約定日に約定金額、受渡金額が決定し、受渡日に売却代金がお客様の証券口座に入金されます。
投資信託(ファンド)の探し方
多くの種類があることが魅力の投資信託。投資テーマやランキングなど、選択の基準はさまざま。ファンドの選び方をご紹介します。
「かんたん検索」なら、話題のNISAや売れ筋商品、ノーロード(手数料無料)など、あらかじめ設定されたキーワードでファンドを検索することができます。
投資信託(ファンド)のよくあるご質問
投資信託(ファンド)に関するよくあるご質問を掲載しております。
はじめての方へ
口座開設に関するお問い合わせは、はじめてのお客様専用ダイヤル(0120-566-166)へお問い合わせください。
平日 8:40~17:10
土日 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
- ご利用の際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。